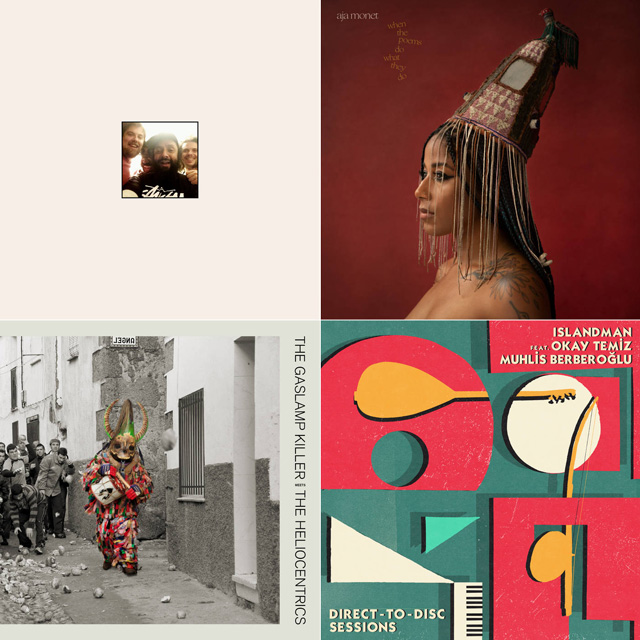MOST READ
- seekersinternational & juwanstockton - KINTSUGI SOUL STEPPERS | シーカーズインターナショナル&ジュワンストックトン
- R.I.P. Steve Albini 追悼:スティーヴ・アルビニ
- Claire Rousay - Sentiment | クレア・ラウジー
- Sisso - Singeli Ya Maajabu | シッソ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Anatole Muster アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 | アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- There are many many alternatives. 道なら腐るほどある 第5回 反誕生日会主義
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- interview with Yui Togashi (downt) 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド | 富樫ユイを突き動かすものとは
- Overmono ──オーヴァーモノによる単独来日公演、東京と大阪で開催
- 『成功したオタク』 -
- 角銅真実 - Contact
- Mars89 ──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作
- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日
- great area - light decline | グレート・エリア
- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも
- Nick Edwards - Plekzationz / Seekersinternational - The Call From Below | ニック・エドワーズ、エコープレックス、シーカーズインターナショナル
- HYPERDUB EPISODE 1 - featuring KODE9 | KING MIDAS SOUND | DVA | HYPE WILLIAMS(Dean Blunt and Inga Copeland) | EntryTitle
Home > Columns > 9月のジャズ- Jazz in September 2023
去る9月6日にジャズ・ベーシストのリチャード・デイヴィスが亡くなった。有名なプレーヤーというわけではなく、どちらかと言えば脇役で光るタイプだった。マイルス・デイヴィス、エルヴィン・ジョーンズなどとの共演で知られるほか、ヴァン・モリソンの『アストラル・ウィークス』、ブルース・スプリングスティーンの『明日なき暴走』、ポール・サイモンの『ひとりごと』など、ジャズを離れてロック方面のアルバムにも参加している。ただ、1970年代には商業的な成功を収めることはなかったものの、とても良質なリーダー・アルバムを〈ミューズ〉に残している。『ザ・フィロソフィー・オブ・ザ・スピリチュアル』(1972年)、『エピストロフィー&ナウズ・ザ・タイム』(1972年)、『ディーリン』(1974年)がそれで、スピリチュアル・ジャズやジャズ・ファンクの観点から再評価されたアルバムだ。

Yussef Dayes
Black Classical Music
Brownswood Recordings
サウス・ロンドンには優れたジャズ・ドラマーが数多いが、そのひとりであるユセフ・デイズのソロ・アルバム『ブラック・クラシカル・ミュージック』がリリースされた。彼のキャリアは2010年代初頭に兄弟のアーマッド、カリームたちと結成したユナイテッド・ヴァイヴレーションズに始まり、テンダーロニアス率いるルビー・ラシュトンへの参加、カマール・ウィリアムズと組んだユセフ・カマールと、サウス・ロンドンのジャズを牽引する動きを見せてきた。2020年にはトム・ミッシュとコラボした『ワット・カインダ・ミュージック』を発表して話題を集める一方、アルファ・ミスト、ビンカー・アンド・モーゼス、スウィンドルなどいろいろなアーティストの作品への参加や共演をおこなっている。リーダー作としてはチャーリー・ステイシー(キーボード)、ロッコ・パラディーノ(ベース)とのトリオ編成のライヴ・アルバム『ウェルカム・トゥ・ザ・ヒルズ』(2021年)があり、ほかにユセフ・デイズ・エクスペリエンスというグループで同じくライブ音源となる『ライヴ・アット・ジョシュア・ツリー』(2022年)があるが、『ブラック・クラシカル・ミュージック』は初めてのスタジオ録音によるリーダー・アルバムとなる。
『ウェルカム・トゥ・ザ・ヒルズ』はトニー・ウィリアムズ張りのテクニカルな演奏を見せるジャズ・ロック路線の作品で、『ライヴ・アット・ジョシュア・ツリー』はサックスを加えたフュージョン調の作品だったが、『ブラック・クラシカル・ミュージック』はよりルーツ色の濃い作品となっている。アルバム・タイトルにあるように、彼のルーツであるカリブやアフロ・キューバン色を感じさせる作品が多く、“アフロ・キューバニズム” というそのものズバリのアフロ・キューバン・ジャズも収録する。タイトル曲も急速調のアフロ・ジャズで、往年のマッコイ・タイナーあたりを彷彿とさせる作品だ。“ジェラート” ほか、ドラムだけでなく種々のパーカッションも組み合わせて有機的で躍動感に富むリズムを作っている点も特徴だ。なお、編成はユセフ・デイズ・トリオを発展させ、そこにシャバカ・ハッチングス、トム・ミッシュなどいろいろなミュージシャンが加わる形となる。
シャバカ・ハッチングスをフィーチャーした “レイジング・アンダー・ザ・サン” はレイドバックしたカリビアン・ジャズ調のナンバーで、トム・ミッシュと共演する “ラスト” は彼らのアルバムの『ワット・カインダ・ミュージック』の延長線上にある作品。“ターコイズ・ギャラクシー” はコズミックな雰囲気を持つエレクトリック・ジャズで、ザ・コメット・イズ・カミングに近い作品。彼の生まれたばかりの赤ん坊の声を乗せたメロウ・フュージョンの “ザ・ライト”、ダンサブルなサンバ・リズムを刻む “チェイシング・ザ・ドラム”、フレットレス・ベースが活躍する南国風のブギー “ジュークボックス”、ジャミラ・バリーのスウィートなヴォーカルをフィーチャーしたメロウ・ソウル “ウーマンズ・タッチ” など様々なタイプの作品が並ぶ。『ブラック・クラシカル・ミュージック』とはユセフ・デイズのルーツを示すと共に、黒人音楽の根底にあるものも指していると思うが、ジャズにしろ、ソウルにしろ、ブギーにしろ、黒人音楽の幅広さや寛容性も感じさせる内容だ。

Matthew Halsall
An Ever Changing View
Gondwana
2000年代後半よりジャズ・トランペッター/作曲家として、〈ゴンドワナ・レコーズ〉主宰者として、マンチェスターのジャズ・シーンを牽引してきたマシュー・ハルソール。リーダー・アルバムやレーベル所属のミュージシャンが結集したゴンドワナ・オーケストラのアルバムなど作品は数多く、『アン・エヴァー・チェンジング・ヴュー』は2020年の『サルート・トゥ・ザ・サン』から3年ぶりの新作。以前レヴューした『イントゥ・フォーエヴァー』(2015年)のときと参加ミュージシャンは幾分入れ替わっていたりするものの、楽曲の傾向や演奏スタイルはさほど変わってはおらず、基本的にはアリス・コルトレーンのように瞑想的で穏やかなスピリチュアル・ジャズや、ジョン・コルトレーン直系のモード・ジャズをやっている。世の中の流行やトレンドなどとは一切無縁で、自身の音楽を愚直に追及するマシュー・ハルソールを改めて示すアルバムだ。
そうした中で今回のアルバムで印象的なのは、カリンバのようなアフリカ発祥の楽器をハープやグロッケンシュピール、チェレスタなどの西洋楽器と絡めて使い、アフリカ音楽と西洋音楽を結び付けるような演奏を見せる点だ。表題曲や “カルダー・シェイプス”、“マウンテンズ、ツリーズ・アンド・シーズ” などがそうで、ハルソールもトランペット以外にカリンバやグロッケンシュピール、チェレスタなどをマルチに演奏している。土着的なフルートやザイロフォン、ハープなどを絡めた “ナチュラル・ムーヴメント” もそうで、アフリカ音楽と西洋のジャズ、そしてミニマル・ミュージックやメディテーション・ミュージックなどの要素も融合したアルバムとなっている。

Khalab
Layers
Hyperjazz
イタリアのDJカラブもアフリカ音楽と縁の深いアーティストで、マリ共和国のシンガー/パーカッション奏者のババ・シソコと共演した『カラブ&ババ』(2015年)や、西アフリカのマリ難民キャンプに避難する音楽家集団と共演した『ムベラ』(2021年)をリリースする。ほかに『ブラック・ノイズ2084』(2018年)というアルバムがあり、こちらもアフリカ音楽の要素はあるが、エレクトロニクスの比重の大きいより実験的なサウンドで、シャバカ・ハッチングス、モーゼス・ボイドらサウス・ロンドンのアーティストと共演している。カラブなりの解釈によるアフロ・フューチャリズムの作品と言えるだろう。
カラブの新作『レイヤーズ』は『ブラック・ノイズ2084』を継承した作品と言える。『ブラック・ノイズ2084』にも参加したトマッソ・カッペラート、クラップ・クラップなどイタリア勢に、ヤズー・アーメッド、タマラ・オズボーン、テンダーロニアス、エマネイティヴなどのイギリス勢が入り混じった編成で、ラッパー/ポエットのジョシュア・イデンハンやシンガーのアレッシア・オビーノなども参加。アレッシア・オビーノの神聖なヴォイスがフィーチャーされた “ドローン・ラー” は、そのタイトル通りサン・ラーの “スペース・イズ・ザ・プレイス” を想起させる不穏なナンバー。重厚なベース音に支配されたダークな “コンシャス・フレンドシップ” はジャズとベース・ミュージックの中間をいくような作品。トライバルな “トンネル・オブ・ジェラシー” はアフロ、ジューク、グライム、ゴムが融合したような世界。クラップ・クラップが参加した “アシッド・ワクチン” は、サンズ・オブ・ケメットのようなホーン・アンサンブルがアシッド・ハウスをやったらというイメージだろうか。テンダーロニアスのフルートが印象的な “ロマンティック・ロコ” は、インダストリアルなビートとアラブからアフリカにかけてのミステリアスなジャズが融合。トマッソ・カッペラートがブロークンビーツ調のドラムを叩く “フィメール・サイド” は、カリンバ風の音色を取り入れるなどカラブが好むアフリカ的なモチーフに彩られる。同じく “メンタル・コーチ” でもカリンバが用いられ、「アフロ・フューチャー・ビート・シェイク」と形容されるカラブの面目躍如たるナンバー。

Kurt Elling And Charlie Hunter
SuperBlue: The Iridescent Spree
Edition
グラミー賞も受賞したアメリカのカート・エリングは、現代における男性ジャズ・シンガーの最高峰に数えられるひとりであり、基本的にはジャズの正統的なヴォーカル・スタイルを継承している。ただし、ギタリストのチャーリー・ハンターと組んだ『スーパーブルー』(2021年)では普段とは異なる一面を見せていた。チャーリー・ハンターとは彼のカルテットの『ソングス・フロム・ザ・アナログ・プレイグラウンド』(2001年)でも共演していて、このアルバムにはモス・デフやノラ・ジョーンズなども参加しているなど、ある意味で現在におけるジャズとヒップホップ、ネオ・ソウル、ファンクなどとの結びつきを先駆けた作品でもあった。そんなエリングとハンターの共演作『スーパーブルー』は、ジャズ・ファンク・バンドのブッチャー・ブラウンのDJハリソンがキーボード、コーリー・フォンヴィルがドラム及び共同プロデューサーを務めていて、言わばブッチャー・ブラウンの演奏でカート・エリングが歌ったと言える。エリングはヴォーカリーズというスキャットを駆使した即興的な歌唱スタイルを得意とするが、ジャズ・ファンク調のナンバーでも見事にそれが生かされていた。ただし、一方的にブッチャー・ブラウンの型に押し込めるのではなく、エリング本来のブルージーな持ち味を生かした楽曲作りもおこなっており、DJハリソンやフォンヴィルのプロデュース能力の高さも垣間見せていた。
その『スーパーブルー』の続編となる『スーパーブルー:ザ・イリディセント・スプリー』がリリースされた。前作と同じくカート・エリング、チャーリー・ハンター、DJハリソン、コーリー・フォンヴィルというラインナップ。オーネット・コールマンのカヴァーの “オンリー・ザ・ロンリー・ウーマン” は、ダブステップを取り入れたようなスペイシーなトラックで、フォンヴィルの小刻みなドラミングに対しエリングのダイナミックで広がりのある歌唱が異色の組み合わせとなっている。ジョニ・ミッチェルのカヴァーの “ブラック・クロウ” はリズミカルなジャズ・ファンク・スタイルで、お得意のスキャットを絡めた即興が光る。“ノット・ヒア/ノット・ナウ” はエディ・ハリスのジャズ・クラシック “フリーダム・ジャズ・ダンス” を彷彿とさせる曲調で、エリングの歌もこの曲に歌詞をつけたエディ・ジェファーソンの歌唱を思い起こさせる。
Profile
 小川充/Mitsuru Ogawa
小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。
COLUMNS
- Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns
♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論
第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2023


 DOMMUNE
DOMMUNE