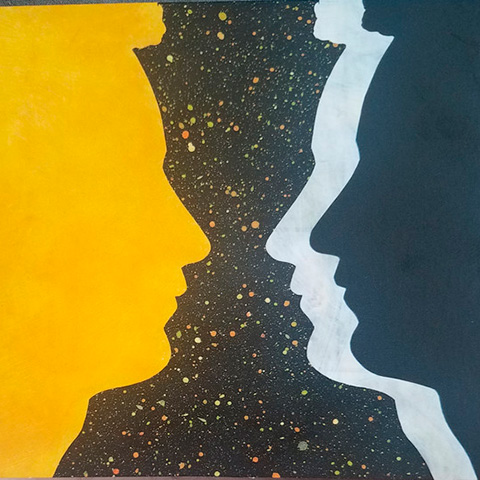MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Tom Misch- Geography
今や若手クリエイターの巣窟となりつつあるサウス・ロンドンでは、例えば日本で言う昨今の東東京リバイバルとも似て、賃料の安さゆえ自然と若者が集りここ数年で急速に活発な音楽シーンが醸成されつつある。一個のシーンとしては未だ確固とした音楽的傾向があるとは言い難いものの、ゴートガールやシェイムといったロック・バンド、またはロイル・カーナーやアミ・ボーイズなどのヒップ・ホップ・アクト、そしてジャズの世界でもプーマ・ブルーやジョー・アーモン・ジョーンズ、ヘンリー・ウーなどといった、ロバート・グラスパーをはじめとするUS勢と呼応するような数多くの新しき才能が揺動している状況だ。それぞれUK伝統のDIY精神を湛えながら、ジャンル越境的で且つインディー~メジャーの区分に割り振れないようなポピュラリティの高いアクトが次々登場しているなか、ここに紹介するトム・ミッシュこそはその圧倒的「ポップ・ミュージック性」から、シーン出身者の中で最大の成功を手にすることになるかもしれない。
2015年に発表されたミックス・テープ“Beat Tape 2”で、若きトラック・メイカーとして注目を集めたトム・ミッシュ。そのミックス・テープでは、いかにもJディラ再評価以降の世代らしく、アンチ・クオンタイズな有機的ビートと、ジョン・メイヤーをアイドルと公言する(その感じも、素直な青年感満点)のも納得の歌心系ギターが融合し、なんとも快楽指数の高い音楽を奏でていたわけだが、今回登場したデビュー・アルバム『ジオグラフィー』では、ジャズの薫りを色濃く湛えながらも、自身のクルーナー・ボーカルを武器にSSW的なポピュラリティの高いソウル世界へ漕ぎ出した。
一聴して、かつてのアシッド・ジャズ~UKソウル、もしくはそれ以前から活動するベン・ワットらに代表されるネオアコを起源とするシンガー・ソングライター像など、80年代から90年代を賑わした音楽との類似性を指摘したくなるわけだが、それにしてもこれは時に赤面してしまうほどに実直なスムース・ポップだ。しかも超ハイ・クオリティの。たしかに先述の通り、ギタープレイにはジョン・メイヤーからの影響色濃いが、それ以上に感じるロニー・ジョーダン的クラブ・ジャズ感。おそらく「あの時代」に青春を過ごした方々にとっては、悶絶モノだろう。しかしここ日本でも、あのサチモスがかつて90年代に青春を過ごした音楽ファンへ郷愁を提供しながらも、むしろバンドと同世代やより若年層から支持を得ていること考えると、これを単にリヴァイヴァルだとかノスタルジーだとかいう言葉で片付けてしまうこともできない……(というか、トム・ミッシュの音楽の魅力を論じようとするとき、そういう言葉で片付けたくなる気持ちをぐっとコラえる必要がある)。
この非常に青々しく爽やかな音楽愛に溢れたトム・ミッシュ氏の内奥に、グログロと渦巻く作家性をなんとか見つけて暴き立てるようなお馴染みのロック精神主義的筆致は当然退けられるべきだろうし、その上、米ラッパーのゴールドリンクや、これまた「あの時代」のレジェンドであるデ・ラ・ソウル、サウス・ロンドン・シーンから先述のロイル・カーナーをフィーチャーしているといった客演情報を挙げていっても、あるいはクルセイダーズの佳曲‘My lady’をサンプリング使用しているとか、ここ10年のディスコ~ブギー・リヴァイヴァルからの影響を指摘できるとか、スティーヴィー・ワンダーの(恥ずかしくなるくらいの)名曲“Isn’t She Lovely”をギターで気持ちよさそうにカヴァーしているといった情報を挙げていっても、なにやらそれは語義通り本当にただ情報を挙げていくだけ以上のことでないように思ってしまうのだった。
常日頃多くの「作家的」音楽について投げかけられているようなオーセンティックな批評言語や、DJ~ディガー的視点をともなった博物学的興味のようなものからするするっと透過し、むしろそれを相対化してしまうような無邪気なセンスと、感嘆すべき手際・仕事の鮮やかさがかえって前景化してくるのだ。
かつて、ネオ・アコースティックから派生しつつブラック・ミュージックへ接近していったようなエブリシング・バット・ザ・ガールといった「歌もの」のアーティストたちも、過去の音楽への歴史的見取り図を少なからず携えていたと思うし、その後のアシッド・ジャズやUKソウル・ムーヴメントは、レア・グルーブ・ムーヴメントや、もっと遡ればノーザン・ソウルやモッズ・カルチャーをルーツとし、いかに享楽的シーンに見えようとも、ハウスやヒップホップをも吸収したUKクラブ文化に継承された諧謔性や批評性というものが(良い悪い別として)潜んでいたとはずだが、明らかにトム・ミッシュによる音楽は、そういった縦軸的な文化継承意識とは浮遊した地点にある。その、衒いなく興味の赴くままに音楽を参照していくような様は、かつてあったような通史的感覚に基づく己のリファレンス・センスの鍛錬によるものというよりも、ここ10年で登場した、例えばジェイムス・ブレイクやキング・クルールといったアーティストと近似性を指摘すべき、先述のサウス・ロンドン・ジャズ・シーンのニュー・アクトたちとも共通する、時制とアーカイヴを自由に行き来する極めてインターネット空間的感性によって培養されているものだろう。
強く「あの時代」を匂わせながらも、これほどまでに摩擦係数の抑制された完成度の高い「ポピュラー音楽」を22歳の多感な若者が作り出したという事実は単純に新時代の技術論的な視点からも驚嘆に値すべきである(FACT Magazineサイト上に彼の曲作りの模様が映像としてアップされているので要チェック。http://www.factmag.com/2018/03/28/tom-misch-clock/)のと同時に、単なるリヴァイヴァリストとして批判されることもなく割合素直にここ日本でも音楽ファンから賞賛されている状況は、多くのリスナーも、作り手トム・ミッシュその人と同様に、もはや通史的な音楽理解から浮遊した地点で日々音楽を摂取しているということを鮮やかに物語っているのかもしれない。
そういった意味でも今、2018年の「ポップ・ミュージック」として、これほどまでに正しいものはないかもしれない。
柴崎祐二
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE