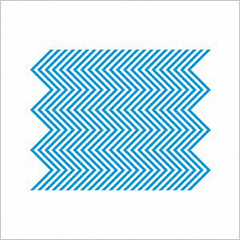MOST READ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm ──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 三田 格
- Beyoncé - Renaissance
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS - きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- KRM & KMRU ──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場
- Beyoncé - Lemonade
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
Home > Reviews > Album Reviews > Pet Shop Boys- Electric
「だから、レインボウ・ステージが必要なんですよ」
フジロックも終わりに近づく3日目の深夜3時、僕は酔っ払って40代のゲイの友人に、日本のフェスでのゲイ・ステージの必要性を説いていた。
「海外のフェスだったらけっこうゲイ・ステージあるじゃないですか。日本で洋楽を含むフェスやるんだったら、その文化も取り込まないと。日本ではゲイ・ポップスなんて皆無に等しいし」
「まあね。世間的にはゲイだと知られてるポップ・シンガーも歌の上ではノンケってことになってるし」
友人は僕のデタラメな思いつきに付き合ってくれている。
「でしょう。だから、マトモスとか、ハンクス・アンド・ヒズ・パンクスとか、ヘラクレス・アンド・ラヴ・アフェアとか、カッコいいゲイのアーティストを呼んで、でもゲイの内輪ノリにならないようにストレートも入りやすいようにして。トリを大物にするとか......わからないけど、カイリー・ミノーグとか」
「いや、カイリーがゲイ・ステージのトリをやる文脈すら、日本には浸透してないよ」
「ええーっ!? そうか。じゃあ、アントニーだったら主旨を伝えればやってくれるかも。でも賑やかな感じも欲しいから、ベタだけどミーカとか、シザー・シスターズとか、それかペッ......」
ペット・ショップ・ボーイズ、と言おうとして、僕は口が止まってしまった。ペット・ショップ・ボーイズは、レインボウ・ステージのトリをやってくれるだろうか?
というのは、ペット・ショップ・ボーイズは自らのゲイ性(と、ここでは呼ぼう)をいつも高らかに謳っていたわけではなかったからだ。いや、どちらかと言えばそこに何かしらの批評を用意している例が多かったように思う。たとえばニール・テナントが大っぴらにカミングアウトする以前の"キャン・ユー・フォーギヴ・ハー?"では、ロックが嫌いでディスコが好きなことを女にからかわれる男のことが歌われているが、もちろんこれは性的嗜好を隠して女と付き合って失敗するゲイについての歌だ。もっと言えば、「異性愛の」セックスに失敗する屈辱についてだろう。ゲイにとってこういった話はよく聞くところではあるが、かと言ってそれをポップ・ソングにしてしまうことはそうあることではない。「みんな違って、みんないい」みたいながんばれソングになりがちなゲイ・ポップス界において、PSBの知性は異色であった。それこそある程度の「文脈」を理解していないと本当の意味で楽しめないものも多く、そのゾーニング自体が、ゲイが社会においていくつもの顔や隠語を用意しておかなければならない状況に対する痛烈なアイロニーのようだ。ヴィレッジ・ピープルによる同性愛賛歌"ゴー・ウェスト"のカヴァーがサッカーの応援歌としてマッチョな連中に無自覚に歌われることを嫌がるゲイも少なくないが、逆に言えばそのねじれた状況にほくそ笑むことだって、ある意味ではできるわけである。
では、ペット・ショップ・ボーイズのエレポップは「文脈」を楽しめるひとたちだけのものなのだろうか?
『エレクトリック』はPSBの久しぶりの快作で、とにかくアッパーなナンバーが揃っている。しかも簡潔。9曲という比較的少ない曲数を、ハウス・ビートとシンセ・サウンドで一気に聞かせてしまう。PSBは何にアッパーになっているのだろうか。イギリスでの同性婚合法化に? UKでのハウスな気分に? たんに内省的だった前作『エリシオン』の反動? わからないが、テンションとして近いのは『ナイトライフ』(99)辺りか。つまり、音としてはゲイ・ポップスの度数がとても高い快楽的なアルバムである。
とにかく、煌びやかなピアノの和音のリフと、得意のゴージャスなストリングス・ワーク、そしてフワフワしたニールのヴォーカルを聴くと、ああPSBだ! と思う。いきなり攻撃的な"アクシス"でのオープニングに驚いている場合ではない。"ラヴ・イズ・ア・ブルジョワ・コンストラクト"なんて"ニューヨーク・シティ・ボーイズ"と"ゴー・ウェスト"を掛け合わせたような臆面もなくキャッチーなナンバーだし、"シャウティング・イン・ジ・イヴニング"のトランスめいたアップリフティングさには腰を抜かしそうになる。
その"ラヴ・イズ・ブルジョワ・コンストラクト"は格差社会における無力感と愛の欠如が重ねて歌われる、いかにもPSBなややこしさが孕まれたナンバーだが、アルバムには彼らならではの皮肉めいたスパイスも用意されてはいる。なかでも"ラスト・トゥ・ダイ"はなんとブルース・スプリングスティーン『マジック』収録曲のカヴァー。ここでは汗と大地の匂いがする男の怒りが、ミラーボールの下のダンスに読み替えられていて、そこには多くのポリティカル・ソングのマッチョさへの批評を見て取ることもできるかもしれない。かつてU2の"ホェア・ザ・ストリーツ・ハヴ・ノー・ネーム"のカヴァーをやって、見事にその男臭さを消していたこと(と、U2がそのカヴァーを聴いて怒ったこと)を思い出すひとも多いだろう。
けれども、アルバムは......PSBは、それ以上にこの音を前にした者を分け隔てなく踊らせることを欲望している。全編を通してきわめてダンサブルだが、ラスト2曲が本作をよく表している。まず"サースデイ"はタイトル通り、週末がまだ訪れていない木曜日についての歌だ。ハウシーなイントロがウィークエンドへの期待をどこまでも高めていく。新しくもなくトレンドでもない音だが、クールとアンクール、インとアウトの境界がここでは消えていく。そして、歌詞もヴィデオも衒いなく古きよきレイヴを謳う"ヴォーカル"。20年前にタイムスリップすることを、この曲は少しも恥ずかしがらない。その高揚において。
だから僕は、いまのPSBにはレインボウ・ステージにぜひ立ってほしいと思うのだ。そこには男も女も、もちろんそうでないひともたくさんいる。「文脈」を知るひとも知らないひとも、等しく踊っている。たくさんのキスとハグがある。レインボウ・フラッグがゲイとストレートを、マイノリティとマジョリティを分断するものであってはならない。ロックよりもディスコで踊りたい気分のストレートが、ダンスフロアで開放されてもいいのだ。「今夜は全てが正しく、すごく若々しい/ぶちまけたかったこと全てが高らかに歌になる("ヴォーカル")」
木津 毅
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE