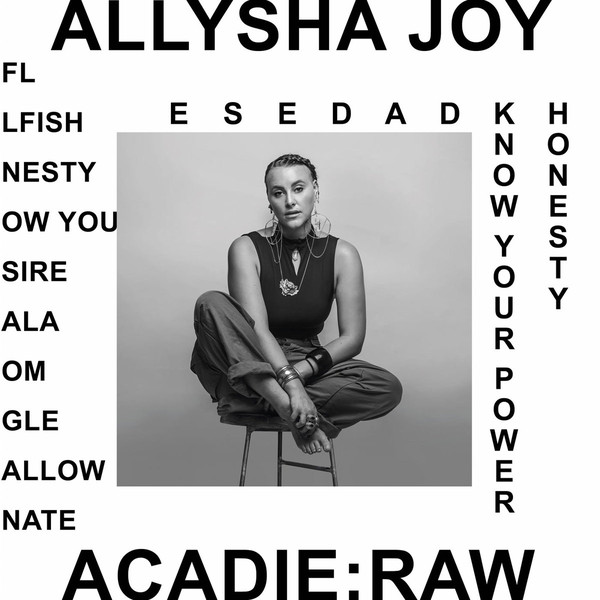MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Interviews > interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作
クラブ・カルチャーは無限に広がり、刺激的で、何でもできるように思えました。とても先進的でクリエイティヴな「ストリート・カルチャー」がそこにありました。労働者階級の子どもたちがただ音楽を作ろうとしていた、とても重要な時代でした。
マシュー・ハルソールが主宰する〈ゴンドワナ〉は、マシュー自身や彼が率いるゴンドワナ・オーケストラはじめ、ゴーゴー・ペンギン、ナット・バーチャル、ママル・ハンズなど注目すべきアーティストを多く輩出してきたジャズ・レーベルだ。そんな〈ゴンドワナ〉から2022年に『Cloud 10』というアルバムを発表したサックス/フルート奏者のチップ・ウィッカム。それ以前からスペインの〈ラヴモンク〉から数枚のアルバムをリリースしてきた注目のアーティストであり、遡ればファーサイド、ニュー・マスターサウンズ、ナイトメアズ・オン・ワックスなど幅広いアーティストの作品に参加し、クラブ・ミュージック・シーンにも深く関わってきた人物でもある。
彼の作るジャズは、1950年代から1960年代に花開いたモダン・ジャズを土台としており、その中でも特にモード・ジャズの影響が色濃い。また、ラテン・ジャズやアフロ・キューバン・ジャズの要素も漂わせるのが特徴で、フルート、ハープ、ヴィブラフォン、パーカッションを絡めたエキゾティックな音色が印象に残る。カマシ・ワシントンやシャバカ・ハッチングスたちとはまた異なるタイプのディープでスピリチュアルなサウンドだ。そんなチップ・ウィッカムの『Cloud 10』とEPの「Love & Life」、そして未発表の新曲をまとめた『Cloud 10 – The Complete Sessions』がリリースとなる。彼にとって本邦初登場作品となるこちらは、その音楽の魅力を余すところなく伝えてくれるものであり、リリースに併せて彼のインタヴューをお伝えする。
チップ・ウィッカム、FUJIROCK FESTIVAL'24 出演決定!
https://www.fujirockfestival.com/
音楽家であるには一貫した信念を持っている必要があるし、自分の仕事に対してもとても謙虚である必要がある。ある時点に到達して、よし、できた、となることはできない。一生が勉強。
■まず、あなたのプロフィールから伺います。ブライトン出身のあなたは、チップ・ウィッカムの前は本名のロジャー・ウィッカムで1990年代より活動しており、またキッド・コスタという変名でマレーナというラテン・ハウス・プロジェクトで活動していた時期もあったりと、かなり長いキャリアをお持ちですね。どのようにしてジャズと出会い、サックスやフルートを始めたのですか?
チップ・ウィッカム(以下CW):父がジャズの素敵なレコード・コレクションを持っていて、子どもの頃、家にはいつもたくさんの音楽があったんです。父には感謝していますね。ラッキーなことに、私はその中から気に入った古いレコードを見つけ出して、まだ子どもだっていうのにソニー・ロリンズの『The Bridge』や、スタン・ゲッツとジェリー・マリガンの共演アルバムをよく聴いていました。全部覚えていますよ。コンテ・カンドリ・オール・スターズのアルバムも持っていましたし、ヴィンス・ガラルディが書いた一連のチャーリー・ブラウンのTVシリーズのアルバムとか、おもに1960年代のウェスト・コースト・ジャズが多かったですね。それから何年かして、私がジャズにのめり込んでいることに気づいた父は、ジョン・コルトレーンのイギリス公演を見たときのことを話してくれました。父はソウルとかファンクとか、クレイジーなイギリスのレコードもたくさん持っていて、ジャズはそうしたものの一部でした。ジョニー・ハリスの『Movements』も持っていて、ああ、なんて素晴らしいレコードが眠っているんだろうと思いましたよ。ジャケットは奇妙な三重露光のような写真で、子どもの私は最初ちょっと怖かったんですが、少し後に名盤だということに気づいたんですね。ほかにもアレサ・フランクリンやホセ・フェリシアーノとか、いろんな面白いレコードを聴きましたね。こうして私は父のジャズ・レコード・コレクションにのめり込んでいったんです。それからずっとずっとレコードを聴き続けて、ジャズはいつも私の生活の一部になりました。そして、サックスはジャズでよく使われる楽器だから、自然とその演奏を聴くようになり、その流れで楽器を弾き始めました。
いまでも、なぜサックスを選んだのかはよく覚えていません。音楽が本当に好きで、小さい頃は最初にハーモニカを吹いていたことは覚えています。ブルースも聴いていて、ハーモニカを吹いていたんですよね。すべての音が揃っているわけではないし、キーごとに違うハーモニカが必要なんですが、私はそれを楽しんでいたし、サニー・ボーイ・ウィリアムソンやサニー・テリー、そしてブラウニー・マギーといった人たちの曲を聴くのが好きでした。こうして、もっと普通の音域の楽器を弾きたくなっていきました。なぜそれがサックスだったのかはよく覚えていないけれど、とにかくサックスだったのです。私がずっと音楽を聴いて、楽器を演奏しようとしているのを見た母がテナー・サックスを買ってくれました。それ以来、一度もこの楽器を手放したことはありません。
■サックスを吹き始めたのはティーン・エイジャーの頃ですか?
CW:10代前半の頃ですね。私が通っていたのは、特に音楽が盛んな学校ではありませんでした。当時、私の多くの興味は学校の外にありました。だから、16、17歳になってから、地元のブライトンでジャズのワークショップみたいなものに通い始めました。そこでジュリア・ニコラスという素晴らしい先生がワークショップをやっていました。当時彼は結構若かったと思うんだけど、チャールズ・ミンガスの曲とかを演奏するワークショップでした。ミンガスの曲をやれるなんて、本当にすごいとめちゃくちゃ感動したのを覚えています。まるで恋に落ちたような気分でした。
■その後マンチェスターの音楽学校に進学したそうですが、そこでは誰かに師事したのですか?
CW:マンチェスターの大学に行って、フィル・チャップマンという先生に個人レッスンを受けました。彼は私と同じブライトン出身でしたが、当時リーズに住んでいました。英国でジャズを専門的に学べる場所はリーズ音楽大学とギルドホール音楽演劇学校だけなのですが、彼はリーズ音楽大学のサックス主任講師をしていました。ブライトンの誰かが私に、この人に話を聞きに行きなさいと言ってくれたんですよね。フィルは私にとって父親みたいな存在の素晴らしい人でした。古いスタンリー・タレンタインのレコードやジョン・コルトレーンのレコードもよく貸してくれました。だけど、入門した当初の私は、彼が一体誰なのか、どれだけ優秀な人なのか、半年くらい経つまで気づかなかったんです……。
レッスンでは最初彼が私に「演奏してみなさい」と言い、私は何かを弾く。そして彼がお手本を示しながら演奏するといった具合でした。当時私は18、19歳でしたが、彼はただ首を横に振って「いや、こう立って、手をここに置いて、こうするんだ」と言って、小さなことでも全部直してくれました。それまで私はなんとなく独学で勉強はしていたけれど、演奏の深いところまでは学んでいなかったんですよね。フィルは本当に深く、あらゆることを教えてくれました。とても情熱的で、エネルギッシュで、私の演奏に対するちょっと散漫なアプローチを成長へと導くその手腕は素晴らしいものでした。彼はときどき私を見て「君の年齢だったらもう少し上手く弾けてるはず」と叱咤激励しました。私はそれまでそんなことを言われたことはなかったし、自分はこの年齢でサックスを吹いている人たちのなかでは世界一だと思っていたから……。彼は私のような年頃の若造にどう話しかければいいか知っていたんです。彼は私に「趣味でやるだけならいまのままで大丈夫だよ」と言ってくれました。でも、同時に彼は私の本心をすぐに読み取り、やる気を起こさせる方法を知っていました。私にミュージシャンとしての努力やモチベーション、日々の生活について、たくさんのことを教えてくれました。音楽家であるには一貫した信念を持っている必要があるし、自分の仕事に対してもとても謙虚である必要がある。ある時点に到達して、よし、できた、となることはできない。一生が勉強。けっして立ち止まってはいけないということを教えてくれましたね。つねに学ぶことを止めない……本当にその通りですね。上達すればするほど、必ず自分より優れた人が現れるわけですから。でも、そんなことは気にせずに、競争相手は自分自身であって他人ではないという、人間として役立つことを、そして私のキャリアにも役立つことをたくさん教えてくれたのです。
■その後プロ・ミュージシャンとなり、1990年代から2000年代はファーサイドからニュー・マスターサウンズ、ナイトメアズ・オン・ワックスなど幅広いアーティストの作品に参加しています。主にクラブ・ミュージック系のアーティストが多いわけですが、こうした分野のセッションに参加するようになったのはどんないきさつからですか?
CW:90年代のマンチェスターはとても豊かなシーンだったと思います。当時はトリップホップと呼ばれていたサンプリング・ミュージックがたくさんありました。80年代後半から90年代前半にかけてはクラブ・カルチャーがとても盛んで、マンチェスターにはハシエンダがあり、ストーン・ローゼズやハッピー・マンデーズなどがいて、クラブ・カルチャーが大爆発していました。だから誰もが、とくにそういう音楽をやっていたわけではなくても、サンプリングという行為に夢中だったのです。クラブ・カルチャーは無限に広がり、刺激的で、何でもできるように思えました。当時はヒップホップとジャズをミックスするというのも流行ってましたね。私が初めて大きな仕事をしたのは、ヒップホップ・レーベルとして大きな影響力を持つ〈グランド・セントラル〉を運営していたレイ&クリスチャンのレコーディングでした。ヒップホップのレコードでしたけど、ジャジーでよりトリップホップ的な作品でしたね。〈グランド・セントラル〉ではエイム(AIM)というアーティストとも仕事をしました。キャリア初期のころの私は、面白いDJタイプのプロデューサーたちに囲まれていたから、音楽は必ずしもミュージシャンが作るものではないことがわかりました。いいアイデアさえあれば音楽を作ることができたのです。もちろんテクノロジーのおかげでもあって、AKAIのサンプラーやMPCをみんなが持っていて、家でその小さなボタンを叩いていました。
初期のドラムンベースにものめり込みましたね。いまはディープ・ハウスの分野で第一人者となっているジンプスターとも一緒に演奏しました。その頃の彼はジャジーなドラムンベースの若手プロデューサーだったんです。1997年にベルリンのジャズ・フェスティヴァルに彼と一緒に出演したのですが、サンプラーやエフェクト、エレクトロニクスなどを使ってドラムンベースを生演奏しました。当時はみんなが音作りを楽しんでいて、文化がとてもオープンでしたから、そこから刺激を受けやすかったです。とても先進的でクリエイティヴな「ストリート・カルチャー」がそこにありました。労働者階級の子どもたちがただ音楽を作ろうとしていた、とても重要な時代でした。
私はレイ&クリスチャンのライヴ・バンドでも演奏していたのですが、そのバンドはみなが音楽クリエイターでした。それぞれがプロジェクトを持っていて、彼らはクールなことをすることしか考えていなくて、何でも取り入れて、何でも使って、何でも組み合わせる。限界なんてない。それは素晴らしくクリエイティヴで、本来の意味で芸術的なものでした。私が過ごした90年代半ばから後半にかけては、自分の好きなものを見つけるには絶好の時期でした。だから、ストレート・アヘッドなジャズはあまりやらなかったけど、バーでDJがターンテーブルやサンプラーを扱う横で一緒に演奏したり、サックスやフルートにエフェクトをかけて演奏したり、そういうことをたくさんしていました。そんなとき私は即興で演奏をして、DJも即興でスクラッチしたり、サンプリングしたループを入れたり出したりしていました。それは私にとって、週末にカルテットで演奏するのと同じように、ジャズ的なものでしたね。だから、スタイルに大きな違いはないと思っていました。私のプロデュース・スタイルや音楽の多くにはクラブっぽい要素もあって、それがいま役立っていると思います。実際にはサンプリングされていなくても、つまりミュージシャンが実際に演奏していても、少しカット&ペーストしたようなサウンドが好きなんです。当時のヒップホップやトリップホップ、ドラムンベースの人たちがいつも持っていたようなパターンやアイデアですね。繰り返される小さなループで構成されていて、それがいつも本当に楽しいと思っていました。私の初期の作品の多くには明確にそのようなサウンドがあるように思います。ほとんどトランシーで反復的なビート。私たちがビートと呼ぶ、深い深いグルーヴのようなものです。

サックス奏者は何百万人もいるけれど、フルート奏者はもっと少ない。フルートの世界を探求するのはとても楽しいことだといつも感じています。ある意味、あまり開拓されていない領域のようにも思えますね。
■初めてのリーダー・アルバムは2017年にスペインの〈ラヴモンク〉からリリースされた『La Sombra』です。スペインのミュージシャンが多く参加していて、録音もスペインかと思うのですが、いつ頃からスペインに住むようになったのですか?
CW:スペインに移住したのは、2007年の年末。妻がスペイン人なので、子どもたちにもスペイン語やスペイン文化に触れさせたかったことが理由です。それとアーティストとして、自分が携わっているプロジェクトが一定の到達点に達したと感じていた、という理由もあります。ナイトメアズ・オン・ワックスのようにポップでハイレベルな相手と仕事もたくさんしましたし、バッドリー・ドローン・ボーイとツアーをしたりと、世界中を旅しました。〈ラヴモンク〉のレーベル・マネージャーのボルハ・トーレスは、私がマドリードで最初に知り合ったひとりで、彼はDJでもありました。彼はいつも私に興味を持ってくれて、マドリードで活動を始めたばかりの頃、遊び半分で彼とシングルを何枚か出しました。そして、私にアルバムを作るようにと勧めてくれたのも彼でした。私はニュー・マスターサウンズをはじめセッション・プレイヤーとして仕事をしたり、ガイ・リッチーの映画『Snatch』(2000年)でターキッシュというキャラクターのフルート演奏を担当するなど、いろいろなことをやりました。ボルハはそんな私の活動や作曲をすることを知っていたので、自分の音楽を作ることを勧めてくれました。私はそれまでいつもほかの人のプロジェクトやバンドのために曲を書いていましたが、100%自分の仕事をするということにコミットしたことはありませんでした。つまり、彼は私を自分自身の音楽を作るアーティストの道へと押しやってくれた最初の人で、これは本当にありがたいことです。
それがアルバム『La Sombra』につながっていきます。『La Sombra』とは、スペイン語で日陰や影という意味。あのアルバムのポイントは、私が誰かほかの人の影のなかにいることをやめて、セッション・プレイヤーであることをやめて、アーティストとして自分自身に光があたる場所へと出ていく、ということでした。だからとても象徴的なタイトルだと感じています。私は、『La Sombra』を自分のために書いたオリジナル曲で構成した一枚のアルバムにしたかった。アルバム制作をするにあたり、レーベルが口を出すことなく自由にさせてくれたので、いい曲を何曲も書くことができました。しかし、このアルバムはスペインでスペイン人のミュージシャンとレコーディングし、タイトルもスペイン語なのに、皮肉なことにイギリスでヒットしたんです。スペインのミュージシャンを使ってアルバムを作り、スペインのマーケットで自分の地位を確立しようというのが私のプランでしたが、そんなに単純なものではありませんでした。ということでツアーでイギリスに戻ったのですが、それはそれで素敵なことで、不満ではありません。スペインのミュージシャンと演奏しても、あのアルバムには私の歴史が組み込まれているから、どうしてもイギリスらしさが出てしまうんですよね。
■『La Sombra』はアルバム・タイトルからしてそうですが、ラテン・ジャズの要素が強い作品です。それは現在までのあなたの作品にずっと共通する要素で、またヴィブラフォンやパーカッションを混ぜた編成もラテン・ジャズに即したものと言えます。あなた自身はイギリス人で特にラテン系の血筋ではないのですが、どうしてラテン音楽に傾倒していったのですか?
CW:スペインに移住する前、イギリスにいたときからラテン音楽を頻繁に演奏していました。サンバやバトゥカーダのようなブラジル音楽をフルートとサックスで演奏することが、私の初めてのプロとしての仕事だったんですよ。サルサ・バンドやグルーポ・エックスのようなブラジリアン・バンドでもたくさん演奏しました。私はフルートもサックスも吹くことができるので、サルサ・バンドのホーン・セクションで演奏する仕事がたくさんきたんですよね。なのでサルサやラテン音楽はよく聴いていましたし、イギリスにいたときはそのラテン音楽のシーンで積極的に活動していたんですよ。でも、スペインに行ってスペイン語を話せるようになったことはよかったのですが、皮肉なことにマドリードでは、イギリスにいたころよりもサルサを演奏する機会は意外と少なかったです。
たしかに私のどのレコードにもラテンやラテン・ジャズ的な要素は入っていますが、いつもそれほど目立たないように隠し味的に入れています。毎回同じテイストにはならないように。でも、私にとってそれは不変のものなんです。私はフルート奏者ですが、フルートをフィーチャーした素晴らしいラテン音楽がたくさんあるんです。繰り返しになりますが、フルートを聴かずにはいられないし、ラテン音楽を聴かずにはいられません。キューバやブラジルには偉大なフルート奏者がたくさんいて、私は彼らを本当に尊敬しています。だからフルートはつねに私の作曲や演奏に入り込んでくるし、そろそろ本格的なアフロ・キューバンのアルバムを作ってもいいんじゃないかと思うくらいです。
質問・序文:小川充(2024年4月03日)
| 12 |
Profile
 小川充/Mitsuru Ogawa
小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。
INTERVIEWS
- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー
- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー
- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ
- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー
- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム
- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る
- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック
- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について


 DOMMUNE
DOMMUNE