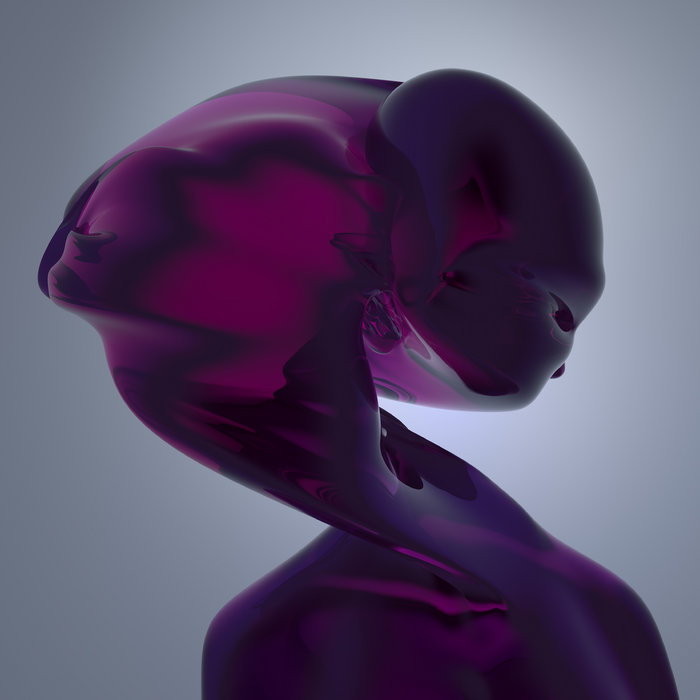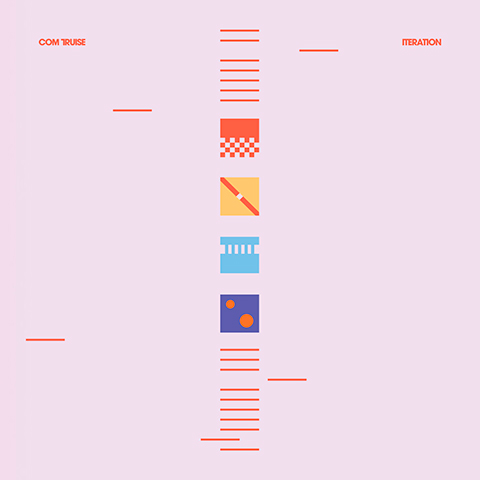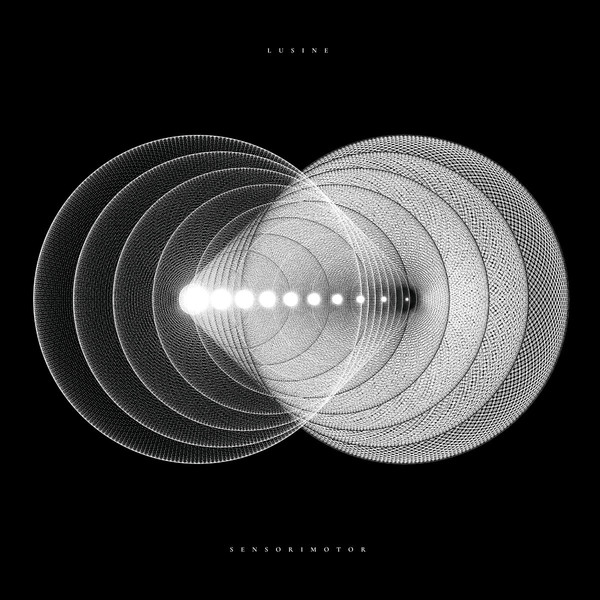MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Reviews > Album Reviews > Whatever The Weather- Whatever The Weather

新名義は日本語に訳すと「どんな天気であれ」。曲名はすべて摂氏。アンビエント作品にとりくむにあたり、天気や気温をテーマに選んだ時点でロレイン・ジェイムズに勝機はあったのだろう。なぜならそれらは、つねにわれわれの生活を「とりまい」ているものだからだ。例外はない。どんな場所に住んでいようと、どんな階級・人種・性であろうと、天候はわれわれの「周囲」にあり、その影響を否応なくわれわれは受ける。
新作でマスタリングを担当しているテレフォン・テル・アヴィヴ(やむをえないとはいえ、昨晩の来日公演中止は残念でした……)やバスなどのエレクトロニカ、あるいは mouse on the keys や toe といった遠い東洋のマスロックに惚れこんだロレイン・ジェイムズは、それらとはべつのところにいると思われているグライムや、リベラルの良識派から嫌忌されるドリルのストリート感覚さえもとりこんで、90年代エレクトロニカのスタイルをアップデイトしてきた。われわれはすでに2枚のクラシック、『For You And I』と『Reflection』を知っている。 全盛期の〈Warp〉なら間違いなく、なにを差し置いてでも契約していたアーティストだろう。
ファースト・アルバムの高層公営住宅の風景は、彼女がどこから来たのかを物語っている。二枚重ねの写真が指し示すそれは、彼女がけっして余裕があるとはいえない経済状況のなかDIYで音楽をつくりはじめた場所であり、その後ジェントリフィケイションによってコミュニティごと破壊されようとしていた場所だ。
郊外の公営団地に育ち、ラップをはじめる──のではない。彼女はIDMを愛し、それをわが音楽とした。文化的な観点からも、彼女の存在は因習打破的だ。労働者階級出身の黒人クィア女性が紡ぐ電子音は、天候が人間にとっての環境であるように、IDMやアンビエントが白人だけのものではないことを控えめながら、しかし強く主張している。
アンビエントといっても、新作を構成する4割くらいはビートを持った楽曲である。ドリルンベースの “17°C” は、90年代後半以降のエイフェックス•ツインやスクエアプッシャーへの愛を惜しみなく披露している。“0°C” におけるもの憂げなメロディとマシナリーなドラムの組み合わせは、もろにAIシリーズを想起させる。それだけだと懐古的に映るかもしれないが、ジェイムズ本人が歌う “4°C” や “30°C” では、声の響きとビート両面における現代的な冒険が繰り広げられている。かつて心酔した音楽へのリスペクトと、未知を探求する好奇心。
ノンビートの曲はどれもうっとりするほど美しい。アートワークどおりひんやりした空気を漂わせつつ、不思議なぬくもりをまとってもいる。どこかジャズっぽいコードのおかげかもしれない。寒くもなく、暑くもなく、夢見心地でありながら現実逃避的にはなりすぎず、うまく日常に寄り添いもするサウンド。前2作にあったラップがないかわりに、本盤は極上の心地良さを搭載している。『AMBIENT definitive 増補改訂版』が「2022年」のページで大枠に選出しているのもむべなるかな、今年上半期におけるエレクトロニック・ミュージックのクライマックスがここにある。
かつてイーノが「周囲の」とか「とりまく」といった意味のことばを初めて自作に冠したのが1978年。14年後、ビートのある音楽をもってそれを書き換えたのがエイフェックス•ツインだった。両者にないバックグラウンドを持つロレイン・ジェイムズは、その固有の感性で先人たちの試みを更新している。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE