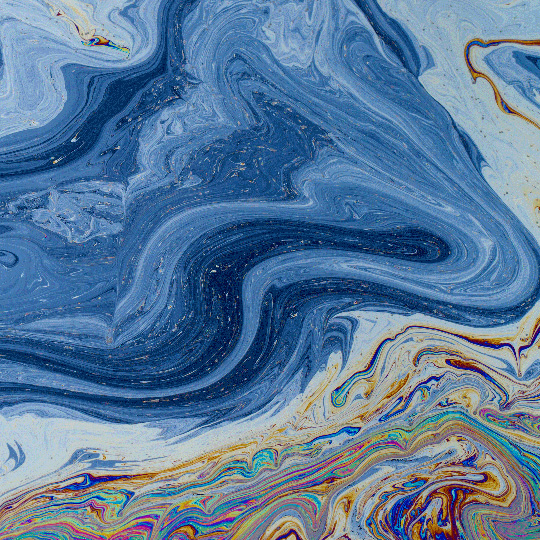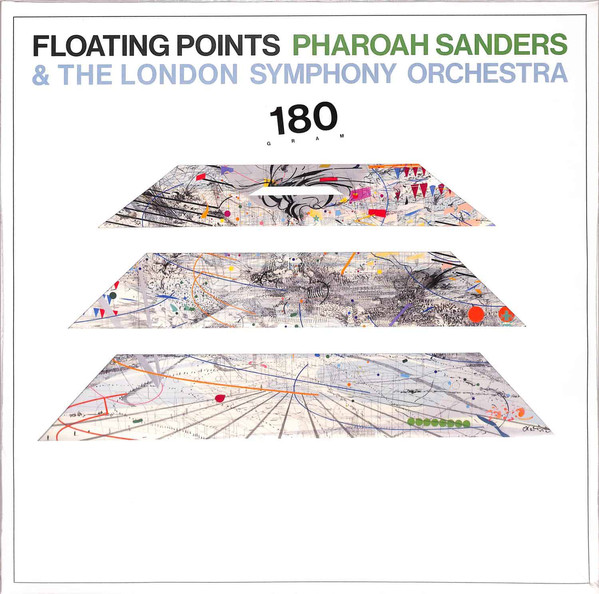MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Interviews > interview with Floating Points - ストリングスと怒りと希望のテクノ
interview with Floating Points
ストリングスと怒りと希望のテクノ
──フローティング・ポインツ、インタヴュー
通訳:エイミー藤木 photo:Dan Medhurst Oct 18,2019 UP
まず弦の響きに驚く。やがて極小の電子音が静かに乱入してくる。終盤、両者は混じり合い、高速スピッカートなのかエレクトロニクスなのか判然としない音の粒子が烈しく舞い乱れる。冒頭の“Falaise”が高らかに宣言しているように、弦(と管)がこのアルバムのひとつの個性になっていることは疑いない。ストリングスは4曲目“Requiem for CS70 and Strings”や10曲目“Sea-Watch”でも効果的に活用されており、そういう意味ではフローティング・ポインツによる4年ぶりのこのアルバムは、昨今のモダン・クラシカルの文脈から捉え返すことも可能だろう。
が。やはり、それ以上にわれわれを惹きつけるのは、そのエレクトロニックかつダンサブルな側面だ。2曲目“Last Bloom”のエレクトロ、3曲目“Anasickmodular”や7曲目“Bias”におけるダブステップ~ジャングルの再召喚、そして先行シングルとなった“LesAlpx”の4つ打ちなんかを耳にすれば、いやでも身体を揺らさずにはいられない。他方で8曲目“Environments”の音の響かせ方はある時期のエイフェックスを想起させるし、穏やかな“Karakul”や“Birth”では細やかな実験が展開されている。サム・シェパードの雑食性が見事に花開いたアルバムと言えるが、ようするに、テクノなのだ。
デビューから6年ものときを経て届けられたファースト・アルバム『Elaenia』(2015)によって、クラブ系以外のリスナーにまでその名を轟かせることになったフローティング・ポインツは、新たなファンの期待に応えるかのようにバンドを結成し、「Kuiper」(2016)や『Reflections』(2017)でロック的なアプローチを追究していったわけだけれど、ここにきて彼はふたたびダブステップやテクノの躍動と、実験に立ち戻っている。何か大きな心境の変化でもあったのだろうか?
本作でもうひとつ注目しておくべきなのは、そのテーマだろう。たとえば“Environments”はリテラルに「環境」を意味しているが、「僕にとって、『Crush』は、じわじわと僕らを蝕んでいく破壊行為を想起させる」と、サム・シェパードはプレスリリースで語っている。「つまり、利己主義に凝り固まった政治的権力闘争、気候変動、抑圧された思想や人びとといった圧倒的に不可避な物事──日常的に僕らが怒りを覚えているこうしたすべてのことにたいし、無力だと感じてしまうような」。
フローティング・ポインツがポリティカルな要素を直接的に作品とリンクさせたのは、おそらく今回が初めてだろう。プラッドがそうだったように、シェパード青年もまたこの暗黒の社会のなかで怒りに打ち震えている。その怒りが生み出した、しかしあまりに美しい音楽に、わたしたちは耳をすまさなければならない。(小林拓音)
今回、デジタルじゃなくて本物の楽器が使いたかったんだよね。本物の楽器を使って、その音をデジタルの楽器であるかのように扱いたかったんだ。僕からしたら同じなんだ。だから、このアルバムの曲の根本はぜんぶストリングスなんだよ。
■今回ヴァイオリンやヴィオラ、チェロを入れようと思ったのは?
サム・シェパード(Sam Shepherd、以下SS):じつはヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、クラリネット、フルート、バスクラリネットとフレンチホルンを使ってるんだ。僕は1日じゅうストリングスを聴いていられるほどストリングスが大好きなんだ。天国の音に聴こえるんだよね。でも木管楽器って忘れられがちな気がするんだ。とくに僕自身が忘れてたりすることが多いんだけどね(笑)。トーク・トークのフロントマンのマーク・ホリスのアルバムに木管楽器の音がたくさん使われていて、僕自身はそのアルバムの曲のアレンジはそこまで好きだとは言い切れないんだけど、サウンドは大好きなんだ。すごくオリジナルで美しい音だったから僕もいつか自分の曲でそういう音を使ってみたいなと思ったんだ。
■ローラ・カネルはご存じですか?
SS:知らないなぁ……名前のスペルは? 聴いてみるよ。
■いまはエレクトロニック・ミュージック全盛の時代ですが、そういうヴァイオリンのようなストリングスの音が逆に求められているのかなという気もしていて。どう思います?
SS:僕は今回、デジタルじゃなくて本物の楽器が使いたかったんだよね。本物の楽器を使って、その音をデジタルの楽器であるかのように扱いたかったんだ。僕からしたら同じなんだ。1曲目はストリングスや木管楽器がふつうにスピーカーから鳴っていて、そこからブクラ(Buchla:モジュラー・シンセサイザー。かなり特定されたもの)に通して、リブートして、音を細かく切って、その切った音をデジタルな音として扱ったんだ。
■エレクトロニクスとストリングスの融合が今回のテーマだった?
SS:まったくそのとおりだよ。
■冒頭“Falaise”の最後のほうで鳴っているシンセはヴァイオリンのようで、まさに両者の区分が融解しているように聞こえます。
SS:モジュラー・シンセサイザーはすごくテクニカルなんだ。ほんとうはオシレイター(oscillator)っていう、シンセサイザーの音のもとになる波形をつくり出す発振器でベーシックな音をつくるんだ。そのベーシックな音をプロセシして、音楽的な音にするんだけど、今回はオシレイターの代わりにヴァイオリンを使ったんだよね。まるでヴァイオリンがこのデジタル機材の一部であるかのように扱った。だから、このアルバムの曲の根本はぜんぶストリングスなんだよ。機械でプロセスして、フェイドインさせたり、フェイドアウトさせたりしているストリングスの音なんだ。「プロセスする」っていうのは、フィルターに通したり、パンを振ったりしてるってことね。サラウンド・サウンドなんだ。
■現代音楽、クラシカルはよく聴いていたんですか?
SS:クラシカルしか聴いてなかったね。エレクトロニック・ミュージックやジャズやソウルを聴きはじめたのは14歳か15歳のときだったかな。目覚めるのが遅かったんだ。僕がそのとき聴いてたエレクトロニック・ミュージックはカールハインツ・シュトックハウゼンとかモートン・サボトニックのようなクラシカル・エレクトロニック・ミュージックで、カール・クレイグとかそっち系ではなかったんだ。
■ダブステップやジャングル的なリズムの曲もありつつ、全体としてはテクノのトーンで、それが見事にストリングスと合体している──今回こういうアルバムにしようと思ったのはなぜですか? 少し前まではバンド・サウンドを追求していましたよね?
SS:『Elaenia』はエレクトロニックだったんだけど、バンド・サウンドになるポテンシャルがすごくあるアルバムだったんだ。ギターやドラムの音も入っててね。だからバンドにしたんだ。アルバムを聴いたときに「バンドとしてできる!」って思ったんだよね。バンドとして世界中をツアーでまわって、よりバンドっぽくなっていって、つねにライヴしてたんだ。毎日毎日ライヴ、ライヴ、ライヴ……。それで僕ら、いや、僕の音が変わったんだよね。サイケデリック・ロック・バンドのサウンドになってしまったんだ。そのツアーが2017年のコーチェラで終わって、僕は自分のスタジオに戻ってふたたび音楽をつくりはじめた。でも、もうこのときはバンドとしてっていうのは終わったので、ひとりで帰って、ひとりでつくりはじめたんだ。べつにバンドに飽きたわけじゃなくて、ちがうことをやりはじめただけなんだよね。『Elaenia』の前はテクノっぽい感じの音楽をずっとやってたし、『Elaenia』はちょっとしたバンド・フェイズだったってだけなんだ。ツアー終了と同時にそのフェイズが終わって、僕はひとりでスタジオに戻って、それまでやってきたことに戻ったんだ。だからこのアルバムは本能的というか、より直感的なものなんだよね。僕と機材だけ。僕が愛してる音楽はそういう音楽なんだ。サイケデリック・ロックも大好きだけど、テクノも大好きなんだ。
ユースセンターや更生施設に力を入れずに警察に権力を与えまくっていることが腹立たしいよ。理解不可能だ。あとは医療制度だね。お金がないと病院に行けないっていう制度には怒りを感じるよ。
■今回の『Crush』はいつごろからつくりはじめたんですか?
SS:今年の2月だね。3月にはつくり終わってたよ。5週間でできたんだ。
■制作にあたり「Shadows EP」(2011)を聴き返したそうですが、原点回帰のような意識が?
SS:僕は自分がつくった音楽はあまり聴かないんだ。だって世の中はもっといい音楽で溢れてるでしょ(笑)? べつに聴き飽きてるわけではないけど、つくってるときに聴きまくってるからちょっと離れたくなるんだよね。でも何年か後に聴いたりすると、なんか予想外というか……まったくちがう聴き方ができて、自分がつくったものじゃないかのような感じがしたりするんだ。わくわくするんだよね。深い意味があって聴いたりするわけじゃないんだけど、「Shadows」はもうちょっと長くやっていたかったって気持ちはあるんだ。その気持ちにたいする答えが『Crush』なのかなって思う。僕はいま「Shdows EP」がすごく好きなんだ。8年くらい前につくったんだけど、聴くといまでもわくわくするんだ。
■『Crush』をつくる際にとくに参照した作品やアーティストはありましたか?
SS:ものすごいスピードでできたんだ。32年間音楽を聴いてきた僕がいて、ロンドンにある僕の大きな、機材がぜんぶ置いてあるスタジオがあって、機材が正常に動いているのを確認してくれるティムって言う仲間がいたから作業がすごく早くなった。このアルバムはスピーディに作業ができた結果みたいなものだと思うんだ。激しかったよ。音楽を聴いて「こういうふうにしたいなぁー」とかはなかったんだ。アルバム制作中は音楽を聴いてなかったからね。ゆっくりめの曲もピアノの前に座って淡々とできていった、溢れ出てきたって感じだったよ。
■《Sónar 2019》でのDJはすごくダンサブルかつ多様なセットでしたが、今回のアルバムがこのようなスタイルになった理由は?
SS:いい質問だねぇ。僕の頭のなかでは、僕がいままで聴いてきた音楽が乾燥機状態になってるんだ。頭のなかで転がりまわってるんだよね。で、僕のスタジオのなかにはブクラやコルグやローランドのようなエレクトロニックな楽器がたくさんある。だから僕のつくる音楽がエレクトロニックなサウンドなんだ。たとえば僕がスタジオに行って、ヴァイオリニスト4人が座ってたとしたら、僕はきっとヴァイオリンの音楽だけをつくるだろう。たとえば「LesAlpx」のBサイドの“Coorabell”って曲なんかはドラムを全部ローランドの新しいドラム・マシーンでつくったんだ。それで8分もあるこの曲のベースを、淡々と10分でつくったよ。できちゃったんだよね。
やっぱりエキサイティングじゃないといけないと思うんだ。エレクトロニック・ミュージックをつくるうえで僕がたいせつだと思うのは、たとえばチェロ奏者。チェロを弾くには、楽器を抱えて、包み込んで弾かないといけない。だから、チェロの演奏をみると、そのチェロの音を通り越して演奏者の心の音まで聞こえると思うんだ。エレクトロニックの機材だとそれが難しいと思うんだよね。自分と機械だからさ。リスナーがその機械を通り越してアーティストの心が聞こえるようにするには、機材のことを知り尽くさないといけないと思うんだ。これは絶対。
■『Elaenia』は音響的にけっこうクリアでしたが、今回は良い意味で濁りがあって、たくさん細やかな音が入っています。それは意図的にやりました?
SS:それもつくりあげたスピードが関係してるんだと思う。今回使った機材はツアー中でも使ってる機材で、曲を早く流したり、ディテールを足すこともできるものなんだ。でもたまに、手を離したら何もコントロールできなくなる状態のセッティングにするんだ。だからつねに機材の舵を取ってないといけないんだよね。前作よりちょっと乱雑な音になっているのはそれが原因かな。ぜんぶセッティングして、機材に声を与えたんだ。でも舵は僕が握っている。野獣に手綱をつけて、暴れすぎたら引く感じって言えばいいのかな。
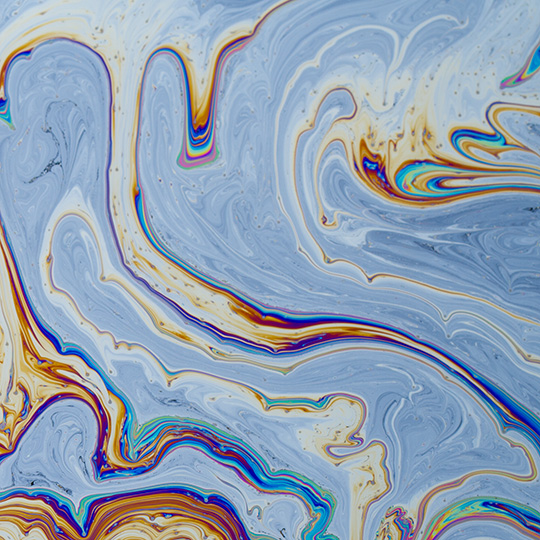
怒りの根本は、僕たち人間が時間を無駄にしていることからきてると思うんだ。でも希望はある。このアルバムをつくったときは絶望を感じていたし、怒ってたけど、希望がなければ何も正せないと思うんだ。希望は捨てちゃいけない。
■本作の背景には「政治的権力競争」や「環境変動」などがあるようですが、やはりいまのUKの情況に影響されたんでしょうか?
SS:グローバルな情況だね。どの問題もちょっと似ていると思う。UKやアメリカ、ブラジルなどでは右派の政治が増えていて、それにしたがって独立主義も増えているんだよね。この世代にとってはほんとうに悲しいことだと思うし、それにたいして闘わないといけないと思うんだ。僕はこの問題についてなら延々と話せるよ。
■そういったポリティカルなことを明確に作品とリンクさせたのは今回が初めてですよね?
SS:そうだね。このアルバム以外の作品はもっと抽象的なものばかりだったと思うな。「自分の信じているものを最前線に」っていう形でやったんだけど、それは自分の信じてることが正しいと思ってるからなんだよね(笑)。
■いま何にいちばん怒ってる?
SS:毎日ちがうんだよね。たとえばUKでは青少年犯罪がすごく増えているのに、政府はどんどんユースセンターを減らしているんだ。ユースセンターや更生施設に力を入れずに警察に権力を与えまくっていることが腹立たしいよ。理解不可能だ。あとはヘルスケア・システム(医療制度)だね。僕はすべての人間がヘルスケアにアクセスできて当たり前だと思ってる。お金がないと病院に行けないっていう制度には怒りを感じるよ。ほかにも怒ってることはたくさんあるけど、僕が生きている限りずっと怒りを感じ続ける問題は、ヘルスケア・システムだろうね。いまでもつねに頭をよぎるからね。
■なぜ今回のアルバムはそういうものとリンクしたんだと思いますか?
SS:リンクしているかどうかは正直はっきりわからない。今年の初めごろに僕は、人生でこれまで感じたことのないほどの絶望を感じていたんだ。その気持ちが僕の音楽に浸透したのは間違いないと思うけどね。修道士のように毎日スタジオにこもる。毎日毎日。僕はそこにいないといけないんだ。でもそれと同時に僕は、世界から自分を締め出してしまいたくないんだよね。だからつねにいろいろ読むんだ。僕自身がより意識するようになったからなのか、ニュースがどんどんひどくなっていってるからなのかわからないけど、確実に読むニュースのひどさに意識が向いているんだよね。そのニュースが僕に怒りを感じさせているし、その怒りから生まれてきた曲も確実にあるんだ。ピアノに向かって「よし、いまからボリス・ジョンソンについて曲を書くぞ」っていう感じでつくってるわけではないんだけど、自分の心が勝手に、つくる曲に反映されているとは思うんだよね。
■今回アルバムをこのような構成にした意図は?
SS:けっこう難しかったよ。最初はアップテンポで次第にゆっくり、って順番で並べてみたりもしたんだけど、ぜんぜんしっくりこなかったんだよね。その並べ方だとソフトな曲を聴いてもリラックスできないって思ったんだ。友だちのキーレンとふたりでいろんなコンビネイションを聴いてみたりしたよ。キーレンはシーケンスをすごく助けてくれたんだ。“Sea-Watch”だけはちょっと多めにスペースを与えたいって思ってね。ほかの曲との距離感をたいせつにしたかったんだ。
■“Sea-Watch”はアルバムのなかでもとくに静かな曲ですよね。
SS:人道的活動グループの曲なんだ。地中海に船を出して難民を救う団体なんだけど、イタリア政府は認めていない。キャロラ・ラケット(Carola Rackete)っていうドイツ人女性の船長がいて、彼女の船だけで500人の難民を救ってるんだよね。彼女やその団体の人たちはイタリアの政府からしたら犯罪者かもしれないけど、僕はほんとうのヒーローだと思ってるんだ。政治家は揉めているだけだけど、この人たちは危険な海に出て、行動を起こして、人を救っているからね。
■8曲めはいきなり唐突に終わります。これは怒りですか?
SS:トラックリストある? 8曲めがどの曲かわからないんだ(笑)。……ああ、“Environments”か。このアルバムは、どの曲もけっこう重めでディテールが強いドラムスが入ってるんだよね。メロディのほうはけっこうピアニスティックでシンプルでメロンコリックだけど。“Environments”の場合はピアノがゆっくり忍び寄る感じで入ってきて、悲しみの感覚が曲の最初から最後まで存在してるんじゃないかな。でもその悲しみのうえに怒りもつねにいる感じなんだよね。曲の最後はすべてがぐるっと回転したかのような激しい怒りで終わるんだ。このアルバムをライヴでやるときがきたら、きっともっと大きな怒りを表現するんだろうなと思うよ(笑)。
■そしてアルバムは“Apoptose”という連曲で終わります。「アポトーシス」と聞くと暗い印象を抱く人もいるかもしれませんが、これにはどういう意味が?
SS:僕は学校に行って生物学者になったから、こういう言葉は日常的に使うんだよね。家のキッチンから出てすぐの壁に、プログラムされた細胞死(アポトーシス)のポスターを貼ってるんだ。オタクっぽいって言われるんだよね。友だちとかが家にくると「なんでこんなポスター貼ってんだよ」って突っ込まれるし。だから僕はふだんから「アポトーシス」って言葉に触れてるんだよね。「アポトーシス」って言葉の響きが好きなんだ(註:黙字を発音して「アポプトーシス」と読むことも)。「ポップ!」ってさ、なんかシャボン玉がはじけるような、かわいい音というか。暴力的には聞こえないんだよね。なんか……良いことのようなさ。ぜんぜんいいことじゃないんだけどね(笑)。曲も悪いことを指してるし。でも言葉の響きはいい。「ポップ!」って。日本語だと風船が割れる音をどう表現するの? パン? パン! 英語だと「ポップ!」なんだよね。「ア・ポップ!・トーセス」。その響きが好きなんだ。曲中のドラムスの音もはじけてるような音になってる。ディデールがたくさん詰め込まれた曲だからいろんな音がはじけてるように聞こえると思うんだよね。アポトーシスは末期というか、細胞が死ぬ、ようするに終わりだからアルバムの最後に持ってきたんだけど、そんな悲しいとか暗い終わりって感じじゃなくて、単純に終わりって感じで最後にしただけなんだよね。
■こちらの考えすぎだったかな?
SS:いや。この曲はたまたまゆるい感じの曲なんだ。逆に“Sea-Watch”とかにはすごく献身的な意味がある。クリアな意味というか。でも“Apoptose”はゆるめなんだ。
■今回のアルバムは、オプティミスティックですか? それともペシミスティック?
SS:オプティミスティックだね。“Birth”は新しい命を祝福する曲だし、いま僕らが目の当たりにしている環境問題や政治問題は人間がつくってしまった問題で、だから人間で正せる問題なんだ。新しく生まれてくる人間たちでね。怒りの根本は、僕たち人間が時間を無駄にしていることからきてると思うんだ。でも希望はある。このアルバムをつくったときは絶望を感じていたし、怒ってたけど、希望がなければ何も正せないと思うんだ。希望は捨てちゃいけない。
取材:小林拓音+野田努(2019年10月18日)
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE