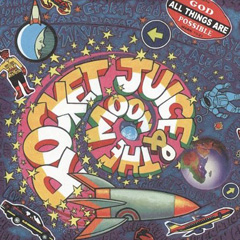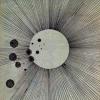MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Thundercat- Drunk
小川充 Mar 08,2017 UP
カマシ・ワシントンの『ザ・エピック』はじめ、ブランドン・コールマンの『セルフ・トウト』、テラス・マーティンの『ヴェルヴェット・ポートレイツ』、ジョセフ・ライムバーグの『アストラル・プログレッションズ』、マイルス・モズレイの『アップライジング』と、ロサンゼルスのジャズ集団のウェスト・コースト・ゲット・ダウン(WCGD)周辺作品が、ここ1、2年で続々とリリースされている。これらの作品は現在のLAジャズ・シーンの活況ぶりを物語るに十分だが、同じジャズ・サークルで共演も多い彼らの作品でも、たとえばスピリチュアル・ジャズのカマシ・ワシントンと、ファンク色の濃いブランドン・コールマンの作品では、たとえ演奏するメンツが同じような顔ぶれであっても、リーダーによって全く異なる作品、演奏になるところがジャズの面白さ、多様性を示している。このたび3枚目のソロ・アルバム『ドランク』を発表するベーシストのサンダーキャットことスティーヴン・ブルーナー、その兄で初のソロ・アルバム『トライアンフ』をリリースするドラマーのロナルド・ブルーナー・ジュニアも、このWCGDのメンバー。前述の『ザ・エピック』はじめ、フライング・ロータスの『ユー・アー・デッド』、ケンドリック・ラマーの『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』などにも参加している。彼ら兄弟の作品が奇しくも同じ時期にリリースされるのだが、やはり兄弟ということもあって共通項を見出せるアルバムである。
とはいえ、今回のブルーナー兄弟の共演は、『トライアンフ』に収録された“テイク・ザ・タイム”でサンダーキャットが客演するのみ。『ドランク』には盟友のフライング・ロータスに、今までもサンダーキャット作品に参加してきたカマシ・ワシントン、テイラー・グレイヴスらが参加しているが、WCGD周辺メンバー自体はそれほど多く参加していない。サンダーキャットの前作『アポカリプス』(2013年)にも参加したチャールズ・ディッカーソンのほか、ディアントニ・パークス、ルイス・コール、デニス・ハムといった腕利きのセッション・ミュージシャンらが脇を固め、ミゲル・アトウッド・ファーガソンがストリングスを手掛ける。ケンドリック・ラマー、ファレル、ウィズ・カリファなどヒップホップ方面のゲストのほか(国内盤ボーナス曲にはマック・ミラーも)、“ショウ・ユー・ザ・ウェイ”ではドゥービー・ブラザーズのマイケル・マクドナルド、ロギンス&メッシーナのケニー・ロギンスと、1970年代初頭よりウェスト・コースト・ロックやAORを作り上げてきたシンガー・ソングライターふたりの参加が話題だ。ジャズ/フュージョンを軸に、ビート・ミュージックやドラムンベースなどクラブ・サウンドの要素も取り入れ、さらにAORをミックスさせてバレアリックなムードの作品も作ってきたサンダーキャットだが、そうしたAOR路線の拡大がマイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスの参加に象徴されている。“ア・ファンズ・メイル”や“ラヴァ・ランプ”などもそうしたAOR路線の曲だ。しかしながら、サンダーキャット自身はAOR路線拡大の狙いからマクドナルドとロギンスにゲスト要請をしたわけではなく、単純に昔から彼らの大ファンだったことが理由だそうだ。サンダーキャットは1984年生まれの黒人だが、LAのようなミクスチャーが盛んな土地では、彼らの世代の黒人はAORや白人音楽を普通に聴いていたようで、我々が日本で想像するようなブラック・ミュージックのイメージも、実際はやや異なるものなのかもしれない。『ドランク』は一般的なブラック・ミュージックというより、ロックやAOR通過後のそれと言えるだろう。サンダーキャットが昔から影響を受けたと述べるジョージ・デュークやスタンリー・クラークにしろ、ジャズ畑出身の黒人ミュージシャンではあるが、ロックをはじめとした白人音楽を柔軟に取り入れ、いわゆるブラコン的な音でメジャーな成功を掴んだ人たちだ。今まではどちらかと言えばベース・プレイに第一の主眼点を置き、いかにその技巧を目立たせるかに注意を払ってきた感がなくもないサンダーキャットだが、シンセ・ファンク系の“フレンド・ゾーン”や“トーキョー”に顕著なように、今回はトータル・サウンドのプロデュースや作曲に重きを置き、同時にシンガーとしての能力を今まで以上に発揮したものとなっている。そうした音楽に対する軸足の置き方という点でも、ちょうど1970年代後半から1980年代にかけて、フュージョンからディスコ、ブラコン方面へシフトするジョージ・デュークの足跡とダブるところもある。余談だが、アルバム・ジャケットの写真は『地獄の黙示録』へのオマージュといったところで、今までの2枚のアルバムに「アポカリプス」という言葉を入れていたサンダーキャットの遊び心が表われている。
一方、ロナルド・ブルーナー・ジュニアの『トライアンフ』には、前述のとおりサンダーキャットのほか、“センセーション”でマック・ミラーと黒人女性シンガーのダニエル・ウィザースがゲスト参加。そして、“ジオーム・ディオーム”にはジョージ・デューク本人がフィーチャーされている(ジョージ・デュークは2013年8月に亡くなっているので、恐らくそれ以前のセッションか、録音素材をもとに完成させた作品だろう)。彼のドラムはジャズやブラック・ミュージック的なそれと言うより、ロックの影響が強いものだ(ロナルドはサンダーキャットとともにスラッシュ・メタルのスイサイダル・テンデンシーズでも演奏してきた)。“トゥルー・ストーリー”や“テイク・ザ・タイム”あたりにそうした特性が表われており、またこれらではサンダーキャット同様にシンガーとしてもアピールをおこなっている。“チックス・ウェブ”はインストのフュージョン・ナンバーだが、これもロックからの影響が色濃い。ジョージ・デュークとの“ジオーム・ディオーム”もそうだ。ジョージ・デュークはジャン・リュック・ポンティと共演し、フランク・ザッパのマザーズで演奏したり、ビリー・コブハムとの双頭ユニットを組んだ時期もあるのだが、そうしたことを思い起こさせる曲と言えよう。そして、“シール・ネヴァー・チェンジ”や“ホエンエヴァー”あたりはウェスト・コースト・ロックの文脈から出てきたような曲だ。サンダーキャットの『ドランク』のAOR路線に呼応する曲と言えるかもしれない。長尺の“オープン・ザ・ゲート”は、AOR的な導入からフュージョン、プログレ風のジャズ・ロックへと展開していく。ほかにハウス・ビートにシンクロしたような“ダズント・マター”、シンセ・ファンク~シンセ・ポップ路線の“トゥ・ユー/フォー・ユー”があり、“センセーション”ではあたかもアース・ウィンド&ファイアを想起させるコーラスがフィーチャーされる。アースはLAのミクスチャー・カルチャーを象徴するような存在であり、真の意味でのフュージョン・バンドだった。ブラック・ミュージックにロックやAORの要素も取り入れた先駆と言える。ジョージ・デュークにしろ、アースにしろ、そうしたLAの音楽文化が、サンダーキャットにも、ロナルド・ブルーナー・ジュニアにも受け継がれていると言えよう。
小川充
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE