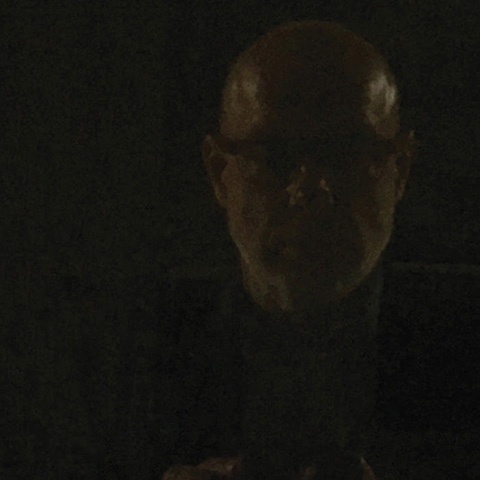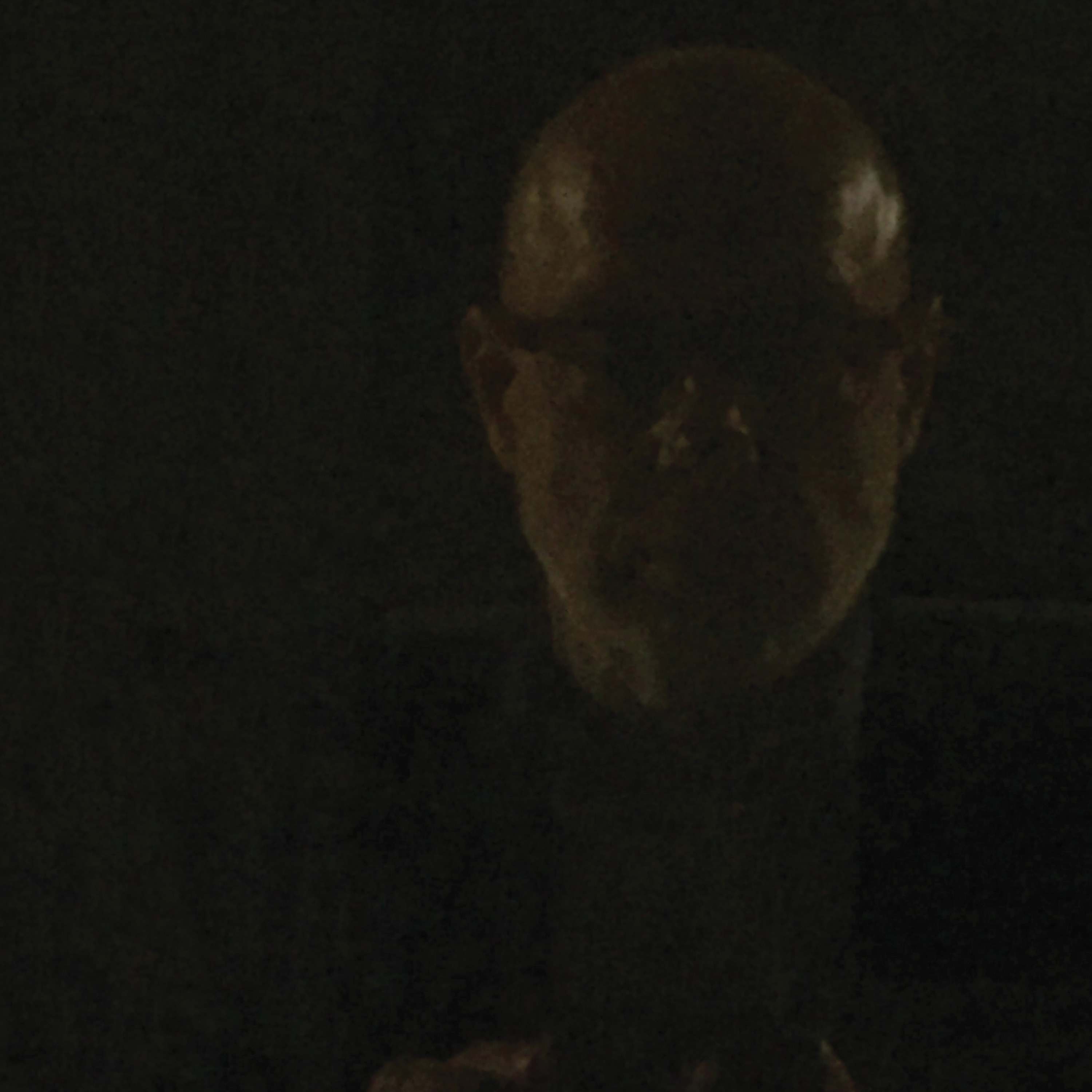MOST READ
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- MURO ──〈ALFA〉音源を用いたコンピレーションが登場
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations | テイラー・デュプリー&ジムーン
- Ikonika - SAD | アイコニカ
- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎、ニュー・アルバム『ヤッホー』発売決定
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎、先行シングル「あなたの場所はありますか?」のライヴ演奏MV公開!
- HOLY Dystopian Party ──ディストピアでわたしたちは踊る……heykazma主催パーティにあっこゴリラ、諭吉佳作/men、Shökaらが出演
- Shintaro Sakamoto ——すでにご存じかと思いますが、大根仁監督による坂本慎太郎のライヴ映像がNetflixにて配信されます
- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー
- ele-king vol.36 特集:日本のシンガーソングライター、その新しい気配
- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門
- heykazmaの融解日記 Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗
- Eris Drew - DJ-Kicks | エリス・ドリュー
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー
- Columns 12月のジャズ Jazz in December 2025
- Masabumi Kikuchi ──ジャズ・ピアニスト、菊地雅章が残した幻のエレクトロニック・ミュージック『六大』がリイシュー
- There are many many alternatives. 道なら腐るほどある 第3回 映画『金子文子と朴烈』が描かなかったこと
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- Geese - Getting Killed | ギース
Home > Reviews > Album Reviews > Brian Eno- Reflection
野田努
私は演奏することよりプランを作ることのほうが好きだったため、いったん機械を作動したら、ほとんどあるいはまったく私の側からの介在なしに音楽を作り出しうるような状態やシステムに興味が惹かれていた。1975年『ディスクリート・ミュージック』イーノ自身によるライナー
私は聴くことができて、そして無視することもできる曲を作ろうとしていた。1975年 前掲同
バイヤールはこの曲のあるところでは記譜されているテンポの約半分で演奏している。そして私は彼の判断の素晴らしい賢明さに敬意を表して、もっと遅いテンポでやった。1975年 前掲同
ある環境におけるバックグラウンドとして特別に考案された音楽のコンセプトは、1950年代、Muzak社によって提唱された。1978年『ミュージック・フォー・エアポーツ』イーノ自身によるライナー
あらたまって書くのも野暮な話だが、ブライアン・イーノの先見の明の非凡さに疑いの余地はない。彼がアンビエント理論を打ち立ててから40年後の未来には、Muzak社のバックグラウンド・ミュージックのテンポを遅らせた反復=ヴェイパーウェイヴまで含まれることになる。それはしかしデジタル的退廃で、「思考のための空間」を導くものかどうかは怪しいところである。
『リフレクションズ』は、感触で言えばここ最近の彼のアンビエント・ミュージックそのもので、コンセプトも、40年前に彼がジャケットの裏面にしたためたそれから逸れるものではない。つまり、「いったん機械を作動したら、ほとんどあるいはまったく私の側からの介在なしに音楽を作り出しうる」ことの最新型だ。ことにアプリでは,その都度その都度自動生成される曲が流れる。そのアンビエンスはバッテリーがもつ限り、終わりがない。このようにイーノは忌々しいスマホ時代に対応しているわけだが、ぼくのまわりにはスマホを所有しないイーノ・ファンもいる。
『ディスクリート・ミュージック』をはじめとする初期の名作には、牧歌的と言ってもいいほどの楽天性があった。イーノは自らが影響を受けたゴスペル音楽のことを“楽天主義のメッセージ”と形容しているが、自分の体験から言っても教会でゴスペルを聴くということには、とにかくなんだかよくわからないけど良いことあるよという、信仰心のない人間をも前向きにさせる力がある。そこまで際だったものではないにせよ、1978年の定義に基づけばアンビエントとは「平穏を導くもの」で、実際初期の作品にはロマンティックなムードもある。そうしたある種の情緒は、もうここ数年のイーノ作品にはない。曲はより物質的で、物理的だ。
『リフレクションズ』のジャケが、どうにも気になる。黒のなかをブライアン・イーノ本人の幽霊のように暗い表情が浮かんでいる。紙エレキングvol.19の表紙を見て欲しい。ガラス板にreflections(反射)しているのは、iPhoneを構えているイーノだが、それがまた何とも茫洋と頼りなく見えるのだ。
BBCによれば、2016年の流行語のひとつに「ポスト・トゥールス(ポスト真実)」があるという。いや、まったく……、時代はいまP.K.ディックというわけだが、要するに、人にとって重要なのはもはや真実ではない。“自分にとって都合が良い”真実なのだと。トランプの醜さという真実よりも、雇用を増やしてくれるという真実を信じるように。細分化されたメディア環境がポスト・トゥールス社会を可能にしている(スマホの話じゃないが、いまは音楽の享受/再生のやり方も細分化し過ぎている)。
本当に何がなんだかわからなくなっているというのもある。テレビを点けると討論番組をやっている。誰かがリベラルの敗北をしゃべり出す。リベラルは口当たりのいい理想ばかりを並べて経済をないがしろにしてきたからこんなことになったんだと唾を飛ばす勢いで言う。これもまた2016年の風景のひとつだが、2017年はその延長にある。
近年のイーノは、まるで、あたかも、若き日に多大な影響を受けたコーネリアス・カーデューの政治活動を追っているかのようだ。1981年に事故死したUK現代音楽の巨匠は、シュトックハウゼンに学び、やがてジョン・ケージと出会い、演奏し、晩年は活動家として、マルクス主義者として生きた。そしていまブライアン・イーノは自ら矢面に立って、真摯な態度で政治的意見を述べる。政治コメンテーターも右往左往するポスト・トゥルースの時代、アーティストが政治に言及するのは昔とは違った意味でのリスクがある。知性派として知られるイーノだが、彼は間違いなく情熱家でもあり、つい先日も、ブレグジットで思い知った自らの無知を打ち明けながら、ポリティカル・メッセージを新たに公表したばかりだ。
アンビエント・コンセプトにおける「無視することも可能」という説明は、真であり、注意深く聴かなければわからないという逆説でもある。『ディスクリート・ミュージック』はぼくをいまでも心地よくさせてくれるが、『リフレクションズ』は上げも下げもせず、むしろ醒めさせ、リスナーを冷静さに導こうとするかのようだ。激烈だった2016年が終わり、2017年がはじまった。紙エレ年末号の特集に沿って言えば、いまぼくたちにできること──しっかりと注意深く聴くこと。
ひとつは作曲、もうひとつが演奏、そして3つめは聴くこと。 ジョン・ケージ(1955年「実験音楽」)
野田努
ALBUM REVIEWS
- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations
- Ikonika - SAD
- Eris Drew - DJ-Kicks
- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet
- DJ Narciso - Dentro De Mim
- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion
- Debit - Desaceleradas
- Sorry - COSPLAY
- K-LONE - sorry i thought you were someone else
- claire rousay - a little death
- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer
- Roméo Poirier - Off The Record
- TESTSET - ALL HAZE
- Kieran Hebden + William Tyler - 41 Longfield Street Late ‘80s
- Xexa - Kissom


 DOMMUNE
DOMMUNE