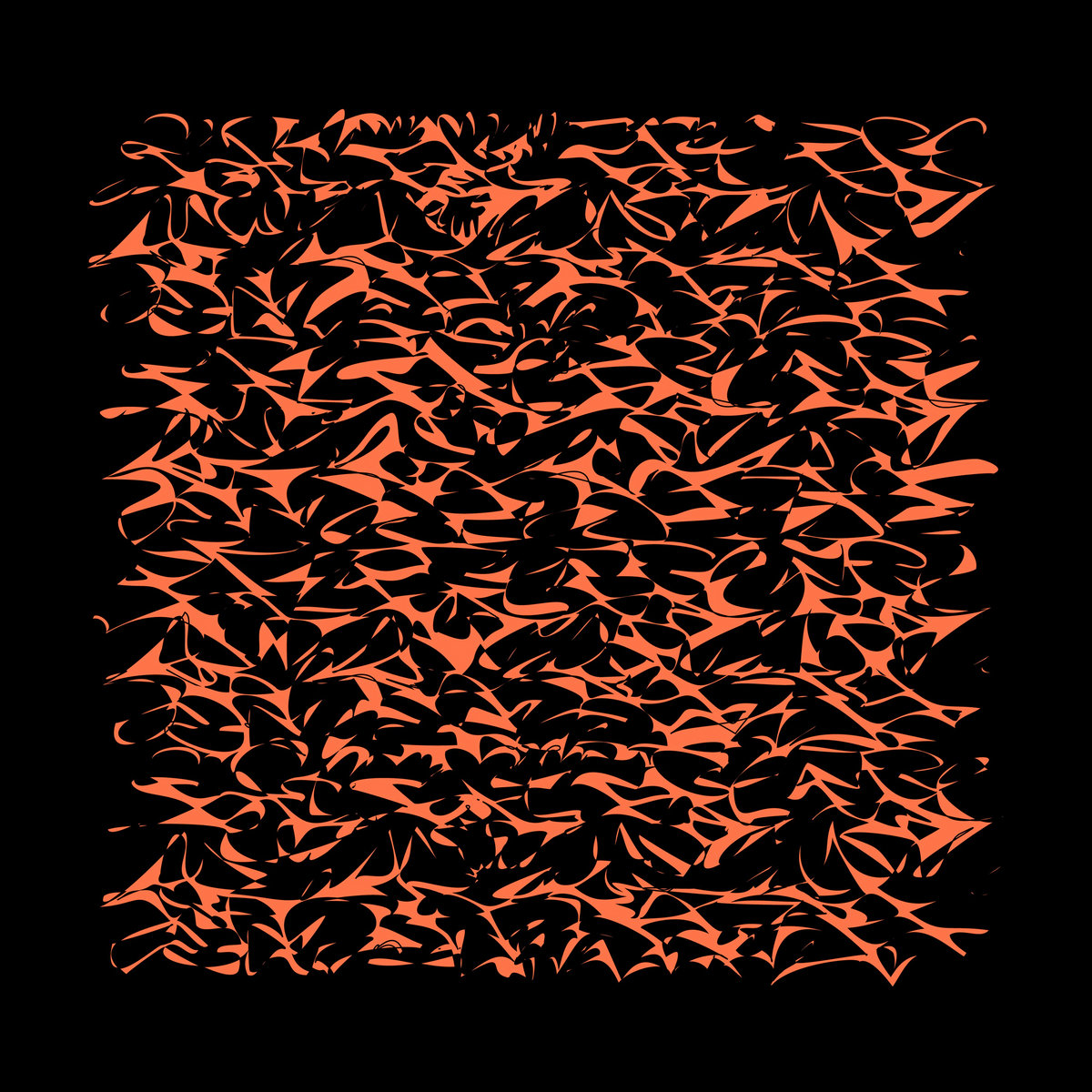MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Interviews > interview with Lucy Railton - 〈モダーン・ラヴ〉からデビューした革新的チェリストの現在
今春、イギリスのレーベル〈SN Variations〉から、本稿でご紹介するチェリスト/作曲家のルーシー・レイルトン(Lucy Railton)と、ピアニスト・オルガニストのキット・ダウンズ(Kit Downes)による作品集成『Subaerial』が送られてきた。アルバム1曲目“Down to the Plains”の中程、どこからともなく聴こえてくる木魚のようなパルス、篝火のように揺らめくパイプオルガンの音、ノンビブラートのチェロが直線的に描き出す蜃気楼、そして録音が行われたアイスランドのスカールホルト大聖堂に漂う気配がこちらの日常に浸透してくる。その圧倒的な聴覚体験に大きな衝撃を受けた。
ルーシー・レイルトンの〈Modern Love 〉からリリースされたファースト・アルバム『Paradise 94』(2018)は、当時のドローン、エクスペリメンタル・ミュージックを軽く越境していくような革新的な内容であると同時に、音楽的な価値や枠組みに留まらないダイナミックな日常生活の音のようでもあった(アッセンブリッジな音楽ともいえるだろうか?)。その独自の方向性を持ちつつ多義的なコンポジションは、その後の諸作でより鮮明化していくが、前述の新作『Subaerial』では盟友キット・ダウンズとともに未知の音空間に一気に突き進んだように思われる。絶えず変化し動き続ける音楽家、ルーシー・レイルトンに話を伺った。

私には素晴らしい先生がいました。その先生はとても反抗的で、クラシック音楽の威信をあまり気にしない人だったので、その先生に就きたいと思いました。というのも、私はすでにクラシック音楽に対して陳腐で嫌な印象を持っていて、何か別のことをしたかったので。
■ロンドンの王立音楽院に入学する以前、どのようにして音楽やチェロと出会ったのでしょうか。
ルーシー・レイルトン(LR):私はとても音楽的な家系に生まれたので、子供のころから音楽に囲まれていました。胎内では母の歌声や、父のオーケストラや合唱団のリハーサルを聞いていたと思います。父は指揮者で教育者でもありました。母はソプラノ歌手でした。父は教会でオルガンを弾いていたのですが、その楽器には幼い頃から大変な衝撃を受けてきました。私は、7歳くらいになるとすぐにチェロを弾きはじめました。その道一筋ではありましたが、子供の頃はいろいろな音楽を聴いていて、地元で行われる即興演奏のライヴにも行っていました。即興演奏やジャズは、私がクラシック以外で最初に影響を受けた音楽だと思います。そこから現代音楽や電子音楽に引かれ、ロンドンで本格的に勉強を開始しました。
■王立音楽院在籍時印象に残っている、あるいは影響を受けた授業、先生はいましたか?
LR:英国王立音楽院では、特別だれかに影響を受けたことはありませんでしたが、私には素晴らしい先生がいました。その先生はとても反抗的で、クラシック音楽の威信をあまり気にしない人だったので、その先生に就きたいと思いました。というのも、私はすでにクラシック音楽に対して陳腐で嫌な印象を持っていて、何か別のことをしたかったので。その先生は、私に即興演奏や作曲することを勧めてくれて、練習の場も設けてくれたので感謝しています。
それから、ニューイングランド音楽院(米ボストン市)で1年間学んだときは、幸運にもアンソニー・コールマンと、ターニャ・カルマノビッチというふたりの素晴らしい音楽家に教わることができました。彼らは私のクラシックに対する愛情を打ち破り、表現の自由とはどのようなものかを教えてくれました。同院にはほかにも、ロスコー・ミッチェルのような刺激的なアーティストが来訪しました。彼はたった1日の指導とリハーサルだけで、ひとつの音楽の道を歩む必要はないことを気づかせてくれました。私はその時点でオーケストラの団員になるつもりはなく、オーディションのためにドヴォルザークのチェロ協奏曲を学ぶ必要もありませんでした。創造的であること、そしてチェリストであることは、オーケストラの団員になるよりも遥かに大きな意味があることを理解しました。これはその当時の重要な気づきでした。

私は、チェロに加えて新しい音の素材を探していたのですが、それらのとても混沌としたシンセは、私が作りたい音楽にとって必要十分で甚大なものだと感じました。自分の好みが固まったところで、すべてのものを織り交ぜる準備ができました。
■ジャズや即興演奏に触れる稀有な機会のなかで、クラシック以外の音楽に開眼されていったとのことですが、電子音楽やエレクトロニクスをご自身の表現や作品制作に取り入れるようになった経緯も教えていただけますか。
LR:それは本当に流動的な移行でした。まず、ルイジ・ノーノの『Prometeo』(ルーシーは同作の演奏をロンドンシンフォニエッタとの共演で行っている)のような電子音響作品や、クセナキスのチェロ独奏曲のような作品に、演奏の解釈者として関わりましたが、その間、実に多くの音楽的な変遷を遂げていきました。それは、私がロンドンのシーンで行なっていたノイズやエレクトロニック・ミュージシャンとの即興演奏、キット・ダウンズとの演奏、そしてアクラム・カーンの作品(「Gnosis」)におけるミュージシャンとの即興演奏に近いものです。インドのクラシック音楽のアンサンブルである「Gnosis」のツアーに参加した際、即興演奏の別の側面を見せてもらいましたが、それは実験とは無縁で、すべてはつながりと献身に関連していました。
また20代の頃は、自分でイベントや音楽祭を企画していたので、自然と実験的な音楽への興味を持つようになりました。そういった経過のなかで、何らかの形で私の音楽に影響を与えてくれた人びとと出会いました。とくに2013年から14年にかけては多くの電子音楽家に出会いました。ことピーター・ジノヴィフとラッセル・ハズウェルとのコラボレーションでは、即興と変容が仕事をする上で主要な部分を占めていて、そういった要素を自分で管理することがとても自然なことだと感じ、いくつかのモジュールを購入して、シンセを使った作業を開始しました。
それから、Paul Smithsmithに誘われてサリー大学のMoog Labに行き、Moog 55を使ってみたり、EMSストックホルムに行ってそれらの楽器(Serge/Blucha)を使ってみたりしました。
私は、チェロに加えて新しい音の素材を探していたのですが、それらのとても混沌としたシンセは、私が作りたい音楽にとって必要十分で甚大なものだと感じました。自分の好みが固まったところで、すべてのものを織り交ぜる準備ができました。私のアイデンティティのすべてを、何とかしてまとめ上げようとしたのが『Paradise 94』だったと思います。
■テクノロジーや電子音と、ご自身の演奏や音楽とのあいだに親和性があると考えるようになったのはなぜでしょうか。あるいは、違和感を前提としているのでしょうか。
LR:これらの要素を融合させることには確かに苦労しますし、まだ適切なバランスを見つけたとは言えません。チェロのようなアコースティック楽器をアンプリファイして増幅することは少々乱暴です。しかし、スタジオでは編集したりミックスしたり、あらゆる種類のソフトウェアやシンセを使ってチェロをプッシュしたりすることができて、それはとても楽しいです。ライヴの際、チェロをエレクトロニック・セットのなかのひとつの音源として使いたいと思っていますが、それをほかのすべての音と調和させるのは難しいですね。
なぜなら、私がチェロを弾いているのを観客が見ると、生楽器と電子音のパートを瞬時に分離してしまい、ソロ・ヴォイスだと思ってしまうことがあるのです。また(チェロが)背景のノイズや音の壁になってしまうこともあり、観客だけではなく私自身も混乱してしまうことがあるのです。スタジオレコーディングでは何でもできますが、ライヴでの体験はまだ難しいです。
■そして2018年に、〈Modern Love〉から鮮烈なソロ・デビュー・アルバム『Paradise 94』をリリースされます。先ほど、ご自身のアイデンティティのすべてをまとめ上げようとしたのが本作であるとお伺いしましたが、本作の多義的なテクスチュアや音色は、生楽器と電子音によるコンポジションと、そのコンテクストに静かな革命をもたらしていると思います。本作における音楽的なコンセプト、アイディアは何だったのでしょうか?
LR:私は、ミュージシャンとしてさまざまなことに関わってきた経験から多くのことを学んだと感じていました。『Paradise 94』を作りはじめるまでは、自分の音楽を作ったことがなかったので、いろいろな意味で自分の神経を試すようなものでした。私は初めて自分の声を発表しましたが、それは当然、自分が影響を受けてきたものや興味のあるものを取り入れたアルバムです。自分の表現欲求と興味を持っている音の世界に導かれるように、このふたつの要素を中心にすべてを進めていったと思います。素材や少ないリソースから何ができるかを試していましたが、このアルバムはその記録です。
‘Paradise 94’
取材・文:渡邊琢磨(2021年10月19日)
| 12 |
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE