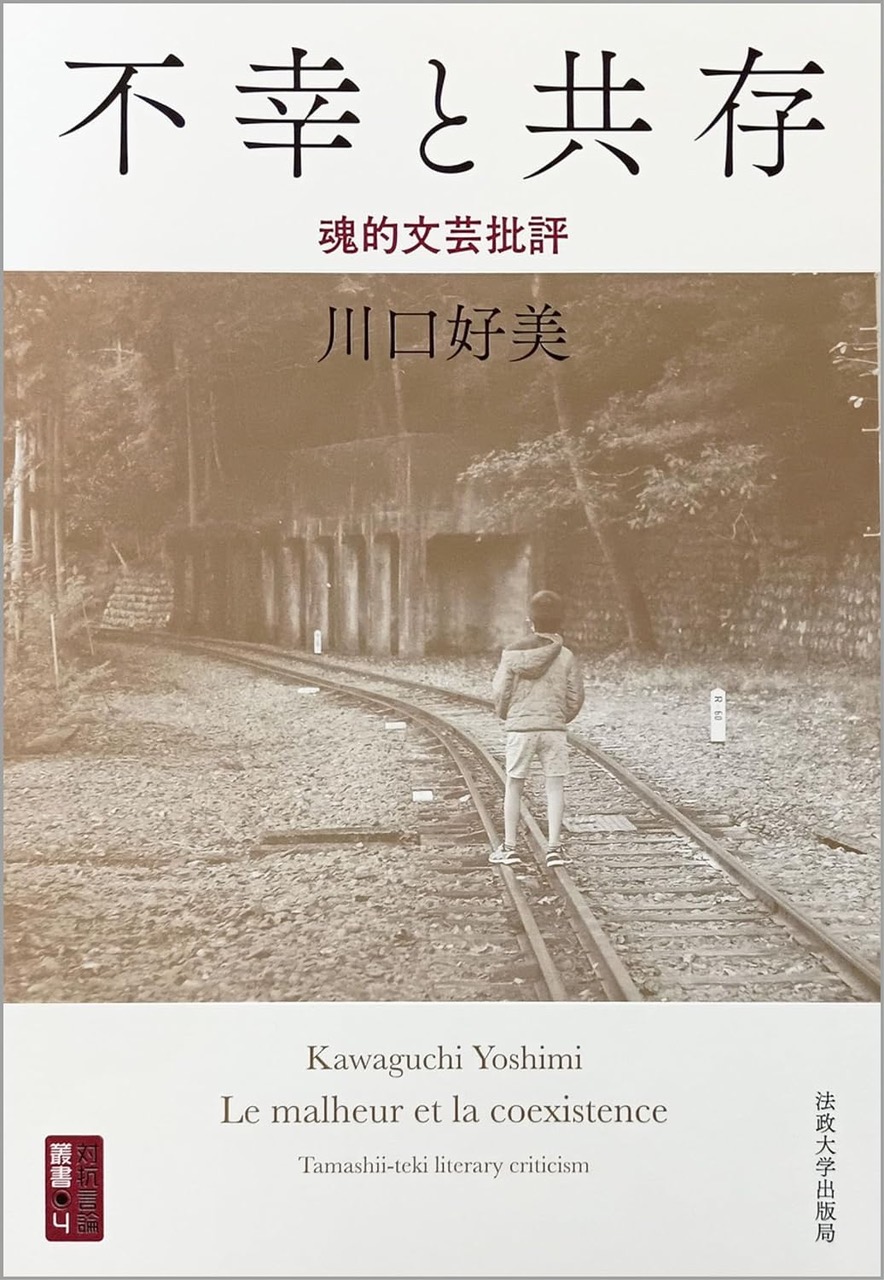MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > 川口好美- 『不幸と共存 魂的文芸批評 対抗言論叢書4』
最初の論考「不幸と共存―シモーヌ・ヴェイユ試論」はロシアのウクライナ侵攻以前、そしてイスラエルのパレスチナへのジェノサイドよりも前に書かれているが、今読まれるべきものに思える。もちろん反戦デモには出ていかなくちゃだけれど、そのみんなで歩いてる道すがら、第二次大戦の最中にヴェイユが絶望のなかで考えたことの一縷でも頭に留め置きながら=人間には戦争を止めることはできないかもしれない、圧倒的な暴力をもってして(爆弾とかではない、内実は本書を読んでくれ)人間が変容しない限り止めることはできないかもしれないという、本稿を留め置きながらシュプレヒコールを叫びたい、というか叫ぶしかない。そんなことしかできなくて思慮が浅くて泣けてくるけれども、さっぱりすっきりすることなどはないのだ。同じことをずっとずっと考え続けながらあきらめていない川口好美の本を読み思う。
小林秀雄という絶対的原点から出発する固有名の数珠繋ぎとしてのいわゆる文芸批評が、排他的・抑圧的な制度であることが明らかになってから—文芸批評が恥ずかしいものとなってから、かなりの時間が経った。(江藤淳ノート)
この本はこんなふうに思っているにも関わらず、自らが文芸批評家を名乗ってしまった著者の第一著作集なのである。2016年の群像評論新人賞の優秀作に選ばれた「不幸と共存シモーヌ・ヴェイユ試論」をはじめ、小林秀雄、中野重治、江藤淳らの文章を自分の魂に引き寄せ、これまで読み継がれてきた歴史の内で誤読されてきた論の再定義、また暴力・差別批判というテーマを軸に読み書き綴られた文章と、これまで新聞・雑誌等に書いてきた散文や書評が並んでいる。
文芸批評というジャンルは、小説などの出版点数の減少とともに80年代よりだんだんとやせ細った「文学」が人々の共通認識から離れ、2000年代になって柄谷行人が「近代文学の終り」などと云って強引に終わらせようとした文学ジャンルであり、以前は燦然としてあった書店のジャンル棚の名札も外されようとしている。でも幾度となく「死んだ、死んだ」と言われてきたロックという音楽を聴き、音楽評論なるものを読み続けてきたみんなにはわかってもらえるだろうけれど、死なないんだよな、これが。
その死を告げられたときに自分が何をしてきたのかを考えると、「死んだ、死んだ」と落胆(するふりを)し、その舌の根も乾かぬうちにSNSで無駄口をたたいているばかりの有様であったのだ。「近代文学の終り」には相応の理由があるのだろうけれど、その理由は自分自身でもあったのだと今になって思い返す。しかし自分よりも一世代以上年若い文芸批評家のねちっこくて正統なそれでいてひりひりするような熱量をたたえた本書を読み、正直呆然とした。奇を衒うでもなく、頭のなかに収まり切らない自らの問題を拠り所に本を読み文を書くという当たり前の表現を見せられてしまった。
どうしてなのかがよくわからないが、川口好美の活動はたった一人で書き始められ、現在は杉田俊介とのインディペンデントな協同雑誌「対抗言論」の編集にも携わっているけれど、いまだ大手の文芸誌からは距離があるようにみえる。また大学の論文を基とするような「文学研究」でもなく、「批評」界隈との間にも距離があるように見える。
ただ商業誌や学校というシステムとは切り離された場所で考え書かれている足かせの外れた文芸批評をぼくは新鮮に感じた。「わたし」「わたしたち」の範囲が狭くて広いというのか、上のようなシステムに回収されないミニコミ、ZINEのような自由闊達さがある。そのシステム・組織のなかで上昇しようという算段が必要ではなく、まず何よりも書かなくてはどうにかなってしまうという必然性がつねにみなぎっている。
そのようなシステム・後ろ盾を必要としない、2023年の年末にぽっと控えめに出現してしまった「文芸批評」の担保は徹底的な対象=本=言葉の熟読にある。対象の文章を自分の、著者自身の魂=言葉に置き換えるという作業によって生まれる。説明すること、理解することはできても、対象に憑依しその後自分の言葉に引き付けることはむつかしいことだ。とてつもない恐怖と逡巡が伴う作業に違いない。しかしその自他の境界を著者は熟読をもって踏み越えてゆく。目に見える拠り所のない場所で言い切る。こんな表現を使うとよくないかもしれないが、著者が言い切るその瞬間のスペクタクルと言ったら名うてのラッパーも裸足で逃げ出すぜと言ってみたくなる。
第二次大戦の最中にわかりにくくなってしまった、スピリチュアルの彼岸に向ってしまったと評される後期シモーヌ・ヴェイユ像の再定義。戦争=暴力を美しいと評する小林秀雄の思念への批判。差別をしてしまったと定義される「雨の降る品川駅」(中野重治)の詩の新解釈。保守的論壇人として知られる江藤淳の新しい読み方など、こうして簡単には説明できないような大きなテーマの論考が並んでいる。
読み進めてゆくと、なんだか妙な感覚に陥る。少し前には批判していたにもかかわらず、次の論考では同じ対象に対する評価がある。論考のなかにも「ジグザグに進むことが可能なのではないか」という言葉が出てくるが、対象を批判し切り捨てるための論考ではなく、あくまでも著者自身、そしてわたしたちの生存/共存のための論考なのだと思えてくるのだ。また常に自らにも暴力性があるという出発点に立って書かれてもいる。この感覚はやはり「研究」とは異なるし、また戦前より続き、この20年途絶えた文芸批評の連なりのなかで新しい現在的感覚なのではないかと思える。
自分の実人生以上の時空のなかで感知しうるはかなく美しい「ふるさと」を土台とする江藤淳の批評を熟読によって自分の側へ引き付ける「江藤淳ノート」は、江藤に対する賛辞ではなく、著者と江藤の立場を切り分けるために書かれているのにも関わらず、この上ないリスペクトにあふれている。その上で、それでも立場を切り分けようとする著者の複雑な態度は、暴力を縮減しているように見える。それこそ最初に戻って<排他的・抑圧的・恥ずかしいもの>=文芸批評の再構築が目論見られているのではないだろうか。
熟読を基とした本を読むのは大変だ。書かれる言葉も厚みを持つから頁を遡ったり、二度・三度繰り返し読まれることを強いるだろう。なかなかわからないことが書かれているけれど、でもだからこそ、なるべくわかりやすく読めるよう考え抜かれて書くという真摯な態度をもった文体だ。心のわかりにくさ、心のやるせなさ、そのどうしようもなさを、しかしちゃんと誰かに読まれるために考え抜かれて書かれている。そこだけは安心して狂おしくも古めかしくて新しい本書を手に取ってほしい。
市原健太
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE