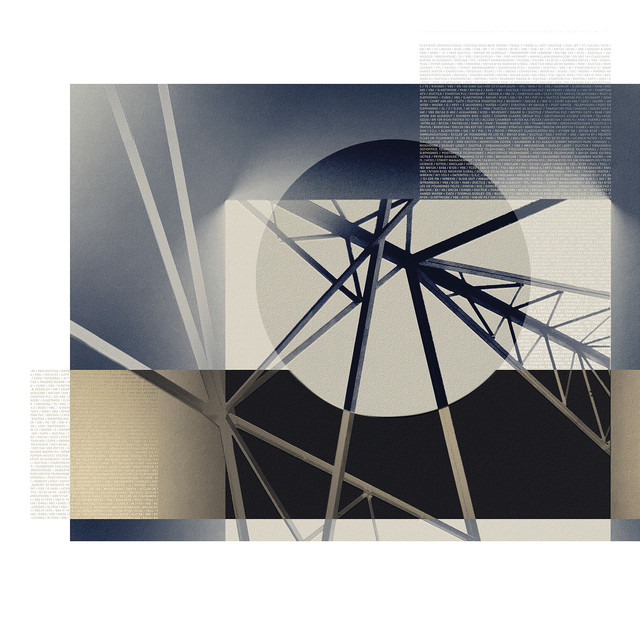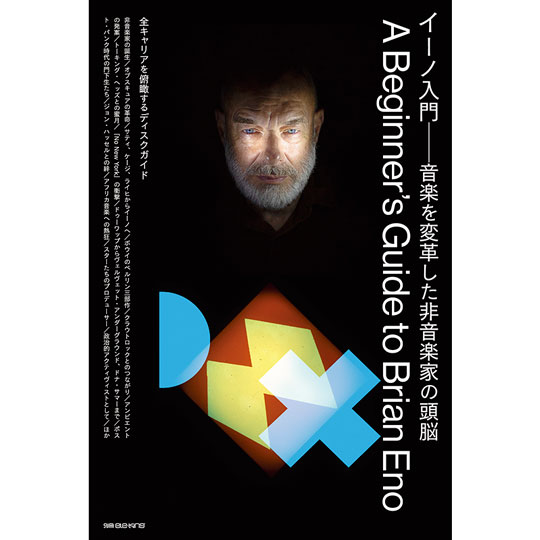MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm- Sushi, Roti, Reibekuchen

ドナルド・トランプとの指名争いからいち早く降りたフロリダ州知事ロン・デサンティスはこの5月、州法から「気候変動」の文字をあらかた消し去った。この改定によってフロリダ州の企業は6月1日から二酸化炭素出し放題、風力発電は禁止、公用車も低燃費ではなくなるらしい。最高気温45度も5000億円の被害をもたらした暴風雨も20センチの海面上昇も左派の陰謀で、デサンティスはフロリダ州を左派や環境活動家から守ったと勝ち誇っている。トランプが再び大統領になれば同じことがアメリカ全土に広がっていくのだろうか。アメリカの消費社会は減速しない。前進あるのみ。『Climate Change(気候変動)』というタイトルを9年も前に付けていた以外、とくに評価できるポイントがなかったNYのハウス・ユニット、ビート・ディテクティブが4年ぐらい前からニューク・ウォッチというサイド・プロジェクトを始め、これがなかなか良かったので、前作から3ヶ月というハイペースでリリースされた新作のレヴューを書こうと準備を始めていたら編集部からイーノ、シューカイ&シュヴァルムの発掘音源について書いてくれというオファーが届いた。はいよと安請け合いしてすぐに聴いてみると、ニューク・ウォッチと同じ方向を向いていて、しかも36年も前の録音なのにぜんぜん完成度が高く、聴き込むほどに引き込まれるのでニューク・ウォッチには退場してもらうことに。ニューク・ウォッチ(核監視)というプロジェクト名は10年後に重みを増しているのかなと思いつつ。
『Sushi, Roti, Reibekuchen(寿司、パン、ポテト・パンケーキ)』と炭水化物の料理が並べられたライヴ音源(料理のイベントで演奏されたものだという)は3人の個性がぶつかり合っているのはいうまでもないことだけれど、シュヴァルムが用意したとされるサウンドの基調はどう聞いてもホルガー・シューカイの過去に規範を求めていて、大半はシューカイが長年にわたって試みてきた即興セッションをベースに、得意のラジオ・ノイズを間断なく挟むなど方法論的には80年代初頭の『On the Way to the Peak of Normal』やS.Y.P.H.のパフォーマンスを強く想起させる。セッションが行われた98年当時、シューカイはそれほど調子が良かったわけではなく、むしろ彼のキャリアのなかでは最悪ともいえるドクター・ウォーカーとのコラボレイト・アルバム『Clash』(97)をリリースした直後で、アンビエント志向の高まりと歩を揃えた『Moving Pictures』(93)以降、もうひとつ方向性を見出せなくなっていた時期にあたっている。テクノとの接点がドクター・ウォーカーだったということがすべてを物語っていて、シューカイほどの才能がなぜテクノの中心にいたマイク・インクやベーシック・チャンネルではなく、それらのフォロワーでしかないドクター・ウォーカーだったのか。テクノを聞き分ける能力がなかったか、テクノと呼ばれていればなんでもいいと思ってコラボレートしたとしか考えられない安易さである。実際、『Clash』以後、シューカイが積極的にテクノと関わっていく姿勢を見せることはなく、彼にとっては発展性のないプロジェクトで終わっている。完全に自分を見失っていた時期だったのだろう。
ブライアン・イーノの90年代も同じようなもので、クラブ・カルチャーの狂騒や猥雑さに馴染まず、意図の伝わりにくい作品が続き、作品数も激減した時期である。よほどのファンならば理解を示しただろうけれど、リミックス・ワークもハズレが多く、新たなファンを獲得できる動きとはとても言えなかった(『The Shutov Assembly』がリリースされた当時、あまり面白くないという評を書いたら石野卓球に怒られてしまった)。イーノ自身が失敗だったと認めているリミックス・ワークにカン〝Pnoom (Moon Up Mix)〟がある。『Sushi, Roti, Reibekuchen』が行われる前年にリリースされたカンのリミックス・アルバム『Sacrilege(冒涜)』の冒頭に収録されたもので、失敗という以前に短くてすぐ終わっちゃうのでもうちょっと聴きたかったと思うリミックスである(これがきっかけで『Sushi, Roti, Reibekuchen』の共演が実現したのかもしれない)。さらにいえば『Sushi, Roti, Reibekuchen』の前夜にはイーノは思い切ってモート・ガーソンやレイモンド・スコットを思わせるスペース・エイジへと回帰し、エイフェックス・ツインやアトム・ハートらによるラウンジ・ミュージック・リヴァイヴァルにどこか文句を言いたげな『The Drop』をリリースする。しかし、これも大きなプロップスを得ることはなく、それどころかニック・パスカルやジム・ファセットに寄せたジャケット・デザインの意図も伝わらずに、ダサいと思われただけで、どちらかというとヤン富田の方が同時期にもっとうまく同じことをやっていたという印象が強い。シューカイほどひどくはないものの、『The Drop』もイーノが道を見失っていたことを記録した作品の一種ではあるだろう。
そして、90年代と反りが合わなかった2人の前に現れたのがJ・ペーター・シュヴァルムだった。スロップ・ショップ名義でシュヴァルムが98年にリリースした『Makrodelia』はトリップ・ホップの最後尾につけたとされるデビュー作で、同じドイツ圏ではクルーダー&ドーフマイスターからドラッグ要素を差し引き、あっけらかんとさせたような作風がメインだった。はっきりいって『Makrodelia』は表層的で、ミュンヘンにはごろごろあるようなサウンドだし(実際にはシュヴァルムはフランクフルトが拠点)、イーノが関心を持つようなサウンドとは思えなかった。イーノが必要としたのは、しかし、ダブを思わせるドラミングや音の組み立て方、あるいはドラッグによる酩酊感とは別の価値観に支えられた “何か” だったのだろう。何度も書いてきたようにイーノは日常から離れることを良しとせず、90年代と肌があわなかったのもそのことに起因しているはずで、『Makrodelia』にはそのような条件を満たすものがあったに違いない。少なくとも『Makrodelia』の2曲目に収録された “Gone” には『Sushi, Roti, Reibekuchen』の基礎となるサウンドが聞き取れ、ここがセッションの起点となったことはなんとなく想像できる(『Makrodelia』ではなぜか “Gone” だけが飛び抜けている)。イーノもシューカイも袋小路にいて、明らかに未熟だったシュヴァルムがこの淀みに “何か” を加えたことで一気に全員のレヴェルが跳ね上がるというマジックが起きたのである。スポ根マンガでいえば起死回生の一打が放たれた。そんな感じがしてしまう。
とはいえ、『Sushi, Roti, Reibekuchen』はオープニングの “Sushi” がまずはジ・オーブやスクエアプッシャーを想起させるところがある。回り道をしてようやくイーノがクラブ・カルチャーの成果と足並みを揃えたというか。これではイーノがアシッド・ハウスやチル・アウトに距離を置いてきた意味がない。曲の完成度は高いけれど、イーノにしてはヴィジョンに乏しく、クラブ・ミュージックに精通しているリスナーにはもうひとつ説得力がない。後半に入ってドラミングが後退するとアップデートされたカンみたいになり、続く “Roti” とともにそこからはなにも文句がなくなる。抑えたリズムで延々と聞かせるかと思えば、様々なSEを駆使して緊張感を高め、パンなど食べてる場合ではなくなっていく。後半から入ってくるドラムもクラブ・カルチャーのそれではなく、ジョン・ハッセルとの『Possible Musics』を彷彿とさせるものに変化している。炭水化物から離れて “Wasser(水)” と題された曲では緊張感を少しといて、穏やかな曲調になだれ込んでいく。おそらくイーノ主導なのだろう、ハウリングを起こしているようなドローンを軸に液体のなかを漂う感触はシューカイが持ち込んでいるのだろうか。背景に退きながら緊張感を残したドラムに “Gone” と同じようなリヴァーブをかけて効果を膨らませているのもおそらくイーノで、これを聞いているとサウンド全体のコントロールはイーノがイニシアティヴをとっていることを確信してしまう。 “Reibekuchen” もまたモロにカンを思わせるものがあり、この頃になると3人の持ち味が完全に融合した状態といえるのだろう。カンのようにパッションが迸らないところが時代の違いというか、それこそ部分的にはP.I.L.『Metal Box』やコールド・ファンク版のジ・オーブといった感じにも聞こえる。最後に “Wein(ワイン)” と題されたサウンド・コラージュ+ダブ。冒頭でイニシアティヴを取っているのはおそらくシューカイで、シューカイはどん底にいながら、この時期は10年をかけて『Good Morning Story』(99)を完成させていた時期でもあり、同作を製作している過程でカンの方法論から離れ、カン以前に取り組んでいたミュジーク・コンクレートに傾倒し始めた意識がこの曲にも見事に刻印されている。同じ時期にウィーンではフェネスがバイオアダプターという概念を音で置き換えるという作業を通してミュジーク・コンクレートを刷新し、ジム・オルーク&ピーター・レーバーグと組んだユニットによってドイツ全体を同じ道に引きずり込み、クリック・ハウスというモーメントとも同期しながらエレクトロニカというタームが幕をあけていた。シューカイがイーノに刺激を受けたかどうかはわからないけれど、00年には『La Luna』で自動生成による不穏で強迫的なドローンを構築し、フェネスたちとあまり変わらない地平にいたことは特筆すべきことである。
イーノとシュヴァルムはこの後もタッグを組み続け、『Music For 陰陽師』(00)に『Drawn From Life』(01)と立て続けに作品を完成させていく。前者で幽霊じみたサウンドトラックを奏でたことはともかく、後者では『Sushi, Roti, Reibekuchen』を滑らかにしたテクスチャーが織り成され、かつてなくコード展開も華やかで、さらにはヘヴィなストリングスまで被せられていく。シュヴァルムはそれから12年後にワグナーを題材とした『Wagner Transformed』をリリースし(『アンビエント・ディフィニティヴ 増補改訂版』P200参照)、イーノは同作で “Tristan & Isolde(トリスタンとイゾルデ)” を演奏することになる。『別冊エレキング イーノ入門』で高橋智子が指摘するように、後期の代表作といえる『The Ship』(16)を製作するまでロマン主義に手を染めることがなかったイーノが、その禁を破った最初が『Wagner Transformed』であり、その予兆をなす作品が『Drawn From Life』なのである。同作はイーノのキャリアのなかでもかなり特異な作品で、ちょっと聴くとアンビエント作品の延長みたいだけれど、全体的には前半の活動からは想像できない要素に満ち溢れている。先に僕はイーノがシュヴァルムのサウンドに「ドラッグによる酩酊感とは別の価値観に支えられた “何か” 」に反応したという書き方をした。その “何か” とはロマン主義に通じるものではなかったのか。イーノが『Makrodelia』に見出したものはそれほどのものではなかったかと思う。シュヴァルムとの出会いからは『Sushi, Roti, Reibekuchen』~『Drawn From Life』~『Wagner Transformed』~『The Ship』という力強い系譜が導かれたのではないかと。
素晴らしいパフォーマンスを展開しながら『Sushi, Roti, Reibekuchen』がこの当時、リリースされなかったのはなぜなのか。無意識のレヴェルで起きたことなのかもしれないけれど、ひとつにはイーノもシューカイもあまりうまくいっていない時期だったためにリハビリ以上の意味をセッションの効果として見出せず、自信を持って世に問う気になれなかったのではないかという推測が最初は浮かぶ。あるいはフィッシュ(Phish)やレイディオヘッドが全盛だった時期にはノスタルジックな響きが強く、その点でも気後れが生じたのかもしれない。うがっていえばゴッドスピード・ユー・ブラック・エンペラーもすでに胎動を始めていた時期なので、同じ即興でも強度に差があり過ぎて『Sushi, Roti, Reibekuchen』をリリースしても霞んでしまったことは想像に難くない。翻って現在はどうだろう。マクシミリアン・ダンバーことアンドリュー・フィールド~ピカリングが彼の運営する〈Future Times〉をハウスのレーベルから脱却させ、様々な実験的試みにトライするなかでプッシュしていたプロテクト-Uがその後にセッション専門の〈U-Udios〉を設立し、ここから生み出されるテープ群がカンのそれに近く、なかでも『別冊エレキング カン大全』で取り上げたオン・ザ・イフネス『U - Udios 4』(20)は新たな流れの始まりではなかったかと僕は思っている。細かく取り上げていけばきりがないけれど、これに冒頭で言及したニューク・ウォッチによる快進撃や、現在、フランスのカンと呼ばれているソシエテ・エトランゼが22年にリリースした『Chance』など即興で行われるセッションがひとつの流れとなってポスト・ロックの後にひと盛り上がりすれば『Sushi, Roti, Reibekuchen』は力強い導線のひとつとなることは間違いない。かつて荒木経惟は「いつ撮ったかではなく、いつ出すか」だと話していた。『Sushi, Roti, Reibekuchen』のリリースもまるでベスト・タイミングを図っていたかのようではないか。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE