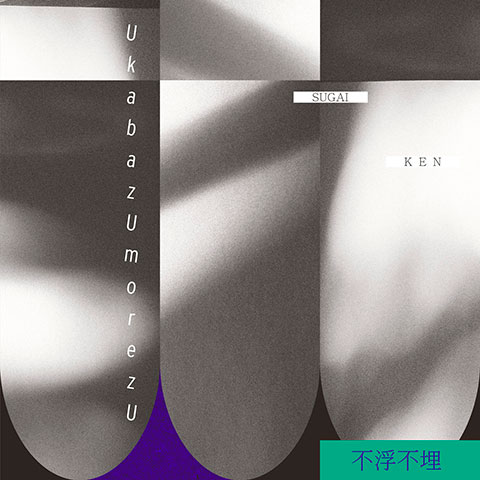MOST READ
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース
- 『成功したオタク』 -
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙
Home > Reviews > Album Reviews > Visible Cloaks- Reassemblage
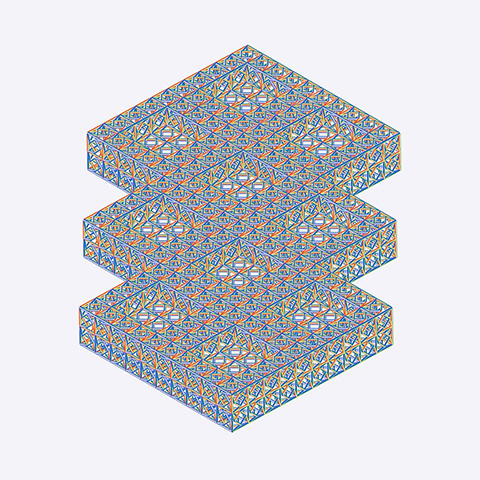
ヴィジブル・クロークスは、ポートランドを拠点に活動をするニューエイジ・アンビエント・ユニットである。メンバーは、スペンサー・ドーランとライアン・カーライルのふたり。スペンサー・ドーランは00年代に、プレフューズ以降ともいえるサイケデリックかつトライバルなアブストラクト・エレクトロニカ・ヒップホップをやっていた人で、00年代のエレクトロニカ・リスナーであれば、知る人ぞ知るアーティスト。スペンサー・ドーラン・アンド・ホワイト・サングラシーズ名義の『インナー・サングラシーズ』など愛聴していた方も多いのではないか。
その彼が、〈スリル・ジョッキー〉からのリリースでも知られるドローン・バンド、エターナル・タペストリーのライアンと、このような同時代的なニューエイジ・アンビエントなユニットを結成し、アルバムをリリースしたのだから、まさに時代の変化、人に歴史ありである。
そう、ここ数年(2010年代以降)、いわゆる80年代的なニューエイジ・ミュージックが、エレクトロニカ/ドローン、OPN以降の、新しいアンビエントの源泉として再評価されており、ひとつの潮流を形作っている。そのリヴァイヴァルにおいて大きな影響力を持ったのが、オランダはアムステルダムの〈ミュージック・フロム・メモリー〉であろう。同レーベルは80年代のアンビエント・サウンドを中心とする再発専門のレーベルで、なかでもジジ・マシンを「再発見」した功績は大きい。じじつ、ジジ・マシンのコンピレーション盤『トーク・トゥー・ザ・シー』は日本でも国内盤がリリースされるほど多くのリスナーに届いた。そのピアノとシンセサイザーの電子音を中心とした抒情的で透明で美しい音楽は、現代にニューエイジ・アンビエントという新しいジャンルを作ったといっても過言ではない。まさに「過去」が「今」を作ったのだ。再発レーベルとしては、理想的な成功である。
その〈ミュージック・フロム・メモリー〉がリリースした、唯一の日本人アーティスト・ユニット作品がディップ・イン・ザ・プールの『On Retinae』の12インチ盤であった。ディップ・イン・ザ・プールは、1980年代から活動をしている甲田益也子(ヴォーカル)と木村達司(キーボード)によるユニットで、日本でも根強い人気とファンがいるし、1986年には〈ラフトレード〉からデビューを飾ってはいるが、しかし、それをニューエイジ・アンビエントの文脈と交錯させた〈ミュージック・フロム・メモリー〉のセンスは、やはり素晴らしい(ちなみに香港のプロモ盤がもとになっているらしい)。だが、ふと思い返してみると、日本の80年代は、細野晴臣をはじめ、安易な精神性に回収されない音楽的に優れたニューエイジ/アンビエント的な音楽が多く存在した。それはときにポップであったり、ときに実験的であったりしながら。
ヴィジブル・クロークスのスペンサー・ドーランは、そんな80年代の日本音楽のマニアなのだ。細野晴臣、小野誠彦、清水靖晃らを深く敬愛しているという。彼らの楽曲を用いた「1980年~1986年の日本の音楽」というミックス音源を発表しているほど。当然、ディップ・イン・ザ・プールの音楽も愛聴していたらしい。そして、本作『ルアッサンブラージュ』は、そんな日本的/オリエンタルな旋律やムードが横溢した作品に仕上がっている。そして、先行シングルとしてリリースされた“Valve (Revisited)”は、ディップ・イン・ザ・プールとの共作であり、甲田益也子がヴォイスで参加。アルバム2曲めに収録された“Valve”には甲田益也子が参加しているのだ(ちなみに、“Valve (Revisited)”は国内盤にはボーナス・トラックとして収録)。
ここで思い出すのだが、昨年、戸川純が復活し、ヴァンピリアとの共演盤にしてセルフ・カヴァー・アルバム『わたしが鳴こうホトトギス』をリリースしたことだ。同時期に『戸川純全歌詞解説集――疾風怒濤ときどき晴れ』も刊行されたこともあり、本盤は、かつて戸川マニアのみならず若いファンからも受け入れられ、大いに話題になったが、こちらは「ニッポンの80年代ポップス/ニューウェイブ」再評価における総括のように思えた。
対して、ヴィジブル・クロークスにおける、ディップ・イン・ザ・プール/甲田益也子参加は、たしかに80・90/2010世代の新旧世代の共演なのだが、文脈はやや異なり、ジジ・マシン再評価以降ともいえる近年のニューエイジ/アンビエント文脈にある。先に書いたように、ディップ・イン・ザ・プールがジジ・マシン再評価の流れを生んだ〈ミュージック・フロム・メモリー〉からリイシューされたことも考慮にいれると、ヴィジブル・クロークスがやっていることは、世界的な潮流である「80年代ニューエイジ/アンビエント文脈」の再解釈なのだろう。そこにおいて、日本の80年代的なニューエイジ・アンビエント、そしてそのポップ・ミュージックが重要なレファレンスとなっているわけだ。〈ミュージック・フロム・メモリー〉からのリイシューや、本作におけるディップ・イン・ザ・プールの参加は、その事実を証明しているように思える。
くわえて本作には、ディップ・イン・ザ・プール/甲田益也子のみならず、現行のニューエイジ/アンビエント文脈の重要な電子音楽家がふたり参加している。まず、昨年、〈ドミノ〉からアルバムをリリースしたモーション・グラフィックス。あのコ・ラのサウンド・プロダクションを手掛けたモーション・グラフィックスだが、彼が昨年リリースしたアルバムにも、どこか80年代の坂本龍一を思わせる曲もあった。また、〈シャルター・プレス〉などからアルバムをリリースする現在最重要のシンセスト/電子音楽家Matt Carlsonも、参加しているのだ。
アルバム全体は、ニューエイジ的なムードのなか、現代的な音響工作を駆使し、現実から浮遊するようなオリエンタル・アンビエント・ミュージックを展開する。非現実的でありながら、どこか80年代末期の日本CM音楽のようなポップさを漂わせている。あの極めて80年代的な「日本人による、あえてのオリエタリズム」を、外国人が参照し、実践すること。そのふたつの反転が本作の特徴といえよう。
本作に限らず現在のシンセ・アンビエントは、80年代中期以降の音楽/アンビエントをベースにしつつ、そこに2010年代的な音響を導入し、アップデートしているのだが、本作などは、アルバム全編から「1989年」的な感覚が横溢しているように思える(たとえば、細野晴臣の『オムニ・サイト・シーング』を聴いてみてほしい)。
余談だが、この80年代初期から後期へのシフトは重要なモード・チェンジではないか。それは「バブル感」の反復ともいえる。ちなみに、80年代と一言でいっても、前半と後半では随分と違う。いわゆる日本のバブル経済は1985年のプラザ合意以降のことで、世間的にその実感が伴ってきたのは、「株投資」と「土地転がし」が(一時的に)一般化した80年代末期(1988年~1989年あたり)だったはず。
そう、最近のいくつかの音楽には、この「景気の良かった時代」への憧憬があるように思えるのだ。それこそ大ヒットしたサチモスは、1989年くらいの初期渋谷系(と名付けられる以前。田島貴男在籍時のピチカート・ファイヴ)的なもののYouTube世代からの反復だろう。そういえば、ディップ・イン・ザ・プールの『On Retinae』も1989年だった。
あえていえば、本作(も含め、近年の音楽)は、「景気が良かった時代の音楽を、景気が悪く最悪の政治状況の時にアップデート」することで、「景気が良かった時代への夢想や憧れ」を反転するかたちで実現しようとしているとはいえないか。つまり、30年以上の月日という時が流れ、新鮮な音楽としてレファレンスできる時代になったわけである。
これは、若い世代には80年代という未体験の時代への憧憬も伴うのだろうが、私などがこの種の音楽を聴くと歴史の平行世界に紛れ込んだような不思議な感覚を抱いてしまうのも事実だ。しかしこの感覚が重要なのだ。つまり、リニアに進化する歴史の終わりという意味を、現在の音楽は体現してまっているのだから。これこそポストモダン以降の、アフター・モダンというべきで状況ではないか?
ヴィジブル・クロークスも同様である。逆説的なオリエタリズムの反転。景気の良さへの憧憬。経済の上部構造と下部構造のズレ。その結果としてのニューエイジ・ミュージックのリヴァイヴァル。そこにレイヤーされるOPN以降の精密な電子音楽の現在。
それらの複雑な文脈が交錯しつつも、仕上がりは極めて端正で美しい電子音楽であること。それが本作ヴィジブル・クロークス『ルアッサンブラージュ』なのである。1曲め“Screen”の細やかな水の粒のような美麗な電子音を聴けば、誰の耳も潤されてしまうだろう。
本作は、ニューヨークの名門エクスペリメンタル・レーベル〈RVNG Intl.〉からのリリースだ。つまり文脈といい、リリース・レーベルといい、近年のニューエイジ・アンビエントの潮流における「2017年初頭の総決算」とでも称したい趣のアルバムなのだ。非常に重要な作品に思える。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE