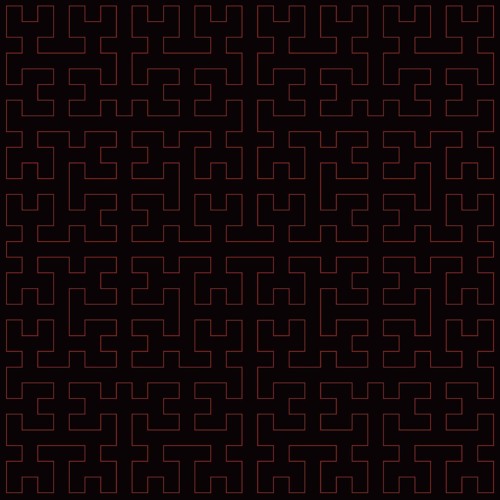MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Thomas Brinkmann- A 1000 Keys
トーマス・ブリンクマンの作りだす音は、はたして「音楽」なのか。ブリンクマンのサウンドは、そのような「問題=意識」をわれわれの感覚にむけて突き出してくる。おなじく〈エディションズ・メゴ〉からリリースされた前作『ホワット・ユー・ヒア(イズ・ホワット・ユー・ヒア)』(2015)もそうだったが、ブリンクマンは音の快楽度数を極限まで削いでいるのだ。
音を単なる「音」として、即物的な触覚を全面化すること。聴き手に即物的な音を聴取するときに生じる「痛み」のような感覚を意識させること。この傾向はオーレン・アンバーチとの共作『ザ・モーティマー・トラップ』(2012)以降、ますます強くなっている。通常のミニマル(・テクノ)から逸脱し、例外的な存在へと変貌を遂げた、とでもいうべきか。
2016年の新作『ア・1000キーズ』においては、その「痛み」が、さらに高められていた。「これは音楽なのか?」という問いは、前作以上にクリティカルである。
なぜか。本作は、ほぼ全曲グランドピアノを加工したサウンドを用いている。しかもピアノによる演奏・旋律がはっきりと残っているトラックがほとんどで(1曲め、7曲め、9曲め、11曲めなど、ノイズ・トラックやリズム・トラックの曲もある)、低音を異様に響かせる「ミニマル・ノイズ・ピアノ・ミュージック」とでも形容したい音楽を展開しているのだ。
そう、たしかに旋律やリズムらしきものはある。しかしそれがどうにも「音楽」には聴こえない。「音楽」の快楽は、ほぼ皆無に思える。ノイズにせよ電子音響にせよ「音楽の快楽」は聴き手のコンテクストに応じて存在するはずだが、本作の異様なピアノの響きにはそれが(まったく?)ないのだ。剥き出しになったピアノの音がゴロンと横たわっている、そんな感覚である。
ブリンクマンは、そのような「音楽」と「音楽ならざるもの」の領域を攻めている。前作『ホワット・ユー・ヒア(イズ・ホワット・ユー・ヒア)』も、ノイズやドローン特有の快楽性が希薄であり、相当に異様な音だったわけだが、その「気持ち悪さ」の向こうに、かすかにリズムの残滓を散りばめることで「音楽」と「音楽ならざるもの」の領域を往復するような実験作品でもあった。極限まで「音楽」的な要素を削いだという意味で、音響的ミニマル・アートともいえるだろう。
本作も同様だ。いや、それ以上だ。極限まで快楽の要素を削いだ新しい音響的ミニマリズムを、ピアノという300年以上の音楽史を背負った楽器で体現させてしまっているのだ。なんという「音楽」への批評性。そして破壊。
「音楽」の破壊? いや、だからこそ新しい創作でもある。とくに異様な低音とノイズのむこうで、極限まで音を削がれたピアノの打鍵が強烈に鳴り響く12曲め“CGN”や最終18曲め“KIX”には、ただ、ただ、圧倒されるほかはない。「聴いたことがある音」と「聴いたことがない音」の領域を徹底的に揺るがしているのだ。まさに、「音楽」から遠く離れて、である。
もはやベテランと称してもいいブリンクマンが、このように真に新しいアート/音楽を追求している姿勢に、私は深いリスペクトを感じてしまう。急いで付け加えておくが、ブリンクマンは新概念や方法論を追求することで「新しさ」を実現できるとは考えてはいないはず。彼が批評的な問題を突きつけるのは、受容=聴き手側の固まった感覚のほうではないか。
ブリンクマンは本作を「ハーシュ・メディテーション」と語っていた。快楽度数が皆無の、剥き出しのピアノの音響に耳と身体を浸すことで得られる「破壊的=瞑想的」領域。それは「21世紀型のミニマル・ミュージック」の響きだ。透明な知性による狂気の構造化、その結晶が本作なのである。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE