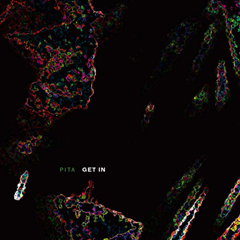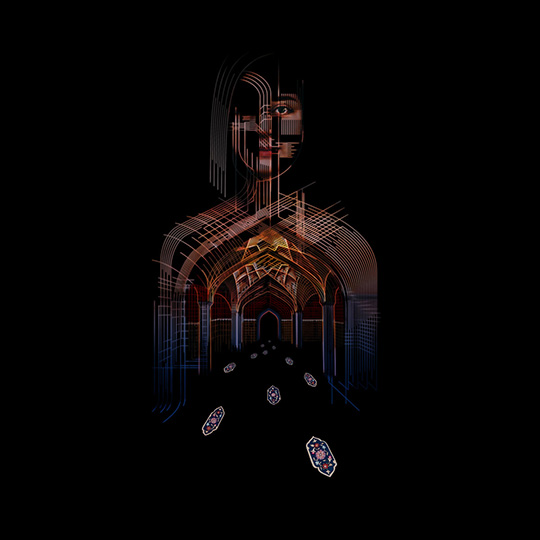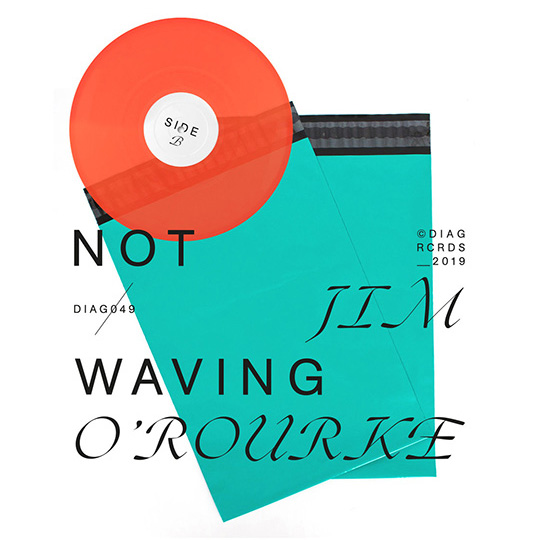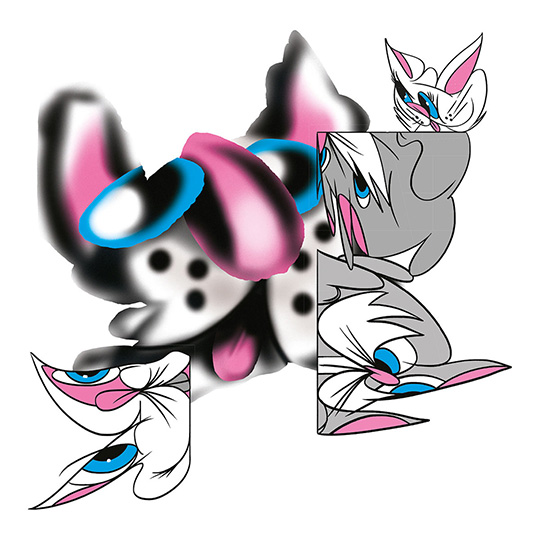MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Christian Fennesz & Jim O'Rourke- It's Hard For Me To Say I’m Sorr…

Christian Fennesz & Jim O'Rourke
It's Hard For Me To Say I’m Sorry
Editions Mego / Commmons
デンシノオト Jun 06,2016 UP
クリスチャン・フェネスとジム・オルークの競演盤が〈エディションズ・メゴ〉からリリースされた。長尺2曲収録の大作である(加えて国内盤は9分ものボーナストラックを収めている)。発売前は、ぼんやりとフェノバーグからピタ(ピーター・レーバーグ)が抜けたような音だろうか? と勝手に想像していたが、1曲め“ アイ・ジャスト・ウォント・ユー・ステイ”が鳴り初めた瞬間に予想を覆された。シルキーな弦楽のような音に、微かな電子を少しずつレイヤーされるという、まさにフェネスらしいロマン派的なアンビエント音響に、いかにもオルーク的のラップトップ作品的なポップネス&センチメンタリズムが交錯する楽曲であったのだ。ここまで衒いなく、両者が自分の音楽性を交錯させているとは予想しなかった。楽曲終盤の炭酸水のようなノイズと弾けるような電子音の交錯が最高に気持ちよい。
つづく2曲め“ウドゥント・ワナ・ビー・スウェプト・アウェイ”も圧倒的だ。フェネスの傑作『マーラー・リミックス』を思わせる後期ロマン派的なアンビエンスに、オルークは『アイム・ハッピー・アンド・アイム・シンギング・アンド・ア・1・2・3・4 』的なセンチメンタルでポップな電子音を繊細にレイヤーしていく。対して、フェネスは叙情的なノイズを細やかに生成し、空間をロマンティックに震わすのだ。そして、途中から鳴り始めるフェネスによるノイジー/叙情的なエレクトリック・ギターの凄まじさときたら! そして、その天空に上昇するような強烈なギターノイズに寄り添うように静かにベースラインが打たれていくのだが、これはオルークによるものか? ともあれ、静寂から雄大なノイズ、水平線のような静かさへ、といった趣に構成されるこのトラックは、両者のファンなら確実に悶絶ものである。それぞれが自由に存在しながらも、しかし、二人の演奏者/音楽家は、互いの音には繊細かつ大胆に反応している。まさに理想的な競演盤であった。
そして、ほぼ同時期に〈エディションズ・メゴ〉からピタの新作(!)がリリースされた。ちなみにピタことピーター・レーバーグは〈エディションズ・エゴ〉主宰にして中心人物である。彼は先に書いたようにフェノバーグ、そしてスティーブン・オマリーらとのKTLなど、ユニットでの活動は継続していたが、いわゆるソロ・アルバムは、しばらくの間、音沙汰がなかった。2010年のカセット作品『メスメル』以来、6年ぶりであろうか。
しかも、その待望の新作の名が『ゲット・イン』とくれば、さらに期待が高まるというものだ。そう、1999年に〈メゴ〉からリリースされた電子音響・グリッチ作品の傑作『ゲット・アウト』、2002年に同〈メゴ〉から発表された『ゲット・ダウン』、2004年に〈ハプナ〉から出た『ゲット・オフ』に続く、待望の「ゲット」シリーズ新作なのだ。ちなみに一連の「ゲット」シリーズは、90年代末期からゼロ年代のグリッチ=電子音響を語るうえで欠かせない作品群。その硬質かつ無機的なノイズの持続の中に不意に表出する微かなセンチメンタル=叙情性は、ゼロ年代のエレクトロニカ/電子音響特融の空気感を決定付けたといってもいい。
というわけで期待に胸と耳を震わせ聴いてみると、かなり驚いてしまった。私はこのアルバムに2度、驚いた。最初の驚きはアルバムの冒頭である。何しろ、00年代の作品群のような、クリアにして重力を反転させたかのような電子音響のレイヤーではなく、霞んだダーク・アンビエントな音色の持続音が流れだしたのだから。一瞬、音盤を間違えたのではないかと思ってしまったほどである。なにしろ1曲め“FVO”など、インダストリアル・ノイズと言っても過言ではないサウンドなのだ。とはいえ、あの傑作『セブン・トンズ・フォー・フリー』のリリースから20年、ピタもまた変化しているのだろう、そしてKTLとしての活動からも影響を受けたのではないかなどと思い直す。続く2曲め“20150609 I”ではグリッチを経由したオールドスクールな電子音が炸裂する。そうか。彼は「グリッチ以降」のサウンドとして電子音楽の歴史を包括するような音響を目指しているのではないか、などと考えながら聴き進めていくと、4曲め“ライン・エンジェル”という美しい曲名のトラックがはじまった。
私はこの“ライン・エンジェル”に相当に驚愕した。本アルバム2度めの驚きである。なんという天国的な美しさか。かつてのセンチメンタルな叙情性を持った電子音響の、その先にある天国的電子音響とでもいうべきか。この7分33秒のトラックには、音響の生成によって聴き手にサウンドへのアディクションを起こした「90年代末期~00年代のグリッチ/電子音響/エレクトロニカ」以降の音が、静謐に、慎ましく鳴っていたように思えてならない。電子音による美的音響空間の生成である。
この曲以降も、ディスコ調のコード進行のシーケンスフレーズを中心にした“S200729”や、まるで電子音による弦楽のレクイエムのような最終曲“MFBK”など、刺激的かつ美しい曲が続く。が、やはり、“ライン・エンジェル”に、もっとも耳が持っていかれた。この端正な音色の運動や蠢きによる美しさの生成に、グリッチ・サウンドのオリジネーターが生み出した「00年代以降」の音を、ついに聴いた思いがしたのである。
それにしてもフェネス、オルーク、ピタという90年代から活動を続けるアーティストの作品が一気にリリースされたいまという時代は、20年におよぶグリッチ/音響/エレクトロニカなど非アカデミック領域の電子音楽の歴史について考え直す、ちょうどいい時期なのかもしれない。新たな総括が必要なのだ。彼らの「驚き」をもたらす新作を聴きながら、この20年の歴史と現在について改めて考え直してみたくなった。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE