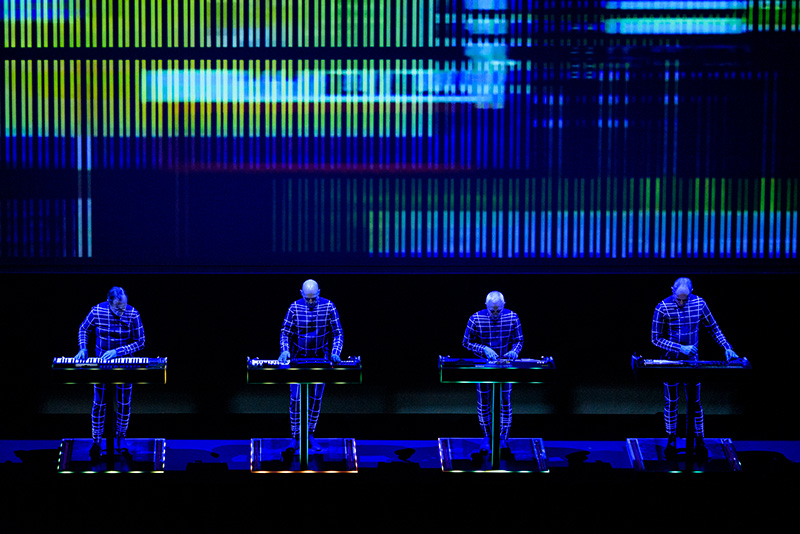ロンドンのジャズ・シーンはいろいろなミュージシャン同士の交流が盛んで、ときにトム・ミッシュ、ロイル・カーナー、ジョーダン・ラカイといった人たちの演奏にジャズ・ミュージシャンがフィーチャーされることも多々あるのだが、そうした中で独立独歩というか、インディペンデントな活動を大切にしているのがテンダーロニアスと彼のレーベルの〈22a〉だ。シャバカ・ハッチングスやモーゼス・ボイドらトゥモローズ・ウォリアーズ出身者が形成するサークルとは一線を画し、テンダーロニアスのほかモー・カラーズ、レジナルド・オマス・マモード4世、ジーン・バッサ兄弟などの仲間内で演奏や作品リリースはだいたい完結する。昨年リリースされたテンダーロニアス・フィーチャリング・22aアーケストラの『ザ・シェイクダウン』やジェイムズ・クレオール・トーマスの『オマス・セクステット』は、ほぼそうした身内で作られたものだった。
ルビー・ラシュトンはそうした〈22a〉の初期から屋台骨として存在するバンドだ。リーダーはテンダーロニアスことエド・コーソーンで、バンド名は彼の祖母の名前を由来とする。メンバーにはユセフ・デイズ、エディ・ヒック、モー・カラーズなどが名を連ねてきており、これまでにアルバムは『トゥー・フォー・ジョイ』(2015年)、『トゥルーディーズ・ソングブック第1集』と『同第2集』(2017年)をリリースしている。作品ごとにメンバーは多少入れ替わり、今度リリースされた通算4枚目のアルバム『アイアンサイド』ではエド・コーソーン(フルート、サックス、シンセ、パーカッションほか)、ニック・ウォルターズ(トランペット、パーカッション)、エイダン・シェパード(フェンダー・ローズ、ピアノほか)、ティム・カーネギー(ドラムス)というラインナップだ。エド、ニック、エイダンは全ての作品で演奏しているので、この3人がコア・メンバーとなるだろう。
『トゥー・フォー・ジョイ』はジャズやアフリカ音楽にヒップホップやビートダウンなどのセンスを融合したサウンドで、かつてマッドリブがやっていたジャズ・プロジェクトに近い方向性を持っていた。ただし演奏面には未熟なところも見られたのだが、『トゥルーディーズ・ソングブック』ではそれをより熟成させ、ジャズ本来の即興演奏の度合いを深めていった。タイプ的にはジャズ・ロックからジャズ・ファンク的な作品が多く、ハービー・ハンコックの“バタフライ”もカヴァーしていた。一方でコルトレーンの系譜に属するアフリカ色の濃いスピリチュアル・ジャズも特徴で、ユセフ・ラティーフに捧げた“プレイヤー・フォー・ユセフ”という曲も収録しており、テンダーロニアスの『ザ・シェイクダウン』とも共通の傾向を持つアルバムだったと言える。
『アイアンサイド』もそうした延長線上にあるアルバムで、ジャズ・ロックやジャズ・ファンク、モーダル・ジャズやスピリチュアル・ジャズが組み合わされた音楽となっている。“ワン・モー・ドラム”はテンダーロニアスの昔のスタジオ・プロダクションのリワーク再演で、西アフリカのリズムを由来とするドラムを軸にニックのトランペットが哀愁に満ちたソロを展開していく。ワルツ・テンポの“ホエア・アー・ユー・ナウ?”はテンダーロニアスのフルートとニックのトランペットの掛け合いで、テンダーロニアスは途中からエフェクトをかけたソプラノ・サックスに持ち替える。フリーフォームで先の読めない展開が多かったジャム・セッション風の『ザ・シェイクダウン』に比べ、『アイアンサイド』はアレンジをきっちり固めてスタジオでの演奏に臨んだそうで、この“ホエア・アー・ユー・ナウ?”や変拍子のヴァイタルなリズムにブレス奏法のフルートが絡む“イレヴン・グレープス”、アップテンポのジャズ・ロックの“ザ・ターゲット”などにはそうした洗練されたアレンジの跡がうかがえる。
“リターン・オブ・ザ・ヒーロー”は『トゥルーディーズ・ソングブック』における“プレイヤー・フォー・ユセフ”同様、テンダーロニアスにとってのフルートのヒーローであるユセフ・ラティーフに対するオマージュが表われた作品。“プレイヤー・フォー・グレンフェル”はイギリスの著名な探検家で医師のグレンフェル卿に捧げた曲のようだが、ここでのフルートもユセフ・ラティーフを彷彿とさせるもの。このようにテンダーロニアスの作品や演奏には、彼が影響を受けた過去の偉大なミュージシャンたちの姿が投影されるケースがあるのだが、そうしたひとつが“ペンギン・6(レクイエム・フォー・クシシュトフ・コメダ)”。ポーランドが生んだ偉大なピアニストで作曲家のコメダに捧げた曲で、実際にコメダによる1965年の映画音楽『ペンギン』がモチーフとなり、エイダンのピアノ・フレーズもかなりコメダに寄せている。テンダーロニアスはポーランドのイーブスというアーティストと共演してコメダのトリビュート曲をやったこともあり、そんな傾倒ぶりがうかがえるモーダル・ジャズだが、終盤は独自の解釈によるジャズ・ファンクへと展開していく。一方で“トリサートップス/ザ・コーラー”は、かつての4ヒーローのようなドラムンベースとジャズを掛け合わせたようなビートから、J・ディラのようなよじれ気味のヒップホップ×ジャズ・ファンク・ビートへと鮮やかに転移する現代ジャズらしい1曲。いろいろなジャズ、いろいろな音楽からの影響を素直に汲み上げ、それを参照しながら自分の音楽を形成していくのはいかにも英国の音楽家らしい。そしていまのアーティストにとどまらず、過去のアーティストたちの影響が多分に感じられるのがテンダーロニアスらしいところだろう。