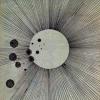MOST READ
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026
- KEIHIN - Chaos and Order
- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築
- 「土」の本
- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん
- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定
Home > Interviews > Flying Lotus - フライング・ロータス最新作『フラマグラ』の魅力とは?
自分はこういうのを期待されているからそれを裏切って、もっと尖った方向に行かなきゃいけないとか、そういう意識もぜんぜん感じない。本人は「誰かがクリエイティヴになるのを励ますような作品にしたい」とふつうに良いことを言っているんですよ(笑)。 (吉田)
原:フライローが出てきた当初は、いわゆるひとりでこつこつと密室でビートを作っているビートメイカーのようなイメージでした。〈Stones Throw〉でインターンをやったりして、LAのビートメイカーのコミュニティのなかにはいたんだけど、じっさいはヒップホップ色は薄かったと思う。デビューも〈Plug Research〉だったし。当時『1983』は日本では「ポスト・ディラ」みたいな紹介のされ方をしていたけど、ぜんぜんそれっぽい音ではなかった。
吉田:いわゆる後期ディラの影響のあるブーンバップに電子音、サイン波ベースというイディオムで作られてるのも1曲目だけですね(笑)。
原:「黒い」か「白い」かでいえば「白」っぽい音だった。レコードより、ネットの隅を掘っているというか、マッドリブみたいな感じではない。だから〈Warp〉と契約したのもすごく納得がいって、むしろああいうのがLAのブラック系の人から出てきたということのほうが当時はおもしろかったんですよね。〈Warp〉は当時プレフューズ73を推していたけど、そのあたりの白人のビートメイカーもなかなかそのあとが作れないという状況だったから。ダブリーもそうだったけど、ヒップホップじゃなくて、テクノなどエレクトロニック・ミュージックの人が作るビートが、期せずしてディラのようなビートとシンクロする流れがあって、そこに影響されたのがフライローや初期の〈Brainfeeder〉のビートメイカーたちだった。その先駆けみたいなところはある。それでフライローをきっかけにLAのビート・ミュージックが注目されて、00年代後半から10年代頭にかけて広がったんだけど、それも頭打ちになった。フライローははやい段階で「俺のビートのマネするな」とか言ってたけど、そのころから特殊な位置に居続けている。
吉田:確かに『Los Angeles』で確立される16分音符で打つヨレたハットに浮遊感のあるシンセのウワモノ、シンセらしさが前面に出た動きの大きいベースライン辺りのビートの文法がフォロワーたちの間で蔓延する。それで本人は『Cosmogramma』に行っちゃいましたからね。
原:そこから先、ビートを作っている人たちがどういうふうに音楽的に成長できるか、成熟できるかということをフライング・ロータスは考えていたと思うんですよ。彼の音楽って、いろいろとごちゃごちゃ入っている要素を抜くと、根本にあるものはティーブスに近くて、すごくメランコリックな音楽の組み立て方をしていると思うんです。ティーブスとかラス・Gとかサムアイアムとか、あのへんが彼にいちばん近かった連中だと思う。そのコミュニティで作ってきたものがベーシックにあって、そのうえに何をくっつけていくのかというところでいろいろ思考錯誤して、それがその後の〈Warp〉での彼の音楽だと思う。
それで、それまでひとりで作ってきたトラックメイカーがそこからさらに成熟したことをやろうとすると、たいていは生楽器を入れたり、あるいは壮大なコンセプトを練るじゃないですか(笑)。彼は今回の新作でそれにたいする答えを出したんだと思います。『You're Dead!』までは筋道がわかるんです。『Cosmogramma』ではアリス・コルトレーンを参照して、じっさいにハープの音を印象的に入れてストリングスも入れたり、『You're Dead!』では凄腕のジャズ・ドラマーを4人も入れてフライロー流のジャズに接近する側面を見せたりして、でも今回の作品ではもう一度、密室でひとりでビートを作っていたころの感じがある。いろんなゲストを交えながらも、原点に戻っているようなところが。
吉田:ジャズとの距離感が変わったというか、ジャズの磁場をそれほど意識していない印象ですよね。コルトレーン一家という自身の出自へのがっぷり四つでの対峙がようやく終わって、みそぎが終わったというか。「俺が考えるジャズをひとまずはやり切った」みたいな感じがありますよね。
いまはもうネタはすぐバレちゃうし、なんでも組み合わせられちゃうし、「こうすればこういうトラックができますよ」というのが当たり前の世界になっちゃったので、つまらないなと思うわけ。そういう意識は当然フライローにもあったと思う。 (原)
吉田:フライローのインタヴューで、今作のドラムの音色には大きく3つあって、それぞれを「小宇宙」だと思っていると言っていたんですよね。MPCとかソフトウェアサンプラーでブレイクビーツをサンプリングしてチョップしたドラムと、ミュージシャンが叩く生ドラム、そして808なんかのドラムマシンという3つです。それぞれのドラム・サウンドは探求し甲斐のある小宇宙と呼べるほどの深みを持っているわけですが、フライローはそれらを並列に扱っている。それぞれの楽曲やアルバムごとに3つの小宇宙の力関係が異なるという。「Reset EP」のときも、“Vegas Collie”という曲ではLAMP EYEの“証言”など多くの曲でお馴染みの、ラファイエット・アフロ・ロック・バンドの“Hihache”のドラムを16分で刻んで複雑なパターンにしていたけれど、他方で最後の“Dance Floor Stalker”ではドラムマシンも使っている。ふつうはそういうふうにまったくソースの異なる音色のドラムをひとつのアルバムに散りばめると、いかにも「さまざまな手法を取り入れてます」みたいな感じになっちゃいますが、フライローは初期からそれがうまくできている。ドラム・サウンドに限らず、ネタと生楽器と電子音をミッスクしたときに徹底的に違和感がない。今回のアルバムも1曲のなかでソースがさまざまに切り替わったりしているし、そういう素材の扱い方はすごく優れていて、それがよく発揮されたアルバムだと思います。
原:もちろんこれまでもやっていたんだけど、その混ぜる能力がすごく洗練されてきている感じはするね。自分ですべての音のデザインまでやる感じになっている。前回まではミックスやマスタリングはダディ・ケヴがやっていて、今回もケヴが関わっているけれど、フライロー自身がけっこうやっている。録音全体にもすごく気を使っているし、いままで以上にアルバム全体を見る力、構成力みたいなものがアップしていますね。ちなみに『You're Dead!』って、じつは40分くらいしかないんですよね。
吉田:意外と短い。
原:今回は60分以上ある。『You're Dead!』はたしかに、あの構成でやると40分しかもたなかったという感じはするんだよね。60分も聴いていられないと思うんだけど、今回は何度でも聴ける感じがある。
吉田:フライローは「ミックスはすごく難しい」と『Cosmogramma』のころに言っていて、当時もダディ・ケヴにも伝わらないから自分でもトライしている。『You're Dead!』では生ドラムの音をめちゃくちゃ歪ませていてすげえなと思いましたけど、あれに行きつくのにそうとう思考錯誤があったと思うんですよ。『Cosmogramma』ではアヴァンギャルドな楽曲のベクトルに合わせるようにベースやドラムは歪みや音圧に焦点を当てて、次作は空間的なアンビエンスに焦点を当てて電子ドラムはハイを出してレンジが広がっている。そういった実験もひと通りやり終えた感じがします。だから今回は極端な歪んだサウンドも聞こえてこない。そうなると普通は「売れ線に走った」とか「きれいになっちゃっておもしろくない」ってなるんだけど、フライローだと「あなたがあえて綺麗な音作りをするということは、そこに何か意味があるに違いない」という像ができあがっていて(笑)、でも本人は裏をかいているつもりはないだろうし、気にしないで自由にやっているだけだと思うんです。自分はこういうのを期待されているからそれを裏切って、もっと尖った方向に行かなきゃいけないとか、そういう意識もぜんぜん感じない。本人は「誰かがクリエイティヴになるのを励ますような作品にしたい」とふつうに良いことを言っているんですよ(笑)。
原:人の励みになる音楽を作りたいとか、そんなこといままで言ったことないよね。たぶん立ち位置が変わってきたんだろうね。〈Brainfeeder〉についてもかなりコントロールしているというか、たんに自分の名前を冠しているだけじゃなくて、アーティストのセレクトもちゃんと自分でやっているし。本腰を入れてやっているからこその責任もあるんだと思う。これまでは自己表現みたいなことで終わっていたのが、あきらかに違うレヴェルに行っている。
Profile
 原 雅明/Masaaki Hara
原 雅明/Masaaki Hara音楽ジャーナリスト/ライター、レーベルringsのプロデューサー、LAのネットラジオ局の日本ブランチdublab.jpのディレクターも担当。ホテルの選曲やDJも手掛け、都市や街と音楽との新たなマッチングにも関心を寄せる。早稲田大学非常勤講師。著書『Jazz Thing ジャズという何か』ほか。
Profile
 吉田 雅史/Masashi Yoshida
吉田 雅史/Masashi Yoshida1975年、東京生まれ。異形のヒップホップグループ8th wonderを中心にビートメイカー/MCとして活動。2015年、佐々木敦と東浩紀(ゲンロン)が主催の批評再生塾に参加、第1期総代に選出される。音楽批評を中心に文筆活動を展開中。主著に『ラップは何を映しているのか』(大和田俊之氏、磯部涼氏との共著)。Meiso『轆轤』プロデュース。
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE