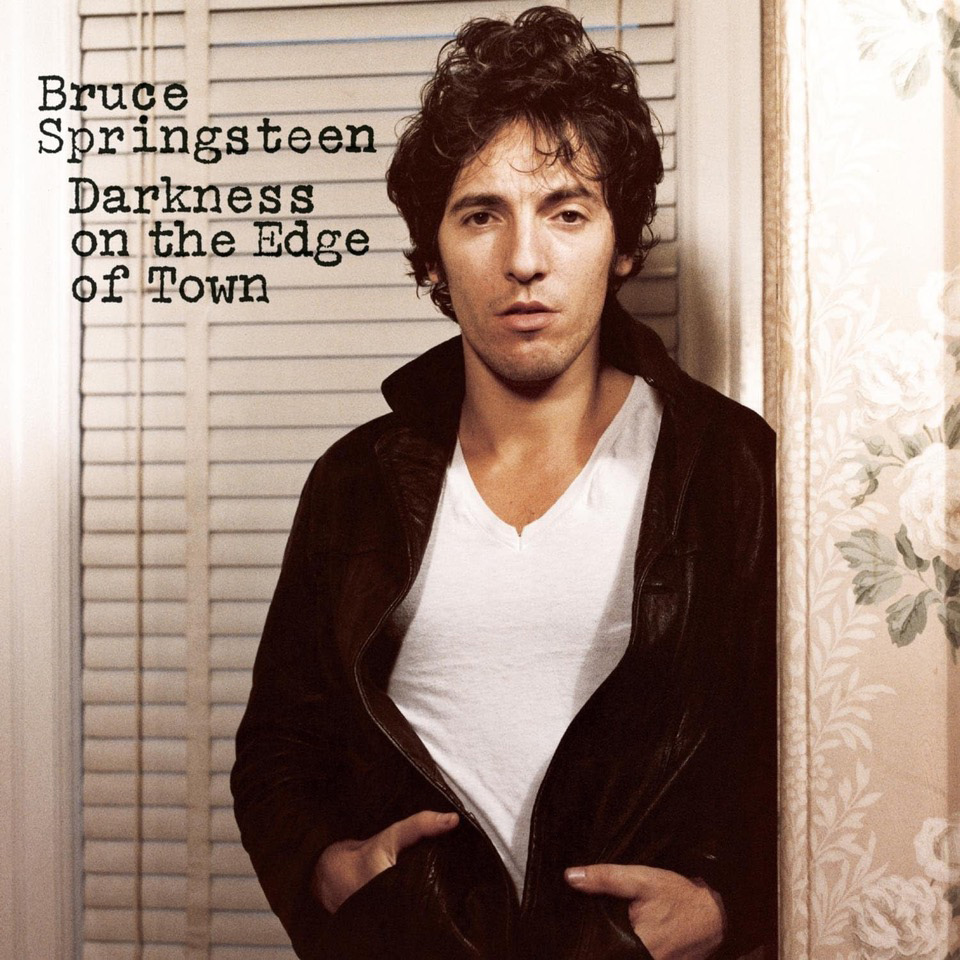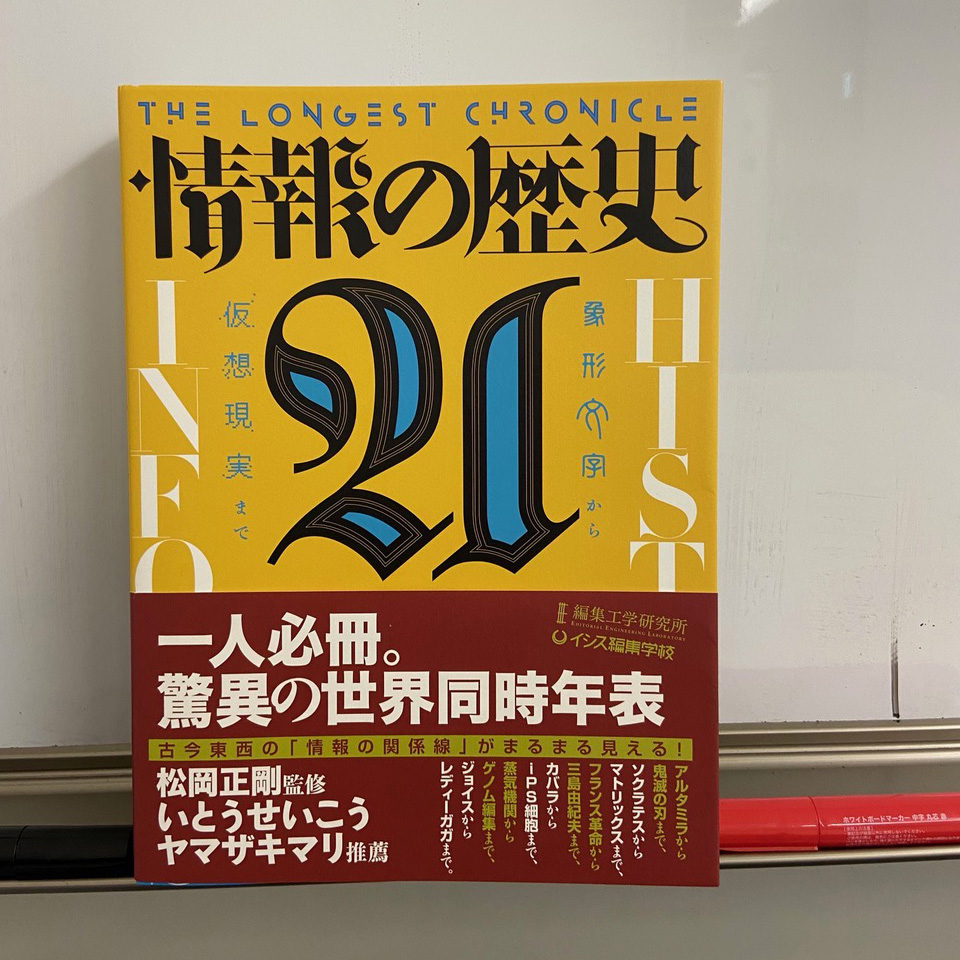MOST READ
- Columns スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- 鈴木孝弥
- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー
- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面
- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも
- Taylor Deupree - Sti.ll | テイラー・デュプリー
- R.I.P. Steve Albini 追悼:スティーヴ・アルビニ
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Mansur Brown - NAQI Mixtape | マンスール・ブラウン
- interview with Mitsuru Tabata アウトサイダーの履歴書――田畑満
- Theo Parrish ──セオ・パリッシュがLIQUIDROOM 20周年パーティに登場
- 相互扶助論 - ピーター・クロポトキン 著小田透 訳
- しばてつ・山田光・荒井康太トリオ ──生々しいフリー・ジャズが響きわたるライヴ録音盤
- John Cale - POPtical Illusion | ジョン・ケイル
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
- Aphex Twin ──30周年を迎えた『Selected Ambient Works Volume II』の新装版が登場
- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン
- interview with John Cale 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 | ジョン・ケイル、インタヴュー
Home > Columns > ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
今年に入って、20数年ぶりに拙著『ブラック・マシン・ミュージック』を読み返す機会があった。近い将来文庫化されるというので、加筆修正のためではあったが、20年以上前に自分の書いたものを読むというのはなかなかの重苦だった。その痛みに身悶えしながら、書き足りていないと思ったのは、デトロイト・テクノにおけるプリンスの影響の箇所である。本のなかではエレクトリファイン・モジョのところで少しばかり触れているが、あまりに少しばかりだ。デトロイトにおけるプリンスの人気はすさまじく、言うなれば、70年代のブラック・デトロイトのエースがPファンクだとしたら80年代のその座はミネアポリス出身のプリンスだった。取材するのが困難だった80年代の人気絶頂期にプリンスが快くインタヴューに応じたのがエレクトリファイン・モジョのラジオ・ショーだった。『サイン・オブ・ザ・タイムズ』の前年には、彼の誕生パーティをデトロイトで開いたほどだ。これはこれで文化現象としていろんな深読みができるトピックだが、当時の原稿では、その程度の事実しか書いていない。
デトロイト・テクノ第一世代は70年代後半に思春期を送っているので、最初の影響という点では圧倒的にPファンクだ。が、カール・クレイグやムーディーマンといったその下の世代になるとその影響は明らかになってくる。クレイグの初期作のエロティシズムおよびキュアーを愛したニューウェイヴ趣味もさることながら、ムーディーマンにいたっては(モジョのインタヴューまでサンプリングしているし)彼の身なりからも影響はあからさまだ。

80年代の『ダーティ・マインド』から『ラヴセクシー』までのプリンスがあらゆる位相において、いま聴き直しても発見があるほどすばらしかったことは言うまでもない。ここでは、彼のディスコ/白人ニューウェイヴ趣味、そして、いまでは“先駆的だった”と各方面から評価されている露骨なクィア・センス(あるいは、レーガンの80年代に“If I was Your Girlfriend”を歌うこと)に着目したい。なにしろ、シカゴの野球場で大量のディスコのレコードが爆破されてから1年後の『ダーティ・マインド』なのだ。「ディスコとして知られる恐ろしい音楽病を根絶するための戦争」のピークのまだその翌年の話である、ブリーフ一丁でアルバムの1曲目からディスコ・ビート。80年代、「黒人らしくない」という批判(参照:ネルソン・ジョージ『リズム&ブルースの死』の最終章およびプリンス “コントラヴァーシー” の歌詞)を浴びていたプリンスは、ストレートなソウルやファンクをやらなかった、のではない。そもそもソウルやファンクには時代のモードこそあれ、スタイルは流動性にあることをこの黒人イノヴェイターは時間をかけて証明し、21世紀へと続く未来を切り拓いたのだった(例:ジャネル・モネイとフランク・オーシャン)。
グラムこそパンクである、歴史的にもコンセプトにおいても。
──マーク・フィッシャー
にしても……である。彼とザ・レヴォリューションはハードコアだった。数年前に映画『サマー・オブ・ソウル』に登場する全盛期のスライ&ザ・ファミリー・ストーンの、黒人女性も白人女性もメンバーにした圧倒的なステージを見ると、ああなるほど、ザ・レヴォリューションの原型はここにあるのかと思ったものだが、ディスコもセクシャリティの攻撃的な発露は当然のことまだない。よく言われるように、ロックの性表現は、基本男根的で、男性優位のそれだった。対してディスコのエロティシズムは両性具有的、ないしは女性的だった(例:グレイス・ジョーンズの“I Need a Man”)。もちろんなかには、マッチョを強調したゲイ・ディスコもあったが(例:ヴィレッジ・ピープル)、「本物の男になれ」という時代にあっては、ディスコは野球場で爆破されるまでのなかば国民的な敵意を生んだというわけだ。
Pファンクがディスコの時代にディスコを非難しながらディスコをやった話はよく知られている。彼らの数あるクレイジーな傑作のなかのひとつ、『Funkentelechy Vs. The Placebo Syndrome』(1977)がそれだ。その前年、Pファンカーたちは、ファンカデリックの“Undisco Kidd”(『Tales Of Kidd Funkadelic』収録)という曲においてディスコの性的な光景をコミカルに風刺した。「一面的なファンクや一面的なディスコは好きじゃない」とジョージ・クリントは言っているが、逆に言えば、一面的でなければ彼はディスコもやった。その最初の成果が消費主義社会を批判したくだんのアルバムに収録の、ヒット曲“Flash Light”だった。そして、そう、続いては、お馴染みの“One Nation Under a Groove”(1978)が待っている。これはファンク神秘主義と政治性が結合した励ましのディスコ・ソングであり、音楽的に見てもプリンスのディスコ・ビートがもうすぐ聞こえてきそうだ。
ディスコは、(ロックもそうだったが、ロック以上に)黒人音楽のリズムを応用している。パーカッシヴな特質をより発展させ、簡素化しわかりやすくしているが、活かしているのだ。しかしながら映画『サタデー・ナイト・フィーバー』がヒットする1977年には、それは音楽産業にとって都合の良いブームとなった(参照:トム・ウルフ『そしてみんな軽くなった』)。庶民からの音楽ではなく、プロデューサー主導型の、庶民に供給され売りつけられる音楽となった。また、性的表現も、おおよそ男性目線のポルノグラフィーと化したことは、当時のレコード・ジャケットを見ても察せられよう。〈スタジオ54〉に代表されるセレブ趣味/金儲け主義が強調されたこと、その恍惚が個人主義の産物であったことは、さらにまた文化的見地からの批判を集めている。Pファンクが反論したのもこうした点だった。“One Nation Under a Groove”は、セレブ趣味の選民性から排除された人たちに呼びかけ、著述家でDJでもあるクリス・ニーズによれば「ディスコ本来の団結力をPファンクの桶のなかで再構築した」曲だった。
ここでデトロイト・テクノのファンのためにもうひとつ、ホアン・アトキンスに影響を与えた曲を挙げておく。ヒップホップのファンにはお馴染みの1979年の“Knee Deep”だ。“Flash Light”、“One Nation Under a Groove”、そして“Knee Deep”、これをぼくはPファンク流ディスコ三部作と呼んでいるが、当初この原稿で書きたかったのは、さらにもう1曲のPファンク流ディスコのクラシック、1978年の“Aqua Boogie”のことだった。ふぅ。やっと本題だ。
“Aqua Boogie”——“A Psychoalphadiscobetabioaquadoloop(サイコアルファディスコベータバイオアクアドゥループ)”なる副題が付いたこの曲も、人気曲のひとつで、そしてデトロイト・テクノのファンなら、ドレクシアの“アクアバーン(Aquabahn)”が、この曲とクラフトワークの“アウトバーン”との語呂合わせであることに気がつくだろう。「水」はいまなら、資本主義社会すなわち「うじ虫(magott)」が生きづらい社会というメタファーとして解釈できる。さすればおのずと、ドレクシア神話の意味もより複層化されるというもの、だ。そう、“Aqua Boogie”を擁する『Motor Booty Affair』は、Pファンクによる水中SF作品なのだ。
水は嫌いだ、俺を行かせてくれ、下ろしてくれ
ひゃぁぁあ、あんたら濡れてるじゃん! 溺れてたまるか
梅雨の季節にも相応しく思えるこの曲は、いつものように脳天気を装いながらも、メッセージはじつにシリアスで、謎めいてもいる。「ああ、息が詰まりそうだ」とわめき立てる“Aqua Boogie”には、ジョージ・クリントならではのキラーなフレーズがある。「With the rhythm it takes to dance to what we have to live through. You can dance underwater and not get wet」(俺らが生き延びるべく踊るために必要なリズムをもってすれば、水のなかで踊っても濡れない)。ジョージ・クリントンはつまり、どんなに苦しい生活でも、苦しさに支配されないリズムがあると言っている。それなら水のなかでも踊っても濡れない。


Pファンクを聴いてつくづく感服するのは……、まあ、しかもこの時期は、ブーツィー、バーニー、ジェローム・ブレイリー、フレッド・ウェズレーにメイシオ・パーカーらJ.B.難民たち、デビー・ライトやジャネット・ワシントン、マッドボーン・クーパー、ジュニー・モリソン、故ゲイリー・シャイダー……燦々と輝く黄金のメンバーが揃っているのでどの楽曲もたいてい魅力的なのだが、文化的なすごさを考えるに、ジョージ・クリントンの表現力の、白い社会(およびそれに憧れる日本)からは見えない奥深い面白さにはあらためて、ほんとうに舌を巻く。その昔デリック・メイが「それを俺たちは哲学として聴いた」と言ったのは、決して誇張ではない。政治的なメッセージを、高級化したリベラル層ではなく街の与太者たちに伝えるには、高度なストリート用語と黒人英語を駆使し、笑えるくらいの言い表しでなければならない。そのためには「ウジ虫」の目を通して宇宙を語り、タイトなブリーフどころか大きなオムツをはいて演奏することも必要だった。
どうせ社会の片隅に追いやられるのであれば、片隅の言葉で話せばいいじゃないか。
——イアン・ペンマン
息もつけないほど苦しい時代のなかで生きていることを、あらためて説明するまでもないだろう。この私めは、先日、ベス・ギボンズのレヴューでうかつにも「小池vs蓮舫」で都知事選が面白くなったなどと軽口を叩いてしまったことを、公約を見てつくづく後悔している次第だ。「ウジ虫」の目を通して言えば、まったく面白くない! だから面白いことを考えよう。Pファンカーたちのことを考えてPファンクのレコードを聴こう。彼らのたくさんある狂った名曲のひとつに、“Give up the Funk (Tear the Roof off the Sucker)”がある。直訳すると「ファンクなんて止めちまえ(その建物の屋根を引っ剥がせ)」、意訳すれば「ファンクをよこせしやがれ(屋根を剥がすほど騒いでパーティしよう)」。Give up the Funk=Give us the Funk。「おまえがファンクを諦めてくれたらそのファンクは俺のもの(だからおまえはファンクを諦められない)」。この共有感覚はハウス・ミュージックの定義を言葉で表現したチャック・ロバーツの“In the Beginning (There was Jack)”を彷彿させる。「君のハウスは俺のハウス、だからこれは俺らのハウス」。しかもPファンクのリズムは、UKポスト・パンク(例:ザ・ポップ・グループ)へと伝染し、“One Nation Under a Groove”を経て人種的ステレオタイプを超越するプリンスの、たとえば “Let's Go Crazy”のような曲へと連なっているのであった。
ジョージ・クリントは自伝『ファンクはつらいよ』のなかで、80年代に「最高に格好良かったのはプリンスだ」と言っている。「彼の曲をじっくり聴いてみると、俺たちがファンカデリックでやっていたことを、ロックやニューウェイヴでアップデートしていることがわかった」
エレクトリファイン・モジョの耳は間違っていなかった。デトロイトがプリンスを愛し、プリンスもデトロイトを「第二の故郷」と呼ぶほど愛したのも、音楽的にも、社会的にも文化的にもなるべくしてなったことだった。それはそれで美しい話だが、問題なのはいま我々が水のなかにいるってことだ。だから、たとえ水のなかでも濡れない、そんなリズムを見つけよう。そして願わくば、永遠の課題である、我らの新しい片隅の言葉を。
※本稿を書くに当たって、Pファンクを愛するふたりのアフリカ系アメリカ人の友人、ニール・オリヴィエラとデ・ジラの助けがあったことを追記しておく。

COLUMNS
- Columns
スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns
6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns
♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns
5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns
E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns
Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns
♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns
4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー


 DOMMUNE
DOMMUNE