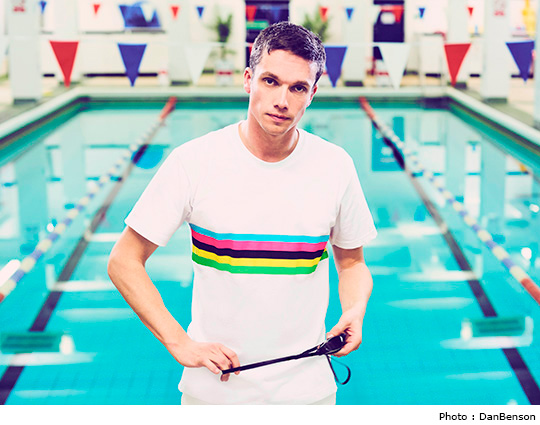MOST READ
- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース
- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース
- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界
- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由
- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!
- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール
- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場
- ele-king presents HIP HOP 2025-26
- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定
- 坂本慎太郎 - ヤッホー
- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて
- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー
- KEIHIN - Chaos and Order
- ロバート・ジョンスン――その音楽と生涯
- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026
- DIIV - Boiled Alive (Live) | ダイヴ
- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー
- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築
- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん
- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」
Home > Interviews > interview with POWELL - すべてのテクノが退屈に聴こえるとき
俺は間違っても君がやっている音楽のリスナーではない。俺は機械化されたダンス・ミュージックが大嫌いなんだ。それがプレイされるクラブも、クラブに行くような連中も、連中が摂っているドラッグも、話している内容も、着ている服装も、やつらのなかのいざこざも、基本的に、100パーセント、そのすべてを憎んでいる。
俺が好きなエレクトロニック・ミュージックは、ラディカルで他と違ったもの──ホワイト・ノイズ、クセナキス、スーサイド、クラフトワーク、それから初期のキャバレー・ヴォルテール、SPKやDAFみたいな連中だ。そういうシーンや人たちが/クラブに吸収されたとき、俺は敗北感すら覚えたものだ。俺はダンスこの地球上の何よりも深くクラブ・カルチャーを憎んでいる。そう、俺は君がやっていることに反対しているし、君の敵なんだ。
──パウウェルがビッグ・ブラッグをサンプリングしたことを
スティーヴ・アルビニに知らせたところ、
本人から返信されたメールより
いや、だからこっちはそれどころじゃないんだって。日曜日のサッカーの時間がはじまる1時間前からもうほかのことは考えられない。時間がずれていたらライヴァルたちの試合も見なければならない。試合後は、監督インタヴュー/選手コメントを3回以上は読み返す。ホント、応援するほうもたいへんだよ。J1昇格、すなわち人生がかかっているんだから。
もちろん某君にとってはどうでもいいことだった。アレックス・スモークもゾンビーも、アルバム、いまひとつだったな、と彼はぶっきらぼうにつぶやいたのだ。それから、彼はこういう。もっとできたはず。
もっとできたはず? いや、いまはどんなに泥臭くてもいいから勝って欲しいし、こう言ってはナンだが、連中はまだずっとマシな部類に入る。多くのクラブ・ミュージックがいま見失っているものはアティチュードにほかならない。テクノというジャンル名は、ホアン・アトキンスによってアルビン・トフラーの『第三の波』の“テクノ・レベル”から取られたという話は有名だが、早い話、その“レベル”の部分が欠落している。つまり、スリーフォード・モッズと〈Editions Mego〉との溝を埋める存在はおらんのかと。パウウェルが注目されなければならない理由はまずここにある。
「絶え間なく新たな難題に直面しているような感覚……」と、パウウェルは説明する。台頭する右翼勢力、シリア内戦と難民、あるいはブリグジットにトランプ、いまやネットで世界中のニュースにアクセスできる。この10年で、未来/フューチャーという、80年代~90年代のハウス/テクノの楽天的な合言葉も喪失したわけだが、パウウェルときたら、まさに日々更新される恐怖のなかで、それでもぼくたちは楽しくやっているんだと言わんばかりだ。笑いがあるんだな。ここにもうひとつ、パウウェルに惹かれる理由がある。
ジョン・サヴェージの『イングランズ・ドリーミング』によれば、否定者とは時代を切り拓くものであるから、期待しましょう。『スポート』は、パンク40周年の2016年にリリースされたテクノ界のブライテスト・ホープの最初のアルバム、アンダーグラウンド・ロックンロールの声明である。
え、もっとできたはず?
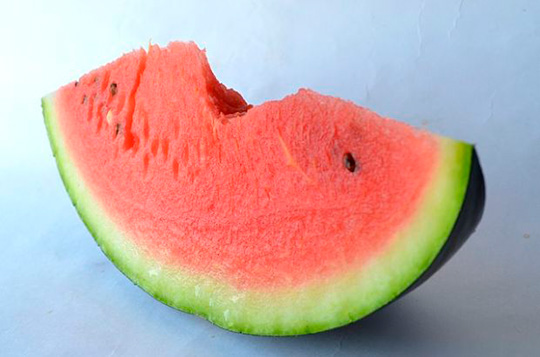
エレクトロニック・ミュージックにはもっとアティテュードが必要だ。極端に味気なく(flat)になってるし、政治性も閃きもアイデンティティも欠落しきっている。あまりにも無難で刺激がない。いまや、フェスティヴァルが音楽界の風景をコントロールしているような気分になってるどこかのエージェントがつまらない出演者ばっかりブッキングして悦に入っているが、ぼくは音楽でエンターテイナーになるのはごめんだ。
 Powell Sport XL Recordings/ホステス |
■最初の質問はちょっとファニーに聞こえるかも、ですが、なぜスイカ(https://www.youtube.com/watch?v=8bYsnJfRcdA)なんですか?
パウウェル:えぇと……、全部は話せないな、ちょっと汚い話なんで。その……どうしよう、誰にも裏話は教えられないな、ちょっと恥ずかしいから。ただ、14才のとき、ぼくの身にあるおかしな出来事が起こった、とだけ言っておく(笑)
■それだと余計に興味を持たれそうだけど(笑)、とにかく何かを象徴してはいるんですね、スイカは。
P:象徴するものはあるよ。ただ、メロン自体はぼくが自分のラジオ番組をメロン・マジックにしたり、ちょこちょこ使ってるうちにぼくのファニーなアイデンティティのようになっていたんで、今回はそれを茶化したってとこだね、ほんとのところ。
■なるほど。じゃあ、こちらで
P:うん。
■さて、あなたは作っているヴィデオもおかしくて興味深くて行間を読みたくなるという……
P:うん、もちろん。
■観る人に「これはどういうこと?」と考えさせようという意図もあるんでしょうか。
P:いや、そんなことないよ。なんだろう……ぼくがやることはみんな、音楽もそうだし、音楽について語るときも、自分の見せ方にしても、ありのままの自分を可能な限り真実で正直な姿で表現しようとしているだけなんで、ヴィデオも……あのメロンにしても、ぼくが友だちとツアー先でメロンで遊んでるっていう、それだけのこと。ぼくが作るヴィデオはどれも自分自身を反映しているにすぎない。みんなに、何がぼくの動機付けになっていて、ぼくがどういう人なのかをわかってもらいたいだけで、わざとらしいものを作ろとしてるわけじゃない。そういう意味じゃ、推測すべきことなんて何もないんだよね。すべてはぼくなんであって、これが真実ってこと、基本的に。
■“ジョニー”のヴィデオもそうだし、“アンダーグラウンド・ロックンロール”(https://www.youtube.com/watch?v=bamMBFc8AtU)も……
P:あぁ、“アンダーグラウンド・ロックンロール”のヴィデオはぼくも好きで、何が好きかっていうと……ぼくはポピュラー・カルチャーの搾取が大好きなんだよ。アンダーグラウンドのどん底あたりにいるアーティストがポピュラー・カルチャーを利用して、搾取して、それで遊んでしまうというのが面白い。ぼくは前からその手のものが大好きだった。ポップ・アートが好きだから、アンディ・ウォーホルを真似て自分の顔を描く、なんてことも、もっと若い頃にはやってみたし。そうやってカルチャーを搾取することには、前々から関心があったんだ。そういうのって、やっていることに注目してもらう手段として面白いし、そこに周囲とのインタラクションを生み出すのもまた面白い。
ぼくはけっこう肯定派なんだよね、その……、マーケティングとかプロモーションとかいう言葉を使うのは好きじゃないけど、ぼくがアートとしてやっていることと別物だとは思っていなくて、実は同じことだと考えているんだ。ぼくは自分の音楽をみんなに聴いてもらう術を探し出すこともまた楽しいと思ってる。だって、結局のところぼくはこれを生涯ずっとやっていきたいんだから、みんなに聴いてもらいたいよ。じゃないと、作り続けていけないし。
■アクセスしやすさ、というのもアートの一環、ということでしょうか。祭り上げるのではなく。
P:そうだね。ただ、アクセスしやすい、という言い方は間違いかも。というのも、ぼくはとっつきやすいものを創ろうとしたことはないんで。出来たものに対して人びとを呼び込もうとはするけど、わかりやすい音楽を作って気に入ってもらおうとしているわけじゃない。ぼくはぼくのやることをやって、その上でみんなに入ってきてもらうための方法を模索する、ということ。入って来ずらいようにはしたくない。
■同じことがタイトルにも言えますか。『スポーツ(SPORT)』というのは、どう解釈したらいいのか。
P:“SPORT”って、ぼくは素敵な概念だと思うんだ。人びとが競い、闘い、苦しみ、努力し……スポーツにはそういうのがみんな詰まってる。精神的なものも、肉体的なことも、そして難しくもあり、楽しくもあり。そこがぼくにはすごく重要なんだよね。ぼくにとってこのレコードは心と体と両方に働きかけるものだ。いまのダンス・ミュージックは体だけ……になっているとぼくは思うんだけど……じゃなくて、もっと全方向的な体験……ゲームみたいな感じかな。多角的で、進んだ先々で予想もつかない楽しみが待っている。ぼくとしては、レコードを中心にゲーム的な感覚を生み出す、という発想が気に入っていて、作りながら自分でもそんな感覚を味わっていたんだ。だから、この言葉がいちばん相応しいように感じた。それに、なかなか素敵な言葉だと思うよ、スポーツって。人によって意味するものがいくらでも変わってくるだろうから、好きに解釈してもらえるのもいいところだ。
■スポーツって、アートとは対極のイメージがありますが。
P:ぼくも子供の頃はスポーツやってたけど、いまはスポーツが得意なタイプじゃない。いまでも観るのは好きだけどね。とはいえ、POWELLのショウを持ちこたえるには、かなり運動能力が必要だから、ね、その意味でも相応しいかも。
■ダンス・ミュージックはおっしゃるとおりフィジカルだし。
P:そう。
質問:野田努+染谷和美(2016年11月16日)
INTERVIEWS
- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー
- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー
- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る
- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー
- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー
- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー
- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る
- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー
- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー
- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト
- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー
- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る
- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る
- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る
- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ
- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」
- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー
- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー
- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE