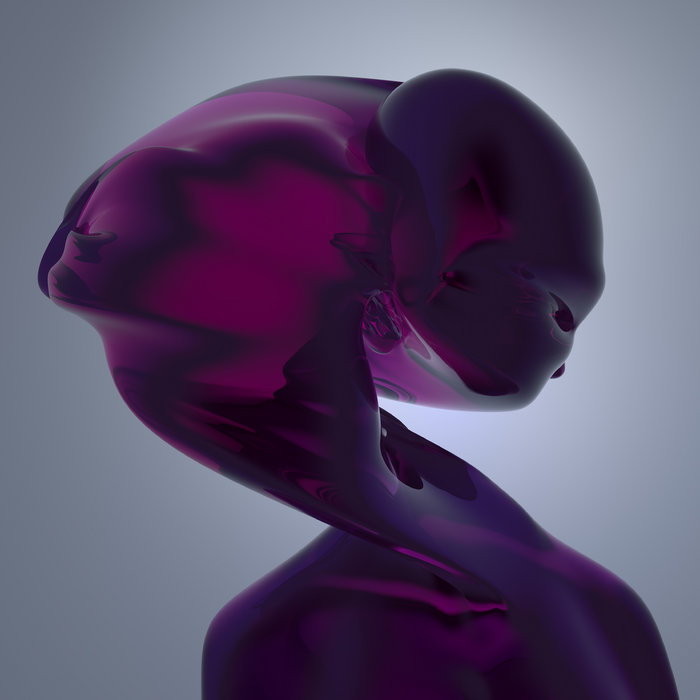歓喜とはこのこと。2022年のすばらしいライヴをおぼえているだろうか。いまもっとも重要なエレクトロニック・ミュージシャンのひとり、ロレイン・ジェイムズの再来日が決定している。嬉しいことに、今回もロレイン・ジェイムズ名義とワットエヴァー・ザ・ウェザー名義の2公演。しかも、ジェイムズが敬愛しているという aus と蓮沼執太がそれぞれの公演をサポートする。いやこれ組み合わせもナイスでしょう。
ワットエヴァー・ザ・ウェザー&ausは5/15に、ロレイン・ジェイムズ&蓮沼執太は5/17に、いずれもCIRCUS Tokyoに登場。なお、ジェイムズはその後STAR FESTIVALにも両名義で出演します。ゴールデンウィーク後はしっかり予定を空けておくべし。
LORAINE JAMES // WHATEVER THE WEATHER JAPAN TOUR 2024
2022年の初来日公演が各所で絶賛され、2023年にLoraine James名義でHyperdubからリリースした最新作『Gentle Confrontation』が様々なメディアの年間ベスト・アルバムにも名を連らね、現代のエレクトロニック・ミュージック・シーンにおける再注目の存在であるLoraine James // Whatever The Weatherの再来日が決定致しました!
Loraine JamesとWhatever The Weatherでそれぞれ東京公演を行い、京都のSTAR FESTIVALにも両名義で出演致します。
また、東京公演のサポート・アクトにはLoraineが敬愛するaus(5/15公演)と蓮沼執太(5/17公演)が出演致します。
ausはハイブリッドなDJ+ライブセットを、蓮沼執太はソロセットを披露致します。
イベント・ページ:
https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/news/loraine-james-2024/
Loraine James // Whatever The Weather
Japan Tour 2024
Whatever The Weather 東京公演
Ghostly International 25th Anniversary in Japan vol.1
日程:5/15(水)
会場:CIRCUS Tokyo
時間:OPEN 19:00 / START 20:00
料金:ADV ¥4,500 / DOOR ¥5,000 *別途1ドリンク代金700円必要
出演:
Whatever The Weather
aus
チケット:
イープラス https://circus.zaiko.io/e/whatever
ZAIKO https://eplus.jp/sf/detail/4082320001-P0030001
Loraine James 東京公演
日程:5/17(金)
会場:CIRCUS Tokyo
時間:OPEN 18:30 START 19:30
料金:ADV ¥4,500 / DOOR ¥5,000 *別途1ドリンク代金700円必要
出演:
Loraine James
Shuta Hasunuma
チケット:
イープラス https://circus.zaiko.io/e/lorain
ZAIKO https://eplus.jp/sf/detail/4082290001-P0030001
STAR FESTIVAL
日程:2024年5月18日(土)〜19日(日)
会場:府民の森ひよし 京都府南丹市日吉町天若上ノ所25 Google Map forest-hiyoshi.jp
時間:2024年5月18日(土)10:00開場 〜 19日(日)17:00閉場
Loraine James, Whatever The Weatherは両名義とも5/18に出演
料金:
前売入場券(ADV TICKET) ¥13,000
グループ割引入場券(4枚):¥46,000(1枚11,500円)
駐車券(PARKING TICKET) ¥3,000(オートキャンプA ¥20,000 / オートキャンプB ¥16,000 / オートキャンプC ¥6,000)
出演:
Craig Richards
DJ Marky
DJ Masda
Fumiya Tanaka
Loraine James
Whatever The Weather
Zip
and more…
チケット:
イープラス https://eplus.jp/starfestival2024/
ZAIKO https://thestarfestival.zaiko.io/e/2024MAY
楽天チケット http://r-t.jp/tsf
オフィシャルサイト:https://thestarfestival.com/
------
主催・企画制作:CIRCUS / PLANCHA
協力:BEATINK

Photo by Ivor Alice
Loraine James // Whatever The Weather:
ロレイン・ジェイムス(Loraine James)はノース・ロンドン出身のエレクトロニッック・ミュージック・プロデューサー。エンフィールドの高層住宅アルマ・エステートで生まれ育ち、母親がヘヴィ・メタルからカリプソまで、あらゆる音楽に夢中になっていたおかげで、エレクトロニカ、UKドリル、ジャズなど幼少期から様々な音楽に触れることとなる。10代でピアノを習い、エモ、ポップ、マス・ロックのライヴに頻繁に通い(彼女は日本のマスロックの大ファンである)、その後MIDIキーボードとラップトップで電子音楽制作を独学で学び始める。自宅のささやかなスタジオで、ロレインは幅広い興味をパーソナルなサウンドに注ぎ込み、やがてそのスタイルは独自なものへと進化していった。
スクエアプッシャーやテレフォン・テル・アヴィヴといった様々なアーティストやバンドに影響を受けながら、エレクトロニカ、マスロック、ジャズをスムースにブレンドし、アンビエントな歪んだビートからヴォーカル・サンプル主導のテクノまで、独自のサウンドを作り上げた。
彼女は2017年にデビュー・アルバム『Detail』をリリースし、DJ/プロデューサーであるobject blueの耳に留まった。彼女はロレインの才能を高く評価し、自身のRinse FMの番組にゲストとして招き、Hyperdubのオーナーであるスティーヴ・グッドマン(別名:Kode 9)にリプライ・ツイートをして、Hyperdubと契約するように促した。それが功を奏し、Hyperdubは2019年に彼女独特のIDMにアヴァンギャルドな美学と感性に自由なアプローチを加えたアルバム『For You and I』をリリースし、各所で絶賛されブレイク作となった。その後『Nothing EP』、リミックス、コラボレーションをコンスタントにリリースし、2021年に同様に誠実で多彩なフルレングス『Reflection』を発表。さらなる評価とリスナーを獲得した。2022年には1990年に惜しくも他界したものの近年再評価が著しい才人、Julius Eastmanの楽曲を独自の感性で再解釈・再創造した『Building Something Beautiful For Me』をPhantom Limbからリリースし、初来日ツアーも行った。そして2023年には自身にとっての新しい章を開く作品『Gentle Confrontation』をHyperdubから発表。これまで以上に多くのゲストを起用しエレクトロニック・ミュージックの新たな地平を開く、彼女にとって現時点での最高傑作として様々なメディアの年間ベスト・アルバムにも名を連ねた。
そしてロレインは本名名義での活動と並行して、別名義プロジェクトWhatever The Weatherを2022年に始動した。パンデミック以降の激動のこの2年間をアートを通じて駆け抜けてきた彼女はNTSラジオでマンスリーのショーを始め、Bandcampでいくつかのプロジェクトを共有し、前述のHyperdubから『Nothing EP』と『Reflection』の2作のリリースした。そして同時に自身が10代の頃に持っていた未知の創造的な領域へと回帰し、この別名義プロジェクトの発足へと至る。Whatever The Weather名義ではクラブ・ミュージックとは対照的に、キーボードの即興演奏とヴォーカルの実験が行われ、パーカッシヴな構造を捨ててアトモスフィアと音色の形成が優先されている。
そしてデビュー作となるセイム・タイトル・アルバム『Whatever The Weather』が自身が長年ファンだったというGhoslty Internationalから2022年4月にリリースされた。ロレインは本アルバムのマスタリングを依頼したテレフォン・テル・アヴィヴをはじめ、HTRK(メンバーのJonnine StandishはロレインのEPに参加)、Lusine(ロレインがリミックスを手がけた)など、アンビエントと親和性の高いGhostly Internationalのアーティスト達のファンである。
「天気がどうであれ」というタイトルにもちなんで、曲名は全て温度数で示されている。周期的、季節的、そして予測不可能に展開されるアンビエント~IDMを横断するサウンドで、20年代エレクトロニカの傑作(ele-king booksの『AMBIENT definitive 増補改訂版』にも掲載)として幅広いリスナーから支持を得ている。

aus:
東京出身のミュージシャン。10代の頃から実験映像作品の音楽を手がける。長らく自身の音楽活動は休止していたが、昨年1月Seb Wildblood主宰All My Thoughtsより久々となるシングル”Until Then”のリリースを皮切りに、4月にはイギリスの老舗レーベルLo Recordingsより15年ぶりのニューアルバム”Everis”をリリース。同作のリミックス・アルバムにはJohn Beltran、Li Yileiらが参加した。Craig Armstrong、Seahawksほかリミックス・ワークも多数。当公演はDJ+ライブセットでの出演となる。

Shuta Hasunuma (蓮沼執太):
1983年、東京都生まれ。蓮沼執太フィルを組織して、国内外での音楽公演をはじめ、多数の音楽制作を行う。また「作曲」という手法を応用し物質的な表現を用いて、彫刻、映像、インスタレーション、パフォーマンスなどを制作する。主な個展に「Compositions」(Pioneer Works 、ニューヨーク/ 2018)、「 ~ ing」(資生堂ギャラリー、東京 / 2018)などがある。また、近年のプロジェクトやグループ展に「Someone’s public and private / Something’s public and private」(Tompkins Square Park 、ニューヨーク/ 2019)、「FACES」(SCAI PIRAMIDE、東京 / 2021)など。最新アルバムに『unpeople』(2023)。第69回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。
web: https://linktr.ee/shutahasunuma
Instagram: https://www.instagram.com/shuta_hasunuma/