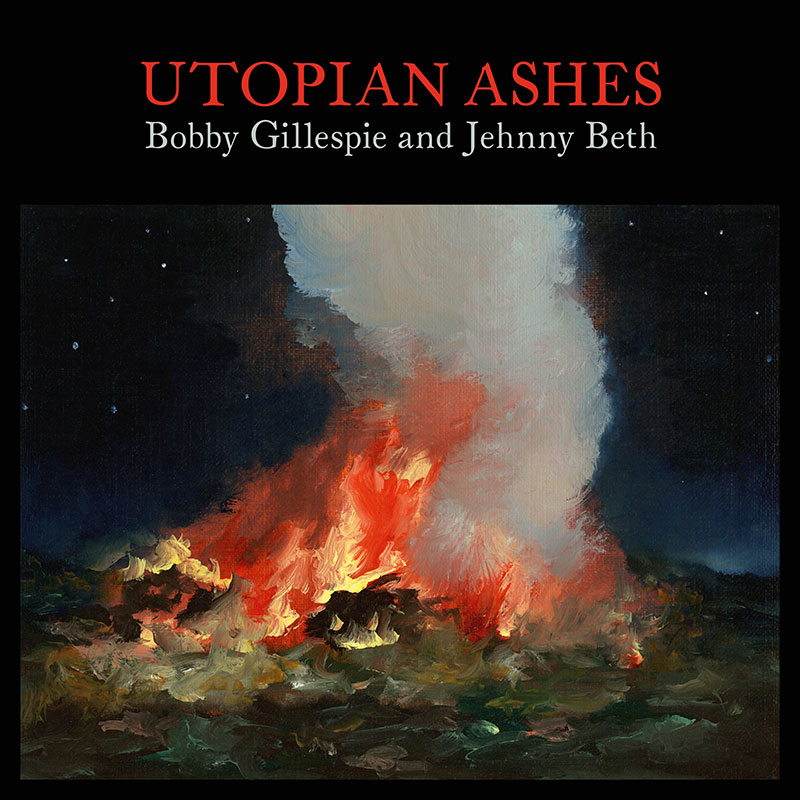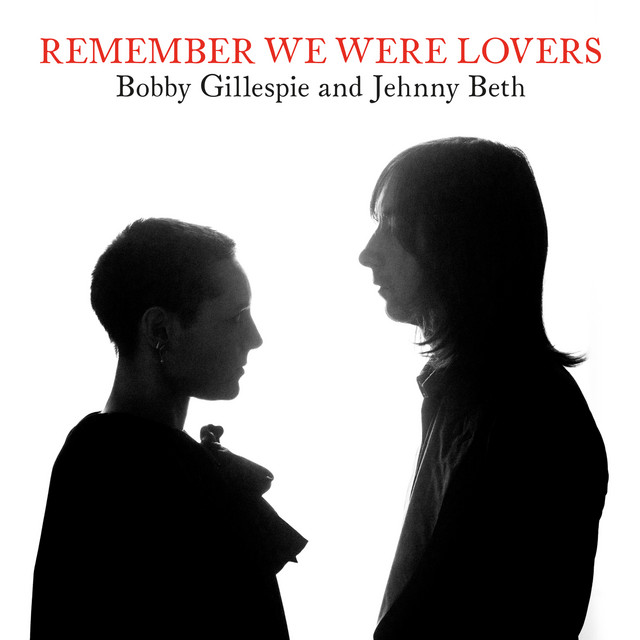MOST READ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 『成功したオタク』 -
- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス
Home > Interviews > interview with Bobby Gillespie & Jehnny Beth - 愛し、愛するのをやめること
■今回のアルバムは、2人の共作による真の意味でのデュエット・アルバムなんですね。
BG:そうそう。このふたつのアルバムは、まったく異なる性質を持っていると思う。もちろん、楽器の構成とか、演奏の部分では共通点がないこともないよ。“(I'm Gonna) Cry Myself Blind”と“Your Heart Will Always Be Broken”は、言ってみれば同じ枠組みのなかにカテゴライズできると思うけど。とにかく、ジェニーは曲作りも手掛けるアーティストで、デニースはシンガーという大きな違いがある。
■残念ながら急逝したデニスとデュエット・アルバムを作ることは考えたりしなかったということですか?
BG:まったく、全然、一度たりとも考えたことはなかったね。僕とデニースの歌声は、デュエットとしてはまったくかみ合わないというか、成立しなかったと思うよ。

僕たちが信じているもののほとんどは嘘で塗り固められたギミックで、僕たちは嘘を信じて嘘にお金を払って買っている。資本主義社会なんて懐疑的な存在だし、僕たちは疑うべきなんだ。
■アルバム・コンセプトは「slow disintegration of a failing marriage(失敗した結婚のゆっくりとした崩壊)」と聞いています。どうしてこのコンセプトになったのでしょうか?
BG:う~ん。説明が難しいな……僕はただ、普遍的な真実というものを描きたかったんだ。経験に基づいた実存的な現実というのかな。人間同士の相容れない矛盾や、不明瞭な感情といったもの。僕は、人間というのは分断によって結びつけられていると思うんだ。つまり、人間が背負っている痛みの大部分は、他の誰かと繋がりたい、結ばれたいという思いから来ているんじゃないか。そう願っているのに、ぴったりと重なり合うことは永遠にないんだよ。ある一瞬、心が通ってひとつになることはあるし、精神的な結びつきをほんのわずかな間感じることもある。でも、それは永遠には続かないし、完全にひとつになることはない。僕たちはまるで、孤島のようなものだと思う。誰かと地続きのように繋がることはないんだよね。それがあらゆる種類のリレーションシップに対する真実だと思う。だからこそ、僕たちは誰かと繋がることにこれほどの魅力を感じるんだと思うんだよね。人間は孤独で、だからこそ誰かと繋がることで力を得る。それは神の定めたルールに則っているんだろうし、神学的・哲学的な領域の話になるんだろうけど。なぜ人がロマンチックな恋愛関係をこれだけ追い求めるのかと言えば、それは誰かと関係を持つことで自分がより大きな存在の一部になったように感じられるからなんだ。自分の存在がより大きなものになったように感じられるんだよ。でも、それは長くは続かない。永遠に続くものではないんだ。
■それは男女間の恋愛関係に限らず、すべてのリレーションシップについて言えることなんでしょうね。
BG:そう、僕たちは動物と同じなんだ。もしかしたら、無償の愛を注げるだけ動物のほうがマシかもしれない。人間はトリックスター、ペテン師だから。このアルバムは、人間には他の人間のことは理解できないということについて書かれたものなんだよ。もちろん、相手のことは知っているけど、本質まではわからないよね。その人のことを知っているつもりでも、本当のところは全然わかっていないんだ。結局完全に理解することなんてできないから、愛が冷めたらもう全然知らない赤の他人になってしまう。そのとき感じた愛がなんだったかなんて、僕たちにはわからない。愛なんて実体のないものだから。
そう、愛は言ってみれば生命そのものなんだと思う。僕たちの命も、一度死んだら宇宙の塵と消えてしまう。愛も同じだよ。一度その愛が冷めたら、宇宙の藻屑だ。そうやって宇宙のサイクルの一部として、喪失と再生を繰り返していくんだ。僕たちの命もそこに生まれた愛も、宇宙の規模からしたらとんでもなく小さな、取るに足らないことじゃない? 愛やリレーションシップは、本当に小さな一瞬の火花のような存在でしかない。燃え尽きたらそれで終わりだ。
このアルバムは、ある意味とても皮肉だけれど、現実的なことをテーマにしているのかもしれないね。実存的な真実を受容することがこのアルバムで伝えたかったことなんじゃないかな。僕たちはわかり合えない、自分以外の人のことは理解できない。表面的なことはわかるし、見えるものについては深く考察するけれど……太古の昔から、ドラマや芝居や脚本や詩や小説のテーマにもなってきたよね。人間はとても複雑な生きもので、人生は葛藤の連続だ。人間関係は葛藤そのものだから、このアルバムの命題は、その“葛藤”について描かれたものと言えるだろうね。そして、その葛藤は痛みを伴うんだ。「葛藤が生み出す無限の痛み」がテーマになっていると言えるかもしれない。ある意味、とてもブルージーなレコードになっていると思う。
■曲が進むにつれて、内面がさらけ出されていき、痛みも増していくようです。一方で、サウンドそのものは美しく、アップリフティングで時には優しく、癒されるような要素も入っていますよね。
BG:そうなんだ。だから、そこに一筋の希望が見えるんだと思う。
■この痛みを美しいサウンドで表現しようと考えた真意はなんだったのでしょうか。そうした希望の光を込めたかったということでしょうか?
BG:そうそう、その通り。痛みを伴う歌詞を美しい音楽で表現しているというのは良い考察だ。なぜなら、それこそがアートの持つ力だからね。それが聴き手を惹きつけるんだと思う。美しく繊細なサウンドが、ダークな歌詞によって傷つけれた心を引き上げて、包み込んでくれる。言ってみれば、美しさのコクーンのようなものだね。美しい花に見えても、実は君を飲み込んでしまうかもしれない(笑)。毒を持った花みたいなものなのかもね。
言ってみれば、人間だってそうじゃない? 外見は小綺麗にしてるかもしれないけど、中身はダークでドロドロだ。怒りやサディスティックな感情を秘めているんだから。うん、なかなか良い指摘だね。考える良いきっかけになった。本当にどうもありがとう(笑)!
■英国は深刻なコロナ禍を経て、回復へと向かいつつありますが、新型コロナウイルスがアルバムに与えた影響はあったのでしょうか?
BG:いやいや、このアルバムは新型コロナ以前に完成していたから、そうした影響はないよ。曲自体は2017、2018年頃に書いたもので、レコーディングも2018年の夏にやったし、ミックスも2018年中には終わらせていたんだ。本当は昨年リリースされるはずだったんだけど、そのタイミングで新型コロナが流行して、ジェニーのソロアルバムのリリースもあったから、発表をここまで先送りにしていたんだよ。
■そうだったんですね。このアルバムはまるでロックダウン下で物理的な距離を取らざるを得なかったふたりの葛藤を描いているように感じたので。
BG:なるほどね。でも、それは関係なかったかな。それよりも、このアルバムは感情の不明瞭さについて描かれたものなんだ。人間の残酷さと言ってもいいかもしれない。その残酷さというのは僕たちのなかにも、あらゆる場所、あらゆる場面に溢れている。詩人だって脚本家だって小説家だって、本当は不明瞭な感情と闘っているんだ。本当は自身の感情について1ページだって書くことができないのかもしれない。映画や詩を創ってはいるけど、自分自身の感情については不明瞭なまま葛藤を繰り返しているんだと思う。自分の感じ方や生き方、もしかすると結婚生活さえ、自ら正すことはできないんだよ。だって、人間は身勝手で利己的で、ナルシスティックな生きものだから。人間は……そう、混沌としている。すべての人間が、矛盾した存在なんだ。
僕がこのアルバムで本当に描いたことは、そうした人間の持つ矛盾についてなんだろうな。あるときは素晴らしい人物で、ある時は愛情の欠片もない人物で、翌日は誰もがその人のことを憎んでいるかもしれない。ある意味、サディスティックとマゾヒスティックな感情を持ち合わせているということかもしれないね。人間は、何か実体のないものに突き動かされて、しかるべき状況に陥っている気がする。何か得体の知れない、僕たちを突き動かすなにか……人間ていうのは、結局何もわかっちゃいないんだ。僕を含めて、誰もが自分の感情についても、どうあるべきか、どんな行動を取るべきかなんて、まったくわかってないんだと思う。
■そうした音楽に込めた思いや考え方、感じ方というのはやはりあなたのこれまでの経験から来ているのでしょうか。
BG:それはもう、僕の作品はすべて自分自身の経験に基づいているものばかりだよ。
■というのも、このアルバムに登場する男女というのは、明確なキャラクター設定があってのことなのか、それよりももっとパーソナルで自然発生的なものだったのかが気になったんです。
BG:ああ、そうだね。たしかにフィクションの部分もあるから、ある意味架空の登場人物に語らせているところはあるね。でも、そうしたキャラクターの人物設定のベースには僕の経験があって、僕がいろいろな人たちの経験やリレーションシップを観察して考察したものを反映しているから、完全に架空のキャラクターを創り上げたという感じではないかな。僕の視点から見た、さまざまな人たちの、さまざまな“痛み”のコレクションといった感じかな。端から見たら幸せな結婚生活でも、そこに葛藤があるかもしれないと思うんだよね。
1曲目の“Chase it Down”は、生命や宇宙、自然、それに人間にさえ備わっている存在の美しさに対する、ある種の不思議な感動や心理的感覚について歌ったものなんだ。滅私的な優しさや思いやりといった美しさ。でもね、日本もそうだしイングランドも西欧諸国そうだけど、経済的に豊かな国に暮らしていると、生きていることがどんなに幸運で恵まれているかなんて、すぐに忘れてしまうと思う。退廃的になってしまって、どんなに生きづらいかっていう文句ばかり言うようになる。でも、僕は生きていることそのものが素晴らしいことで、奇跡的なことなんだってこの曲で歌いたかった。
「Love while you can / Every woman every man / Everybody is a star / No matter who / Or what you are / And we don’t have too long / Run your race / Sing your song」の部分には、そうした想いが込められているんだよ。人生は短い、僕たちは自分たちに命を授かって、この人生を生きていることを讃えるべきなんだってね。僕たちはこの美しい人生を授かったんだから。でも、人は新しい家が欲しい、新しい車が欲しい、新しい冷蔵庫が欲しいって、不平不満ばかりを言っている。
■貪欲になればなるほど自分の不遇さに絶望してしまって、経済的に豊かな国の方が自殺率が高かったりしますよね。
BG:そうなんだ。結局人は、自分より裕福だったり、成功していたり、美貌を備えていたり、そんな人たちと自分を比較して羨んでばかりいるよね。セクシーでスタイリッシュで大きな家に住んでいるセレブと比較することで自分の価値を決めてしまっている。結局、そうした比較対象を設けて、ある種のゴールみたいな人たちを示すことで、資本主義は機能しているわけだから。フェラーリを乗り回して美人のモデルの奥さんがいて大きな家に住んで、という結論を提示することで、わかりやすくそこに向かっていくことになる。だから人は資本主義社会に疑問を持たずに暮らすことができるんだ。成功者はこんな暮らしを手に入れているという幻想を見せることで、君にもその暮らしを手に入れることができるよ、手に入れたら勝者だよ、手に入れられなかったら敗者だよ、とわかりやすく示すことができるわけだよ。敗者には負けた理由があるんだよ、というのが資本主義社会の根底になっている自由競争からのメッセージなんだ。こんな平等な社会で何も手に入れられなかった君自身に理由があるってね。経済や社会が悪いんじゃない、頭が悪いとか、醜いとか、頑張りが足りなかったとか。成功者はみんな身を粉にして働いているっていうけど、実際の金持ちは、そのほとんどが親から受け継いだものだったりするんだけどね。土地とか不動産とか、両親が築いた財力や先祖代々受け継いだ遺産がほとんどだ。
僕たちが信じているもののほとんどは嘘で塗り固められたギミックで、僕たちは嘘を信じて嘘にお金を払って買っている。資本主義社会なんて懐疑的な存在だし、僕たちは疑うべきなんだ。魅惑的な嘘で塗り固められてる。エルメスのハンドバッグやイブ・サンローランのコートは、消費主義者にとっては魔力を持った魅惑的な存在で、僕たちは幻想に投資してその魔力を持ったフェティッシュな所有物を手に入れている。僕自身だって、他のみんなと同じようにその行為に罪の意識を感じているよ。消費社会の現実は、大衆の奴隷になることなんだ。僕はもちろんその資本主義消費社会の一部だし、ブランドのキャンペーンとかもやってるし、だからこそ罪の意識を感じているよ。でも、この社会の一部だから、その一員として生きていくしかないんだよね(笑)。
■“Sunk in Reverie”を聴いて、そういった消費社会に対する幻滅みたいなものを感じました。
BG:あの曲は、人間に対する最上級の嫌悪感を歌ったものなんだ。人びとの行動を目撃している主人公の語りという体裁を取っているんだけど。人間が持つ、寄生本能とでも言うのかな。それを暴こうという内容なんだ。人はみんなさまざまな仮面を被っていて……この主人公も、俳優としてかつてはそちら側に属していた。だから、自分について歌っている歌でもあるんだよ。最後のコーラスの「The bodies keep on coming / The party never ends」の部分は、パゾリーニの映画『ソドムの市』を観て書いたんだ。ラストシーンで少年少女を次々に虐殺するところを描いたんだけど、人間の死体が累々と重なっている様は、まるで肉屋みたいだな、と思って。人間も、虐待されて使い尽くされてやがて死体となって転がっている。つまりこの曲は、そういう放蕩的なライフスタイルや、そういうライフスタイルを送って吸血鬼のようになってしまった人たちの空虚について書いたものなんだ。繰り返しになるけど、ここで描かれているようなライフスタイルはとても魅力的かもしれないけど、そこに愛はないし、とても空虚だ。でも、そこにいる人たちは気付かないふりをしているんだよ。
■では、少しサウンド面のお話しを聞かせてください。コンセプトの世界を表現するサウンドですが、方向性についてふたりで話し合ったのか、それともあなたが主導していったのかどちらでしょうか?
BG:2017年の1月に僕とアンドリュー(・イネス)がパリに行って、ジェニーと彼女のボーイフレンドのジョニー・ホスティルと一緒にスタジオに入って、本当にごくごく簡単なアイデアを出し合った感じではじまったんだ。当初はかなりエレクトロニックな雰囲気でね。クラフトワークとか、そんな感じの。それでロンドンに戻って来て、頭のなかにあった曲をアコースティック・ギターで弾いてみたんだよ。で、ギターのコードを決めていった。それから少し曲をシェイプして、歌詞を書きはじめた。5曲くらい書いたところで、『ロックのアルバムを作るべきだな』って思ったんだ。アンドリューとデモを作ってみたんだけど、いまのスタイルにすごく近い、ロック・ミュージックになった。もちろん、もっと原始的な感じではあったけどね。それをジェニーに聴いてもらって、「こんな風に作りたいんだけど」って言ったんだ。生演奏でレコーディングしたいことを伝えたら、「いいわ、最高!」って言ってくれて。それでこういうサウンドになったんだよ。
■共作していて思いもよらず、良い方向に向かった曲はありますか?
BG:例えば“Remember We Were Lovers”は、最初はクラフトワークみたいなサウンドだったんだ。ドラムマシーンやストリングマシーン、ピアノが入ってて。でも、自分的にはしっくりこなくて。雰囲気もないし、感情がこもっていない感じがしてね。それで、ギターで曲を書き直してみたんだ。それから、生演奏でレコーディングしたらどうかって提案したんだよ。マーティン・ダフィーとダリン・ムーニーと一緒に。ジョン・レノンの曲みたいなピアノが入れたかったんだよね。(“Mother”を歌う)とかね。“Jealous Guy”とか(“Jealous Guyを歌う)、そんな感じ。アメリカのブラック・ソウル・ミュージックみたいな感じにしたかった。オーティス・レディングとかね。クラフトワークより、ジョン・レノンみたいな曲にしたかった。
■それが、共同プロデューサーとしてブレンダン・リンチを迎えた理由のひとつでしょうか?
BG:ブレンダンは優れたエンジニアであり共同プロデューサーでもあるし、とくにバンドの生演奏をスタジオ録音するのがすごく上手なんだ。だから、このアルバムにぴったりだと思ったのは間違いないね。
■彼を起用したのは『XTRMNTR』以来ですよね?
BG:そうだね。いや、ちょっと待って。2017年にレコード・ストア・デイに合わせてリリースした“Golden Rope”のリミックスをブレンダンにやってもらったな。
■タイトルの『Utopian Ashes』はこれ以上ないほど合ったタイトルだと思いますが、どこから生まれたのでしょうか?
BG:僕の頭のなかから生まれたのさ。アルバムのサウンドとコンセプトを詩的に表現できるタイトルはないかなって考えてて。それでいて、抽象的で聴き手に考える余白を与えるようなものにしたくてね。
■たしかに、このアルバムのライヴは朗読劇でも成立しそうですね。
BG:ああ、本当に? 歌詞が? 嬉しいな、ありがとう。
■実際にこのアルバムを引っ提げてのライヴの予定はありますか?
BG:うん、11月にライヴができないかって考えているところなんだ。キャンドルを灯してライヴをやりたいと思ってて。
■プライマルとしては『Chaosmosis』以来となる新作を期待したいところですが、いかがでしょうか?
BG:『Riot City Blues』の17曲入りアルバムを再発する予定だよ。オリジナルは10曲入りなんだけど、7曲ほど足して17曲入りにしたんだ。
■リミックスなどを含めた構成になるということでしょうか?
BG:いや、全部オリジナル曲なんだけど、シングルのB面を入れることにした。オリジナルがリリースされた15年前は、シングル1、シングル2、7インチシングルという体裁でシングルをリリースしていたから、曲がたくさんあって。レコード会社にとにかくたくさん曲をレコーディングしろって言われていた時代で、アルバムに合わせて17~18曲ほどレコーディングしていたからね。それを全部含めて、セッションでレコーディングしたものを『Riot City Blues Sessions』というタイトルで、曲順も変えてリリースする。4つの章に再構成した感じの作りになってて、第1章はハイエナジーなロック、第2章はバラード、第3章は再びハイエナジーなロック、第4章はよりハイエナジーなロックという感じで、面白い構成になっていると思うよ。
それから、これははっきりとしたことはまだ言えないんだけど、『Screamadelica』もなんらかの形で再発することになりそうだよ。ちょうど今年で発売30周年を迎えるからね。それに、ライヴ・アルバムも出る予定だよ。2015年にオースティンで開催されたサイケデリックのフェスティヴァル、LEVITSTIONに出演したんだけど、その時の音源がライヴ・アルバムとしてリリースされるみたいだね。アハハハ! こんなにいろいろ出るのかって自分でも驚いたよ(笑)。
INTERVIEWS
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE