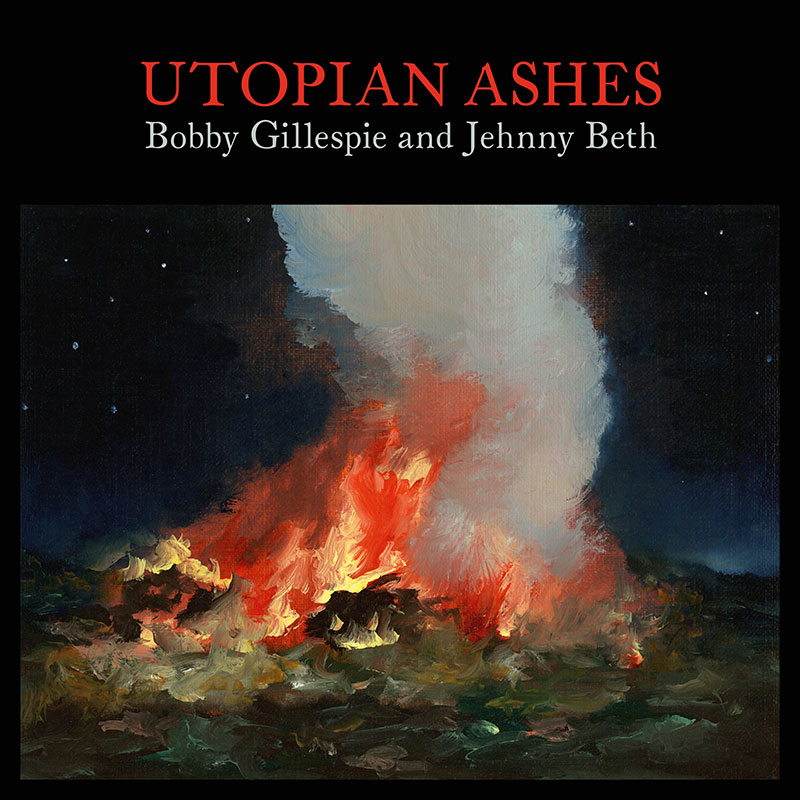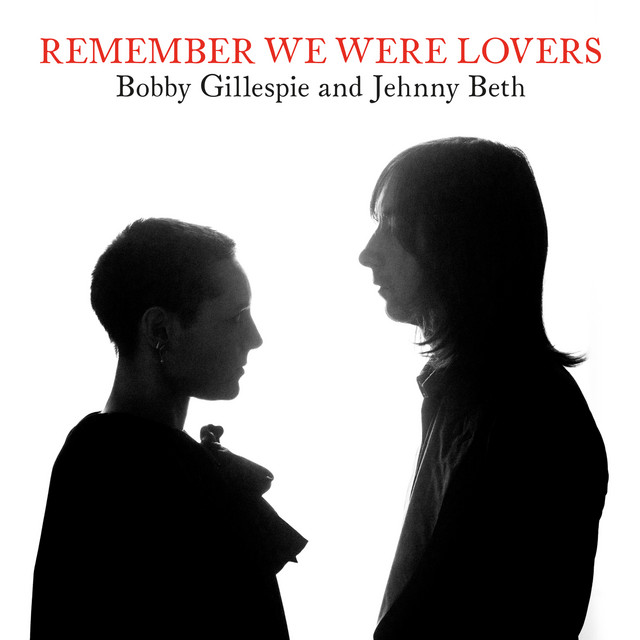MOST READ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- Beyoncé - Renaissance
Home > Interviews > interview with Bobby Gillespie & Jehnny Beth - 愛し、愛するのをやめること

interview with Jehnny Beth
もう愛していないって言っているけど、それはまだ愛が残っているから言えるセリフなのよ(笑)。
──ジェニー・ベス、インタヴュー
質問:油納将志 通訳:長谷川友美
このアルバムは、リレーションシップの崩壊に焦点を当てているというよりも、その問題に対峙して、なんとか関係を立て直そうと葛藤する男女の姿を描いていると思う。そのために対話を重ねているんじゃないかな。
■いまはロンドンにいらっしゃるんですか?
JB:いいえ、パリよ。4年前にパリに移ったの”
■パリはいまどんな状況ですか?
JB:相変わらず悪夢のようよ。まあ、世界中のどの都市にも言えることかもしれないけど。
■最初にボビーに会ったとき、どんな印象を持ちましたか?
JB:最初にボビーに会ったのは、パリで行われたイブ・サンローランのキャットウォークショーに、彼と私が招かれたときだったの。もちろん彼のことはアーティストとして知っていたけど、個人的に会ったことはそれまでなかったわ。彼も私のことを知ってくれていたから、会話を交わして連絡先を交換したのよ。でも、そのときはそれ以上のことは何も起こらなかったわ。
その後、スーサイドのラスト・ステージとなるA Punk Massっていうイベントがバービカンで行われて、そのときにまた会ったのよ。アラン・ベガが亡くなる直前のことだったんだけど。そこで、スーサイドに“Dream Baby Dream”をボビーと一緒に歌わないかと誘ってもらって。この曲はすでにサヴェージズで歌ったことがあったから、ボビーに「是非やりたいと思ってるけど、一人で歌いたかったら私は遠慮しておくわ」って言ったの。そうしたらボビーが、「いやいや、いいアイデアだからやろうよ」って言ってくれて。なんだかカオスな夜だったわ。ヘンリー・ロリンズが怒ってステージを降りちゃったり(笑)。それで、いつが私たちの出番かさっぱりわからなくて、突然曲がはじまっちゃったの。そうしたら、すぐにボビーがステージに出ていって、こう、客席に向かってかがんだのよ。それが本当にロックスターっぽくて、なんてかっこいいんだろう、って感動したわ。曲の始まりも終わりもわからなくて混乱したけれど、ステージが終わった後は大満足だったし、ハッピーで誇らしい気持ちになって。それでボビーともすっかり意気投合したのよ。
それから、プライマル・スクリームとサヴェージズがブリストルで行われたマッシヴ・アタック・フェスティヴァルで共演する機会があって、アンドリューとボビーが私にプライマルのステージで歌わないかって誘ってくれたの。その後、アンドリューがボビーに2人でレコーディングしてみたらどうかって薦めてくれて。ジェニーとジョニー(・ホスティル)も一緒に曲を書いてみないかって言ってくれて、断る理由なんてひとつもなかったわ。ボビーとの共演は本当に楽しかったし、彼と私の声はデュエットにぴったりだと自分でも感じていたから。それで、ボビーとアンドリューがパリに来てくれて、いま、私がいるこのスタジオで2回ほどセッションしたの。そこで、曲のベースとなるようなものを書きはじめて。
当初は、どんな曲を書いているかはっきりしないような状態だった。ただ、なんとなく曲のアイデアを出す感じだったんだけど、私とジョニーはまるでプライマル・スクリームの曲を書いているような気分だった。ベースとなるサウンドはエレクトロニックで、モノコードで。それで、ボビーはロンドンに戻って歌詞を書きはじめたのよ。パリでは歌詞ではなくて、メロディを書くことに集中していたから。
でも、歌詞がメロディのアイデアにマッチしないと考えたようなのね。それで、「このレコードはエレクトロニックなサウンドのものにはならないと思う」って言われたの。もっと、バラードや、オールドスクールのフォークといった、ソングライティングに重きを置いたアルバムになりそうだって伝えられた。それからアルバムのコンセプトの話になって。“結婚生活の崩壊”というテーマが浮かび上がってきたのよ、ごめんなさい、ちょっと長かったわね。でも、これがボビーと出会った事の顛末なの。
■出会う前は、ボビーをどのようなアーティストとして見ていたのでしょうか。
JB:とても強い個性を持っていて、素晴らしいソングライターだという印象だったわ。プライマル・スクリームの曲はもともと好きだったしね。とくに“I Can Change”がすごく好き。とても良く書かれた曲だと思ったわ。最初に彼を目撃したのは、ニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズのアフターショーパーティの会場だったの。もちろんそのときはボビーがどんな人物かまったく知らなかったんだけど、ボビーがニックと談笑しているのを見て、意外と明るくてよく笑う人なんだなって思ったわ。というのも、彼は酷いドラッグ中毒者だって噂を聞いていたから。もちろん、あの時代の人たちは多かれ少なかれそういう印象がつきまとっていると思うけどね。
それが、実際に彼と会って話をしてみたら、そんな悪い印象はすぐに吹き飛んだわ。全然シラフだしクリーンだし。それって、私にとってはとても重要なことなのよ。私はお酒も飲まないし、ドラッグをやるような人たちとつるんだこともない。そういうものは、私が求めているものではないから。ロックンロールミュージックをプレイしているのにね(笑)。ロック界はアンフェタミンと密接に結びついていて、ドラッグまみれという歴史があることもよくわかっているけど、私はもうそういう世代の人間ではないの。サヴェージズは自分自身を律して、自分のやっていること、やるべきことに集中するという考えを共有しているからね。だから、ボビーに会って彼の内面を知ることで誤解が解けて、このプロジェクトは絶対にうまくいくと確信したわ。
■最初に「結婚生活の崩壊」というコンセプトを聴かされた時、どう思いましたか?
JB:電話で突然言われたのでビックリしたけど(笑)、すごく面白いと思ったわ。いろいろな音楽やレコードで語られてきたテーマでもあるしね。このテーマが一体どこから来たのか、少し不思議には思ったけれど。でも、題材としてはいろいろな曲で取り上げられているし、ある種のキャラクターを設定するというコンセプトにはとても興味を持ったわ。もちろん、そうしたキャラクターには私たちの素の部分も大いに反映されてはいるけどね。そうでないと、オーセンティックなサウンドにはならないから。
最初のシングル(“Remember We Were Lovers”)では、一組の男女が彼らの抱えている葛藤と、それをどう乗り越えるのか、その難しさについて歌っているけれど、ある意味伝統的なテーマだと思うのよ。ティーンエイジャーの恋の悩みや失恋とは明らかに異なる胸の痛み。それは、彼らがそれまで一緒に旅してきた軌跡があるからなの。結婚して、生活を共にして、もしかしたら子供もいるかもしれない。責任感の重みも違うし、人生のコミットメントなわけだから。このアルバムは、そうしたリレーションシップの崩壊に焦点を当てているというよりも、その問題に対峙して、なんとか関係を立て直そうと葛藤する男女の姿を描いていると思う。そのために対話を重ねているんじゃないかな。もし話し合うこともなくなってしまったら、関係性は完全に壊れてしまうから。「I don’t love you anymore」なんてとてもヘヴィで辛いフレーズだけど、そうやって自分の心の内を語ることで、なんとか関係性を修復したいと考えているからこそ出て来た言葉じゃないかと思っているの。もう愛していない、って言っているけど、それはまだ愛が残っているから言えるセリフなのよ(笑)。その愛を取り戻したいという心の叫び。まずは自分の相手に対する正直な感情をぶちまけることで、2人の未来を変えたいという気持ちの表れだと思う。私は、このアルバムのコンセプトをそういう風に解釈したけれど。
■たしかに相手に対する感情や情熱が残っていなかったら、もう話しても無駄ですもんね。
JB:その通りよ。情熱が残っているから、なんとかしたいと相手との対話を望むのだと思うわ。もう相手のことがどうでもよくなっていたら、自分の気持ちをぶちまける必要なんかないもの。ただ去って行けばいいだけの話だから。
■アルバムに登場する女性のペルソナは、あなたが創造した架空のキャラクターですか? それとも、自分自身を投影させたもので、キャラクター設定のようなものはなかったのでしょうか。
JB:そのどちらの要素もあると思う。歌詞はすでに書きためていたものがあったし、私が書いた歌詞のほとんどは、アルバムのコンセプトが決まる前に書いたものだから。私の歌詞が、ボビーがアルバムの方向性を決めるプロセスに少なからず影響を与えたところもあるんじゃないかな。コンセプトがはっきりしてから、歌詞を修正したりして曲のテーマや世界観に合うように、無意識のうちにキャラクターを設定していたかもしれないわね。曲のすべてにキャラクターを設定したコンセプトアルバムという発想も悪くはないけど、私は音楽で自分の本当の気持ちや感情を表現したいから、キャラクター設定にはあまりこだわらず、自分の経験を元にして素直な感情を込めたつもりだし、自分が経験していないようなことを歌った歌については、自分だったらどうするかな、どう感じるかなということをつねに念頭に置いて歌詞を書いたのよ。

“Utopia”という希望に満ちた言葉と、“Ashes”という破滅的な言葉とのコントラストがとても面白いと思った。ある意味、さっき話したような、歌詞の持つダークさとサウンドの持つポジティヴさとを的確に表現したタイトルじゃないかしら。
■曲が進むにつれて、内面がさらけ出されいき、痛みも増していくようです。歌詞の一部はある意味、とてもストレートな表現にもなっていますよね。この痛みを男性と女性の両面から描くことが真意だったように思いますがいかがでしょうか?
JB:その通りよ。でも、そこには一筋の光のようなものもあったと思うの。
■たしかに、サウンドそのものはアップリフティングだったり、穏やかだったり、歌詞の内容とのコントラストが鮮明だったように思いました。
JB:私たちは、気の滅入るようなレコードを作りたかったわけじゃないからね(笑)。スタジオで曲作りをしている時は本当に楽しかったし、ジョークを飛ばして笑い合ったり、和気藹々としていたから、そういう心が軽くなるような経験もサウンドに反映されていたんじゃないかしら。それに、さっきも言ったけど、人間関係の真実をこのアルバムに込めたのは、そこに希望の光があるからなの。少なくとも私はそういう風に感じているわ。本音を語るのは、解決の糸口を見つけたいからなのよ。自分たちの素直な感情や考え方を表現するのは、まだ希望が残っているからだと思う。もしかしたらこの状況を変えられるかもしれない、良い方向に舵を取り直せるかもしれないという思いから来ているのだと思うわ。だから、一見真逆に見えるサウンドと歌詞の世界観をひとつにまとめることは、それほど難しいことではなかったのよ。悲しい気持ちや暴力的な感情やトラウマといったものを、全編を通して悲しいサウンドで表現する必要もないし、そこにコミュニケーションが介在する限り、様々な方向へと形を変えていくと思うから。
ボビーが、このアルバムは“表現力の欠如”について描かれていると言ったの。人によっては、会話が苦手で自分の感情や思考をうまく言葉にできないこともあるでしょう。だから、誤解を招くようなきつい言い方になってしまうこともある。でも、このアルバムが最終的に目指すところは、個人や2人の未来を良い方向へと変える力なのよ。カップルとしてすでに機能しなくなっていても、2人とも一緒にいる未来を思い描いている。だから、このアルバムはデュエットとして成立しているのよ。誰かが誰かに属している、そんな感覚を描いていると思うから。
■アルバムで描かれている男性については、どのような印象を抱きましたか? ボビーが自分自身を投影しているように感じる部分はありましたか?
JB:そのことについてはボビーに直接たしかめたことがないからわからないけど、彼が自分のことを歌っているのか、それともフィクションの世界を創り上げたのか、私にとってはどちらでも構わないかな。彼はきっと、この男女のキャラクターを使って自分自身の世界を創ろうとしたんじゃないかと思うから。彼はきっといろいろな経験をしてきて、私たちもメディアを通してしっていることもあるし、彼は結婚もしているしね。でも、そこに彼自身の経験が投影されていたとしても、きっともっと普遍的なものを作ろうと思ったんじゃないかしら。もちろん私は彼ではないし、想像で話しているに過ぎないからもしかしたら正しくないかもしれないけど、これまでのインタヴューで彼が語ったことを総合して考えると、きっとあらゆる人に向けてこうした曲を書いたんだと思うのよ。
人によって受け取り方が違っても良いと思う。多くの人が結婚生活を体験しているわけだし、誰もが最初の頃のときめきや燃え上がるような気持ちを多かれ少なかれ失うのは間違いないと思うから。それで、その頃の思いを取り戻したい、なんとかこの関係を修復したい、って思うのは自然なことよ。だって、リレーションシップって、言ってみれば進化し続けるものなんだから。リレーションシップはレボリューションなのよ。このアルバムの2人も、最後の曲が終わったあとにもしかしたら自分たちの解決策を見つけたかもしれないな、って思うの。
私はいまやボビーとは友だちだと思っているから、友だちが過去について率直に語るのは素敵なことだな、って思って聴いたわ。例えば“You Can Trust Me Now”は、彼が歌うから美しく聞こえるんじゃないかなって思うの。だって、このセリフって、本来なら全然信用ならない感じでしょ? 「僕のことを信じていいよ」って言われたら絶対に信じないわ(笑)。でも、彼がそう歌うことで、なんだかとても美しいフレーズに聞こえるの。だって、ある意味とても脆いでしょ。そう言われてもまた裏切られるかもしれない、信じていいよ、って言った方が裏切られるかもしれない。それを、ドラッグに溺れたこともある、さまざまな経験を積み重ねてきたボビーが言うことに意味があるのよ。彼が言うと、とても心に響くわ。スタジオのなかでこの曲を聴いたとき、感動したのを覚えているわ。
■このアルバムのなかでいちばん好きな曲はどれですか?
JB:やっぱりこの曲かしら。歌詞もサビもとても素敵な曲だと思うから。もう僕は昔の僕じゃないんだ、生まれ変わったんだ、信頼に値する人間になるよ、っていう彼の心の声が聞こえる気がするし、その過程というのはとても美しい軌跡だと思うの。そこに女性キャラクターのヴァースが入ってきて、「You turned into someone / I don’t know」って歌うのは、ある種の拒絶じゃない? それは、彼女のビターな経験から来ている。男は自分を信じてくれっていう。女は信じられないっていう。愛はリスクを伴うもので、だからこそ愛は美しいものだって私は信じているけれど。一方で、リスクを伴うものはもはや愛ではないのかもしれないけれどね。
■あなたは女優としても活動しています。今回のアルバムはとてもドラマチックなストーリーを持っていますが、演じるように歌ったのでしょうか?
JB:(笑)どうかしら。演じることと歌うことは私のなかでは全然違う種類のものだから。もちろん、演じるような表現を用いて歌うこともあるけれど、歌には“真実”がないと心に響かないと思っているの。敢えて穿った表現やシニカルな視点を込めて歌う歌手もいるけれど、そこに自分自身が投影されていなければ、それは聴き手にも伝わってしまうって信じているのよ。信用できないシンガーは好きじゃないの。この人は真実の感情を歌っているなって信じられなかったら、その歌を聴く気にはなれないわ。私は歌に、真実を込めたいと思っている。私はボビーよりも若いし経験も少ないかもしれないけれど、それなりに年を重ねてきたし、ジョニーとは18年間付き合っているから、1人の人と長いリレーションシップを持つことがどういうことかも多少はわかっているつもりよ。だから、自分の知らないことを作り出す必要もないし、身の丈以上の表現を取り入れる必要はないと思っているの。
■サウンド的には、グラム・パーソンズとエミルー・ハリスの“Grievous Angel”、ジョージ・ジョーンズとタミー・ワイネットの“We Go Together”などのカントリー・ソウルに触発されたと読みました。サウンド自体はどのようにしてやり取りしながら完成していったのでしょうか? 男女のデュエットアルバム、というコンセプトには最初から興味があったのでしょうか。
JB:とくにサウンド的なリファレンスについては話をすることはなかったわ。もちろん、多少はこんな感じの雰囲気で、っていう話はしたけれど。ボビーと私の声はすごくマッチしていると感じていたから、デュエット・アルバムというコンセプトは面白いと思ったわ。ボビーと私のハーモニーは、自分でも素晴らしいと思ったの。それがこのアルバムを作った最大の理由なのよ。ハーモニーというのは本当に心地良い体験で、ある意味人間にとって最も原始的なコミュニケーション術だと思うのよ。ふたつの異なる振動がひとつになって、人と人とを結びつける感覚。とても心が温かになる感じがするし、強い力を持っていると思うの。言葉によるコミュニケーションを超えた、本当に原始的な感覚よ。最初のセッションから、2人で歌うのがスムーズにいって、2人の声を重ね合わせた時、本当に驚いたの。ボビーも、アンドリューも、私も、ジョニーも思わず全員で顔を見合わせてしまったわ。“これはアルバム1枚作れちゃうんじゃないの?”って(笑)。2人のハーモニーに無限の可能性を感じたのよ。
■あなた自身は、そうしたハーモニーを取り入れたフォークミュージックやカントリー・ソウルのような音楽には興味がありましたか?
JB:ええ、もちろん。サヴェージズの音楽も、ハーモニーを重視したサウンドを目指しているから。フォークというよりは、もっとリズムが強くてモノコードを使ったサウンドになっているけれどね。ずっとジャズを歌ってきたし、ハーモニーやメロディの美しい曲は大好きよ。私にはこういう歌い方もできるんだって、今回のプロジェクトが再確認させてくれたところもあるの。私にとっては大きな収穫だったわ。このアルバム以来、ちょこちょこ『Utopian Ashes』のときの歌い方を使うようになったから(笑)。
■今回のコラボレーションがあなた自身、またサヴェージズに影響を与えることはありそうでしょうか?
JB:サヴェージズ自体は残念ながらもう何年も活動を休止していて。また活動を再開する可能性はゼロではないんだけど、いまのところは何も今後のことは決まっていない感じなの。でも、ええ、サウンド的なこととは別として、ヴォーカル面では私のソロ・プロジェクトにかなり影響を与えることになると思うわ。歌い方のスタイルの、サヴェージズ時代には閉じていた扉を再び開けてくれたような気がするから。メロディの歌い方や豊潤なハーモニー、それにそうした歌い方への喜びみたいなものを取り戻すことができると思うの。
■新型コロナウイルス禍は、人びとの生活だけではなく、人間関係やリレーションシップの在り方についても大きな変化をもたらしたと思います。あなた自身、影響を受けた部分はありますか?
JB:もちろん、どのミュージシャンやアーティストにも言えることだと思うけれど、完全に私の音楽活動を停滞させてしまったわ。去年、パンデミックの最中にソロ・アルバムをリリースすることになってしまって。本当はアルバムを引っ提げてヨーロッパにツアーに行くはずだったし、アメリカをナイン・インチ・ネイルズと一緒に回る予定だったのに、大きなフェスティヴァルも全部キャンセルになってしまった。私の記念すべきソロ・アルバムが大きな犠牲を強いられた気分だったわ。世界中にファンを持つ安定した人気のポップ・バンドには、いつでも待っていてくれるファンがいるし、他の形でファンと交流する機会もあったと思うからさほど大きな影響はなかったかもしれないけれど、私の場合は、閉じ込められてしまった気分だったの。
でも、良い面ももたらしてくれたのよ。この1年間、フランス国外に出られないからずっとパリにいる必要があって。12年間ロンドンで暮らしていたから、どこにも行けない状況に最初はフラストレーションを感じていたわ。でも地元に戻ってきてみて、自分の周りは才能を持った人たちやインスピレーションの源で溢れているって気が付いたのよ。以前の私はそれに気付いていなかったと思う。それによってまた新しい扉が開かれたし、そのことについてはとても感謝しているの。クリエイティブワークにとって、私にとって大きなターニングポイントになったと思うわ。いまも新しい曲をどんどん書いているし、状況が好転したら、次のソロ・アルバムをリリースしてすぐにでもツアーに出たいわ。
■アルバムの話に戻りますが、タイトルの『Utopian Ashes』はこれ以上ないほど合ったタイトルだと思います。ボビーが決めたそうですが、このタイトルは気に入っていますか?
JB:そうなの。ボビーが提案したんだけど、他にもたくさんタイトルの候補があったのよ。テーマである「結婚生活の崩壊」や、破れた夢を的確に表すとても良いタイトルだと思うわ。そう、夢破れた後の余波というべきかしら。だって、ここで描かれているのははじまりではなく、終わりのその後、すべての出来事を通り過ぎて来たあとの後遺症のようなものだから。燃え尽きたあとに何が残っているのか、ここからどう立て直していくのか。“Utopia”という希望に満ちた言葉と、“Ashes”という破滅的な言葉とのコントラストがとても面白いと思った。ある意味、さっき話したような、歌詞の持つダークさとサウンドの持つポジティヴさとを的確に表現したタイトルじゃないかしら。
■このアルバムのライヴは朗読劇としても成立しそうですが、ライヴの予定は?
JB:わあ、賛成だわ! ボビーの書いた歌詞は、純粋に詩としても優れていると思っていたの。文字で読んでも、読み応えがあるし心情が伝わってくる。スタジオでも、ときどきボビーが大声で歌詞を読誦していたことがあって。私の耳元に囁いてくることもあったわ(笑)。そうやって、みんなが弾いているメロディを聴きながら、歌詞をぶつぶつ唱えることで、曲にぴったり合うようにアジャストしていたみたいなの。それからノートに書き留めて……というのを繰り返していたわ。歌詞のライティングには本当に細心の注意を払っていたと思うから、歌の歌詞というだけではなく、喋り言葉としても成立するかどうかについても細かく考えていたんじゃないかと思う。語彙力の豊かさやイメージの鮮やかな表現力も素晴らしいと思うから、ボビーはこのアルバムで、作詞家としての優れた才能についても遺憾なく発揮していると思うわ。
■サウンド面でも、共作していて思いもよらず、良い方向に向かった曲はありますか?
JB:パリのスタジオに入った当初は、一緒に曲を書き始めたの。それを彼がロンドンに持ち帰って、自分のパートを書いて、曲を綺麗に整えた感じなんだけど、最初はエレクトロニックだったりモノコードを使っていたりした曲も、最終的にはメロディを重視した、真の意味でのソングライティングの力を重視したものになったのね。それをボビーがまたパリに持って来てくれて、私が自分の歌のパートを吹き込んだという感じのプロセスだった。もちろん、一緒にスタジオでやってみて、少し変えた部分もあるけどね。レコーディング自体は本当に楽しかったし、とてもよい経験になったわ。新型コロナウィルスが流行る前にこのアルバムを作っておいて、本当に良かったなって思ってる(笑)。プレッシャーもストレスも心配もなくて、最高のレコーディングだった。ボビーもアンドリューもプライマル・スクリームのメンバーもジョニーもプロフェッショナルだから最高のプレイをしてくれたし、何の心配もなかったし、このアルバムは素晴らしいものになるっていう確信が最初からあったのよ、そう、これこそ“信頼”、信じる力なのよ(笑)!
■(笑)では最後に、あなたのこれからの活動プランを教えてください。
JB:いまは2枚目のソロアルバムの制作でスタジオに入っているところなの。それから今年2本のフランス映画に出て、状況が好転したらソロツアーに出て、このアルバムのライヴも11月くらいに出来たらいいね、っていう話をしているところだし……やることはたくさんあるけど、とにかく来年が今年より良い年になっていればそれでありがたいかしらね(笑)。
INTERVIEWS
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー
- interview with Nubya Garcia - ヌバイア・ガルシアのジャズにはロンドンならではの芳香が漂っている ──来日インタヴュー
- interview with Evian Christ - 新世代トランスの真打ち登場 ──エヴィアン・クライスト、インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE