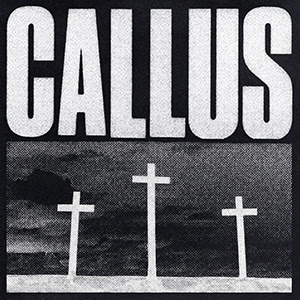Sherwood & Pinch Man Vs. Sofa On-U Sound/Tectonic/ビート |
ロンドンから北西に向かったハイ・ウィコムという街で10代の少年エイドリアン・シャーウッドはレゲエと出会った。彼はほどなくしてDJを始め、その後、音楽業界に関わるようになり、20歳になるころにはレコード店を運営するようになっていた。UKダブの歴史に名を刻むことになる伝説の始まりだ。
流通会社を立ち上げたほか、複数のレコード・レーベルを運営したシャーウッドは、1980年になると、プロデューサー・エンジニアとして独自のダブ・ミックスを、ジャズからインダストリアルまであらゆる音楽へ積極的に施していった。彼が関わったプロジェクトの数は圧倒的だ。彼のディスコグス・ページを見るだけでも、その膨大さがわかるはずだ。アフリカン・ヘッド・チャージとのサイケデリックなアフロ・ダブ。デペッシュ・モードのリミックス。リー・スクラッチ・ペリーとのスタジオ作品。タックヘッドとのエクスペリメンタル・ヒップホップ。ほかにもプライマル・スクリーム、ナイン・インチ・ネイルズ、マシーンドラムなど、挙げればきりがない。そんな彼が近年活動をともにしているのがDJピンチだ。
ピンチは2005年にレーベル〈テクトニック〉を設立。ブリストルを拠点にダブステップの先駆者としてシーンを牽引した。ダブステップがメインストリームな音楽になっていき、定常化した音楽となっていくなかで、彼はテクノ、インダストリアル、グライムなどほかのジャンルへダブステップを拡張していき、新鮮なサウンドを提供し続けてきた。00年代後半にはファースト・アルバム『Underwater Dancehall』を発表。以降も〈コールド・レコーディングス〉の設立や、シャクルトンやマムダンスとの共作など、常に革新的な音楽を志向し続けてきた。
シャーウッド&ピンチは2013年に2枚のEP「Bring Me Weed」と「The Music Killer」を発表したものの、プロジェクトへ本格的に着手することになったのは、2013年におこなわれたSonar Tokyo公演でライヴ・パフォーマンスをおこなうことになってからだった。そして2015年に発表したファースト・アルバム『Late Night Endless』から2年、待望の新作『Man Vs. Sofa』が先月発表されたばかりだ。同作はこの2年間に生まれた変化を見事に反映したアルバムとなっている。作品の背景を聞き出すべく、リリースに先駆け東京公演のために来日していたふたりにインタヴューをおこなった。

以前は〈Tectonic〉ミーツ〈On-U Sound〉みたいなサウンドだった。でも今回のアルバムは、俺とピンチというアーティストの融合なんだ。俺たちが、よりひとつになれている。 (シャーウッド)
■新作の発表おめでとうございます。前回の『Late Night Endless』からこれまでの2年間、ふたりはどのように過ごしてきましたか?
ピンチ(Pinch、以下P):この新作を作っていたよ(笑)。
エイドリアン・シャーウッド(Adrian Sherwood、以下S):アルバムを5分で作ることはできないからね。この2年間をかけて少しずつアルバムを仕上げていったんだ。例えば“戦場のメリークリスマス”のカヴァー(『Man Vs. Sofa』の収録曲)は、『Late Night Endless』の制作時に作り始めていたけど、なかなか満足できなかった。だから、今回のアルバムでいちばん古いのはあの曲で、それ以外の収録曲はすべてこの2年で作ったよ。
■“戦場のメリークリスマス”をカヴァーしようと思ったのは?
S:以前からあの曲のメロディが好きだった。坂本龍一も好きだし、“Forbidden Colours”ヴァージョンのデヴィッド・シルヴィアンの歌も好きだったからカヴァーすることにしたんだ。歌詞を入れてみようと試したり、何種類か違う方法でレコーディングしたりして、やっとパーフェクトなものが完成したよ。
P:よりサイケデリックな仕上がりになったから、前回のアルバムよりも新作によりフィットすると思う。前回のアルバムは、もっとトライバルでリズミックだったからね。ニュー・アルバムは、もっとサイケデリックでダイナミックなんだ。今回は、俺のスタジオで作ったものをエイドリアンのスタジオに持っていって、そこから発展させていって作ったトラックが多いね。でも表題曲の“Man Vs. Sofa”は、エイドリアンのスタジオでノイズができたところから始まった。今回のアルバムでは、そういうふうにしてエイドリアンのスタジオで作り始めた曲もあるし、それぞれにアイディアを持ち寄ってそれを組み合わせた曲もあるんだ。ふたりで作ったトラックがたくさんあって、その中から今回のアルバムにフィットするものを選んでできたって感じだね。
■アルバムにしようと意識して制作するようになったのはいつ頃ですか?
S:2年前だね。
■というと『Late Night Endless』をリリースした直後ですか?
S:いや、そういうわけじゃない。ファースト・アルバムをリリースしてから1年後にまた一緒にスタジオで作業しようって決めたと思う。
P:待って。それだと2年前に作り始めたことにならないだろ? エイドリアンの計算って、ときどきおかしいんだ(笑)。
S:そうなんだよ(笑)。1年じゃなくて、2、3ヶ月かな。スタジオに戻って、ピンチが俺に送ってきたトラックをもとに作業を始めたんだ。
P:ファースト・アルバムが2015年の春で、そのあと同じ年の冬くらいにセカンドのために作業を再開したんだと思う。
■ファースト・アルバムと今回のアルバムでは、どちらの制作期間が長かったんでしょうか?
S:ファーストの方が制作期間は長かったね。
■ふたりが出会ったのは2011年ですよね? ピンチがファブリック(ロンドンのクラブ)でやったイベントへエイドリアンをブッキングして、そこから親交を深めていったそうですが、『Late Night Endless』はその時点から作り始めたんでしょうか?
P:俺たちが最初にリリースした作品は12インチの「Bring Me Weed」で、出会った時からアルバムを作ることを考えていたわけではないんだ。
S:「Bring Me Weed」が最初の12インチで、そのあとEPの「The Music Killer」を出して、アルバムはその後だな。
P:アルバムのために曲を作り始めたというよりは、ライヴのために曲を作ったり、スタジオで曲を作ったり、時間がある時にふたりでとにかくトラックを作っていた。
■さっき、ファースト・アルバムの制作期間について尋ねたのは、『Late Night Endless』よりも、『Man Vs. Sofa』のほうが作品に一貫性を感じたからなんです。
S:そうなんだよ。ふたりで制作を始めた頃は、ふたりで何ができるのかを模索していて、サウンドシステムの人がエクスクルーシヴのダブプレートを持っているみたいに、自分たちだけにしかプレイできないトラックを作ろうと思っていた。そうやって何曲か作っているうちに、アルバムを作っている感じになったんだ。でも今回は、マーティン・ダフィが参加していたり、一貫性のある雰囲気になっていたりと、サウンドをまとめる要素がたくさんある。俺とピンチがしっかりと混ざり合っているね。正直、『Late Night Endless』は違うものが色々と入っている感じだった。
かなり小さい時からエイドリアンの音楽を聴き続けてきたんだ。だから、彼のインパクトや影響は自分にとってすごく大きい。その影響が、俺とエイドリアンの共通点に繋がっていると思うんだ。様々な音楽要素を取り入れ、色々な方向に進みながら、ムードのある自分の音楽を作る。エイドリアンも俺の音楽からそれを感じ取ってくれたと思う。 (ピンチ)
■なるほど。前回と比べて、制作環境は変わりましたか?
P:エイドリアンが、以前よりも広くて新しいスタジオ・スペースに移ったんだ。前回と比べて制作環境が良くなったと思う。あと、古い機材をたくさん手に入れて使ったんだ。
S:環境は今回の方が良かったと思うね。俺の家と息子の家の間にスタジオを作ったんだよ。だから庭と庭の間にスタジオがあるんだ。面白いだろ?
P:本当に変わっているんだよ。エイドリアンの庭を歩いて、もともと塀だったところをくぐると違う家なんだ(笑)。
S:機材に関しては、ずっと探していたけどなかなか手に入らなかったものを手に入れて使うことができた。
P:俺はいつもデジタル的な考え方で音楽にアプローチしてきたんだけど、エイドリアンに説得されて、自分のスタジオでも前よりアナログのものを使うようになったよ。
■逆に、エイドリアンがピンチの影響を受けてデジタルになった部分はありますか?
S:必要なのはPro Toolsくらいだな。あと、それを操作してくれる人。俺は年だから、あまりそういうのは操れないんだよ(笑)。ものすごく怠け者だからな(笑)。でも、俺のエンジニアのデイヴ・マクィワンが最高なんだ。できることならどこにでも彼を連れていきたいくらいだよ。
■機材について詳しく教えてもらってもいいでしょうか?
P:ライヴではAbleton Liveを使っているけど、トラックを作る時はLogicを使っている。あとはVSTや色々なエフェクトを重ね合わせたものをコンソールに戻してアナログ機材を通じてさらに加工する、というのが俺の作業の流れだね。
S:俺は、イギリスのAMSっていう会社のファンだったんだ。そこの製品はもう作られていないんだけどね。俺はAMSのディレイとリヴァーブをずっと使ってきた。あとアメリカの機材も好きだよ。今年はOrbanのEQとスプリング・リヴァーブを買ったよ。高くないし、ずっと欲しかったんだけど、なかなか手に入れられずにいたんだ。しかも安いんだ。あとは、Fulltoneのテープ・ディレイも買ったな。もう1台欲しいと思っていたんだ。いちばん重要なのがEventide。俺はEventideの大ファンなんだ。Eventideも高くないよ。EventideのH9は本当に素晴らしいマシンで、みんなにオススメしているよ。あと何年も探していたのがLangevin。ここのEQは〈タムラ/モータウン〉の作品すべてで使われているし、キング・タビーやサイエンティストのEQスイープでも使われている。彼らのレコードを聴いていると見事にLangevinが使われている場面がけっこうあるよ。普通のEQとは違って独特の回路になっているんだ。
P:ハイハットとかに向いているね。
S:あとリヴァーブやドラム・サウンドにも向いている。このEQでかなりのドラム・サウンドを加工したよ。
■最新作のプレス・リリースに、サウンドシステムで今回のアルバムを聴くとボディーブローのように身体に効くサウンドでありながら、ヘッドフォンで聴くと意識を没頭できる音楽だと書いてありました。アルバムを聴いて確かにそうだなと思ったのですが、どのようにしてそういったサウンドを作り上げたんでしょうか?
P:そのふたつのアイディアをミックスダウンの時に忘れないようにすることかな。サウンドシステムで聴くと身体で感じられるサブベースが、ヘッドフォンではそこまで伝わってこない。例えばブリアルなんかの音楽だと、ディテールがすごく緻密で微細だけど、それをサウンドシステムで鳴らしても、そのディテールがわかりにくい。サウンドシステムの大きなボリュームに比べて音がさりげなさすぎて聴き取りにくいからね。だからミックスダウンの時に、サウンドシステムから感じられる音のパワーと、ヘッドフォンで聴いたときに意識を没頭できる細かいディテールの両方を兼ね備えたスペースを作ることが大事なんだ。
■前作と比べて、今回はヴォーカルを使ったトラックがかなり減っていますね。
S:それは意識してやったことなんだ。以前は〈Tectonic〉ミーツ〈On-U Sound〉みたいなサウンドだった。でも今回のアルバムは、俺とピンチというアーティストの融合なんだ。俺たちが、よりひとつになれている。ヴォーカルを入れすぎてしまうと、その俺たちらしさが薄れてしまうだろ? 今回はふたりのポテンシャルを追求しているんだ。
■そういった中でもリー・スクラッチ・ペリーやスキップ・マクドナルドの声が使われているのは、歌としてというより、音の要素のひとつとして彼らのヴォーカルが使われているのでしょうか?
S:ちょっとしたフックとして使っているだけだね。
P:例えば、リー・ペリーが参加しているトラックも、最初から最後まで歌声が入った普通のヴォーカル・トラックじゃない。もっと音楽が呼吸できるスペースがある。タズにしたってそうだ。タズのスタイルはもっとグライムっぽいけど、ずっと声を発しているわけじゃないし、歌モノになっているわけでもない。声によるテクスチャーとして使っているんだ。
[[SplitPage]]ひざの手術をしたいと思っても、ひざの知識だけではどうにもできない時もある。身体全体のことを知っていることが必要な時だってあるだろ? (ピンチ)
■エイドリアンはこれまで多くのミュージシャンやプロデューサーとコラボしてきました。ピンチはいわゆるDJカルチャーのアーティストですが、ふたりのコラボレーションをどのように感じていますか?
S:ピンチとのコラボは、すごく理にかなっているんだ。ピンチは〈On-U Sound〉やレゲエ、ヒップホップ、コンテンポラリー・ダンス・ミュージックの歴史を理解している。これまで、デペッシュ・モードやタックヘッド、ザ・マフィアといった様々なアーティストとコラボしてきたけど、その結論としてピンチとコラボするようになったと言えるかな。俺はダンスできる音楽をずっと制作してきたし、家でも楽しむことができる音楽も制作してきた。クラブ・ミュージックに関わるときは、ただクラブにとってパーフェクトな作品であることだけじゃなく、家で聴いても楽しめる、クラブを超えた作品を俺はイメージするんだ。それを一緒に実現できるのがピンチなんだよ。
■数々のアーティストとコラボしてきた中で、ピンチとコラボをしてみて何に新鮮さを感じましたか?
S:彼には、誰よりもシンパシーを感じる。誰かと作業し続けるにあたって、それは本当に重要なことなんだ。ピンチとのコラボは本当に心地がいい。俺とピンチは、最高のコンビネーションなんだ。誰でもいいってわけじゃないんだ。下手にコラボするくらいなら、自分の家でゆっくりしていたいね。コラボするなら、楽しくてワクワクするものじゃないとな。ピンチは本当にクリエイティヴだし、新鮮なアイディアを持っている。俺たちは互いの可能性を広げて、いちばんいいところを引き出し合えるんだよ。
P:あと、俺はすごくおいしいお茶を入れるよ(笑)。
S:俺は料理だな(笑)。
■あはは! ふたりは互いのどういうところにシンパシーを感じていますか?
P:俺は、幼い時から兄を通して〈On-U Sound〉の作品をずっと聴いてきた。『Pay It All Back Vol.3』とかのコンピレーションをテープで持っていたし、ダブ・シンジケートのアルバムとかね。かなり小さい時からエイドリアンの音楽を聴き続けてきたんだ。だから、彼のインパクトや影響は自分にとってすごく大きい。その影響が、俺とエイドリアンの共通点に繋がっていると思うんだ。様々な音楽要素を取り入れ、色々な方向に進みながら、ムードのある自分の音楽を作る。エイドリアンも俺の音楽からそれを感じ取ってくれたと思う。だよね?
S:その通り。
■そこから現在にいたるまで一緒に音楽を作り続けていますが、出会う前は知らなかったけど、出会ってから気づいたお互いの面は何かありますか?
P:俺が知っていた以上に、エイドリアンの音楽スタイルの幅は広い。本当に計り知れないよ。バンド、アーティスト、ヴォーカリストといった様々なミュージシャンとコラボしているし、一緒にいると本当にいろんな話が聞けるよ。彼が関わったプロジェクトの数はすさまじい。制作面でもエイドリアンとコラボしていろいろと学んだよ。特に、フェーダーやパンをどう処理するのかってことをね。パンの処理やステレオ音場の捉え方から、トラックに動きやスペースを生み出していけるんだ。コラボを通じて得たものを自分のプロジェクトでも活かそうと心がけているよ。
S:俺は時期によってリズムを担当する人が変わるんだ。フィッシュ・クラークやスタイル・スコットとかね。どの時期にもリズムを構築する大事な役割の人がいて、ここ数年、その役割を担当しているのがピンチなんだ。最近はライヴ・ミュージシャンの音をとりあえずカッティング処理するようなことをしたくないんだ。一緒にグルーヴまでもカッティングしたくないし、つながっている感覚が好きだからね。だから今はピンチとのコラボがしっくりくる。

■制作をする時に、これをやったら相手が喜ぶんじゃないかなというのを意識しますか? それとも、自分が好きなものをまず相手に提示しますか?
S:俺が何を気に入るかをピンチが考えることが多いと思う。リズムを作っているのはピンチだからな。俺の気に入りそうなアイディアをピンチが持ってきて、俺がそこから気に入ったものを使って、それを基盤に俺のアイディアを加える。基本的に俺たちのトラックはそこから進化してくんだ。
P:自宅で制作するとき、常に方向性がはっきりしているわけじゃないけど、自分の中でこれはシャーウッド&ピンチのプロジェクトに向いているなって思えるリズムやトラックがある。そういう点では確実に意識しているね。
ジャンルに関係なく、聴いていてどこか他の世界に連れていってくれるというのが音楽の魅力と素晴らしさ。癒しの力があり、パワフルでもある。ジャズでもダブでも、それは変わらないね。 (シャーウッド)
■エイドリアンはダブの手法をダブ以外の音楽で起用したパイオニアであり、最近ではにせんねんもんだいのダブ・ミックスが話題になりました。以前読んだ記事で、あなたはごちゃごちゃしていない音にすることが大事だと言っていましたが、そこをもう少し詳しく聞かせていただけますか?
S:例えば、にせんねんもんだいのレコードを聴いてみると、あのレコードではハイハットがたくさん使われている。表ではあまり複雑なことは起こっていないけれど、ピンチが話していたブリアルの作品と同じで、深いところでは様々なことが起こっている。それがサウンドをより一層魅力的にしているんだよ。俺はにせんねんもんだいのアルバムが大好きだったから、あのレコードでの挑戦は、シンプルさをできるだけ美しく提示することだった。だから、すごくシンプルなテクニックを使って、音源に輝きを加えたんだ。ほんの少しだけ手を加えるアプローチを取って、音の分離と全体像、それに、強度が素晴らしくなるように心がけたよ。それとは別に、多くのことが起こっている音楽もあるよね。レゲエで言えば、スネアはここ、ハイハットはここ、キックドラムはここ、っていう感じで絵みたいにトラックの全体像を捉えるんだ。そこで俺にとって重要なのは、EQ、スペース、サウンド。ひとつひとつの要素がハッキリと聞こえるようにして、耳に飛び込んでは消えるようなサウンドにするんだよ。エイジアン・ダブ・ファウンデーションやプライマル・スクリームのようなロック・バンドみたいに多くの要素が詰まった音楽でも、すべての楽器を適切に配置してハッキリと聞こえるようにしないといけない。そういう密度が高いものを扱うときは、すべてを適切にEQ処理しないといけない。あまりにも要素が多い場合は、いくつか要素を全部か一部を取り除くことも考えられるね。リフの要素を半分にするとかね。
P:ダグ・ウィンビッシュが言っていたんだけど、ミックスでは「道」を理解することなんだ。トラックで鳴っている音にはそれぞれの道があって、その道を聴き取れるようにすることが大事なんだってね。
■ミックスにおいて、ピンチがエイドリアンに何かリクエストをすることはありますか?
P:ミックスはエイドリアンの役割ではあるけど、俺はいつも一緒に部屋の中にいる。で、このスネアはちょっとヘヴィすぎるんじゃない? とか、たまに意見を言うんだ。でも、やっぱりエイドリアンはスペースを作るのがうまいから、そこまで言うことはないね。
■最後にヘヴィな質問をひとつ。UKダブの歴史は、ジャマイカ移民の話抜きでは語れないと思うのですが、そういう意味では、移民というのは文化的な面で良いところもあると思うんです。それを音楽のスタイルやジャンルに置き換えるとすれば、エイドリアンはさっきも話したようにダブを他のジャンルに持ち込んで新しいものを生み出し、ピンチは、ダブステップから始まりはしたものの、それをテクノやハウスに取り込み、すごく面白い音楽を作っています。しかし今、世界では移民に対して反感が巻き起こっていますよね。同じようなことが音楽に起こった場合、例えば、ダブステップ以外の音楽と認めない、というような状況になった場合、その音楽はどのようになると思いますか?
S:つまらなくなるだろうね。
P:進化しなくなると思う。新しいものが生まれなくなるし、亀裂がおこる。その亀裂が不和を起こすし、視野を大きく持てなくなって、自分が見ているものがすべてだと思い込んでしまう。色々なものを受け入れることで、より広い世界が見られるようになるよね。
■これまでどのようにして、視野が狭くならないようにしてきました?
P:矛盾しているように聞こえるかもしれないけど、ひとつのことに専念することにも価値はある。要は両方の考え方を受け入れる意識を持つことが大事なんだ。視野を狭くすることで専門的なレベルで何かを詳しく理解するようにはなるだろうし、例えばそれが医療だとすれば、その知識はすごく役に立ち、特定の手術を可能にするかもしれない。でも、それが可能なのは身体の構造について広範な知識を知っているからだ。ひざの手術をしたいと思っても、ひざの知識だけではどうにもできない時もある。身体全体のことを知っていることが必要な時だってあるだろ? それと同じさ。だからどちらかひとつってことではなく、ふたつとも必要なんだよ。答えになってないよね(笑)?
S:俺は良い答えだと思うよ。ジャンルに関係なく、聴いていてどこか他の世界に連れていってくれるというのが音楽の魅力と素晴らしさ。癒しの力があり、パワフルでもある。ジャズでもダブでも、それは変わらないね。