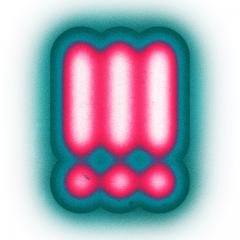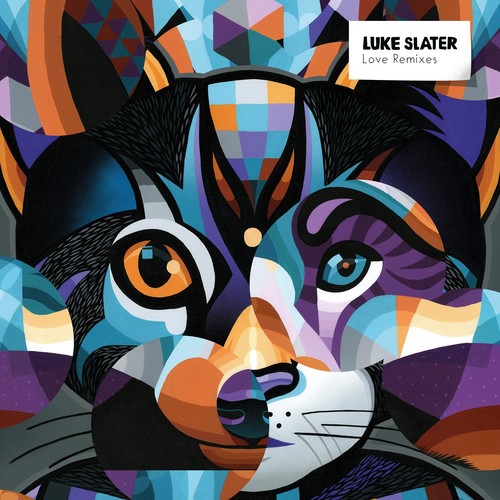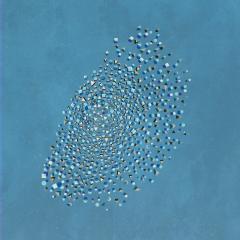たったいま6月末売りの紙エレキングの「日本の音楽」の特集号を編集している。そこで問われるのは、海外からの影響と土着性との関わりの問題だ。土着性はどのように意識され、海外の影響をどのように取り入れるか。たとえば70年代までのはっぴいえんどからシティ・ポップまでの系譜であれば、アメリカをどこまで受け入れそれをどう日本と混ぜるかということで、これがまんま100%アメリカであればまったく面白くないことは、たとえばジャマイカの音楽を聴いているとよくわかる。
ジャマイカの音楽は同じようにアメリカの音楽(こと黒人音楽)の影響下にあるが、これがアメリカのR&Bやソウルの模倣に過ぎなかったら、世界の音楽ファンはジャマイカの音楽に目を向けなかった。R&Bやソウルの影響を受けながら、メントのような土着の音楽が残存したからこそスカやレゲエは生まれている。
イアン・F・マーティンによれば、イギリスのメディアがイギリスっぽいUK音楽を賞揚するのも、骨随までアメリカ文化に支配されていない土着性を重視するからだそうで、なるほど、グライムをはじめ最近の Dave のようなUKラッパーの作品を聴いていても、アメリカに影響を受けながらアメリカを真似しないという姿勢が徹底されている。これは、音楽文化の力が強い国の特徴である。
リー・ペリーには手に負えないほど強いジャマイカ訛りがあり、それを彼は決して捨てない。彼の代表曲のひとつ、1968年の“ピープル・ファニー・ボーイ”はポコマニア(アフリカ系の土着的な宗教)を取り入れているわけだが、ペリーは長いキャリアのなかで、歌い方、喋り、あるいはその歌詞の世界(スピリチュアリズムなど)においても、長年スイスで暮らしているこのジャマイカ人は、西洋テクノロジーとアフリカの魔術との両方を使いながらジャマイカの土着性を保存し、文化的な混合体を撒き散らしている。そしておそらく、彼に期待されているのはそういうことであることを彼自身もわかっている。ひとつの文化に染まらないこと、その姿勢は、エイドリアン・シャーウッドの〈ON-U〉レーベルにおいてより際だった形で表現されている。

リー・ペリーとエイドリアン・シャーウッドは、すでに何枚ものアルバムを制作している。もっとも有名なのは1987年の『Time Boom X De Devil Dead』だが、その後も1990年の『From The Secret Laboratory』、最近では2008年の『The Mighty Upsetter』、そのダブ・ヴァージョンとしてリリースされた2009年の『Dubsetter』がある。今作『レインフォードは、このタッグではおよそ10年ぶりのアルバムというわけだが、まったく素晴らしい内容となっている。
それはひとつの、持たざる者たちの知恵なのだろう。もしこれを読んでいる人があの過剰なダブ・ミキシングが施された『Time Boom X De Devil Dead』を聴いているなら、本作は、むしろ60年代末のジャマイカのサウンドに漂う〈温もり〉のようなものが断片的にではあるが響いていることに気が付くだろう。
それもそのはずで、本作においてシャーウッドが取った方法論は、60年代のリー・ペリー音源まで遡って、ペリーのこれまでの作品の数々の音源をマッシュアップすることだった。言うなればこれは、サウンドによるリー・ペリーのバイオグラフィーであり、シャーウッドの愛情が込められたオマージュでもある。
“月の上のコオロギ”というとぼけた曲からはじまる本作は、しかしメッセージも忘れていない。懐かしいジャマイカの響きが随所で鳴っているその音のスペースのなかで、リー・ペリーは国際通貨基金(IMF)を名指しで批判する。悪魔よ、この街から出て行けと繰り返すわけだが、IMFとは経済のグローバリゼーションを押し進めている機関で、外資参入をうながしている。結果としてその国の労働者の仕事が奪われ、格差者社会を加速させていることは、その歪みの表れであるフランスの黄色いベスト運動やイギリスのブレグジットを鑑みればわかるだろう。リー・ペリーは、グローバリゼーションの憂き目に遭う前のジャマイカのサウンドを使いながら、例によって道化たフリをしながらも、現在のジャマイカでおこなわれている経済政策に反論している。82歳という高齢になっても、こうした怒りを忘れないこともまた尊敬に値する。
まあ、それはそれとして、とにかく本作を特徴付けているのは、その懐かしい響きであり、それこそ“ピープル・ファニー・ボーイ”に赤ちゃんの泣き声がミックスされていたような、ペリーらしいいろんなもののミキシングもまた随所にある。シャーウッドは彼自身のテイストはあまり表に出さず、サウンドにおいても彼なりの解釈でペリーらしさを出すことに注力している。
「アルバム全体が彼自身についてなんだよ」と、鈴木孝弥によるオフィシャル・インタヴューでシャーウッドはこうコメントしている。「彼と一緒に、彼にとってとても近いレコードを作りたかった。これまでで彼にとって一番私的なアルバムを作るということは、俺にとってはチャレンジだった。でも俺は挑戦することが好きだし、よし、やってみよう! と思ったんだ」
また、本作には、じっさいのリー・ペリーの人生が描写されている。最後に収められている曲“Autobiography Of The Upsetter”がそれで、歌詞ではコクソン・ドット、デューク・リード、ボブ・マーリーやマックス・ロメオらについて語られ、ブラック・アークを焼き払ったことについても、自分が狂ったと思われたことについても言及している。そのサウンドは70年代後半のブラック・アーク時代のペリーのようでありながら、しっかりと現在にアップデートしたものとなっている。
久しぶりに昔のアップセッターズをレコード棚から引っぱり出して聴きたくなった。ほとんどの歌をジャマイカで録音し、1曲をブラジルで、1曲をイギリスで録ったという、リー・ペリーの本名を表題に冠した『レインフォード』は、決して過去の焼き直しではない。古くて新しい、これから何度でも聴くであろう愛らしいアルバムである。
野田努
[[SplitPage]]
アフロフューチャリズムが批評家のマーク・デリーによって1994年に提唱されたとき、音楽におけるその始祖とされるサン・ラーが土星から地球に降り立って50年近く経っていた。アフリカン・ディアスポラにルーツを持つものが、テクノロジーや未来像を用いて自身の物語を生み出すという、思弁的な未来主義が理論化される前から、サン・ラーはすでに彼自身であり続けていたのだ。
その十数年後、1973年にジャマイカのキングストンから黒い箱舟が宇宙に打ち上げられようとしていた。その操縦士がリー・スクラッチ・ペリーである。彼もまた、アフロフューリズムの概念があとを追いかけた人物である。
周知の事実のように、エコーやリヴァーヴというエフェクトそのものが楽器として使用されるペリーの録音テクノロジーは世界に衝撃を与えた。デヴィッド・トゥープの『オーシャン・オブ・サウンド』によれば、ペリーのブラック・アーク・スタジオは単なる録音場ではなく、彼の楽曲のタイトルが示すように“スクラッチ研究所(Scratch Laboratory)”であり、“アンダーグラウンド・ニュース局(Station Underground News)”であり、“音楽移植手術(Musical Transplant)”だった。
電子的かつ思弁的なエンジニアリングは、スタジオをそういったヴァーチャル・リアリティが渦巻く場へと変容させ、ペリーは福音伝道者やフランケンシュタイン博士になったのである。彼のファッションがぶっ飛んでいなければならないのは、あの「装飾具」が、スタジオの潜在性が創出する空間に人間の身体性をフィットさせるための「宇宙服」的な、つまり生存に必要不可欠なアクターであったからだ。
自身の本名を冠した今作『Rainford』でも、ペリーは宇宙へと飛翔している。6曲目の“アフリカ宇宙船(African Startship)”は、クリエーション・レベルによって1978年に組み立てられ、1980年に〈4D Rhythms / On-U Sound〉から打ち上げに成功している『Starship Africa』が捉えた宇宙空間からの皆既月食のヴィジョンを、船長にハイレ・セラシエ1世を迎え入れることにより、さらに拡大する。ここでペリーのミックス卓の下に置かれているのは、天空の星々すべてである。
船長 ハイレ・セラシエ1世
レッキー・レック 国王万歳 アフリカの王
国王万歳 アフリカの王
乗船せよ
天空の星すべて 私のコントロール下に
ハイヤーアップセッター
マーカス・ガーベイ宇宙船 黒い宇宙船 セブンマイル宇宙船
マーカス・ガーベイ デザイナー 音楽的に 過激に 音楽的に
アフリカ宇宙船 宇宙を飛んでいる
──“アフリカ宇宙船”
宇宙船の移動速度に合わせトランペットが伸縮を繰り返し、乗船する宇宙飛行士としてのペリーが、アフリカ回帰運動指導者のマーカス・ガーベイが、さらにはイエス・キリストまでもが顔を出す。ここで彼が自らのスタジオをブラック・アーク、つまり黒い箱舟と読んだ理由が想起される。ペリーがトゥープに語るように、彼の目的あらゆるものの上空に位置する箱舟によって、動物、自然、音楽といった万物を平等に救うことである(なお、ペリーの言う「ark」は、宇宙船であるのと同時にモーセの十戒を運ぶ契約の箱「Ark of the Covenant」も意味している)。宇宙のヴィジョンを持つペリーは、偉人たちを対等に並べる。そこでは、同船者としてすべてがイコールになる。
ペリーが浮遊する宇宙空間においては、その万物間のヒエラルキーは皆無に等しい。この宇宙論、つまりコスモロジーは、ペリーがかつて自身のブラック・アーク・スタジオについてトゥープに語ったことばにも確認することができる。彼によれば、スタジオの機材も人間のように生きており、そこを操作することによって、共存関係にある人間と機械が音楽を作り出す。よって、機械にも魂がある。このペリーのアニミズム的コスモロジーにおいて、機械が人間に操作される側にのみ位置しているような主体-客体関係は適応されない。この事物の水平的関係性は、先ほど触れた宇宙船内平等のアナロジーとしても考えることができる。
悔い改めよ 月の上のコオロギは言った
(……)
月の上でロックしてみろ ロックしてみろ
私は月でローマ法王を蹴っ飛ばした男だ
私は奴を追いだし 奴のケツを蹴り飛ばした
蹴り飛ばせ 蹴り飛ばせ
──“月の上のコオロギ”
このペリー・コスモロジーは、彼が1曲目で降り立った月面上にも拡張し、動物と人間の垣根さえも曖昧になっている。彼のリリックによれば、月で説教を説くのは人間ではなくコオロギだ。かつてよりペリーの楽曲では自然物の存在が人間を凌駕することがあったように、『Rainford』でも各所にそのモチーフは現れ、バビロンの邪心を退治する存在として描かれている。ここでも従来のヒエラルキーなどなく、力を持っているのは、蹴られるローマ法王よりもコオロギの声である。
このような彼の宇宙観は、あらゆるアフロ-カリブ文化の混合体でもある。それは黒人の人種的文化的アイデンティティの普遍性を謳歌するラスタファリアン神話にも由来しており、絶対的な王としてのハイラ・セラシエ1世がいるものの、ペリーの宇宙観そのものは絶対的なものではない。5曲目の“マクンバ・ロック”で歌われるように、ブラジルのマクンバや、アフロ-ジャマイカのオベアなど、中南米の黒魔術にもペリーは目を向けている。このように、ペリーの宇宙の捉え方において、ラスタの導きを得つつも、異なる宗教や魔術、エンジニアリング・サイエンスまでもが混在し、それらが楽曲のなかで奇妙なイメージの連鎖を作り上げている(また法王のケツを蹴り飛ばしてはいるものの、彼自身は反キリスト教徒ではないことでも知られている)。
ボーナストラックの“天国と地獄”や、最後の“アップセッター自叙伝”などで語られるように、自身のルーツというマイクロで、ときに社会問題をつぶさに捉える視点と、宇宙に存在するアフロ-カリビアン文化というマイクロな視点を行き来している点も、『Rainford』を興味深いものにしている。これまでのキャリアで編み出された独自のペリー・コスモロジーだけではなく、彼の表現においていかに非合理的で魔術的で、フューチャリスティックなイメージが生まれようとも、そこにいたる自身のルーツをもペリーは忘れ去ろうとはしない。
冒頭で述べたサン・ラーは、彼は宇宙を自分の場所とし、シンセサイザーと宇宙船というテクノロジーを装備し、人間に不条理に設定される人種のカテゴリーを拒否した。ペリーも同様に宇宙を目指すが、彼のベクトルはラーとは異なり、その目的は自分がやってきた場所を交差する関係性を増幅させることにあった。遠くへ行くためには、自分自身が何者であるかが分からなければならない。今作からはアフロフューチャリズムだけではなく、ペリーのそのような人生哲学までもが見えてくるようである。
髙橋勇人