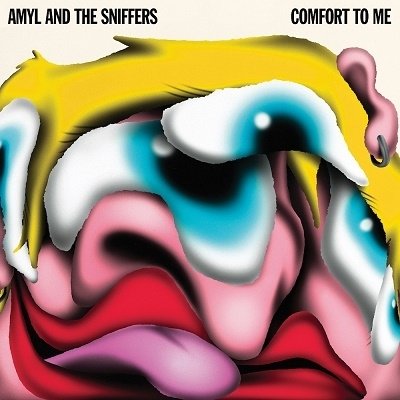古い中国の絵画の中に描かれる花や鳥たちのような電子音楽である。
中国出身、現在ロンドンを拠点とするサウンド・アーティストの Li Yilei のアルバム『之 / OF』を聴いたとき、まずそう思った(Li Yilei はアジアとイギリスを拠点とするアート・コレクティヴ〈NON DUAL無二行動〉のメンバーでもある)。じじつ、宋王朝の芸術がインスピレーションの源だったようだ。特に宋王朝時代の絵画、特に花や鳥の絵画は、曲やトラック全体で共通のテーマだという。
それにしてもなんと優雅な電子音楽だろうか。ミニマルでいて絵画的。空間的にして無時間的。瀟洒にして美麗。この「無時間的な感覚」は、やはりコロナ禍の状況からの影響か。前作とはサウンドの質感やムードが異なるのだ。
じじつ、コロナ禍の初期に中国・上海に戻った Li Yilei は、検疫のために二週間ホテルに滞在することになったという。ここで Li Yilei は時間に対する意識が高まった。この『之 / OF』の制作自体はコロナ以前からはじまっていたとのことだが、やはりコロナは本作の制作に大きな影響を与えることになった。
ちなみにコロナ禍で生まれたアンビエント的な電子音楽といえば KRMU『Peel』やイーライ・ケスラー『icons』がある。『Peel』は不安の中の癒しを鳴らし、『icons』は都市の静寂と変化を表現していた。対して『之 / OF』はコロナ禍によって生まれた停止するような無時間的な感覚を音によって表現しているように感じられた。いわば1曲1曲が詩や短歌のように、時を凍結していくような感覚が濃厚なのである。
同時により浮き彫りになったのがより「個」的なサウンドでもある。アスペルガー症候群でありノンバイナリーのアジア人でもある Li Yilei 自身が以前から自身のアイデンティティに対して誠実に向かいあって作品を制作していたことと無縁ではないだろう。先の二作も同様だが、コロナ禍でなくとも、アーティストたちは、やがてこれらのような「個」を濃厚に感じる傑作を作り上げたはずだ。よって聴き手側が、社会と作品を結びつけるのは、卵が先か鶏が先か程度の戯言とすべきかもしれない。だが、われわれが世界という大きな状況の中に生きている以上、世界の変動から無縁に生きられるわけではない。互いに相関しているのだ。
ともあれ本作には、ミニチュアールな感覚と無時間性、有限と無限が横溢している。小さなものに宿る永遠性の感覚がある。ミニマルで室内楽的な音楽性の中に東アジア的な時間感覚があるとでもいうべきかもしれない。2020年にリリースされた前作『Unabled Form』は電子音とノイズが交錯する作風でこのようなアジア的な要素が希薄だった。やはり『之 / OF』は自身のルーツへと遡行する中で生まれた作品なのでないかと考えてしまう。
リリースは Meitei / 冥丁のアルバムを送り出してきたUKの〈Métron Records〉である。アルバムには全12曲が収録されているが、どの曲にも「TAN / 潭」「CHU / 處 」「HUO / 惑」「WEI / 未」「HAI / 海」などの漢字一文字が用いられていて、これまた無時間的な感覚を表しているように思えた。
じっさい『之 / OF』には、ミニマルな電子音楽、フィールド・レコーディング、アンビエント、テクノ、ドローン、現代音楽的な要素など、さまざまな音のエレメントが交錯している。しかしそれらは、ただ雑然とまとめ上げられたような印象はまるでない。
時を超えるような永遠性のなかで、まるで中国の古い絵画のように、静寂と音の「あいだ」で慎ましく音楽が鳴っているように私には感じられた。1曲1曲がまるで小さな詩のように、有限と無限をあいだを往復しているような感覚を発しているとでもいうべきか(「之 / OF」という前置詞を用いたタイトルも「部分と全体」を意味しているという)。
加えて『之 / OF』を聴いていると近年再評価が続いた吉村弘、芦川聡、廣瀬豊などの日本の「環境音楽」からも影響を受けていることも想像できる。しかし彼らの音楽にもミニマルな無時間的な、あえていえば東アジア的な時間感覚があったと思う。となればこれは「影響」というよりも30年以上の時を経た繋がったアーティスト同士の「共振」といえるのではないか。音楽は時代も国境も世代も超えるのである。
ちなみに本作は、レコード、CD、データで販売されているが、Li Yilei が自ら制作した中国版オカリナにダウンロード・コードを付属したものも販売されている。音楽とアートフォームの新たなあり方を提案してもいるといえよう。