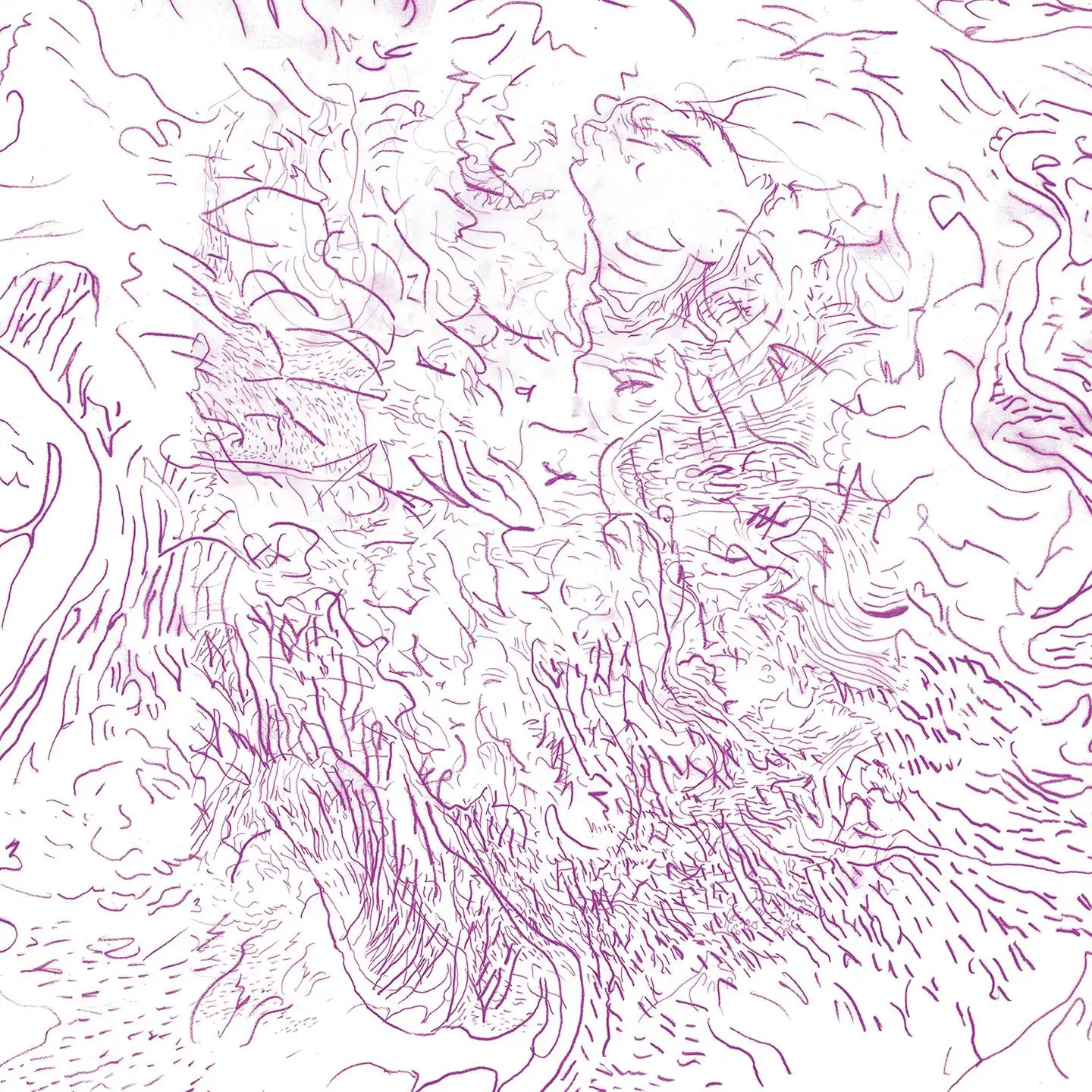ビートメイクと映像のオンラインコンテスト「BEAT GRANDPRIX(ビートグランプリ) MUSEUM 2022 supported by TuneCore Japan」が作品を募集している。これは、パンデミック前は名古屋で開催されていた「ビートグランプリ」という、全国から凄腕のビートメイカーが集結し、1on1のバトル形式で勝敗を競うという人気のコンテストだったもののオンライン版。
過去、多くの著名なビートメイカーを輩出してきた大会。今回は、オンラインということもあってか、映像にも視野を広げ、名称もあらたにアート・コンテスト「ビートグランプリ MUSEUM」として再スタート。ちなみに昨年は、Mitsu the Beats (GAGLE / Jazzy Sport) 、☆Taku Takahashi (m-flo,block.fm)、TOMOYUKI TANAKA (FPM) 、鈴木光人(スクウェア・エニックス)など第一線で活躍しているアーティストが審査員として集結した。ビートを作っている人たちは参加しよう!
なお、コンテストに関する詳しい説明は、ビートグランプリWEBサイト(https://beatgp.com/)を参照ください。