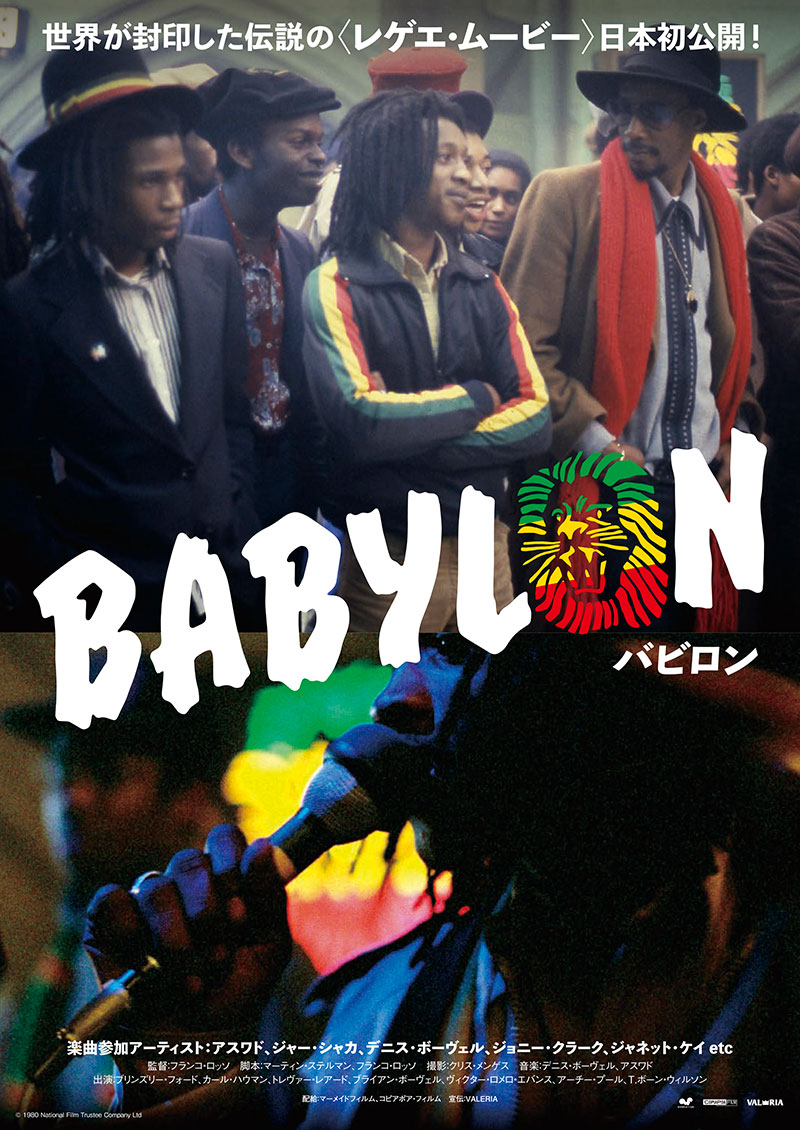「ONE BLOOD, ONE NATION, ONE UNITY and ONE LOVE」。LIVE はいつもこの一言から始まった。本作は昨年惜しくもこの世を去ってしまった“RAS DASHER”。彼といっしょに音楽を作ってきた仲間から、 最大限の感謝を込めて、それぞれのアーティストが現在進行形の音を天に響かせる追悼と音の祭典が開催される。
10/14 (金) 場所: 新宿Loft
Open:18:00-Til Late 27:00
REGGAELATION INDEPENDANCE & Special Guests from Cultivator & KILLA SISTA
MILITIA (SAK-DUB-I x HEAVY)
光風 & GREEN MASSIVE
UNDEFINED
BIM ONE PRODUCTION
LIKKLE MAI (DJ set)
MaL & JA-GE
外池満広 *Live
I-WAH & MARIKA
176SOUND
OG Militant B
山頂瞑想茶屋 feat. FLY-T
And more
Sound System by EASS HI FI
Food:
新宿ドゥースラー
Adv. ¥4,000
Entrance ¥4,500
前売りチケット情報
ZAIKO
https://tokyodubattack.zaiko.io/e/voiceoflove
ローソンチケット https://l-tike.com/order/?gLcode=72177
( Lコード:72177)
INFO
新宿LOFT
tel:0352720382
About Ras Dasher:
80年代後半〜90年代初頭、SKA バンドのトランペットから始まったという彼の音楽キャリア、 その後 JAMAICA や LONDON を旅して帰国後、レゲエ・ヴォーカリストとして歌うようになった。 下北沢のクラブ ZOO (SLITS) で行われていたイベント「ZOOT」などに出演し、Ska や Rockstedy のカヴァー曲を歌っていた。
その後、Mighty MASSA が始めた Roots Reggae Band “INTERCEPTER" の Vocal として参加、 Dennis Brown や Johnny Clark の ROOTS REGGAE を主に歌っていた。 95年頃、前述の クラブZOOT では、MIGHTY MASSA が本格的にUK Modern Roots Styleの SOUND SYSTEM を導入し、自作の音源を発表し始める。 発足よりシンガーとして参加し、97 年に MIGHTY MASSA の1st 12inch 「OPEN THE DOOR/LOVE WISE DUB WISE」 (Destroid HiFi) がリリース。 (Singer RAS DASHER として録音された最初のリリース) 後の MIGHTY MASSA 作品への参加 (2001 年 Album『ONE BLOW』、2003年 7inch 「Love Wise Dub Wise」) や DUB PLATE の制作に繋がっていく。 また、INTERCEPTER も音楽性の趣向がUK Modern Roots色が強くなり INTERCEPTER 2 として活動が始まり、 後の DRY & HEAVY の 秋本“HEAVY" 武士と RIKITAKE が加入し、その出会いが CULTIVATOR の結成に繋がっていく。
CULTIVATOR は、何度かメンバーチェンジと試行錯誤を繰り返し 徐々にオリジナルの楽曲とサウンドアイディアで LIVE 活動が始まったのが90年代ももうすぐ終わる頃。 2000年に1st 12 inch Vinyl 「Promise Land/More Spilitual」を〈Reproduction Outernational〉レーベルからリリース.。この音源と DIRECT DUB MIX を取り入れた LIVE が注目される。
2001 年 6月 1st CD mini album “BREAKOUT FROM BABYLON”をFlying Highレーベルから発表。 同年 FUJI ROCK FESTIVAL (RED MARQUIE)にも出演を果たした。また、 UK SOUND SYSTEM の重鎮 ABA SHANTI」の東京公演や、IRATION STEPPERS, ZION TRAIN の東京公演のフロントアクトを務めるなどLIVE も活発化し、2003年3月 2nd CD album 『Voice Of Love』 をリリース。 2004 年にこれらのシングル・カットとして 「Hear the voice love / In My Own / Freedom of reality」と 「Aka-hige /Spanish town」を発表した後、残念ながら活動を休止となった。

■Cultivator - 『Voice of Love』 レコードリリースについて
Bim One Production / Riddim CHango Recordsの1TAによる、国産ルーツ/Dubの魅力を再評し新たな視点を深堀りするべくスタートするレーベル〈Rewind Dubs〉が始動!
記念すべき第一弾は、2003年発表のCultivatorの名作CDアルバム『Voice of Love』 をLPアナログ用にリマスターした復刻盤! 本作は昨年惜しくもこの世を去ってしまった同バンドのフロントマン、Ras Dasherをトリビュートした限定300枚の再発作品である。
https://rewinddubs.bandcamp.com/releases
■ Voice of Love / Cultivatorオリジナルロゴ復刻T-シャツ販売決定
限定枚数販売!お見逃しなく!
Ras Dasher - Voice of Love T-Shirts (White / Black)
Cultivator Logo T-Shirts (Black)
M / L / XL / 2XL
¥3,000