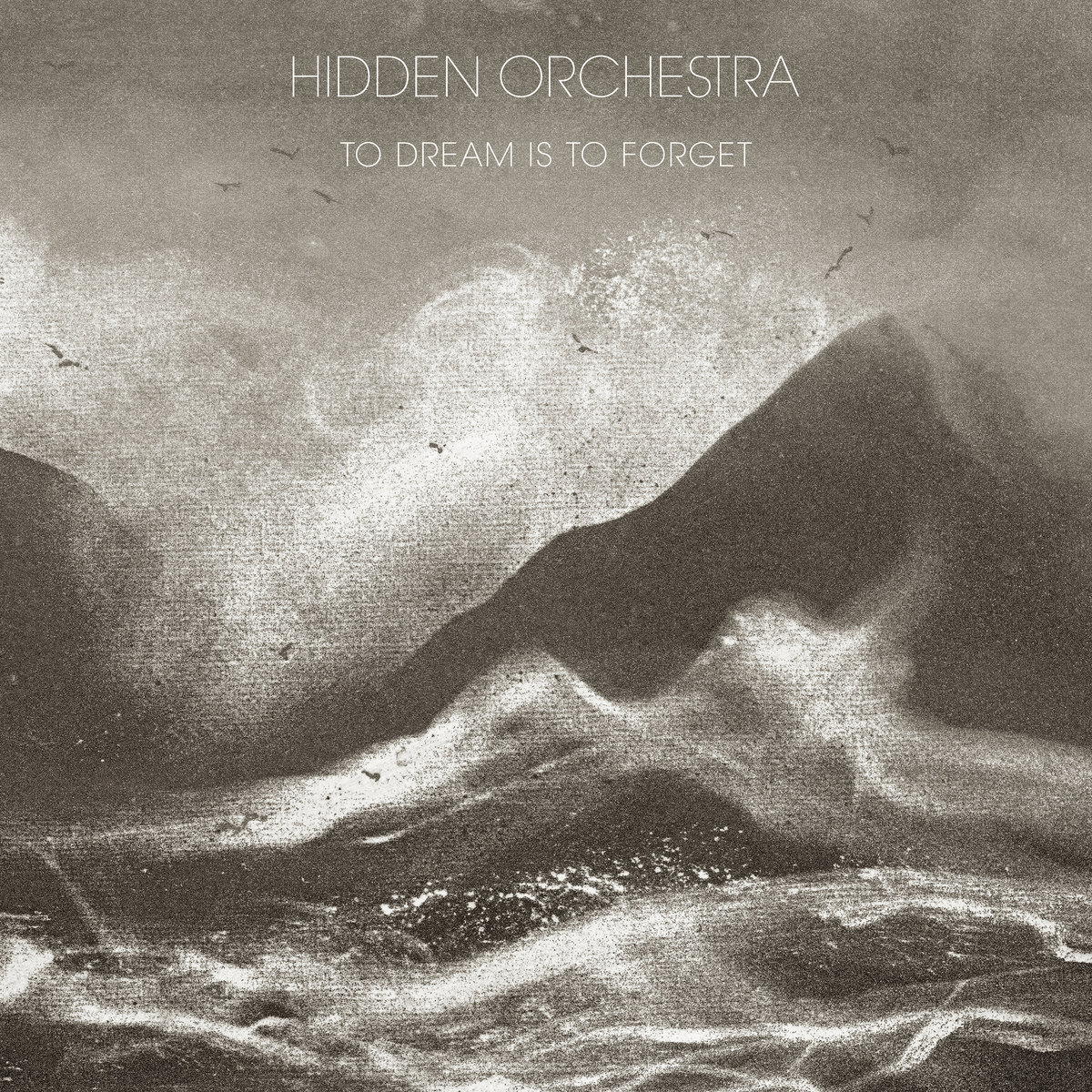現在AMBIENT KYOTOでもインスタレーションが展示中の坂本龍一。その大規模個展が開催されることになった。会場は東京都現代美術館で、会期はおよそ1年後の2024年12月から。大型インスタレーションを紹介する、日本では初めての規模の個展になる模様。詳細についてはこれから順次発表されていくと思われるので、続報を待とう。
アート作品を包括的に紹介する、日本初となる大規模個展
坂本龍一展(仮)
2024年12月21日~2025年3月30日 開催決定
東京都現代美術館では、来年2024年12月から音楽家・アーティスト、坂本龍一(1952―2023)の大型インスタレーション作品を包括的に紹介する、日本では初となる最大規模の個展を開催いたします。坂本は多彩な表現活動を通して、時代の先端を常に切り拓いてきました。2000年代以降は、さまざまなアーティストとの協働を通して、音を展示空間に立体的に設置する試みを積極的に思考/実践しました。今回の展覧会では、生前坂本が本展のために構想した新作と、これまでの代表作を美術館屋内外の空間にダイナミックに構成・展開し、クロニクル展示を加えて、坂本の先駆的・実験的な創作活動の軌跡をたどります。
展覧会概要
■展覧会名:坂本龍一展(仮)
■会 期:2024年12月21日(土)~2025年3月30日(日)
■会 場:東京都現代美術館 企画展示室 1F/B2F(東京都江東区三好 4-1-1)
■主 催:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館
■お問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)
■展覧会ウェブサイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/RS/
※観覧料、休館日等詳細は決定次第ウェブサイト等で公開します。
坂本龍一 (さかもと・りゅういち/音楽家)
1952年、東京都生まれ。1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年「Yellow Magic Orchestra」結成に参加し、1983年の散開後も多方面で活躍。映画『戦場のメリークリスマス』(83年)の音楽では英国アカデミー賞、映画『ラストエンペラー』の音楽ではアカデミーオリジナル音楽作曲賞、グラミー賞、他を受賞。環境や平和問題への取組みも多く、森林保全団体「more trees」を創設。また「東北ユースオーケストラ」を立ち上げるなど音楽を通じた東北地方太平洋沖地震被災者支援活動も行った。1980 年代から2000年代を通じて、多くの展覧会や大型メディア映像イベントに参画、2013年山口情報芸術センター(YCAM)アーティスティックディレクター、2014年札幌国際芸術祭ゲストディレクターを務める。2018年 piknic/ソウル、2021年M WOODS/北京、2023年M WOODS/成都での大規
模インスタレーション展示、また没後も最新のMR作品「KAGAMI」がニューヨーク、マンチェスター、ロンドン、他を巡回するなど、アート界への積極的な越境は今も続いている。2023年3月28日、71歳で逝去。