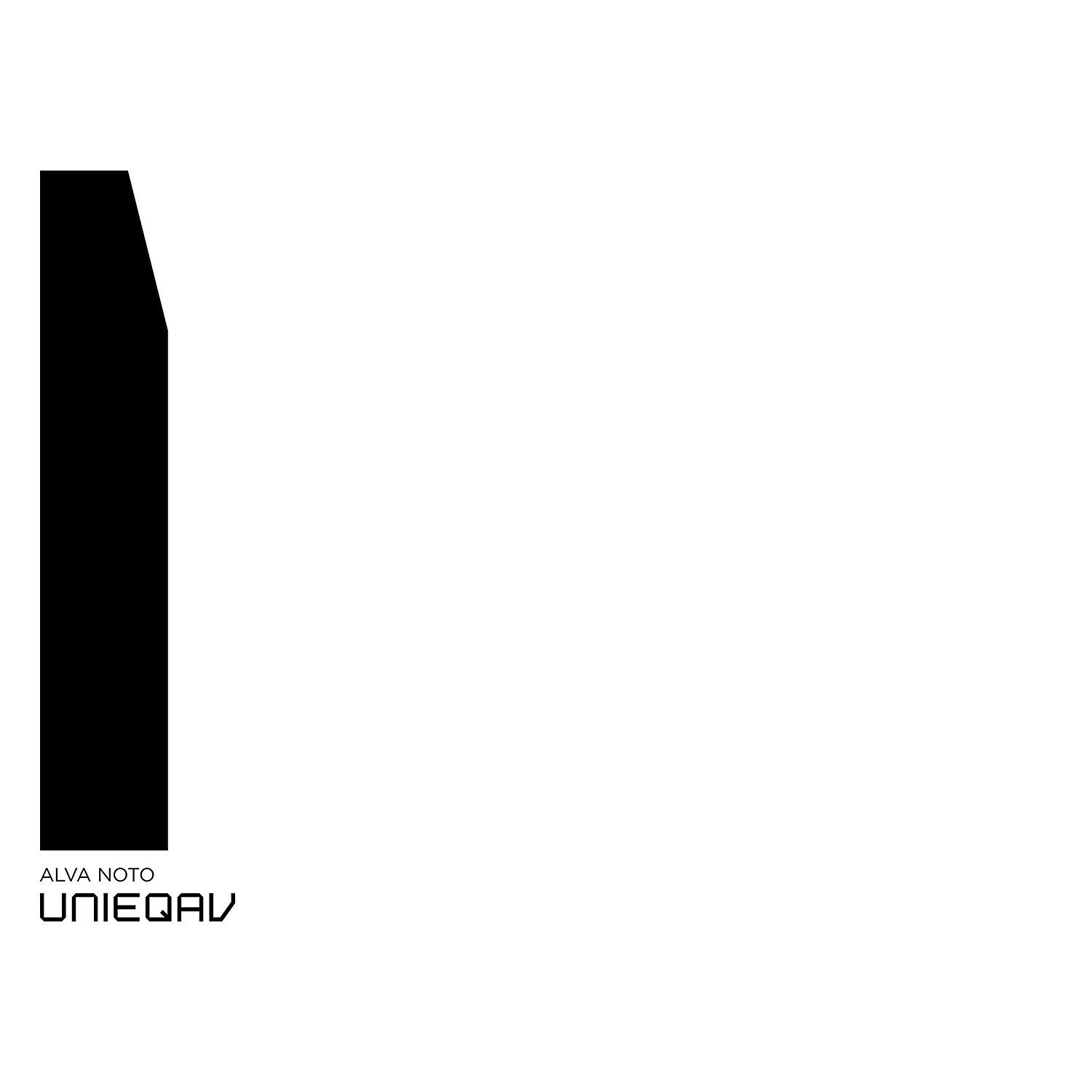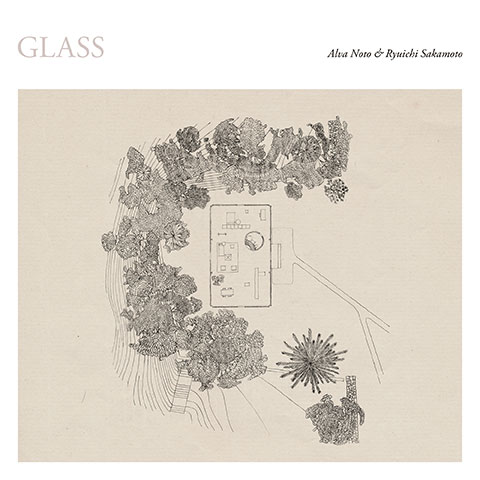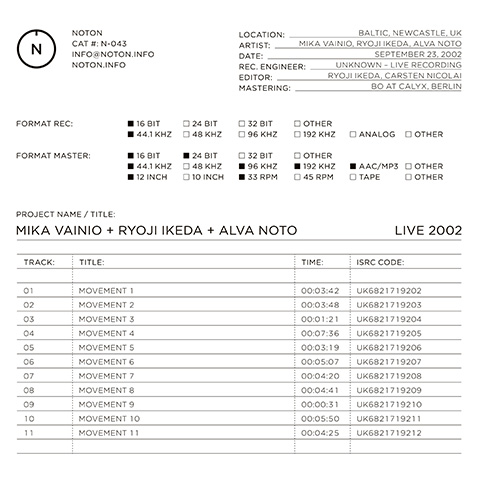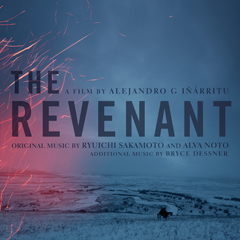MOST READ
- Ryuichi Sakamoto | Opus -
- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー
- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース
- 『成功したオタク』 -
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙
Home > Reviews > Album Reviews > Alva Noto- Xerrox Vol.3

過去は同時に未来だ。いまや私たちの時間はリニアには進んでいない。過去と呼べるものは、常に未知のフォームとして再生成し、未来に置かれるからだ。それはリングのように円環している時間構造といえよう。クリストファー・ノーランの映画『インターステラー』のように、過去と未来という時間の概念が紙の両面のように存在する感覚は、21世紀=インターネット的に階層化したデータ閲覧社会を生きる私たちにとっては実感できる感覚のはずだ。新/旧という概念がフォルダの中に並列に置かれ、無制限にコピーされていく。コピーの余剰に生まれるノイズ。そして、その果てにある新しいロマン主義の誕生……?
カールステン・ニコライ=アルヴァ・ノトが2007年から進める「ゼロックス(Xerrox)」シリーズは、現代社会を覆うコピー=オリジナルという問題をテーマとしたアンビエント作品だった。同シリーズは2007年に「Vol.1」、2009年に「Vol.2」がリリースされており、今回、6年ぶりにリリースされる本作「Vol.3」によってシリーズは、さらに大きな円環を描く。
「Vol.1」が「旧世界へ」、「Vol.2」が「新世界へ」がテーマだった。そして、本作「Vol.3」のテーマは「宇宙にむかって」。宇宙という円環する時間領域にむけて、まるで反射する光のように美しい音響/音楽で結晶させていくのだ。このアルバムはまずもって徹底的に美しい。
先に書いたように、「ゼロックス」シリーズは、オリジナルとコピーという現代的な諸問題をテーマとしつつも、音楽的にはカールステン・ニコライ=アルヴァ・ノトによるアンビエント作品となっている。2000年代後半以降のカールステン・ニコライ=アルヴァ・ノトは、大きく分ければ、「ユニ(Uni)」シリーズがビート作品、「ゼロックス」シリーズがアンビエント作品と2系列に分かれている。その2つのシリーズによって、90年代からのデザイン的/建築的/科学的な音響構築から一歩も二歩も前進し、「音楽」というもののフォームを、ビート(リズム)とアンビエント(ドローン)の両極から刷新させてきた。
ビート・トラックである「ユニ」シリーズが、バイトーンとのダイアモンド・ヴァージョンへと発展し、ポップ/アートの様相を極めていくことに対し、「ゼロックス」シリーズは、まるでカールステン・ニコライの個人史へと遡行するように、より内面的な作品となっている。
この「Vol.3」は、「宇宙にむかって」というテーマからもわかるように本作がSF映画的だが、『2001年宇宙の旅』にせよ、『惑星ソラリス』にせよ、『コンタクト』にせよ、『インターステラー』にせよ、「宇宙の果て」で人は自分自身の投影するもの(コピー?)と出会い、そのことによって自らの内面性が乱反射し、自己の再認識(=再統合?)が行われる構成であった。
いわば世界の果ての自己との邂逅。本作もまた、宇宙的な音響と旋律の中に、カールステン・ニコライの幼少期の記憶が圧縮され解凍されていく。
事実、本作はカールステン・ニコライが幼少期・少年期に観たであろう『惑星ソラリス』などのSF映画にインスパイアされているという。アンドレイ・タルコフスキーの『惑星ソラリス』は1972年のフィルムなので、1965年生まれのカールステン・ニコライ、6歳か7歳のときの作品ということになる。もっとも東ドイツで生まれた彼が「ソラリス」を観たのはもう少し後かも知れないが、いずれにせよ、彼の幼少期である70年代の記憶や気分とこの映画がつながっているのはわかる気がする。
そう、この『ゼロックスVOL.3』には、幼少期や当時に観たSF映画への追想などによって、彼の「70年代の記憶」が折り畳まれているのかもしれない。現代社会におけるコピーとオリジナルの問題をアンビエント/グリッチノイズ作品として昇華した「ゼロックス」シリーズが、「Vol.3」において、このようなパーソナルな領域に行き着いたことは非常に興味深い。
カールステン・ニコライの幼年期の記憶。それは「東ドイツの幼年時代」とでもすべきものか。さながらヴァルター・ベンヤミン的でもあるが、それと呼応するかのように、この作品はカールステン・ニコライの旅行=トランジットのさなかで(空港で、飛行機で、車中で)制作されたという(マスタリングなどの仕上げは2014年にスタジオで行われている)。つまり、本作には旅の記憶と幼少期の記憶が交錯している(つまり、この『ゼロックスVol.3』は東ドイツ出身のアーティストのエッセィ的なアルバムとはいえないか)。
また、「70年代とドイツ」とすると、70年代のクラフトワークや初期タンジェリン・ドリームなどジャーマンロックとの関連性も無視できない。本作の重く暗い旋律とアンビエントなサウンドにはそれらからの(無意識の?)影響を強く感じる(同時に硬いノイズの響きが現代へと直結している)。
さらに「ゼロックス」シリーズには、アルヴァ・ノトの作品にあって旋律的な要素が表面化しているのだが、本作は、旋律は、はっきりと「作曲」という次元にまで高められている。このメロディはまたドイツ的なのだ(10曲め“Spiegel”のピアノは誰の演奏か。クレジットはない。坂本龍一のようにも聴こえるが……)。
幼少期。映画。音楽。ドイツ。旅。それら記憶のフラグメンツが交錯するときに生まれるロマンティックな電子音響。それが本作だ。私は、このようなアルバムをカールステン・ニコライが作ったことに「成熟」を聴きとりもするが、同時にある種のロマン主義の萌芽を感じもする。そして、このパーソナルな個人史や内面への遡行は、2015年現在の電子音響の状況を考える上でとても重要なことではないかと思う。
そう、私たちはインターネット社会以降の新しい「ロマン主義」を生きている。コピーとノイズが溢れかえり、それらがすべて可視化されてしまう社会。その「悪い場所」において、より個人の内面性や実存性を重視すること。そのロマンティックな記憶の結晶が、新しい「美学」とでもなるかのように(だが、それは外部への連携として表出してはならず、あくまで個人の中に煌めきとして輝くべきものとも思える。それが作品化されるからこそ美しい)。
本作に煌めいているパーソナルで美しい響きは、そんな現代社会からの美しい乱反射のようにも思えてくる。2015年の最重要電子音響作品だ。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Li Yilei - NONAGE / 垂髫
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain


 DOMMUNE
DOMMUNE