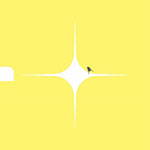ジョン・フルシアンテ、そして彼の近作と非常に結びつきの深いRZAを通し、ウータン・クランファミリーの一員として知られるブラック・ナイツはフルシアンテに出会うことになった。「こんなに素晴らしいコラボレーションの関係を他人と築けるとは思わなかった」とフルシアンテ自身が述べるように、互いへのリスペクトと、それぞれのキャリアにとって新鮮でもある出会いは、彼らに1枚のアルバムを作らせる……それがこの『メディーヴァル・チャンバー』だ。
フルシアンテが楽曲・トラックをプロデュースし、ブラック・ナイツのふたりがラップする。先にコンセプトを固めることなく、フルシアンテから投げられたトラックにリリックをのせ、最終的にはそもそもとは大きく異なるかたちをしたものへと変化していったというこの作品からは、彼らが試行錯誤を重ねながらも、コラボレーションを楽しんでいる様子がうかがわれる。
プロデューサーとしての角度を深め、つねに歩みを止めずに己が道をゆくフルシアンテの、新たな一歩に注目したい。
■BLACK KNIGHTS / MEDIEVAL CHAMBER
(Produced by John Frusciante)
(RUSH!×AWDR/LR2)

日本盤には、先行ダウンロードで話題になった“Never Let Go”、そしてジョン・フルシアンテのオリジナル“Wayne”のリミックスという豪華な日本盤ボーナストラック2曲に加え、高音質Blu-spec CD 2、日本先行発売など、日本びいきのジョンらしい特典が満載。さらに目玉として、バルーチャハシム氏による日本盤限定スペシャル・インタヴューも付属! 買うならば絶対に国内盤をおすすめしたい。
発売日:2014.01.08
定価:¥2,200
曲リスト:
1.Drawbridge
2.The Joust
3.Medieval Times
4.Trickfingers Playhouse
5.Sword In Stone
6.Knighthood
7.Deja Vu
8.Roundtable
9.Keys To The Chastity Belt
10.Camelot
11.Never Let Go -Bonus Track for Japan-
12.Wayne Remix -Bonus Track for Japan-