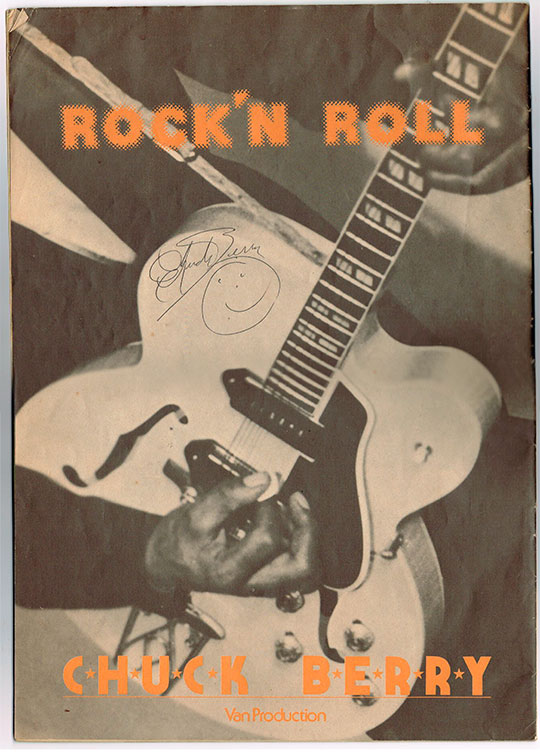季節の即興音楽、あるいは形式に還元されざる余剰の響き
演奏の展開はいつも同じで、まず手探りのようにはじまり、まんなかで盛り上がり、静かにおわる。この曲線がかならずついてまわる。これ以上の形式がないとしたらまったく空疎だとしかいいようがない。 ――ギャヴィン・ブライアーズ
昨年の夏、とあるミュージシャンが率いるグループのライヴを観に行った話から始めよう。そこでは電子楽器とアコースティックな楽器が入り混じった7、8人ほどの演奏者たちによる、いくらか「決めごと」を設けられた即興アンサンブルが披露されていたのだが、演奏が開始したとき、もの凄く奇妙な体験をしたことをよく覚えている。まるでサイン波のような電子的な音を発する管楽器や声が、エレクトロニクスの響きと混ざり合い、どちらがどちらともつかないような、どの音がどの人間から発されているのかわからなくなるような、視覚的な風景と聴覚的な体験が撹乱されるような不可思議な音響空間が成立していたのである。「これはすごい! ここからどういうふうに展開していくのだろう」と思ってしばらくすると、しかしアンサンブルは、そのミュージシャンの音盤で経験したことのある「あの感じ」に近づきはじめていく。それぞれのプレイヤーが短いフレーズを繰り返すことで即興を織り成していくその演奏は、そこからは案の定「あの感じ」を追体験/再確認させるかのようにして、予想した通りの展開になっていった。探り探り始められたアンサンブルは盛り上がりをみせ、その後静かになっていき終了した。
もちろん、音盤と同じ展開をみせるのは、なにも悪いことではない。むしろそのミュージシャンの変わらぬ個性を聴くことができた、と言うこともできる。しかしその日の演奏で素晴らしかったのはやはり、最初の段階でみられた「聴いたことのない」サウンドだったのだ。そしてこと即興演奏に関しては、互いの探り合いから始まり、それがノってくると盛り上がり、そこから終わりへ向けて静かに収束していく、という展開は、このミュージシャンに限らず広くみられるものである。
こうした展開を前にして、即興音楽の形式の単調さに絶望し、作曲へと活動領域を移したのが、かつてデレク・ベイリーのもとでベーシストとして活躍していたギャヴィン・ブライアーズだった。たしかに言葉に還元してしまえば、多くの即興音楽はことほどさように単純極まりない形式をとっているようにみえる。じっさいに、こうしたある種の予定調和のような展開に安住する即興演奏家も少なからずいる。そのほうが展開を気にしなくていいぶん、より「自由」だとも言えるのかもしれない。だがしかし、同時に、言葉にしてしまえば単純だとしても、現実に鳴り響く音楽はより複雑で多様なありようをみせているものである。冒頭に書き記したライヴの体験でいえば、その展開と成り行きは「あの感じ」から逸脱するものではなかったのだとしても、少なくともその始まりの部分では、「探り探り」でありながら、この言葉には絡め取ることのできないようなサウンドに満ち溢れていた。そしてそうした言語化しえないような、還元された形式の外へと零れ落ちる響きを聴かせてくれるグループとして、たとえばここに、ザ・ネックスがいる。
*
オーストラリア連邦最大の都市であるシドニーを拠点に活動してきたザ・ネックスは、ピアノのクリス・エイブラムズ、ベースのロイド・スワントン、ドラムスのトニー・バックという3人のメンバーによって1987年に結成された。かつて90年代の初めごろ、トニー・バックは日本とも交流をもち、大友良英らとともにバンドを組んでいたので、そこから彼らの存在に辿り着いたという日本のリスナーも多いのかもしれないが、とりわけ昨年の暮れにザ・ネックスは活動30周年を前にして初めての来日を果たし、東京、大阪、滋賀の3箇所でツアーをおこなったので、そのことから彼らの存在を知るに至った人も多いのかもしれない。東京公演にはわたしも駆けつけ、1時間近くも続けられるトリオ・インプロヴィゼーションに圧倒された。しかしながら彼らの音楽は言葉にしてしまうともの凄く単純である。メンバーのそれぞれが短いフレーズをひたすら繰り返す。彼らはそのフレーズを即興でゆるやかに変化させていく。時折フレーズ同士が絡み合い、グルーヴする場面もみられるが、無関係に並走することもある。3人ともにフレーズの繰り返しをおこなっているため、通常の即興演奏におけるような丁々発止のインタープレイはみられず、まるで植物の生長のような、あるいは広々とした空に流れる雲のような、じっと耳を凝らしていないと変化していることにさえ気づかないような緩慢な移り変わりを聴かせてくれる。それは静かな演奏から幕を開け、中盤では盛り上がりをみせ、また静かになって終えられる。
ブライアーズが非難した単純極まりない形式である。けれどもそれは、予定調和と言ってしまうとちょっと違う。盛り上がった後に静まりかえって終わるのだろうなという予想はつく。しかし彼らの音楽は、その始まりからは予想だにしないような成り行きをいつも聴かせてくれるのだ。それはたとえば、緩慢な四季の移ろいが、春の後には夏が来て、秋の後には冬が来るとわかっていながらも、昨年の夏と今年の夏が異なっていることにも似ている。反復することが同じ結果をもたらすのではなく、繰り返すことが異なる結果をもたらすようなものとしての音楽。
そんな彼らの19枚めのアルバムがリリースされた。リリース元は、1994年以来ザ・ネックスの音源を発表し続けてきた彼らの自主レーベル〈フィッシュ・オブ・ミルク〉ではなく、エレクトロニカ/電子音響作品で知られる〈エディションズ・メゴ〉の傘下にあり、Sunn O)))のスティーヴン・オマリーが監修するレーベル〈イデオロジック・オルガン〉である。過去の大半のアルバムでは1時間近くの長尺の演奏が1曲だけ収録されているというパターンが多く、それは74分間もの長さを記録することが可能なCDというフォーマットが、音楽の流通手段として人口に膾炙し始めたのと同時期に、ザ・ネックスが活動を始めたことと無関係だとは思えないのだが、ならばなおさら本盤が、2枚組LPおよび音源配信のみで出されているということは興味深い。収録されているのは15分ほどの曲が2曲、20分ほどの曲が2曲の計4曲で、それらはちょうどLPの片面の長さに相当する演奏である。だがCDというフォーマットの栄枯盛衰を眺め続けてきた彼らにとって、これがLPでリリースする初めてのアルバムというわけではなく、過去に『Mindset』(2011)『Vertigo』(2015)と2枚のLPアルバムを出している。
ついでにザ・ネックスのこれまでの活動を音盤から振り返ってみると、彼らは1989年にファースト・アルバム『Sex』を発表し、同じフレーズが1時間近くも延々と続けられるその衝撃的な音楽を世界に提示した。しかし翌年にリリースされたセカンド・アルバム『Next』(1990)では早くもコンセプトをやや変えて、6曲の短い演奏(とはいえ、うち1曲は30分近くある)を、複数のゲストを迎えながら収めたものとなっている。続く3枚め『Aquatic』(1994)はそれから4年後にリリースされ、30分弱の、タイトルと同名の楽曲が2曲収録されているのだが、片方はトリオで、片方はハーディ・ガーディ奏者をフィーチャリングしたカルテットによる演奏。4枚めのアルバム『Silent Night』(1996)では1時間1曲というスタイルに戻り、しかしそれが2枚組アルバムとなって2曲まとめて発表された。その後は映画音楽を手掛けそのサントラ『The Boys』(1998)を出したり、ライヴ・アルバム『Piano Bass Drums』(1998)をリリースしながらも、スタジオ・アルバムとしては1時間1曲というスタイルが踏襲されていく(『Hanging Gardens』(1999)『Aether』(2001))。もちろん、同じスタイルとは言っても内容はそれぞれに異なるモチーフが扱われているためまったく別ものの演奏となっている。そして2002年にリリースされた4枚組のライヴ・アルバム『Athenaeum, Homebush, Quay & Raab』は、オーストラリアにおけるグラミー賞とも言うべきARIAミュージック・アワードにノミネートされた。続けざまにライヴ・アルバム『Photosynthetic』(2003)を出した彼らは、同年にリリースした『Drive By』(2003)でARIAミュージック・アワードのベスト・ジャズ・アルバムに選出されることになる。12枚めとなるアルバム『Mosquito / See Through』(2004)は2枚組で、木片が飛び散るような物音と力強いベースのグルーヴなどは、同じく1時間1曲の2枚組だった『Silent Night』を思わせもする。そしてさらに『Chemist』(2006)では2度めのベスト・ジャズ・アルバムに輝いてしまうのだ。同作品はそれまでのスタイルとは異なり、20分前後の楽曲が3曲収録されている。スティーヴ・ライヒmeetsロック・ミュージックな3曲め“Abillera”は、ポストロックにも通じるサウンドを聴かせてくれる。また、このあたりからドラムスのトニー・バックが積極的にギターも使用し始める。4枚めのライヴ・アルバム『Townsville』(2007)を挟んでからは、2曲収録されたLP作品『Mindset』(2011)を除いて、1アルバムに長尺の1曲というスタイルで『Silverwater』(2009)、『Open』(2013)、『Vertigo』(2015)の3枚の作品をリリースしていく。
ここまで振り返ってみて興味深いのは、ゼロ年代の終わりごろを境にして、彼らの音楽性がやや変化しているということである。それまでは「リフ」とも言うべきベースとドラムスの具体的/音楽的なフレーズの反復を基盤にして、その上で主にピアノが装飾的な彩りを加えていく、というアンサンブルの組み方がなされていたのだった。場合によってはベースとドラムスは徐々に変化するということもなく、『Sex』のように全く同じフレーズを1時間ひたすら続けるということもあった。しかし『Townsville』あたりからそうしたスタイルに変化の兆しが見え始める。ベースとドラムスはともに同じリズムを奏でるのではなく、それぞれが独立し各々のフレーズをゆるやかに変化させていく。そのフレーズも具体的/音楽的というよりは、反復されることで初めてリズムやパターンを見出せるような抽象的/音響的なものとなっていく。『Open』や『Vertigo』などに顕著だが、リズムを生み出す下部構造としてのベース&ドラムスに対して彩りを添えるウワモノとしてのピアノ、というのではなく、むしろ三者がそれぞれリズムもサウンドも担いながら三様に変化していき、それらが絡み合いときに衝突しあるいは共振するアンサンブルといったものになっていく。その時点でザ・ネックスは結成からすでに20年以上経っているわけだが、彼らの音楽がクラウト・ロックやミニマル・ミュージックとは全く異質な独自のインプロヴァイズド・ミュージックとなったのは、むしろここからのようにも思える。しかも彼らはあくまでピアノ・トリオという伝統的なジャズ・フォーマットを踏襲した上でそれをおこなっているのである。新たな音楽性へと突き進むためにメンバーが次々に楽器を持ち替えていくというわけではなく。
そして本盤『Unfold』はまさにそうしたザ・ネックスに独自の音楽が収められた現時点での最高傑作である。叙情的なピアノの旋律から幕を開ける1曲め“Rise”は、さらにオルガンの揺らめく響きとベースのアルコ奏法による持続音が漂うなかで、雨音のようにパラパラと叩かれるシンバルが絡み合い、終始穏やかな音の風景を聴かせてくれる。2曲めの“Overhear”では、アルコ奏法の持続音が鳴り響く一方で、ドラムスは速度感のあるパルスを刻んでいき、そしてそれらのサウンドの波に乗るようにしてオルガンは旋律を奏で続けていく。より「波」の形容が相応しいのは3曲め“Blue Mountain”だ。ベースは太い低音を出しゆったりとしたリズムを形成し、ドラムスは強くなったり弱くなったりするスネアやシンバルのロール奏法を聴かせ、そこにオルガンの揺らめきが加わるサウンドは、まるで打ち寄せては引き返していく浜辺の波のようでもある。だが後半では、ドラムスのリズムが速度を増していき、それに呼応するようにベースとピアノも変化することで、演奏の緊張感が高まっていく。その高まりを打ち破るかのように4曲め“Timepiece”は強烈な打撃音から幕を開ける。不規則なパルスがポリリズミックに絡み合うその演奏は、しかしながらしばらく聴いていると、ある周期で反復されているために一定のグルーヴを生み出しているのがわかるようになる。そこにオルガンが入ったサウンドは、どこかエレクトリック期のマイルス・デイヴィス・グループを彷彿させる。あるいはその揺らぎモタつくシャッフル・ビートは祭囃子のようでもある。それはいくつもの自動機械が置かれた工場のなかで、それぞれの機械が自らの周期で反復することから生まれる、空間全体のアンサンブルを耳にしていると形容することもできる。
*
1時間に長尺の1曲だけが収録されたアルバムというのは、いかにも取っつき難そうに思えるかもしれず、その意味では本盤は、抽象化/音響化以降のザ・ネックスの音楽が、それぞれに特徴的な4つの楽曲として、LP片面というほどよい短さで収録された、彼らについて知るための導入口として打って付けのアルバムになっている。ちなみに余談だが、本盤に収録されている楽曲の長さを合計すると74分40秒弱になり、CD初期の収録可能時間74分42秒とほぼ一致する。それが偶然の産物なのか意図的に編集されたものなのかは定かではないものの、たとえLPというフォーマットでリリースされた「ほどよい短さ」の楽曲であったとしても、ザ・ネックスの音楽にCDのフォーマットが纏わりついているという事実は、基本的にはアコースティックなピアノ・トリオでありながら、多重録音やプログラミングにも取り組んできた彼らの、音響テクノロジーとの関わりを象徴的に示しているように思える。この30年はザ・ネックスの活動の軌跡であるとともにCDというフォーマットの栄枯盛衰の歴史でもあったのだった。生きた即興音楽を録音するとは如何なる行為なのか? それは避けられるべき演奏を殺す行為なのだろうか? 少なくともザ・ネックスにとってそれは、彼らの表現を成立させるための基盤になってきた条件のひとつであった。彼らの即興音楽はCDになることで死物と化するのではなく、むしろそのフォーマットによって生み出された身体感覚を備えることではじめて可能になるような特異性を内包している。それはLPでは短すぎ、音声ファイルでは際限がなさすぎるのである。そうした特異性の影が、「ほどよい短さ」であるLPの片面に収められた演奏にも、ひっそりと刻印されていると考えることはできないか。余談が過ぎたようだ。ともあれ、これまでとはレーベルを変えて出されたということも含めて、活動を始めてから30周年を迎えたザ・ネックスにとって、本盤のリリースが画期となる出来事であることはあらためて述べるまでもないだろう。
最後に付言しておくと、ザ・ネックスの音楽にじっくりと耳を傾けてみるならば、ここまで述べてきたような様々な発見と出会いと驚きがあるものの、かといってバックグラウンド・ミュージックのように聞き流すことができないものであるというわけではない。その点では、集中的聴取に耐え得る強度を備えた音楽でありながら、同時にその場の空間に溶け込んでしまうこともできるような特徴もあるという、「環境音楽」(ブライアン・イーノ)としての側面を備えている。聴感的にもアンビエント・サウンドやポスト・クラシカルな傾向と共振するものがあるとも思う。とはいえ、やはり彼らの音楽はあくまでも「即興音楽」なのである。少なくともこの側面なくして彼らの音楽は成立することはないだろう。なぜなら事前に音を配置しては決して得られることのないようなサウンドの移り変わりこそが、ザ・ネックスの音楽に特有の独自性であると言うことができるから。そしてそれはやはり、変わりゆく移ろいそのものの美しさというものであり、あるいはわたしたちが気づかぬ間にそこで生成し変化していき、ふと振り返ると美しく佇んでもいるような、迷路のように複雑に入り組んだ「季節」に似ている。