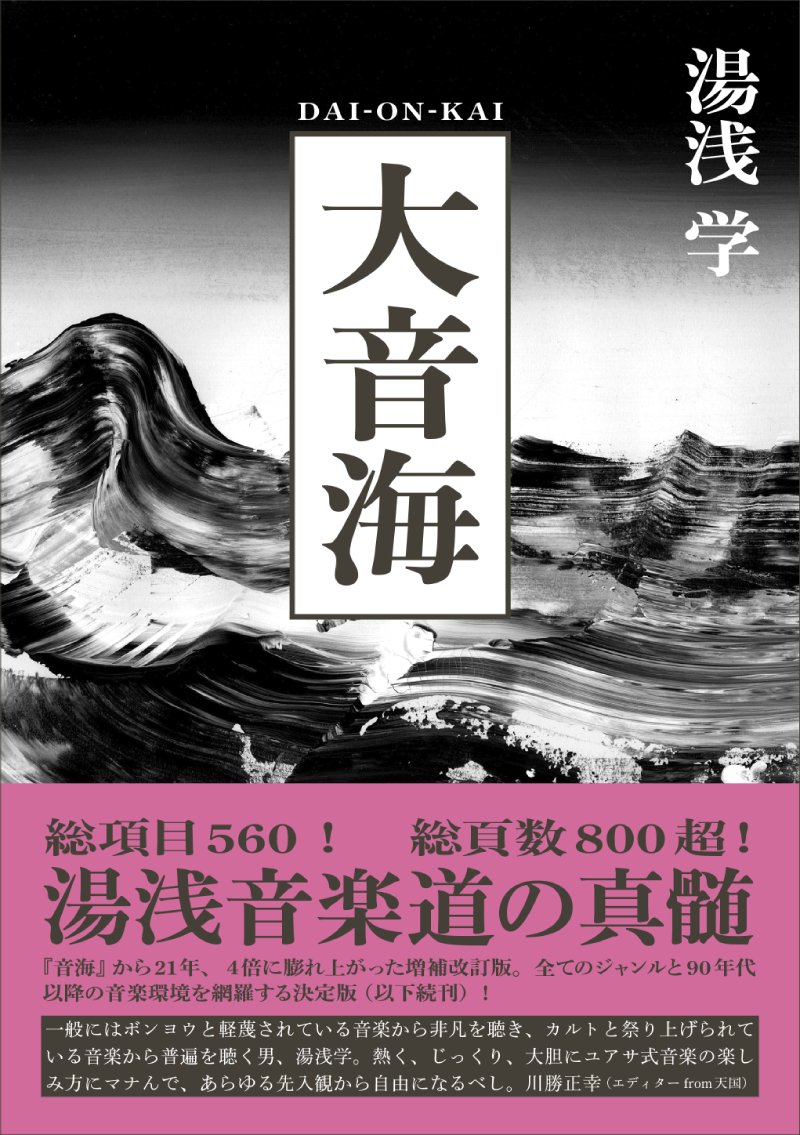いまでもスフィアン・スティーヴンスの『イリノイ』(05)について考える。あのアルバムの凄いところは、イリノイ州にまつわる事件や伝承をストーリーテリングに落としこみつつ知的にコンセプトとした……のみではなく、そこにスフィアン個人の屈折した内面や誇大妄想が編み込まれていたことにある。彼個人の狂気がアメリカ中西部に埋もれた歴史と重なるという事態。音楽的にはランディ・ニューマンやヴァン・ダイク・パークスの血筋にあるオーケストラル・ポップだが、「音楽的」という領域に留まらない深淵が口を開けていた。その才覚があまりに突出したものであるために、00年代のUSインディ・ロックにおいてスフィアンは個として屹立した存在になってしまった。背中を追えない存在に。その後彼は自身の生い立ちの暗部によりフォーカスするようになり(『キャリー&ローウェル』~シングル「トーニャ・ハーディング」)、もはや誰も踏み込めない領域に入りこんでいるように見える。
だが、スフィアン・スティーヴンスのアメリカに対する強い関心が刺激を与えたのか、彼の「音楽」部分はケンドリック・ラマーがサンプリングするなど個を剥奪しながら、むしろ他ジャンルに広がっていくこととなった。ソウル/ゴスペル/R&Bにスフィアンからの影響が色濃いチェンバー・ポップを混ぜ合わせるモーゼズ・サムニーの登場は、ジャンルの横断が柔軟になったいまらしい出来事であるように思える。にわかにスフィアンの功績が再浮上しているようなのだ。
コナー・ヤングブラッドの本デビュー作は、まさにスフィアン・スティーヴンスのこの15年ほどの存在の大きさを思い知らされるものだ。はっきりと直系だと言っていいだろう。バンジョーやクラリネット、ハープやタブラまでこなすというマルチ奏者であり、ダラス出身のこのシンガー・ソングライターが鳴らすのは、スフィアン・スティーヴンスのチェンバー・ポップをボン・イヴェールのアンビエント・フォークを通過させたものだ。祖父は黒人であることを理由に大学に入学できず、父親は人種差別の抗議運動に参加していたそうだが、ここからブラック・ミュージック性はほとんど聴こえてこないし(薄くソウル色がある程度か?)、直截的な政治性もない。本人はイェール大学でザ・バンドについての論文を書いた経験があるそうだが、つまり、高等教育を受けられる立場となった黒人である自分が、人種性をきわめて無効化した地点で音楽について学術的な視点を通して考え、鳴らせることを謳歌しているようだ。
『シャイアン』は彼が旅した風景がもとになったアルバムだそうで、たしかにランドスケープ的な静謐ながら空間の広い楽曲が並ぶ。まろやかな耳障りのオーガニック・フォークと、ときに消え入りそうに繊細に響く歌声。アルバム序盤、“Los Angeles”~“Lemonade”の時点で多楽器によるざわめきのようなアンサンブルが親密に広がっていく。その温かみのある音像は初期のスフィアン・スティーヴンスを想起させるし、オートチューンの歌声をアンビエント・フォークと合わせる手法は明らかにボン・イヴェールからの影響だろう。が、スフィアンの深い闇もボン・イヴェールの身を切るような孤独もここにはなく、ただただ衒いなく旅の美しい風景が一遍ごとに立ち上がっていく。その素朴さはこのアルバムの魅力でもあるし限界でもある。良くも悪くも透徹した風景ばかりがある清らかな歌で、聴き手を苦しめることはない。おそらくもっとも近いのは、ボン・イヴェールのドラム/パーカッションを務めるS. キャリーのソロ名義作だろう。自然と世界の美しさへの素直な敬意がこもった柔らかなフォーク・ソング集。とても優秀で、破綻はない。
もちろん、音楽的な偏差値は非常に高く、コーラスとハープの掛け合いがユニークな“Stockholm”のように挑戦的なアレンジも随所に発見できる。「シャイアン」は先住民族の部族の名前だそうでコンセプト性もいくらかあるようだし、行ったことのないフィンランドを思い描いたという“The Birds of Finland”のアイデアも面白い。だからこそ、そうした冒険が彼の優秀さを凌駕する瞬間にも期待したい。スフィアンのように狂気じみたコンセプトや彼個人の内面の暗部が、この整った音楽を乱す瞬間も聴いてみたいと僕は思ってしまうのだ。それが本人にとって幸せなことかはわからないけれど……彼の音楽の旅は、この基礎体力があればもっと果てしない場所にまできっと行ける。