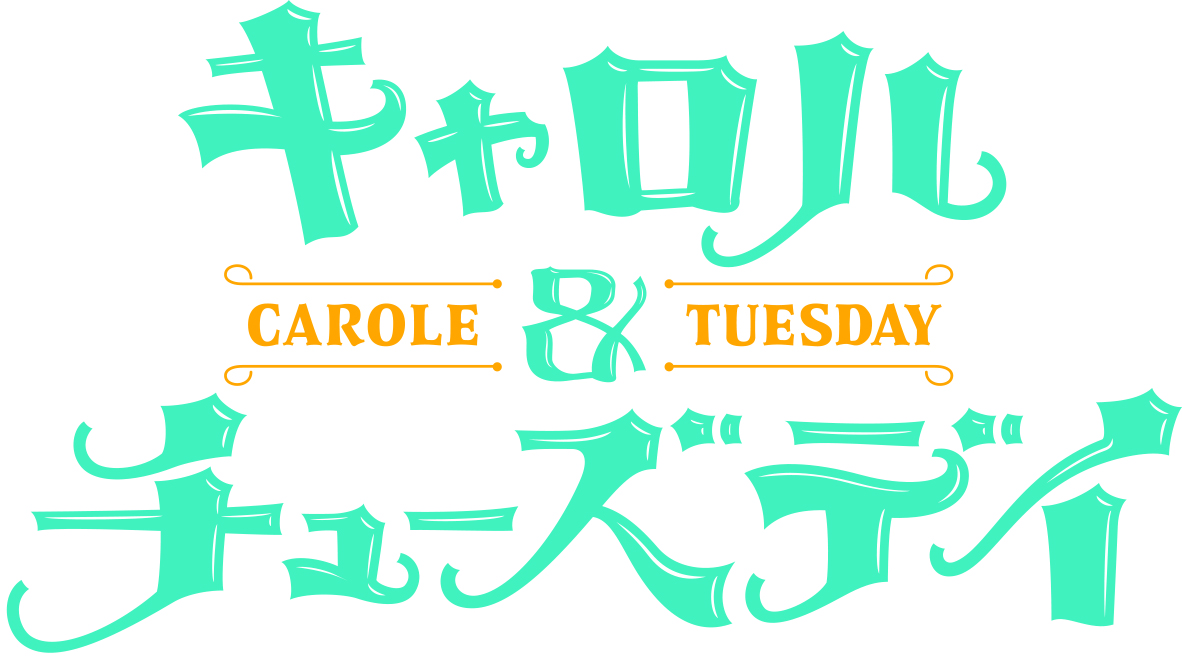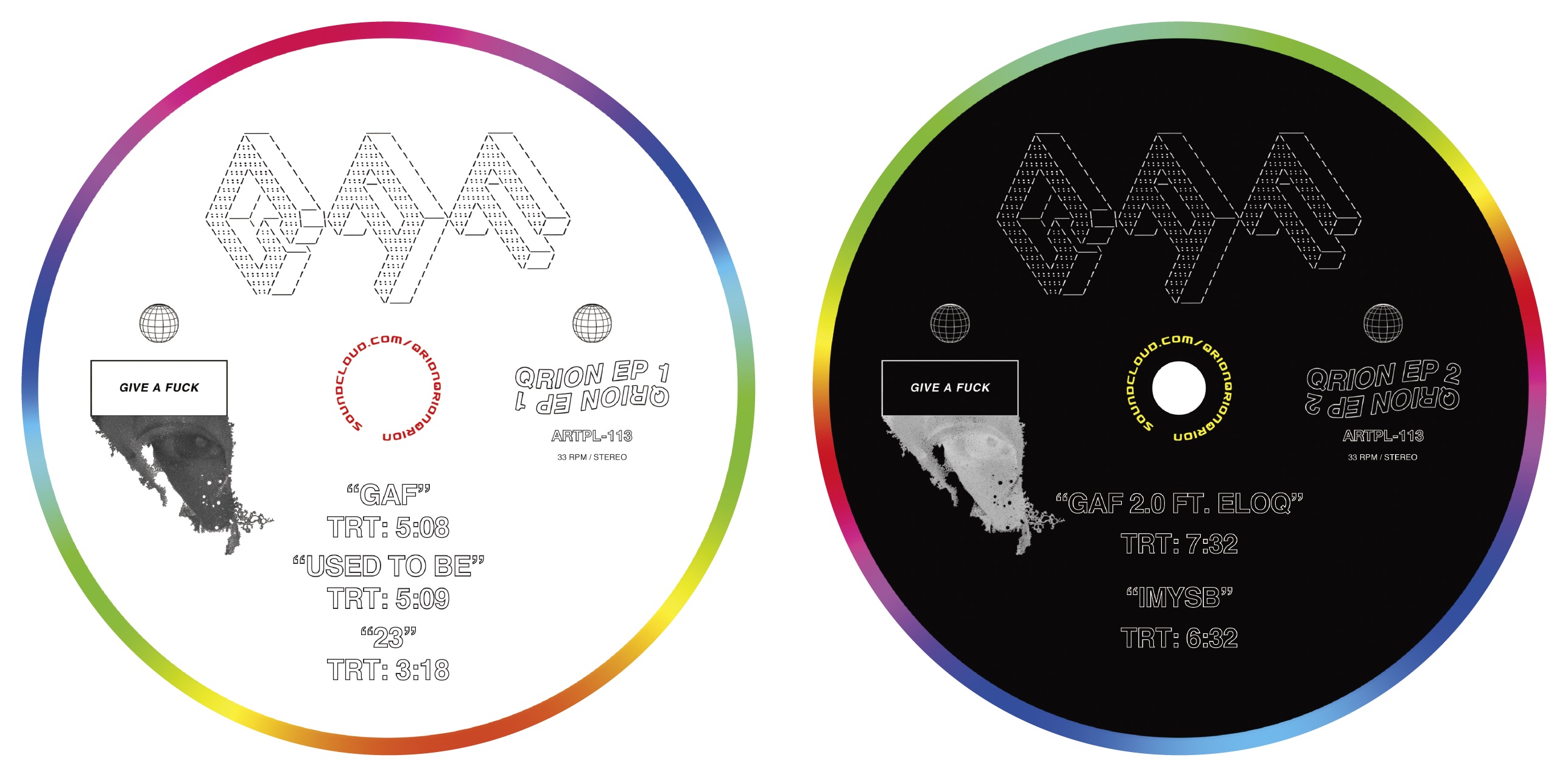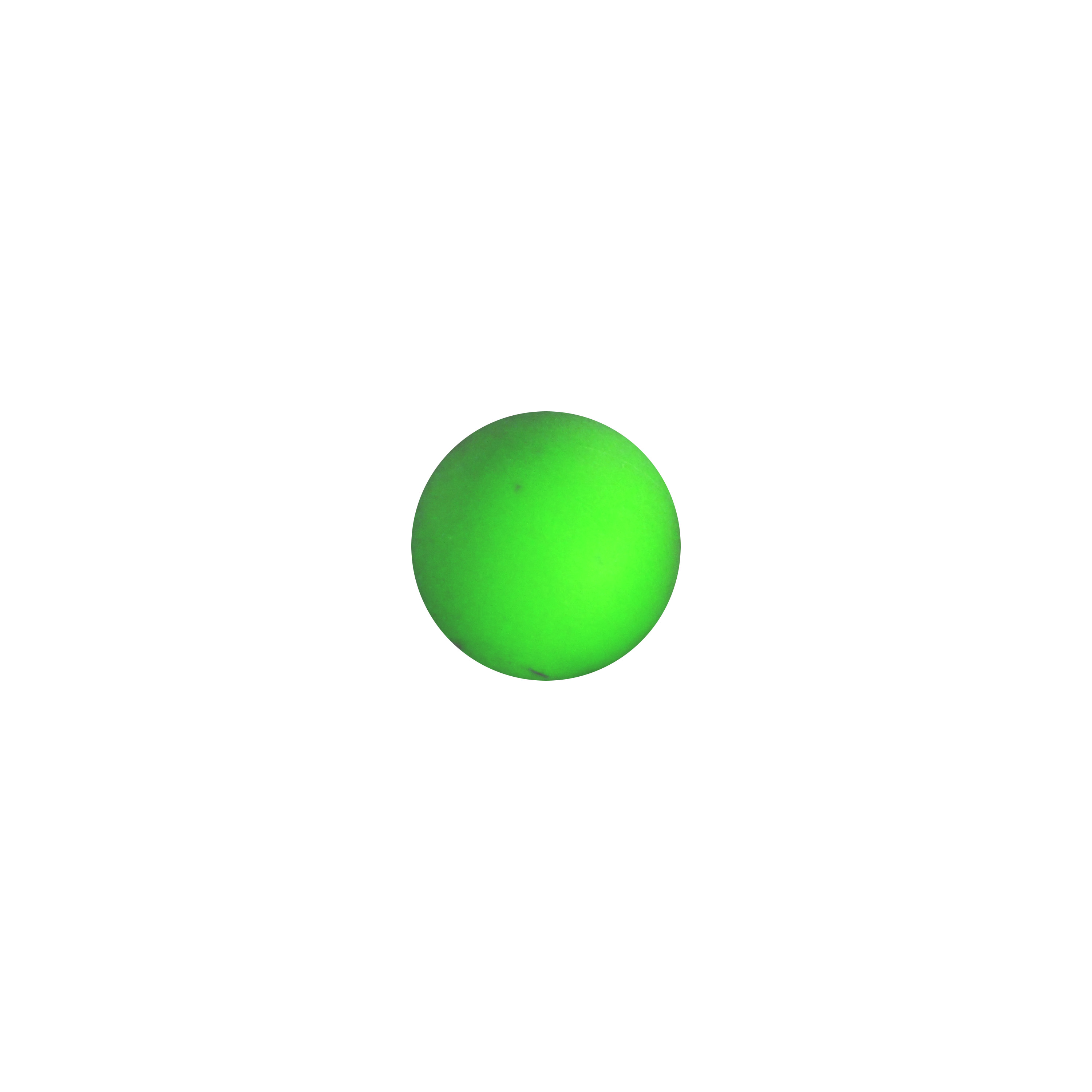2007年にリリースされたブルー&エグザイル名義でのアルバム『Below The Heavens』でのデビュー以降、様々なプロデューサーとのタッグ、あるいは自らのプロデュースによって数々の作品を生み出してきたLA・イングルウッド出身のラッパー、ブルー。最近では2015年に MED、マッドリブとのコラボレーションによるアルバム『Bad Neighbor』が話題となったり、昨年はヴァージニア出身のプロデューサー、ノッツとの『Gods In The Spirit, Titans In The Flesh』や、サーラーのシャフィーク・フセインとの『The Blueprint』など、かなりのハイペースで良質な作品を発表してきた彼が、今回、新たに手を組んだのがマッドリブの実弟としても知られるオー・ノウだ。ラッパーとしては2004年に〈ストーンズ・スロウ〉からリリースされたソロ・アルバム『The Disrupt』でデビューを果たし、プロデューサーとしても〈ストーンズ・スロウ〉周辺や地元オックスナードのアーティストを中心に、アンダーグラウンドからメジャーまで数多くのアーティストの作品に関わってきたオー・ノウだが、すでにブルーとも前出の『Bad Neighbor』などで共演を果たしている。とはいえ、このふたりががっぷり四つで1枚のアルバムを作るというのは当然、初めてのことであり、南カリフォルニアのアンダーグラウンド・シーンを代表する両者の夢のコラボレーションは、必然的に期待も高まる。
イントロにてブルーがLAの主要なストリートの名前を羅列し、LAのギャング・カルチャーがこのアルバムのテーマのひとつであることを提示することで、本作の幕は開ける。イングルウッドで育ったブルーにとって、ギャングは日常の一部でもあり、これまでもたびたび曲の中でテーマにしてきたが、彼の目線でのLAストーリーが独特の語り口によって実にスタイリッシュに、アルバム1枚を通して綴られていく。ひたすらディープに突き進むマッドリブに対して、オー・ノウのトラックはアグレッシヴな部分とクールな一面がバランス良く融合しているのが特徴であるが、本作のテーマにも彼のサウンドは実にマッチする。アルバムのリード曲とも言える“The Lost Angels Anthem”はそんな両者のポテンシャルが最大限に引き出され、ファンキーで緊迫溢れるオー・ノウのトラックに、ブルーはパーカッシヴに言葉をはめ込み、極上のグルーヴを作り出す。ドラムとエレピのサンプリングトラックに、ブルーが巧みにセッションを仕掛ける“Straight No Chaser”なども実にドラマティックな展開で、両者の音楽性の豊かさがダイレクトに伝わってくる1曲だ。また、この曲に限らず、オー・ノウのトラックは映画のサウンドトラックとも通じるものがあり、ブルーがラップで語るストーリーの深みを彼のサウンドがより強く引き出しているようにも感じる。
ブルー、オー・ノウ共に繋がりの深い MED を筆頭に、有名、無名含めて多数をフィーチャリング・ゲストとして迎えているが、特筆すべきはLAアンダーグラウンド・シーンのベテランであるアブストラクト・ルードとセルフ・ジュピター(フリースタイル・フェローシップ)の参加だ。本作における彼らふたりの存在は、90年代から脈々と引き継がれてきたLAアンダーグラウンド・シーンの延長上にブルーとオー・ノウがいるということの証明でもあり、彼らのゲスト参加は実に意味が深い。
同じ南カリフォルニアの中でお互い出身地も微妙に異なり、音楽的なバックグランドやルーツも微妙な違うふたりであるが、そういったギャップがお互いにとって大きなプラスとなり、これまでのコラボレーターともまた一味違う、タイトル通りのLAならではの作品になったと言えよう。ここ最近は作品ごとにプロデューサーを毎回変えているブルーであるが、いずれまたオー・ノウとのコラボレーションを期待したい。