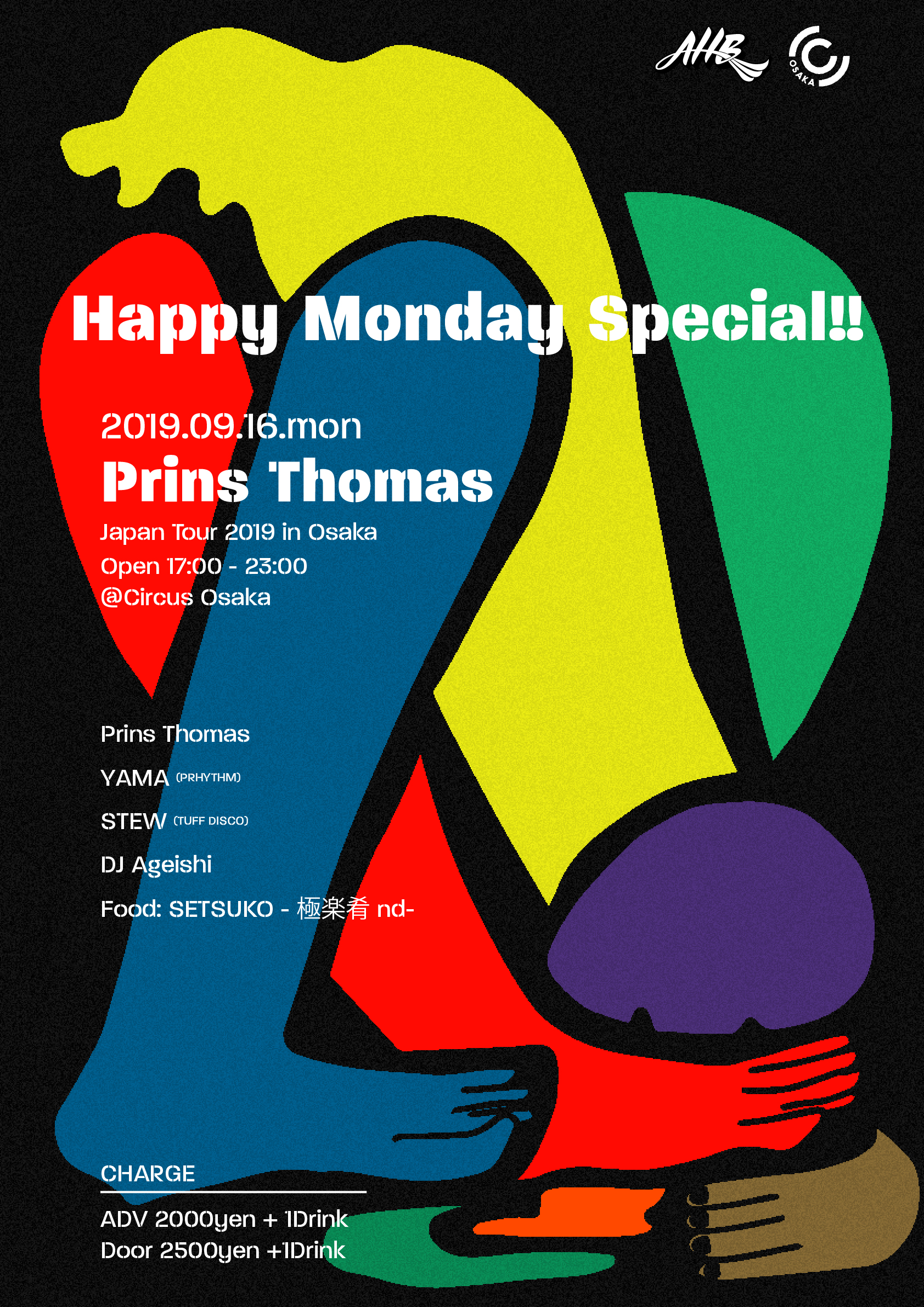先日アナウンスのあった WWW と WWW X のアニヴァーサリー企画《WWW & WWW X Anniversaries》。そのうちのひとつとして開催される《Local X5 World》の詳細が発表された。すでに告知済みのツーシン(Tzusing)およびキシ(Nkisi)の初来日公演に加えて、2年前の CIRCUS でもその存在感を見せつけてくれたガイカ(Gaika)と、日本の現代美術家にしてホーメイ歌手の山川冬樹がライヴを披露する。また、《Local World》のコア・メンバーである行松陽介、Mars89、Mari Sakurai、speedy lee genesis らも勢ぞろい。9月20日は WWW X に集合だ。
Tzusing — Circa Taipei
https://youtu.be/8CzVrZlm1sA
Nkisi | HARD DANCE LDN | DJ Set
https://youtu.be/eiM4NSBlmwo
GAIKA • 1800 FENDI [Official Video]
https://youtu.be/X9rNAbubhg0
A scene featuring Fuyuki Yamakawa from "We Don't Care About Music Anyway..." documentary
https://youtu.be/KVC0-Uuc6XY
WWW & WWW X Anniversaries Local X5 World - Third Force -

未来へ向かう熱狂のアジア&アフロ・フューチャリズム! ハードに燃え盛る中国地下の先鋭 Tzusing とコンゴ生まれ、ベルギー・ハードコア/ガバ育ちのアフリカン・レイヴなロンドンの新鋭 Nkisi (UIQ)、同じくロンドンのゴス・ダンスホール等で話題となったディストピアン・ラッパー/シンガー GAIKA (WARP)、日本のアヴァンギャルドから己の身体をテクノロジーによって音や光に拡張する現代美術家/ホーメイ歌手 Fuyuki Yamakawa をゲストに迎え、ローカルから WWWβ のコア・メンバー Yousuke Yukimatsu、Mars89、Mari Sakurai、speedy lee genesis が一同に揃い、世界各地で沸き起こる “第3の力” をテーマとした WWW のシリーズ・パーティ《Local World》のアニヴァーサリーとして開催。
WWW & WWW X Anniversaries
Local X5 World - Third Force -
2019/09/20 fri at WWW X
OPEN / START 24:00
Early Bird ¥1,800 / ADV ¥2,300@RA | DOOR ¥3,000 | U23 ¥2,000
Tzusing [Shanghai / Taipei]
Nkisi [UIQ / Arcola / London] - LIVE
GAIKA [WARP / London] - LIVE
Fuyuki Yamakawa - LIVE
Yousuke Yukimatsu [TRNS-]
Mars89 [南蛮渡来]
Mari Sakurai [KRUE]
speedy lee genesis [Neoplasia]
※ You must be 20 or over with Photo ID to enter.
Local 1 World EQUIKNOXX
Local 2 World Chino Amobi
Local 3 World RP Boo
Local 4 World Elysia Crampton
Local 5 World 南蛮渡来 w/ DJ Nigga Fox
Local 6 World Klein
Local 7 World Radd Lounge w/ M.E.S.H.
Local 8 World Pan Daijing
Local 9 World TRAXMAN
Local X World ERRORSMITH & Total Freedom
Local DX World Nídia & Howie Lee
Local X1 World DJ Marfox
Local X2 World 南蛮渡来 w/ coucou chloe & shygirl
Local X3 World Lee Gamble
Local X4 World 南蛮渡来 - 外伝 -