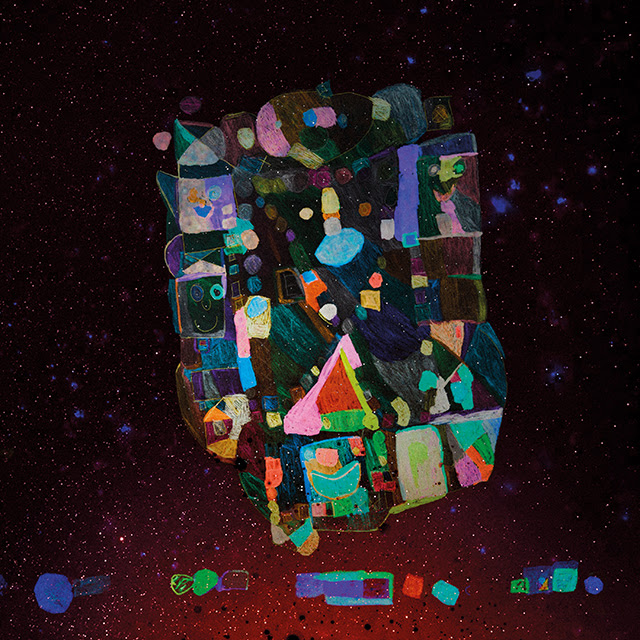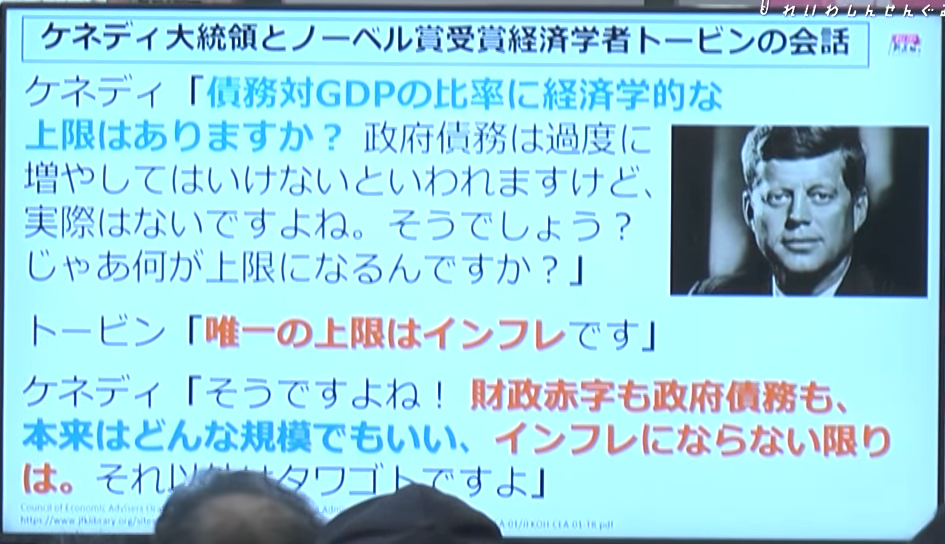みなさんこんにちは、ミュート・レコードのダニエル・ミラーです。
1978年のはじめ頃、ケンジントン・パークロードにあったRough Tradeショップでの出来事をよく覚えています。
ちょうど私がやっていたバンド"The Normal"の最初の納得のシングルを持ち込んだ時のことです。
その時に店番をしていた、Rough Trade創設者のジェフ・トラヴィスとリッチ・スコットがその曲を少し聴いてくれて、その場で契約してくれることになりました。
まさに人生が変わったような瞬間でした。
それによって私は、ミュートレコードを発足させ、自分が大事に思い敬愛するアーティストたちと一緒に働くことができるようになりました。
言ってみれば、それはインディペンデントのレコードショップが持つ最高の力であり、
アーティストをサポートし勇気づけるものだと思います。
もちろんその時からは音楽を取り巻く環境も大きく一変しました。
それでも、私は今でもインディペンデントのレコード店の力を信じています。
そこはミュージック・ラヴァーの中心であり、音楽をよく知る人々が
みなさんの音楽の好みを良く理解してくれています。
みなさんもご存じの通り、いますべての店が閉まっています。
しかし、彼/彼女らはオンラインサービスやメールオーダーを通じて営業しています。
私はみなさんにそのサービスを使って注文し、サポートていただくことを奨励します。
レコードショップが生き残るのはとても重要なことです。
現在起こっている危機は永遠に続くことはありません。
私たちは、ミュージックラヴァーやアーティスト、レーベルの未来についてよく考える必要があります。
どうぞ、みなさまお大事になさってください。
ありがとうございました。
MUTE創始者 ダニエル・ミラー