ヴラディスラフ・ディレイの新作も迫力あったし、ベアトリス・ディロンはUKだけど彼女のアルバムにはベルリンのミニマル・ダブからの影響を感じたし、そしてPole(ポール)の5年ぶりの新作もかなり良さげです。
1998年に登場したPoleことステファン・ベトケは、当時数多あるベーシック・チャンネルのフォロワーたちのなかでも抜きんでた存在のひとつで、彼自身のレーベル〈~scape〉の展開とともにミニマル・ダブを進化させたイノヴェイターでもある。2003年に〈ミュート〉から5枚目のアルバムを出しているが、この度はそれ以来の同レーベルからのリリースで、5年ぶり9枚目のアルバムとなる。(2017年にはベルリンの前衛シーンの伝説、コンラッド・シュニッツラーとの共作も出している)
新作のタイトルは『フェイディング』。“記憶の喪失”がコンセプトで、ふとケアテイカーを思い出す人もいるかと思うが、認知症になった母親が作品の契機にあるそうだ。「自分の母親が当時認知症にかかっていて、彼女が91年にもわたって積み上げてきた彼女の記憶すべてを無くしていく様子を見ていたんだ。まるでその様は、生まれたてで彼女の人生がはじまったばかりのような感じに思えた。まさしく、まだ中身が空っぽの箱のような」
それでサウンドはどうかと言えば、アンビエント、ダブ、そしてジャズが少々といった感じの構成だが、音の空間性が素晴らしく、その重いテーマに対して音は決して重々しくはない。クラブで鳴らすというよりは、あきらかに家で聴く音楽で、これは注目してもいいでしょう。リリースは11月6日(金)です。
■「Röschen」 (Official Audio)
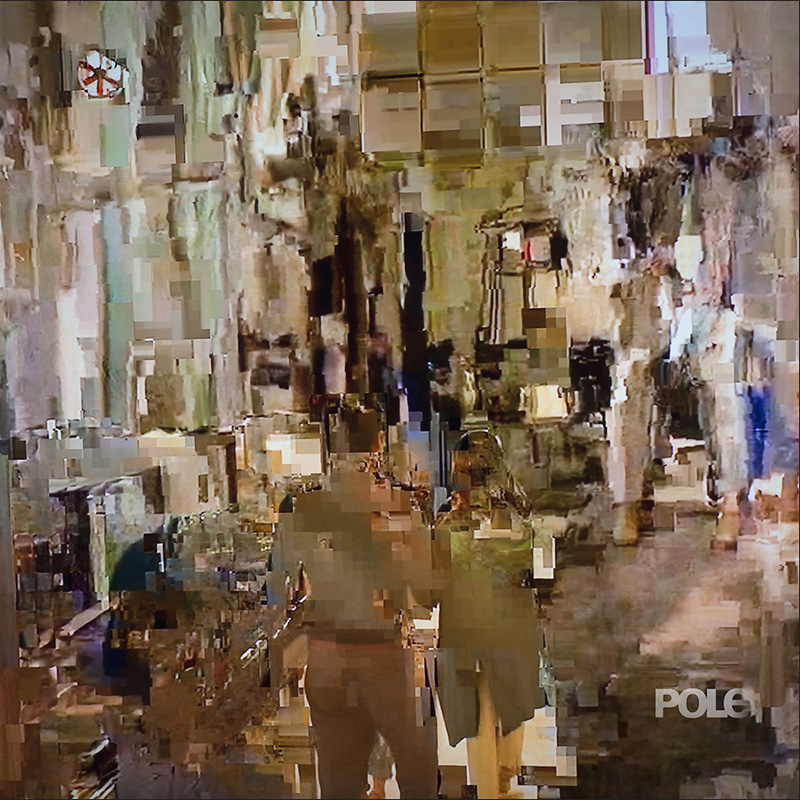 Pole
Pole
Fading
Mute/トラフィック
https://smarturl.it/pole2020
https://www.facebook.com/pole.stefanbetke
https://pole-music.com/






