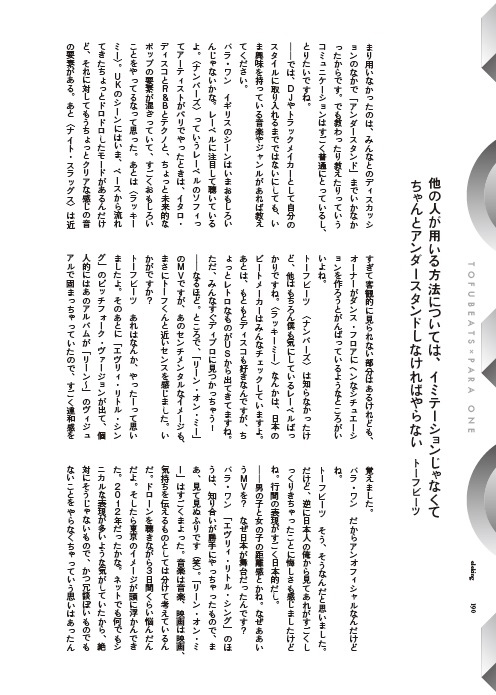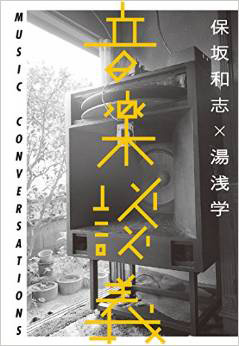Tofubeats - First Album ワーナーミュージック・ジャパン |
 Tofubeats - lost decade tofubeats |
初のメジャー・デビュー・アルバム『First Album』をリリースし、12月にはツアーファイナルを迎えるtofubeats。あまりにも語ることの多いこのアルバムだが、そのなかで2枚組での限界価格という「お得感」にもこだわりを見せた彼に倣って、ele-kingでは新譜発売時に掲載したロング・インタヴューの「ボーナス・トラック」をお届けしよう。2013年9月に発売された弊誌『ele-king vol.13』(通称「tofubeats表紙号」)に収録された、tofubeats×パラ・ワン(Para One)対談をウェブでも公開! メジャー契約直前、環境が大きく変わろうとしているなかでtofubeatsが考えていたこと、そしてヒップホップとエレクトロニック・ミュージックとの接合点でラディカルな活動を見せ、90年代半ばのフランスのシーンをリードしたTTCのプロデュースでも知られるマルチ・クリエイター、パラ・ワンとの対話から見えてくる、彼の若きリスナー遍歴。
■tofubeats / トーフビーツ
1990年生まれ。神戸で活動するトラックメイカー/DJ。〈Maltine Records〉などのインターネット・レーベルの盛り上がりや、その周辺に浮上してきたシーンをはやくから象徴し、インディでありながら「水星 feat.オノマトペ大臣」というスマッシュ・ヒットを生んだ。
くるりをはじめとしたさまざまなアーティストのリミックスや、アイドル、CM等への楽曲提供などプロデューサーとして活躍の場を広げる他方、数多くのフェスやイヴェントにも出演、2013年にはアルバム『lost decade』をリリースする。同年〈ワーナーミュージック・ジャパン〉とサインし、森高千里らをゲストに迎えたEP「Don't Stop The Music」、藤井隆を迎えた「ディスコの神様 feat.藤井隆」といった話題盤を経て、2014年10月、メジャー・ファースト・フルとなる『First Album』を発表。先のふたりの他、新井ひとみ(東京女子流)、okadada、の子(神聖かまってちゃん)、PES(RIP SLYME)、BONNIE PINK、LIZ(MAD DECENT)、lyrical schoolら豪華なゲスト・アーティストを招いている。

他の人が用いる方法については、イミテーションじゃなくてちゃんとアンダースタンドしなければやらない。(tofubeats)
■トーフくんは浜崎あゆみのリミックスではじめてパラ・ワンを知ったといっていましたね。
tofubeats(以下T):TTC(テテセ)のセカンドのほうが先だったんですが、その後myspaceであのリミックスを聴いて、「この曲をこうすればクラブ・ミュージックになるのか」っていう手法的な発見がありました。こんなふうにすれば、いまの自分をブレさせずにヒップホップから違うところへ行けるんじゃないかって。高校2年くらいのときのことですかね。
■浜崎あゆみは日本のポップ・シンガーですけれども、そうしたアーティストのリミックスをパラ・ワンがやるというのは、TTCから聴いていたリスナーからすれば意外なものでもありました。ですがその結びつきによって、ヒップホップのシーンで窮屈な思いをしていたトーフくんはジャンルの檻から自由になったと。これについて何か思うところはありますか?
パラ・ワン(以下P):正直に言ってあのときはとても緊張していたんだ。ただ音楽家としては、TTCもそうだけれども、全然違う文脈のものの間にコネクションを作っていくという仕事をしているつもりだから、トーフビーツくんが違和感なくインスパイアされたと言ってくれるのはすごくうれしく思うよ。
■「違う文脈のものの間に……」というのはトーフくんの活動と重なるところがあるよね。
T:そこからの影響が大きいんですよ。毎回自分のスタイルをリセットして変えていっていいんだって。
■逆に、スタイルを変化させることにこだわりがあったりはしますか? ダンス・ミュージックにとってはモードに対応していくのもすごく大切なものだと思いますが。
P:つねに変わっていくべきだというスタンスでやっているわけではないけれど、ダンス・ミュージック自体は若者の音楽だと思っているから、ある一面においてはそれはサヴァイヴァル精神でもあるよ。柔軟でいなければダメだし、新しくて良いものは自分なりに消化しなきゃいけない。ただ、刺激的なアーティストに会ったりしてみても、その影響を自分の音として出力するには時間がかかるんだけどね。
■気に入ったアーティストに話をきいてみたりするんですか?
P:曲作り自体が呼吸のようなもので、息を出しきったら吸わなきゃいけない。スタジオにこもりきりだとエゴを吐き出すばっかりで吸収がないよね。だからツアーをしたり人に会ったりインタヴューを読んだりするのは吸収と消化のチャンスだととらえているよ。
■トーフくんのアルバムも曲によってアプローチが違うわけだけど、リスナーとして新しい音を聴いて、それをいかに自分流に消化するかということを繰り返しているように見えるんですよね。そこにはこだわりがありますか?
T:他の人が用いる方法については、イミテーションじゃなくてちゃんとアンダースタンドしなければやらない、ってふうに自分では決めています。新しいジャンルに取り組むにても「それっぽいもの」に終始してしまいたくはないですね。いまベッドのスプリング音がすごい流行っているみたいなんですよ。でもそういうものをいま日本でやることにどんな意味があるのかっていうところから、僕はきっちり考えますよ。今回パラ・ワンのリミックスにあたって、僕は炭酸飲料を開ける音を多用しているんですが、それも同様です。自分のなかでちゃんとボーダーを引いて、他人にわかってもらえなくてもいいけど他人に説明できるくらいにそれをやる意味を理解してなければ、やらない。
■10年くらい前にTTCにインタヴューしたとき、テキは、サウスのラップがすごくおもしろいんだけど、それをいかに自分のスタイルとして消化するのかが大切だと言っていたんです。彼らには表面的なイミテートを良しとしないスタイルが一貫してあったことを思い出しました。
P:セカンド・アルバムを作っているときには魔法のような瞬間があった。みんなの関わり方やジャケットのアートワーク、いろいろなことを含めて、そのときその場所に魔法のように重なって、あるべきものであるべきものを作ることができたという感覚を持っています。原点になっているのはあのセカンドの頃だね。
T:当時とても未来っぽく感じました。アートワークにしてもほんとにブローされたものだと思った。高校生が聴くにはヤバすぎましたね(笑)。
P:ははは。
■トーフくんの表現がヒップホップからダンス・ミュージックに広がっていったというのも、まさにTTCと同じですね。
T:そうそう! 「こんなことやれたらいいな」が全部ある、みたいな。日本だと、そういうことを迂闊にやると「ジャズをサンプリングしろ」みたいに言われる時代だったんですよ。まだまだヒップホップ後進国で、シーンのなかにいまのカニエの新譜みたいなアプローチを良しと言えるような人がほとんどいなかった。
P:僕自身ももともとはジャズやソウルなんかをサンプリングしたヒップホップをやっていて、DJプレミアとかピート・ロックとかを目指していたんだよね。DJメディに憧れたりもしたけど、TTCに出会って「お前は未来がわかってない」と言われてね(笑)。いまじゃなくてこれから最高と呼ばれるものをやれって。それで考え直したんだ。
■トーフくんも、ジャズをサンプリングしろって言ってくるような人よりは、よっぽど自分のほうがフューチャリスティックだしオーセンティックだしって思ってるんじゃないですか?
T:ほんとそう思ってますよ! ただ、言ったら角が立つと思って黙っているだけです(笑)。いまのお話で勇気づけられました。これで間違ってないんだって。
P:TTCも最初は嫌われていて、僕自身も友だちから「これとにかくひどいから聴いてみて」って言われて彼らを聴かされたんだ。だけど僕はこれヤバいじゃんって思って。フランスのすごくコンサバな家庭に育ったものだから、ああいう音を聴いて前向きに進んでいく気持ちが湧いてきたんだ。だからヒップホップかそうじゃないかということは気にせずに前進していくのがいいんじゃないかな。斬新さしかないんじゃないかと思うよ。名盤はつねに新しいものだったからね。

TTCのころから思っていることでもあるけど、ルールを壊すか、ルールを持たないのがルールなのかもね。(パラ・ワン)
■パラ・ワンさんはTTCの1枚めから2枚めにいたるまでに、彼らとのディスカッションを通して築いたものが下地になっているということでしたが、トーフくんはどうですか? 仲間とのディスカッションから何かを得ることは?
T:それはもちろんあります。シーパンク論争とかね。僕がシーパンク的なものをあんまり用いなかったのは、みんなとのディスカッションのなかで「アンダースタンド」までいかなかったからです。でも教わったり教えたりっていうコミュニケーションはすごく普通にとっているし、とりたいですね。
■では、DJやトラックメイカーとして自分のスタイルに取り入れるまでではないにしても、いま興味を持っている音楽やジャンルがあれば教えてください。
P:イギリスのシーンはいまおもしろいんじゃないかな。レーベルに注目して聴いているよ。〈ナンバーズ〉っていうレーベルのソフィってアーティストがパリでやったときは、イタロ・ディスコとR&Bとテクノと、ちょっと未来的なポップの要素が混ざっていて、すごくおもしろいことをやってるなって思った。あとは〈ラッキーミー〉。UKのシーンにはいま、ベースから流れてきたちょっとドロドロしたモードがあるんだけど、それに対してもうちょっとクリアな感じの音の要素がある。あと〈ナイト・スラッグス〉は近すぎて客観的に見れない部分はあるけれども、オーナーがダンス・フロアにヘンなシチュエーションを作ろうとがんばっているようなところがいいよね。
T:〈ナンバーズ〉は知らなかったけど、他はもちろん僕も気にしているレーベルばっかりですね。〈ラッキーミー〉なんかは、日本のビートメーカーはみんなチェックしていますよ。あとは、もともとディスコも好きなんですが、ちょっとレトロなものがUSから出てきてますね。ただ、みんなすぐディプロに見つかっちゃう!
■なるほど。ところで、“リーン・オン・ミー”のMVですが、あのセンチメンタルなイメージも、まさにトーフくんと近いセンスを感じました。いかがですか?
T:あれはなんか、やったーって思いましたよ。そのあとに“エヴリィ・リトル・シング”のピッチフォーク・ヴァージョンが出て、個人的にはあのアルバムが“リーン~”のヴィジュアルで固まっちゃっていたので、すごく違和感を覚えました。
P:だからアンオフィシャルなんだけどね。
T:そう、そうなんだと思いました。だけど、逆に日本人の俺から見てあれがすごくしっくりきちゃったことに悔しさも感じましたけどね。行間の表現がすごく日本的だし。
■男の子と女の子の距離感とかね。なぜああいうMVを? なぜ日本が舞台だったんです?
P:“エヴリィ・リトル・シング”のほうは、知り合いが勝手にやっちゃったもので、まあ、見て見ぬふりです(笑)。“リーン・オン・ミー”はすごくまよった。音楽は音楽、映画は映画、気持ちを伝えるものとしては分けて考えているんだ。ドローンを聴きながら3日間くらい悩んだんだよ。そしたら東京のイメージが頭に浮かんできた。2012年だったかな。ネットでも何でもシニカルな表現が多いような気がしていたから、絶対にそうじゃないもので、かつ冗談ぽいものでもないことをやらなくちゃっていう思いはあったんだ。そしてシンプルに気持ちが伝わるもの。ちょうど桜の季節だったから、自然のなかで起きている新しいこととともに新しい気持ちが生まれる瞬間を見ることができるんじゃないかと考えてね。
■この機会にお互いに訊いてみたいことはありますか?
T:さっき学校っておっしゃってましたけど、レーベルをやるにあたって心がけていることはありますか?
P:TTCのころから思っていることでもあるけど、ルールを壊すか、ルールを持たないのがルールなのかもね。レーベルがダメになるのって大抵の場合は齢をとって若い人間を受け入れられなくなっていくことに原因がある。それに、子どもらしく興味を持っていろんなものを楽しめたらいいなと思うから、オープンマインドということも心がけているかな。あなたはどう? あなたはどこを目指していて、どんなものを消化しようとしているところなの?
T:僕はついこの間メジャーと契約して、セールスを出さなきゃいけないアーティストになったわけです。ポップスとして、クラブ・リスナーとかではない人にも届けられないと契約が切れてしまう。自分のもともとの個性とそうした事情の間で悩んでいる時期ですね。それから、その傍らで日本のアイドルに曲を書いたりしていくことにもなると思いますが、そこに〈マーブル〉とかから受けている影響をどういうふうに落とし込んでいくか。海外の人たちにも「日本のポップがなんかヤバいぞ」って思われるようなところまでどうもっていくか。それが課題ですね。
■補足すると、日本ではダンス・ミュージックがポピュラーではないんですよ。
T:それから、森高千里とか松田聖子のよさって海外の人に伝えるのは難しいかもしれないけど、ちゃんとしたハイブリッドなものを作れば、Jポップの良さを世界に説明することができると思う。まずは自分がちゃんとセールスを作って、なおかつ海外のレーベルに対しても納得させられるようなある程度のラインを作る、そういうコンテクストを作っていくことができるかどうかという挑戦ですね。そのためには〈マルチネ〉のような存在も必要だと思っています。
P:エキサイティングな話だね。でも、冗談抜きでできると思うよ。
T:あなたにまた会えるように、がんばりますよ。やるしかない!