ジャパン解散後、なかば人目を避けるように暮らしながら、純粋なまでに自らの芸術活動を貫く──
デヴィッド・シルヴィアンの評伝の大作、いよいよ翻訳刊行!
いまだに根強いファンを持つデヴィッド・シルヴィアン。
探求心と美学を失うことなく、いまだにコンスタントな活動を続けているこの芸術家は、いったい何を考えなが ら、どこで、どんな風に作品を作ってきたのか?
膨大な資料、発言、証言をもとに、彼のソロ活動を音楽の観点から、そして歌詞の観点から詳細に綴る、デヴィッド・シルヴィアンの評伝がいよいよ刊行される。
「デヴィッド・シルヴィアンはなんだか謎そのものに思える。
ジャパン後の人生で最高の音楽を作っていながら、彼はほとんど隠遁者のようになってしまった」
「私としては、シルヴィアンが歌を書いたときどこに暮らしていたか、結婚していたかどうか、どのレコード会社に所属していたか、
どんな精神的・哲学的思想が彼の作品にみなぎっていたか……といったことが違いを生むと考えている」
「音楽が作られた状況を表わすのだ。作品を聞けば自ずとわかるはずだと言う人もいるかもしれないし、実際そうなのではあるが、
新しい次元を開いてくれるささやかな状況説明は、まったくの別物なのだ」
(本書、序文より)
目次
PART 1:ふさわしい語彙を求めて
今やひとりぼっちの僕/より良い世界が目の前に/広がる可能性/過ぎ去りし日々/ふたたび戦いに敗れ
PART 2:救済への道
波に足を取られて/愛の家へと/歓喜に倒れ込んで/恩寵は僕の知人/弾丸は放たれた
PART 3:灰色の空
真実の始まり/ネクタイを直せ/世界がすべて/仕返ししてやったんだ/時代の終わりの歌/影たちは息を潜め/さすらいに飽きて/あたりに家はない





 ダブステップ・シーンから火が点いた2562ことア・メイド・アップ・サウンドは近年、そのイメージから離れていくように、尖った実験性を持ってダンスフロアに面白い提案を投げかけている。レフトフィールド・サウンド筆頭レーベル〈スード〉から発表したこのコラボレーションもそのひとつ。
ダブステップ・シーンから火が点いた2562ことア・メイド・アップ・サウンドは近年、そのイメージから離れていくように、尖った実験性を持ってダンスフロアに面白い提案を投げかけている。レフトフィールド・サウンド筆頭レーベル〈スード〉から発表したこのコラボレーションもそのひとつ。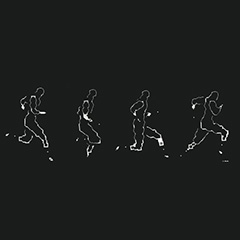 ドント・ディージェイという名前からもレフトフィールドぶりが伝わって来る彼は、デビューから一貫してポリリズムによるミニマルな陶酔性を探求している。中でも特にこの”ガムラン”は出色の仕上がり。
ドント・ディージェイという名前からもレフトフィールドぶりが伝わって来る彼は、デビューから一貫してポリリズムによるミニマルな陶酔性を探求している。中でも特にこの”ガムラン”は出色の仕上がり。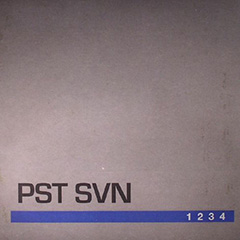 何度も制作を共にしているポーン・ソード・タバコ(PST)とSVNのふたり。簡素な4つ打ちリズムの中に潜むロウなテクスチャーとじんわりと滲み出てくるトロピカルなムードによる反復の快楽がたまらない。
何度も制作を共にしているポーン・ソード・タバコ(PST)とSVNのふたり。簡素な4つ打ちリズムの中に潜むロウなテクスチャーとじんわりと滲み出てくるトロピカルなムードによる反復の快楽がたまらない。 00年代を代表するアンセム“レイ”を生んだアムの一員、フランク・ヴィーデマンの初ソロ作品に収録されているトラック。電子音による特異なセッション空間とグルーヴを実現している。
00年代を代表するアンセム“レイ”を生んだアムの一員、フランク・ヴィーデマンの初ソロ作品に収録されているトラック。電子音による特異なセッション空間とグルーヴを実現している。 ドント・ディージェイ、そして彼が参加するプロジェクトであるザ・ドリアン・ブラザーズ、ひび割れたトロピカルサウンドが特徴的なハーモニウス・セロニウスの楽曲をコンパイル。その共通項にあるのはやはりポリリズム。
ドント・ディージェイ、そして彼が参加するプロジェクトであるザ・ドリアン・ブラザーズ、ひび割れたトロピカルサウンドが特徴的なハーモニウス・セロニウスの楽曲をコンパイル。その共通項にあるのはやはりポリリズム。
 デイヴィッド・シルヴィアン
デイヴィッド・シルヴィアン