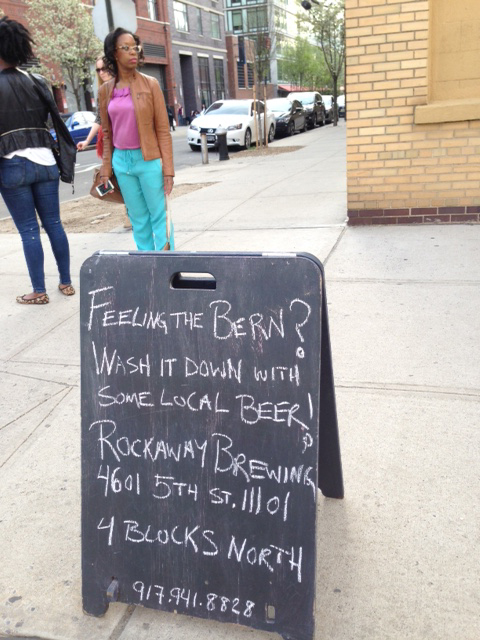2016年4月20日練馬文化センターにおけるエグベルト・ジスモンチの単独公演は本当に素晴らしいものだった。なんだか"モノ"が違う演奏に、有り余る現役感に、圧倒された。また同時にあまりに大きなパーカッショニストを失ったことを感じた公演でもあった。
めくるめくギター演奏がメインの1stセット。パーカッシヴな演奏と言ってしまえばそれまでだが、基本になるリズムのエンジンがまずあって、それを元にまた別の噛み合うリズムやメロディーがついていく。そのリズムの理にかなった構築性と説得力、そして緻密且つ自由に放たれるメロディーとの融合たるや! そうやって発信される音楽は複雑にも聴こえるが、その実はシンプルだ。しかし一人で何人分やっているのだろう。なかなか日本では見られれないスタイルの演奏とその完成度にただただ圧倒された。
そしてそこにナナ・ヴァスコンセロスを見た気がした。会場にいた全員が見たであろうし、曲間にジスモンチ本人も言っていたと思う。左手がナナのビリンバウだった。
ナナはそこにいないのに十分なまでの打楽器奏者としての言わば編集能力みたいなものを発揮していた。音楽における編集は重要な要素であるが、ナナは打楽器を通してプリミティヴな形でそれをやってのける。ギターリストでも歌でも例はなんでもよいが、ナナがいるとなんだかいい演奏が出来てしまう、という感じが大いにする。それは打楽器奏者の最も大きな仕事であり、ナナがここまで愛される要因の一つでもある。ジスモンチの左手にナナがいることによって、一気に音楽は昇華したのではないかと思わせるナナの存在と、ジスモンチの信頼みたいなものに感動した。
MCで、喧嘩して「もうあなたはいらない」とナナに言ったというようなことを喋っていたように思うが、ジスモンチのその信頼の裏返しに自分は聞こえた。
2ndセットは、どんどんジスモンチの自己に入っていく演奏に見えた。美しい演奏の向こうに見える自己や何か見えないものと格闘していく姿や、その準備のための演奏の完璧なコントロールは、ナナを向いていたかもしれないが、ナナがそこにいるようには思わなかった。正直着いていけないくらいの修行のような感じを受けた。曲間にピアノに両手をついて下を向く姿にも象徴されていた。
そのピアノという楽器のまま、アンコールでのスクリーンに映ったナナのビリンバウ演奏とのコラボは、まさにナナの打楽器奏者としての懐の大きさが際立った。一気に視界が開けて行くような気がした。
一体彼らは何を見ていたのであろうか。想像も及ばないものであったかもしれないが、そのベーシックには彼らのトラディショナルへの敬愛が間違いなくあった。それはあまりに大きな土台である。
島国の隅で活動する一打楽器奏者として、真摯に0からスタートする気持ちにさせてもらうには充分であり、会場にいたほとんどの人に実りあった素晴らしいステージだった。