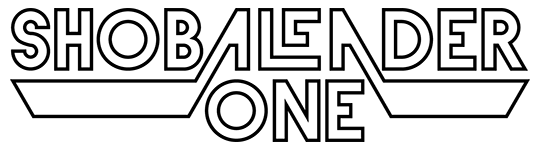Sampha - Process Young Turks/ビート |
UKの新しい世代の男性シンガー・ソングライターのひとりであるサンファことサンファ・シセイ。詳しいバイオがなく(生年は1988年とも、1989年とも)、謎めいたところの多いアーティストであるが、ロンドン在住の彼は覆面アーティストとして知られるSBTRKT(サブトラクト)の作品にフィーチャーされたことで、2010年頃から注目を集めるようになった。ソロ・アーティストとしても作品をリリースする一方、ジェシー・ウェア、キャティB、FKAツイッグスなどの女性シンガーたち、ブリオン、コアレス、リル・シルヴァなどUKの気鋭のプロデューサーらと次々とコラボをおこなっていく。ドレイクはじめ北米のメジャー・アーティストとの共演もあり、2016年はカニエ・ウェスト、フランク・オーシャン、ソランジュのアルバムにも参加している。EPを出してはいるものの、アルバムは未発表であったそんなサンファが、遂に待望のファースト・アルバム『プロセス』を完成させた。今回はサンファに『プロセス』についてはもちろん、今までの音楽活動を振り返り、音楽を始めた経緯から、サブトラクトとの出会いなど、いろいろな方向から話を訊いた。インタヴューをしたのは2016年12月上旬で、ちょうどザ・エックス・エックスの公演に帯同して来日し、自身でもピアノ・ソロ・コンサートをおこなった後日のことだ。サンファにとってザ・エックス・エックスも、リミックスやカヴァーするなど昔から交流の深いアーティストなのだが、くしくも彼らの新作『アイ・シー・ユー』とともに、〈ヤング・タークス〉の2017年のスタートを切るのが『プロセス』である。ちなみにサンファは4度目の来日で、今まではサブトラクトとのツアーで来ていたのだが、今回がもっとも長く日本に滞在していたそうだ。
音楽とは自分のいた場所や経験した時間をドキュメントするものだと思うんだ。
■サブトラクト、ジェシー・ウェア、ドレイクなどの作品にフィーチャーされたことで、あなたは2010年代の新たなシンガー・ソングライターとして注目されるようになりました。そもそも歌を始めたのは、どんなきっかけからですか?
サンファ・シセイ(Sampha Sisay、以下SS):記憶がある子供の頃からずっと、家の中で歌っていたね。小学校でも合唱団に入っていた。でも、ティーンエイジャーになるとトラック制作とかプロダクションのほうへ興味が移って、歌からは少し遠ざかってしまったんだ。トラックはMyspaceにアップしていたけど、当時はキッド・ノーヴァというコミックから名付けた名前でやっていた。まあ、アンダーグラウンドな覆面プロデューサー気取りで、そんなときにアップした曲をサブトラクトがたまたま見つけて、とても気に入ってくれたんだ。それで彼と連絡を取るようになり、一緒に曲を作り始めたというわけさ。そうして作った曲がラジオとかで流れて注目されるようになったけど、そこで僕は歌を歌っていたから、みなは僕のことをシンガーとして見ていたようだね。でも、そもそもはヴォーカリストを目指していたわけではなく、あくまでトラックメイカーとしてキャリアは始まっているんだ。それでプロダクションと歌を並行して進めていくようになり、今のスタイルに至っているよ。
■あなたの歌にはスピリチュアルなムードを感じさせるものが多いです。合唱団にいたという話ですが、ゴスペル・クワイアや教会の聖歌隊などからの影響もあるのでしょうか?
SS:特別にゴスペルや教会音楽を意識したことはないけど、子供の頃からいろいろなことに疑問を持ち、親にもあれこれ質問するたちだった。「神様って本当にいるの?」とか言って困らせたり。そうして、その疑問に対する答えを見つけていく人生だったけど、そうした姿勢が僕の歌にも表われているんじゃないかと思う。そのあたりが君の言うスピリチュアルなムードに、ひょっとしたら繋がっているのかもしれないね。
■ちなみに両親はアフリカのシエラレオネ出身だそうですが、あなたの生まれもシエラレオネですか?
SS:いや、僕の生まれたのはロンドンだよ。
■神様についての話が出ましたが、宗教はアフリカの信仰だったりするのですか?
SS:神様がいるか、いないかの質問は5歳の頃で、宗教的なことというより、子供ながらの純粋な疑問だったね。僕の家庭はキリスト教だけれど、僕自身は特別に強い信者ではなく、どちらかと言えば特定の宗教に属しているわけではないんだ。いろいろな宗教には興味があって、それに関する本も読んでいるけれど、今も「神様とは?」「自分にとっての信仰とは?」と探し求めている途上にある。
■スピリチュアルということにも繋がるかもしれませんが、あなたの作る曲、またあなたの歌声にはメランコリックなムードが通底していると感じます。それは何かあなたの人生体験からくるものなのでしょうか?
SS:確かにそれはあるね。音楽とは自分のいた場所や経験した時間をドキュメントするものだと思うんだ。たとえば、僕が17、8歳の頃に作った曲を聴き直してみると、とても光り輝いていたなと思うことがある。大人になりきれない、ナイーヴなところがある一方、ハッピーで多幸感に溢れている。やっぱり、その頃の自分の心の中を反映しているんだなと。その後、大人になっていろいろと経験をして……家を出て自立し、大学に通ったり……兄が大病を患って、母が癌になって亡くなったり……。人生における苦難や悲しみが、子供の頃とは違う、もっと現実的なものとなってきたんだけど、そうした経験が今の僕が作る曲には反映されていると思うよ。
ずっと音楽を作ってきて、最近は一般的なソウル・ミュージックだけに「ソウル」が存在しているわけではないことにも気づいたんだ。たとえば、ミニマルなテクノやハウス・ミュージックの中にも「ソウル」はあるんだなって。
■あなたは歌と同時にピアノ演奏においても優れた才能を持っています。ピアノはどのように学んだのでしょう?
SS:中学の頃に3年ほどピアノのレッスンを受けたけど、あとは全て独学で学んだよ。僕が初めてコード・パターンを理解したのは、アル・グリーンの“レッツ・ステイ・トゥゲザー”を聴いたときだったな。
■いまアル・グリーンの名前が出ましたが、ほかに影響を受けたシンガーや音楽家などはいますか?
SS:最初に影響を受けたのはマイケル・ジャクソンだね。それから7、8歳の頃はスティーヴィー・ワンダーやトレイシー・チャップマンをよく聴いていたよ。ティーンエイジャーになるとフランスのエールとかを聴くようになって、あとゼロ7やミニー・リパートンも好きだった。ほかにもトッド・エドワーズ、ダフト・パンク、ネプチューンズとか、いろいろだよ。その頃はグライムも聴き始めて、ラピッドとかはトラック制作の上でも影響を受けたな。
■確かに、一昨日(2016年12月7日)に見たあなたのピアノ・ソロ・コンサートの雰囲気とかは、トレイシー・チャップマンを彷彿とさせるところがありましたね。でも、一方でグライムにハマっていたというのは意外ですが。
SS:うん、僕とグライムの結びつきが意外という意見は結構あるんだけれど、でも僕のiTunesには自作の曲もいろいろと入れてあって、実はその中にはグライムもいろいろとあるんだよ。それらはまだリリースしていないけれど、僕は13歳の頃からグライムを作っているんだ。今回のファースト・アルバム『プロセス』には、聴いてすぐそれとわかるグライムは入っていないけれど、たとえば“リヴァース・フォルツ”は最初グライムのイメージで作って、最終的にヒップホップ寄りのプロダクションに落ち着いたんだ。
■それでは、いつかあなたの作ったグライムも聴けるかもしれないですね(笑)。ちなみに作曲はどのようにおこなっていますか? 多くの曲はピアノから生まれたメロディが軸となっているようですが。
SS:僕の場合、フリースタイルで作ることが多いね。歌いながらとか、ピアノを弾きながらとか。その場の思いつきで、自由にやるんだ。あと、ひとつの歌詞が思い浮かんだら、そこから広げて曲を作っていくこともある。でも、たいていは曖昧な状態の歌詞があって、その後にメロディをつけて、それをピアノで弾いてみるってことが多いかな。
■あなたの曲のキーとなるものはソウルとエレクトロニック・サウンドです。このふたつの異なるルーツを持つ音楽は、あなたの中でどのように融合されていくのでしょうか? もちろん、過去にもスライやプリンスをはじめ、そうしたアプローチをおこなうアーティストはいますが、あなたの場合にはまた違った独自のアプローチがあるように思うのですが。
SS:先にも話したように、僕はもともとシンガーではなく、トラックメイカーだったわけだけど、多くの人の場合は逆のパターンが多いと思うんだ。歌うことから始まって曲作りをするようになるとか。そういった経緯があるから、僕は今もプロデュースという部分についてもとても楽しくやっていて、音をいろいろいじって遊ぶことが好きなんだ。自分にとって新鮮に響く音というものを、常に探し求めている。エレクトロニックなプロデューサー・ワークが、僕の中における音作りを支えていることは間違いない。君が言うソウルとエレクトロニック・サウンドの融合は、そうした背景が生み出しているんだろうね。でも、それはいつも意図的におこなわれるものでもなくて、試行錯誤を重ねていく中で偶然に生まれることもある。そうした実験の中から、いい音楽っていうのはできるんじゃないだろうか。サウンドをいろいろといじくって、トライ&エラーして、そうしてできたものに少し「ソウル」が足りないなと感じたら、ハーモニーやメロディをアレンジして、そうやって「ソウル」を加えていく。僕が思うところの「ソウル」とは感情ってことだけどね。でも、ずっと音楽を作ってきて、最近は一般的なソウル・ミュージックだけに「ソウル」が存在しているわけではないことにも気づいたんだ。たとえば、ミニマルなテクノやハウス・ミュージックの中にも「ソウル」はあるんだなって。今後はそうした方向性でも曲を作ることがあるかもしれないね。
[[SplitPage]]ある日、録音をそのままにして家を出て、帰ってきたら兄が「ごめん、パソコンのデータが全部消えちゃったよ」と謝ってきて、そんな具合に消えてしまった曲も多かったね(笑)。
 Sampha - Process Young Turks/ビート |
■トラック制作からシンガーに進んだタイプとして、ジェイムス・ブレイクが思い浮かびます。ソウルや歌に対するアプローチについて、あなたとジェイムス・ブレイクには共通するところもあるように感じますが、どうでしょうか? ほかにもUKの同世代の男性シンガー、およびシンガー・ソングライターとして、サム・スミス、ジェイミー・ウーン、クウェズなどがいますが、彼らからは何か刺激を受けるところはありますか?
SS:ジェイムス・ブレイクもジェイミー・ウーンも、それからクウェズも、みな音楽はとても好きだよ。特にクウェズにはシンパシーを感じることが多くて、それは彼がマイスペースで最初に僕をフックアップしてくれたひとりでもあるからなんだ。2008、9年あたりだけど、クウェズとMyspaceで繋がって、その頃の彼が作っていたサウンドはとてもオリジナリティがあるものだった。当時はまだ面識がなかったので、実際に会ってそのサウンドと本人のキャラクターとのギャップに驚いたりもしたけれど、でも同じ黒人ということもあって親しくなった。彼は自分の繊細なところ、弱いところもさらけ出して曲を作るけれど、それはある種僕にも共通するところでもあり、そんなところで惹かれ合うんだろうね。彼と出会った頃、僕の周りにはラッパーとか、ハードな音楽を作っている人が多かったから、クウェズはその対極にあるようなタイプで、僕はとてもシンパシーを感じたし、自分のやろうとする方向性にも自信が持てたんだと思う。ジェイムス・ブレイクとは2010年に初めて会ったけど、彼と僕にも共通点は多くて、そうしたことについていろいろと語り合ったよ。僕たちのようなタイプのミュージシャンはあまり多くはないから、そうした点で共感できる存在だね。同じロンドンで育って、同じような音楽を聴いてきたという共通するバックボーンがあって、もちろんそれぞれ違うところもあるけれど、クウェズやジェイムス・ブレイクはじめ、君が挙げたアーティストたちからはシンパシーを感じ、影響を与え合う存在だと思っているよ。
■サブトラクトとのコラボがあなたを飛躍させるきっかけになったと思いますが、彼との出会いについて改めて教えて下さい。
SS:うん、Myspaceを介してサブトラクトと出会ったわけだけど、その頃から彼はレーベルの〈ヤング・タークス〉に所属していて、そこに僕と共通の知り合いがいたんだ。その人を通じて実際に連絡を取り合うようになった。そして、サブトラクトが僕の音楽に興味を持ってくれて、一緒に音楽を作ろうよと言ってくれたんだ。その頃は既に僕もサブトラクトの音楽は知っていたし、とてもいい作品を作るプロデューサーだと思っていた。だから、一緒に曲作りができると聞いて、とてもワクワクしたね。実はサブトラクトのアパートは、僕が住んでる町から地下鉄で3駅先のところにあってすごく近かったから、その後お互いの家を行き来してよく一緒に曲作りをするようになった。もちろん音楽的にも気が合ったので、家でジャム・セッションを何時間でもやっていたよ。毎週火曜の午後を共同作業の日にして、その行きの電車の中で作曲をしたりしていたね。僕にとってあの時期は、アーティストとしての土台を形成する期間だったと思っている。彼との出会いからツアーにも出られるようになったし、世界のいろいろなヴェニューを見ることもできた。ラジオで僕たちの曲がオンエアされたりと、本当に実りの多い時期だった。
■最初のEP「サンダンザ」(2010年)も、サブトラクトとのコラボを始めた頃の作品ですか?
SS:いや、あれはもっと前に作ったもので、17歳のときの作品だよ。大学受験の勉強をしなければいけない時期だったけれど、僕はそれが嫌だったから、ああやって曲を作っていたんだ(笑)。
■今とは制作方法なども違っていたのでしょうね?
SS:当時は母親のWindows 2000を使っていて、そこに付いているウェブ・カメラのマイクで録音していたんだ。録音もWindowsのサウンド・レコーダーだったので、今とは比べものにならない低スペックのレコーディング環境だったよ。制作や録音のプロセスも違うけど、その頃はまだ本気で音楽をやろうとは思っていなかったから、バックアップもきちんと取っていなかったんだ。ある日、録音をそのままにして家を出て、帰ってきたら兄が「ごめん、パソコンのデータが全部消えちゃったよ」と謝ってきて、そんな具合に消えてしまった曲も多かったね(笑)。
■2013年のEP「デュアル」はどのようにして生まれましたか? このEPは今回のあなたのファースト・アルバム『プロセス』へと至る原型のようなものだと思いますが。
SS:2012年にサブトラクトとツアーをしていて、その終わり頃にできた作品だよ。ツアーの合間に曲を作り貯めて、それらを最終的に自宅のスタジオで録音している。だから、そのツアーのリアクションだったり、その頃の心境などが反映されているね。
たとえばアフリカ音楽とインド音楽の共通点を見つけたり、アフリカ音楽と中国の音楽の類似点がわかったりとか、そうした発見があるから音楽って面白いんだ。
■ファースト・アルバム『プロセス』について伺います。デビューから随分と時間が経ってのリリースとなりますが、それだけ長い時間をかけ、じっくりと準備して作り上げた作品ということでしょうか?
SS:EPを何枚か出したときは、そもそもアルバムを作ろうとは考えていなかったんだ。一般的にシンガーがEPやシングルをいくつか出すと、次はアルバムを期待されるだろ。僕は周りのシンガーがそうした状況に置かれ、プレッシャーを受ける場面をいろいろと見てきた。僕自身はまだその段階になくて、準備ができていないと思っていた。音楽的にもだけど、人間的にも未熟で、世界が見えていなかったと思う。でも、いろいろと経験を積んで、ようやくきちんとした作品が作れるかなと思うようになった。アルバムを出して、それをライヴで伝える術も身に付いたと思う。アルバムを出すと、それに対する批判を受けることがあるかもしれないけど、それをきちんと受け入れられるくらいに成熟したしね。
■〈XLレコーディングス〉のロデイド・マクドナルドが共同プロデュースをしていますが、特に目立ったゲスト参加もなく、あなたひとりで集中して作ったアルバムのようです。それだけパーソナルな部分に向き合ったアルバムでしょうか? “ブラッド・オン・ミー”、“テイク・ミー・インサイド”、“ホワット・シュドゥント・アイ・ビー?”といった曲目にもそうした傾向は表れているように感じますが、何か個人的な体験などが反映されたところはありますか?
SS:“ホワット・シュドゥント・アイ・ビー?”はサブトラクトとのツアーの経験から生まれている。僕の人生で初めて家から離れ、ツアーに出かけるという体験だったけど、父親と離婚してシングル・マザーの母親を家に残して、自分の夢を追うために行ってしまっていいのかと、いろいろと悩んだ。この曲にはそうした自分の夢と母親への責任の間で葛藤する僕が表われている。“ブラッド・オン・ミー”にはヴィジュアル的なイメージがあって、「醒めない悪夢」とでも言おうか。自分を客観的に見たもので、それがインスピレーションとなっている。“テイク・ミー・インサイド”は人間関係、男女関係などにおいて、どれだけ自分の内面をさらけ出せるか、そうしたパーソナルな側面について歌った曲だよ。この3つの中で、もっとも個人的な体験に基づくのは“ホワット・シュドゥント・アイ・ビー?”だね。
■“(ノー・ワン・ノウズ・ミー)ライク・ザ・ピアノ”もあなたの内面が映し出された曲で、あなたの歌声以上に美しいピアノの音色がそれを物語っています。ソロ・ライヴでもとても印象的に演奏していて、あなたのピュアなところが出た素晴らしい曲ですが、これはどのようにして生まれたのですか?
SS:母の家を出て、自立した生活を送るようになってから作った曲だけど、レコーディングの最中に母の癌が末期のステージに進行していることを聞かされた。それを知ってから、母の家に戻ってしばらく過ごしたんだけど、居間にあるピアノの前に座ったときに、ふとこの曲のタイトルが浮かんだんだ。ここで登場するピアノはほかのどんなピアノでもなく、母の家にある母のピアノ、僕が子供のときに弾いて一緒に育ったピアノなんだよ。その後、母は亡くなって、母はもうこの世にいないという事実、人生は無常であるという現実に僕も打ちのめされるけれど、そうした母がいたから、ピアノのある家があったから今の自分があると思い、この曲が生まれたんだ。
■“コラ・シングス”はタイトルどおりコラの物悲しい響きが印象的です。“プラスティック 100℃”にもフィーチャーされていますが、アフリカの民族楽器であるコラを用いようと思ったアイデアはどこから生まれたのですか? あなたの両親の故郷であるシエラレオネに結び付いているのでしょうか?
SS:シエラレオネが直接結び付いているわけではないけど、ずっと昔に父がウオモサグリという西アフリカのアーティストのCDを買ってきてくれたことがあった。ウォラトンというマリの音楽の一種だけど、その影響が強いかな。そのアルバム自体はコラがそれほど使われてはいなかったけど、それがきっかけでアフリカの民族音楽をいろいろと調べるようになったんだ。アフリカ音楽には独特のリズムやメロディがあって、とても惹かれたんだ。そうした中でコラを知るようになって、YouTubeでいろいろと実演風景も見て研究したよ。実は“ホワット・シュドゥント・アイ・ビー?”のピアノ演奏もコラに影響を受けた部分があるんだ。ここではヤマハのDX-7というエレピを弾いているんだけど、コラに似せた音色となっているんだよ。僕はアフリカ音楽以外にも、世界のいろいろな民族音楽に興味があって調べているけれど、たとえばアフリカ音楽とインド音楽の共通点を見つけたり、アフリカ音楽と中国の音楽の類似点がわかったりとか、そうした発見があるから音楽って面白いんだ。