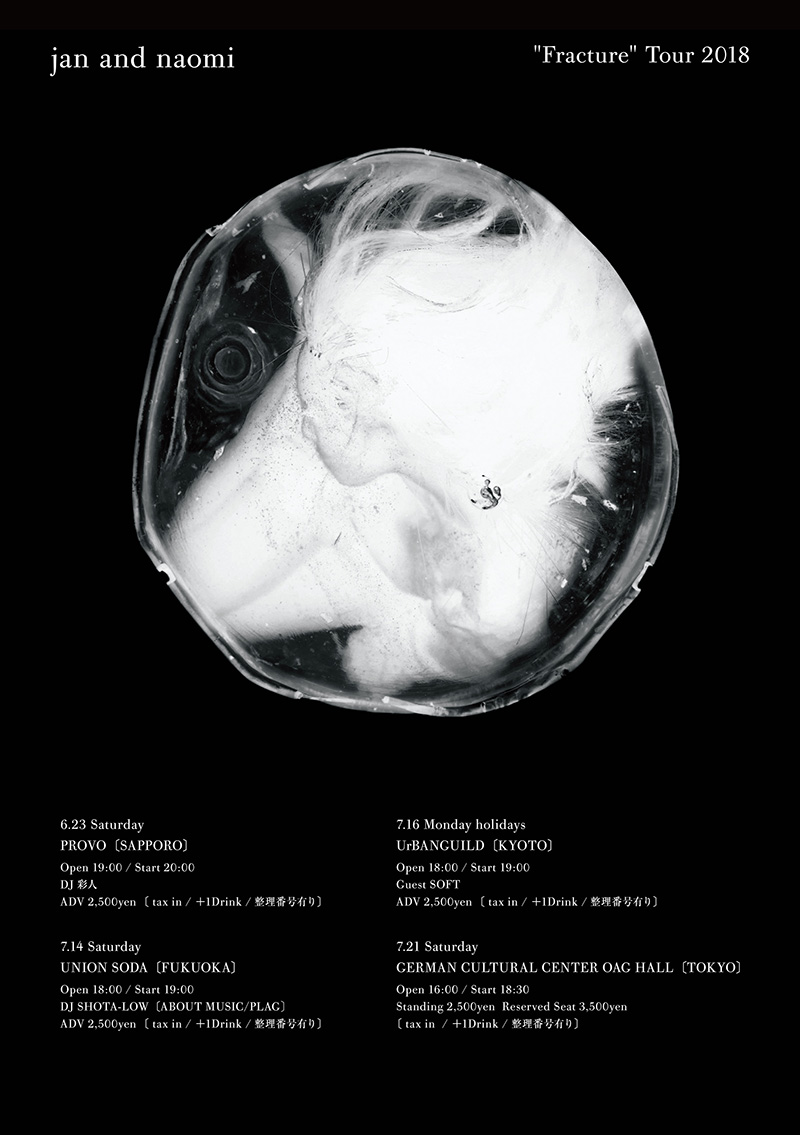ジム・オルークがソロCD(フィジカル)作品としては3年ぶりとなる新作アルバムをリリースした。リリースは〈felicity〉の兄弟レーベル〈NEWHERE MUSIC〉から。同レーベルは「アンビエント、 ニューエイジ、ドローン、ポストクラシカル、等々。これらジャンルの境界線を取り払い 「エレクトロニック・ライト・ミュージック」 と定義付けて電子的な軽音楽を創造するニューブランド」と称されており、本作『sleep like it's winter』は、王舟 & BIOMAN『Villa Tereze』についでレーベル2作目のリリース作品となる。その霞んだ空気と霧のような音響は、オルーク作品のなかでも異彩を放つ仕上がりであり、今後も参照され続けていくに違いない重要なアルバムといえる。音と音が折り重なることで生まれる時間の層のなんという繊細さ、豊穣さだろうか。
そもそもジム・オルークという類まれな才能を誇る音楽家は、20世紀音楽の「時間の層」をいくつも折り重ねることで、複雑な時間軸を内包した音楽を作曲してきた人物だ。彼の楽曲において構成されるさまざまな音のモジュールは、「接続」というより映画/映像でいうところの「ディゾルブ」のように折り重なり、そして、つながっている。
むろん、それはたんに「手法」の問題だけに留まらない。つまりは「歴史」への接続だ。そこにおいて折り重ねられるものは、個々の音楽モジュールそれ自体の時の流れと、音楽の歴史である。90年代以降、ジム・オルークが「音楽」に導入したもっとも重要な要素は、このメタ音楽の生成・構成であった。彼の音楽がドローン、ノイズ、インプロヴィゼーション、ポップ・ミュージック、電子音楽、映画音楽という領域を超えて成立しえるのも、メタ的視線(聴覚)で音楽史を捉え、音楽として再構成しているからだろう。
デヴィッド・グラッブスとのガスター・デル・ソルを経て発表されたソロ・アルバム『ユリイカ』(1999)などでは、ジョン・フェイヒィ、ヴァン・ダイク・パークスなどのアメリカーナ/大衆音楽(の異端?)とトニー・コンラッドの実験音楽/現代音楽を、「現代アメリカの民族音楽」として、メタ的に作曲・構成したことを思い出してみればいい。
ディゾルブする歴史・音楽。オルーク作品において、複数/単数の歴史/音楽が重なり合う。聴き手はその重なり合うさまを聴いている。それは歴史以降の音楽だ。歴史は終わっても、歴史以降の世界は続く。以降の世界で耳を拓くこと。音楽を聴くこと。オルークの録音作品は、それを突き詰めている。
当然、本作も同様なのだが、ここではかつてのアメリカ音楽的なものはそれほど全面化していない。それらは音の層のなかにすでに融解している。アルバムは全部で45分ほどあるが、トラック分けされておらず長尺1曲である。とはいえドローン作品のように一定の持続音が微細に変化していくわけでもない。さまざまな録音素材(演奏や電子音なども含む)がつながり、ひとつの大きな変化を「語っていく」かのような構成になっているのだ。
その意味で、彼の初期の長尺ドローン作品『Disengage』(1992)や、『Mizu No Nai Umi』(2005)、『Long Nigh』(2008.1990)、「Jim O'Rourke & Christoph Heemann」名義『Plastic Palace People Vol. 1』(2011、1991)、同じく「Jim O'Rourke & Christoph Heemann」名義『Plastic Palace People Vol. 2』(2011、1991)、「Fennesz&Jim O'Rourke」名義『It's Hard For Me To Say I’m Sorry』(2016)、「Kassel Jaeger&Jim O'Rourke」名義『Wakes On Cerulean』(2017)や、自身のバンドキャンプ「Steamroom」で定期的にリリースされている音響作品などを思い出しもする。長尺1曲でサウンドが接続し、変化していく『Happy Days』(1997)、『Bad Timing』(1997)、『The Visitor』(2009)や、カフカ鼾の『Okite』(2014)、『Nemutte』(2016)も想起することもできるだろう。また「ディゾルブ的な編集」という意味では8cmCDとしてリリースされた映画的な環境音楽作品『Rules Of Reduction』(1993)も重要な参照点になるはずだ。
本アルバムも、このような「ディゾルブ的」感覚が見事に生成していた。アルバムの色彩が、どこか霞んだような冬の響きから、春の夜明けのようなサウンドへと微細に、かつ明瞭に変化を遂げているのである。また、冒頭の霞んだ持続音、少し湿ったピアノ、低音のベースのようなドローンがそれぞれ別の時間を有しているかのようにレイヤーされていく展開にも、折り重なる音響の時間が生まれているように感じられた。
個人的には冒頭のベース的な持続音に加えて、18分から20分あたりの、密やかな鳥の声の音や環境音の挿入を経て、暗さから明るさに変化しつつあるドローン/環境音のパートにも惹かれた。冬/夜から春/夜明けへと移行する中間の音響的なトーンが生成しており、楽曲全体が「ディゾルブ的」に重なっていく感覚を覚えたのだ。また、楽曲全体に空気のように満ちている繊細な電子音も素晴らしい。
本作の音楽の構成・作曲にはジム・オルーク単独作品特有の感覚と技法の現在形が封じ込められている。録音は2017年にオルークの「Steamroom」で行われ、おそらくペダルスティール、ピアノ、シンセなどの録音素材を、ジム・オルークがひとりで時間をかけて編集したのだろう。直近の作品では「Kassel Jaeger&Jim O'Rourke」名義の『Wakes On Cerulean』にも共通する質感を感じる(ジム・オルークのなかではこういったコラボレーションとバンドキャンプで定期的に配信されているアルバムと、今回のようなソロ作品との差異はそれほど付けていないのだろう。すべては自身の音楽として繋がっている)。ジム・オルークのなかでは録音とミックスと作曲が分かちがたく一体化しているのだろう。
では、それによってどのような音楽が生成しているのだろうか。私見では、声のない音響作品であっても、どこか感情と感覚が淡く交錯する「歌」のようなものが折り重なる音響のむこうから、微かに感じられるのだ。かつてのオルーク作品をもじっていうならば「こえのないうた」とでもいうべきか。
ともあれ、このアルバムが「ジム・オルークのソロCD作品」としてリリースされたことの意味はやはり大きい。なぜなら、このような日々の創作/コラボレーションにおける思考錯誤と実践の成果が、この1枚の銀盤に、驚異的な創作力の成果として集約されているのだから。となれば、われわれリスナーは、その事実に耳を傾け、オルークが本作に込めた音楽・音響の移り変わりに注意深く耳を傾け、より深いリスニングの時間を得ることが大切のはずだ。そう、繰り返し聴くことだ。
じじつ、本アルバムを手にされた方は、今後の人生において何度も何度も、まるで水を求めるように折に触れて聴き返すに違いない。いわば人生の傍らにあるエクスペリメンタル・ミュージック。かつてジム・オルークが、その再発盤にライナーを執筆したルチアーノ・チリオ『Dialoghi Del Presente』の横に本作を置いてみると、意外としっくりくる作品ではないかとも思う。20世紀音楽の歴史が、繊細な実験性と上質なロマンティシズムのなかに凝縮されているのだ。