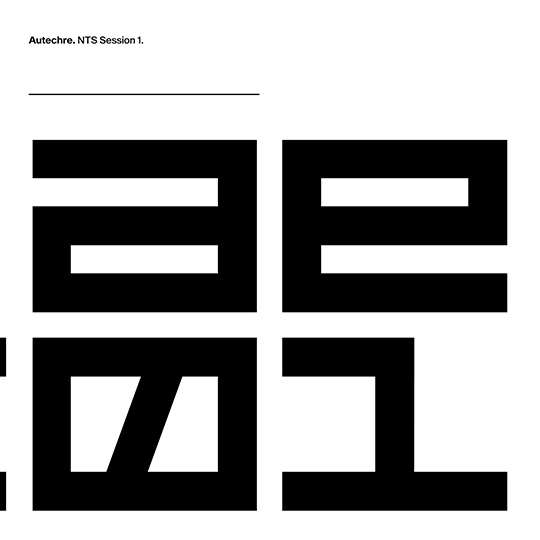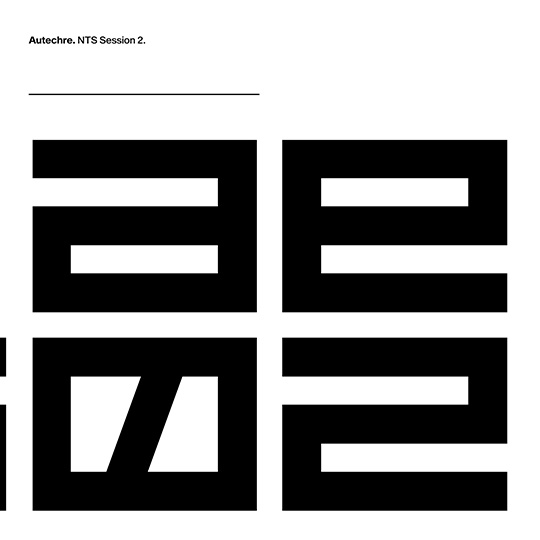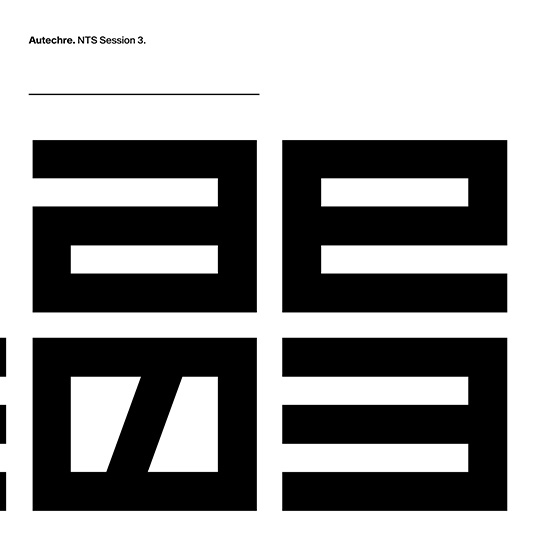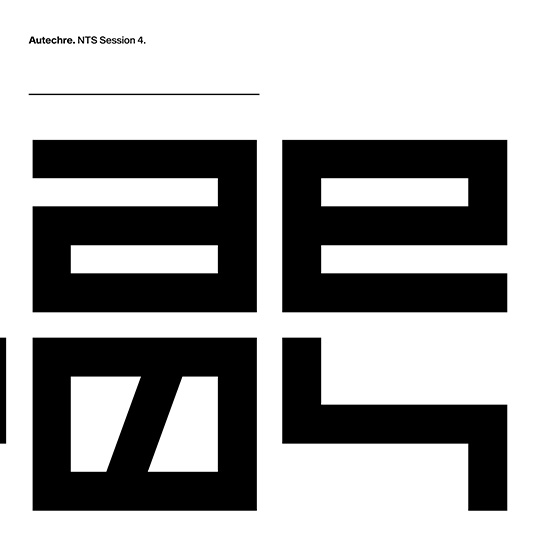さすがに昨晩は爆睡したので、イングランドとコロンビアの試合は見逃した。録画で観るといまひとつ力が入らないんだよなぁ。
その前日はたいへんだった。23時からのブラジルとメキシコの試合を見終わったあと2時間睡眠して、日本とベルギーの試合を午前3時から観た。終了後2~3時間ほど寝てから出社し、いま作っているブラジル音楽の本の入稿準備をした。
午後は、アカの入ったゲラを持って、デザイナーの渡辺光子さん(松村正人の奥様ですね)の事務所まで行って校正の直しをしてもらった。渡辺さんが集中して作業しているあいだ、ぼくは松村と雑談。その最中に、故郷の友人から35年ぶりのメール。なんという日だろうと思いながら、夕方の6時前に渡辺さんのところを出て会社に戻ってから、編集者の小熊俊哉君と合流してPiLのライヴに向かった。
短い睡眠と忙しさによる疲労は、老体に生やさしくはないけれど、時間限定とはいえアルコールによってある程度は解消された。
そんなわけで六本木のEXシアターの席にビールを片手にどっかり座っていたのだが、ぼくは席の番号を読み違えていて、しかもそこは石野卓球とピエール瀧の席だったのだ。暗闇のなかでどこかで見た顔が……「ちょっとちょっとお客さん、マナー悪いよー」とピエールから注意されてしまった。ほんと、なんという日だろう。
さて、ライヴの前半は、新生PiLの2作からの楽曲が続いたが、後半の“Death Disco”以降は、ジョン・ライドンが自ら切り拓いたポストパンクという広がりにおいて、その黄金期が過ぎたあとに発表された曲が演奏された。“This Is Not A Love Song”~“Rise”の演奏中、ガン踊りしている卓球……たしかにこの2曲がこの夜のクライマックスだった。とくに“Rise”はすごかった。
俺は間違っているかもしれない
俺は正しいかもしれない
ジョン・ライドンは例によって少々ふざけながら、しかし曲の後半はマジな声を交えてなんども執拗にこう繰り返す。
Anger is an energy
Anger is an energy
Anger is an energy……
1983年の初来日のライヴで、ぼくがもっとも印象にのこっているのは“Religion”だ。なぜなら、その当時の硬直したパンクの幻想(パンクとはかくあるべきであるというオブセッション)を嘲笑するかのように、基本ひょうきんで、ほとんどおちゃらけていたジョン・ライドンは、その曲を演奏したときだけはすごんでいたし、マジだったからだ。今回のライヴでそれに相当する曲は間違いなく“Rise”だった。
というわけでいまでも頭のなかで“Rise”が鳴っている。「怒りこそエネルギー。さすれば汝とともに道は立ち上がろう」……本当は、日本とベルギーの試合の雑感を書こうと思っていたのだけれど、なんだかそれどころではなくなってしまった。PiLのライヴには、いまの日本にもっとも欠けているものがたしかにあった。