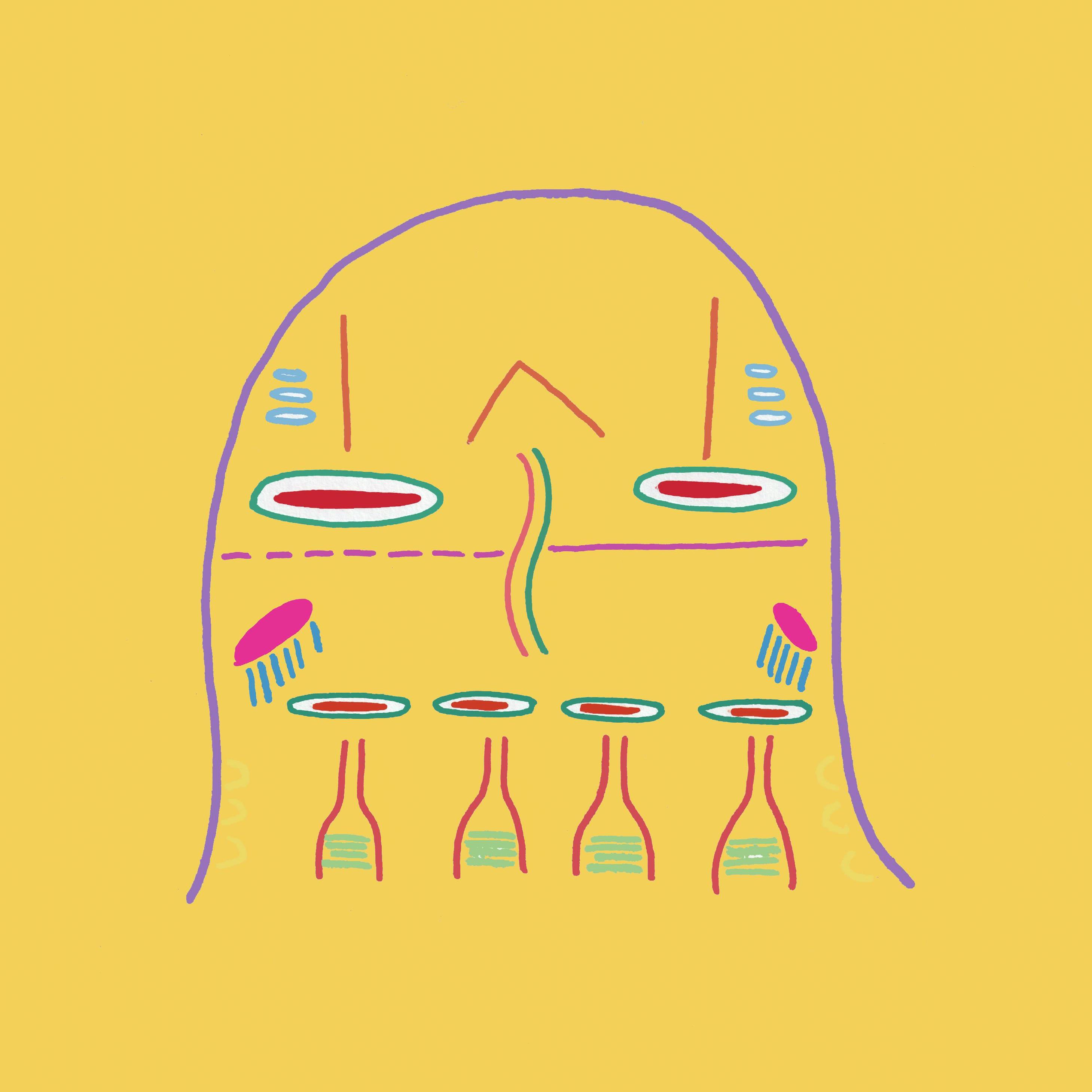ポエトリー・リーディングとジャズやファンクを結び付けたアーティストの元祖と言えば、ギル・スコット・ヘロンやラスト・ポエッツが思い浮かぶが、その系譜を今に受け継ぐのがアンソニー・ジョセフである。アンソニー・ジョセフの生まれは西インド諸島のトリニダードだが、1989年にロンドンへ移住している。2000年代半ばより音楽活動を始め、最初はスパズム・バンドというアフロ・ビート・スタイルのバンドを率いて、アルバムも数枚リリースしている。声質やヴォーカル・スタイルが近いところから、当時よりギル・スコット・ヘロンと比較されることも多かった。オランダの〈キンドレッド・スピリッツ〉、フランスの〈ナイーヴ〉や〈ヘヴンリー・スウィートネス〉からアルバムをリリースしていることからわかるように、活動範囲はイギリスだけでなくヨーロッパ全土に渡る。セカンド・アルバムの『バード・ヘッド・ソン』(2009年)ではキザイア・ジョーンズと共演し、3枚目の『ラバー・オーケストラ』(2011年)ではジェリー・ダマーズとマルコム・カトゥーをプロデューサーに迎えていたが、単なるアフロ・ビートというよりもスピリチュアル・ジャズ、サイケ・ロック、辺境音楽なども含めたミクスチャー度の高いバンドであった。
そんなアンソニー・ジョセフだが、2013年よりソロ活動に転じ、『タイム』というアルバムを発表する。ミシェル・ンデゲオチェロがプロデュース、作曲、アレンジ、ベース演奏、ヴォーカルと全面参加したこのアルバムは、それまでのアフロ・サウンドのエッセンスを引き継ぐところはありつつも、モダンでコンテンポラリーなジャズ・スタイルを融合し、アンソニーのヴォーカルはより洗練された印象を与えるものだった。ミシェル・ンデゲオチェロが深く関わったこともあり、ロックやファンクの要素もミックスさせ、アルバムとしては非常に完成度の高いものであった。曲によってはスパズム・バンド時代のような呪術的でミステリアスな雰囲気もあり、アフロ・スピリチュアル、ゴスペル、ブルース、フォークなどのルーツ色を打ち出す場面もあった。彼の歌詞には自身のルーツである西インド諸島やアフリカに紐づけられるものもあり、それは2016年の『カリビアン・ルーツ』で前面に表れている。このアルバムはシャバカ・ハッチングス、ジェイソン・ヤード、エディ・ヒックなどロンドンのミュージシャンから、フローリアン・ペリッシエール、ロジャー・ラスパイユなどフランス勢、ベテランのスティールパン奏者であるアンディ・ナレルなどが参加しており、『タイム』に比べてずっと土着的な匂いの強いものとなっている。アフリカ音楽やラテン音楽など民族色豊かなものだが、中でもアルバム・タイトルとなっているカリブ色が濃厚で、アンディ・ナレルのスティールパンが効果的に用いられている。シャバカ・ハッチングスやジェイソン・ヤードはトゥモローズ・ウィリアーズに学び、シャバカはバルバドス出身。いわゆる南ロンドンのディアスポラなミュージシャンたちと言えるのだが、そうした者たちのルーツ・ミュージックへの志向と、アンソニー・ジョセフのカリブの血が結びついたアルバムと言えるだろう。
2年ぶりとなる新作『ピープル・オブ・ザ・サン』も、基本的に『カリビアン・ルーツ』の世界を継承したものである。今回もジェイソン・ヤードなど前作から引き継いで参加するミュージシャンもいるが、録音はツアーの合間のトリニダードで行われており、1970年代から活動するレノックス・シャープ(ブージー名義で『フェイズ2』などのアルバムを出している)ほか、エラ・アンダール、ブラザー・レジスタンス、スリー・カナルなど現地のミュージシャンが多く参加。同じ西インド諸島のセントクリストファー・ネイビス出身のジョン・フランシスも加わるほか、アンソニーの娘であるミーナ・ジョセフもフィーチャーされている。こうした面々の参加により、『ピープル・オブ・ザ・サン』以上にカリブ・テイストが強いアルバムとなっている。エラ・アンダールの歌声をフィーチャーした“ミリガン・ジ・オーシャン”はヨルバ民謡のエッセンスを感じさせ、ダイメ・アロセナの曲に近いスピリチュアルな雰囲気を持つ。レノックス・シャープのスティールパンがフィーチャーされる“サン・スーシ“は、彼のブージー時代の作品に近いカリビアン・ディスコ・スタイル。ジョン・フランシスをフィーチャーしたタイトル曲“ピープル・オブ・ザ・サン”も同系のフュージョン・ファンクだが、こちらのビートはブロークンビーツ的。“ディグ・アウト・ユア・アイズ”はブロークンビーツとレゲエを取り入れたリズム・アレンジを施し、ジェイソン・ヤードのサックス・ソロも印象的なアフロ・ジャズへと導いている。
“オン・ザ・ムーヴ”と“バンディット・スクール”はアルバムの中でひときわファンキーな楽曲。“オン・ザ・ムーヴ”はラスト・ポエッツのやっていたジャズ・ファンクに通じるような楽曲で、一方“バンディット・スクール”はPファンクのカリブ版と言えるかもしれない。“ジャングル”でのミーナ・ジョセフの歌はインド音楽風で、楽曲そのものからもピースフルな雰囲気があふれ出ている。スティールパンに象徴されるカリビアン・ミュージック最大の魅力は、このピースフルなムードと言えるかもしれない。一方、“サファーリング”における哀愁も西インド諸島特有のもの。この曲は“ディス・サヴェージ・ワーク”という副題が示すように、アフリカから西インド諸島に奴隷として連れてこられた祖先についての歌。アンソニー・ジョセフの歌もラップ、ポエトリー・リーディング、レゲエのトースティング、オペラをミックスしたような自在なスタイルを見せている。ダブ・ポエット風のブラザー・レジスタンスをフィーチャーした“ディーリングス”は、レゲエ、ファンク、アフロ・ビートなどがミックスされた雑食性の高い楽曲。『ピープル・オブ・ザ・サン』はカリビアンを軸に、その周辺や関係の深いルーツ音楽をいろいろとミックスしたアルバムと言えるが、それを象徴するような楽曲である。シャバカ・ハッチングスやモーゼス・ボイドなど、南ロンドンのミュージシャンの多くにディアスポラの意識が流れているが、アンソニー・ジョセフの本作もまたそうした意識に基づく一枚と言えるだろう。