ジャズ・チェロ奏者、アブドゥル・ワドゥドが亡くなった。ネオ・ソウル系シンガー、ラヒーム・デヴォーンの父であり、メアリー・ハルヴォーソンやジェイミー・ブランチらとの共演でも知られる現役チェロ奏者トミカ・リードから深い敬愛を受ける才人である。
1947年4月30日オハイオ州クリーヴランド生まれ(アルバート・アイラーやトレイシー・チャップマンと同郷)、出生名は Ronald Earsall DeVaughn。12人兄弟の末っ子で、両親も含めて一家の誰もが音楽好きだったという。少年の頃にサックスをはじめ、やがてクリーヴランド管弦楽団の奏者にチェロを師事。オバーリン大学在学中に改宗し、3人組ユニット “ブラック・ユニティ・トリオ” で頭角を現した。72年にはセントルイスに赴き、BAG(ブラック・アーティスツ・グループ)の一員だったサックス奏者ジュリアス・ヘンフィルと親交を結んでいる。同時期に録音されたのが、ヘンフィル畢生の名盤『ドゴンA.D.』。縦横無尽の弓さばきと指さばき、ソリストとリズム陣を結びつけるグルーヴの魔術的な粘り。それはもう、この時点で完成の域にある。
筆者が彼の名前を最初に知ったのは1977年、いわゆる「ロフト・ジャズ」が話題を呼んだ頃のことだ。もっとも後年、トランペット奏者のオル・ダラ(ラッパー、NAS の父)に当時の状況を尋ねたら「ロフト・ジャズは実体のない言葉。ブームと呼べるものも何もなかった」とニベもなく言われたものだが、ただ日本のジャズ雑誌でもロフト・ジャズ関連の記事はよく取り上げられていたし、関連アルバムのリリース点数も明らかに増えた。ベイ・シティ・ローラーズや、あとにはアレサ・フランクリンやホイットニー・ヒューストンで大ヒットを飛ばす〈アリスタ・レコーズ〉まで参画したのだ。オル・ダラがどうあれ我が頭の中には、クロスオーヴァー~フュージョン/AORに対するニューヨーク・パンク/ロフト・ジャズという図式が拡がっている(このあたりのむちゃくちゃエキサイティングな流れに対する推論は、ほんの少しだが、昨年9月に元ザ・スターリンのイヌイジュン氏が主宰したイベントで、行川和彦氏や野々村文宏氏と語った)。アブドゥル初のリーダー作である無伴奏ソロ・アルバム『バイ・マイセルフ』は77年に登場。リロイ・ジェンキンス、アンソニー・デイヴィス、ジェイムズ・ニュートンなどと残した、室内楽的滲みをたたえた諸作も、こたえられない魅力を持つ。
ところでジャズ界に用いられるチェロにはふたつの流れがある。ひとつはベース奏者オスカー・ペティフォード(1950年頃、野球で怪我をし、入院中にチェロをはじめた)からはじまるもの。調弦をベースの1オクターヴ上に変え、指弾きで演奏する。サム・ジョーンズ、レッド・ミッチェルなどもこのアプローチをとっている。もうひとつはチェロをチェロ本来の調弦で弓弾きするやり方。筆者の知る限り50年代のカロ・スコット(キューバ出身)、チコ・ハミルトン・クインテットの奏者(フレッド・カッツ、ネイサン・ガーシュマン)がこちらだった。ロン・カーターはジャズ・ベーシストとして大成するが、少年の頃はクラシックのチェロ奏者を志しており、ジャズ界入りしてからもエリック・ドルフィー『アウト・ゼア』などでチェロの弓弾きを聴かせている。ロン以降アブドゥル以前の逸材にはデイヴィッド・ベイカー(元トロンボーン奏者だが、事故でアゴの骨を折ってチェロに転向)がおり、アブドゥルとともにロフト・シーンで活躍した世代にはムニア・アブドゥル・ファター、ディードレ・マレイがいる。60~70年代にピックアップやアンプが発達したことも、ジャズ・チェロ奏者に大きな可能性を与えたことだろう。うねるような弓弾き、ベーシストばりの指弾きウォーキング・ベース、立ち上がり鋭いコード(和音)、スラップ奏法的なアプローチまで、ベースやギターのパートもおそらく視野に入れながらアブドゥルは突進した。残念ながら92年に演奏活動から退いてしまったが、83年にはアーサー・ブライス・クインテットの一員として来日している。
現在入手しやすいのはヘンフィルの『ドゴンA.D.』『ザ・ボイエ・マルチ・ナショナル・クルセイド・フォー・ハーモニー』、ロフト・シーンを現場録音で捉えたオムニバス『ワイルドフラワーズ』ではないかと思われるが、アーサー・ブライス『メタモルフォシス』、白石かずこ『死んだジョン・コルトレーンに捧げる』でのプレイも鬼気迫る。再評価必至のチェロ奏者だ。
「Nothingã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®
アスワド(Aswad)はボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズやバーニング・スピアらの影響下でUKに誕生したルーツ・ロック・レゲエ・バンドで、UKレゲエのパイオニア、その代表的な存在のひとつに挙げられる。去る9月2日、バンドのヴォーカルでありドラマーだったドラミー・ゼブが永眠したことを英国のメディアがいっせいに報じた。
アスワドに関しては、最初の3枚のスタジオ・アルバム、最初のダブ・アルバム、最初のライヴ・アルバム、最初の編集盤『Showcase』は必聴盤である。また、ドラミーの活動領域は幅広く、セカンド・サマー・オブ・ラヴの時代にはポール・オークンフォルドによるMovement 98のヒット曲「Sunrise」にて見事なリミックスを披露したり、ウルトラマリンの「Barefoot E.P.」においてもリミキサーとしてカール・クレイグやリチャード・H・カークらとともに名を連ねている。それから、アンドリュー・ウェザオールはアスワドの“Warrior Charge”をオールタイム・フェイヴァリットに挙げている。
アスワドは1984年に初来日し、いまは無き後楽園ホールでライヴを披露しているが、ほとんど同じ時期に初来日したスティール・パルス(同じく初期UKレゲエの重要バンド)が座席指定の立ち見禁止ライヴだったのに対して、アスワドは座席無しのオールスタンディングだった。いまでこそこれは当たり前だになっているが、当時の日本ではパンクのライヴでさえも座席指定が常識だったので、このときはアスワドのパフォーマンスも素晴らしかったが、オーディエンスがみんな自由に踊ることができるライヴ公演自体が画期的だった。
初めてレコード店でアスワドのファースト・アルバムのジャケットを見たとき、その神秘的なアートワークに魅了されてしまった。買いたかったが、ジャマイカ産以外のレゲエは認めなかったこの頃の日本の音楽誌の辛口の評を読んでいたので、最初はスルーした。2回目に見たときも3回目も……、スルーしながらもそのジャケットを見るたびに魅了され続け、結局、迷いに迷った末に買った1枚となった。後日、このジャケットがプリントされたトレーナー(おそらくバッタ物)を服屋で見つけたときは、もう迷うことはなかったけれど。それにしてもこのアルバムは1976年のリリースだから、当時ドラミーは17歳、後楽園ホールのときは20代半ばということになる。そうか、そんなに若かったのか。エネルギッシュな演奏だったもんな。あのときの“African Children”は、老人力がついてきたいまでも忘れることができない。(野田)
今年の3月に上映された「This is Charles Burnett チャールズ・バーネット セレクション」第一弾が好評だったことを受けて、自主上映グループ After School Cinema Clubは、その第2弾として、90年代のバーネットの代表作『トゥ・スリープ・ウィズ・アンガー』を10月に上映する。
『トゥ・スリープ・ウィズ・アンガー』は、中流階級の黒人家庭を舞台にしたホームドラマであると同時に、ダークコメディ、マジックリアリズム、民俗学の要素を取り入れた、カテゴライズすることが困難な作品。
本作が制作された80年代後半のサウスセントラルでは、すでにクラックなどのドラッグによって家庭やコミュニティが破壊されていた。『トゥ・スリープ・ウィズ・アンガー』はそんな時代に作られた、過去と現在を結び つけるための物語だ。
本作に登場する音楽も、前二作に劣らず印象的。オープニング・クレジットで流れるシスター・ロゼッタ・ サープの美しいブルース・ソング“Precious Memories”をはじめ、“Stand By Me”や“See See Rider”、そして物語が終わろうとするまさにその時、 「魂の進歩の指標としてのブルース」が響き渡り、観客の胸を打つ。
はからずともジョーダン・ピールの新作『NOPE/ノープ』が話題のいま、もうひとつの黒人映画の魅力を体験してください。
■This is Charles Burnett
チャールズ・バーネット セレクション vol.2 開催概要
【日程】2022年10月1日(土)
【会場】ユーロライブ(渋谷区円山町1-5 KINOHAUS 2F) 【タイムテーブル】 13:00 開場 / 13:30 1回目上映 / 15:30 2回目上映 *入替制
【チケット】学生1,500円 / 一般 1,800円 チケットはPass Marketにて9月3日(土) 正午より発売
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02f1zj6bu8j21.html
【イベントサイト】 afterschoolcinemaclub.com/charlesburnett/
【主催】 After School Cinema Club
【問合せ】afterschoolcinemaclub2014@gmail.com
*当イベントやチケットに関してユーロライブへのお問い合わせはご遠慮ください。

『トゥ・スリープ・ウィズ・アンガー』
1990年/アメリカ/102分/アメリカンビスタ/カラー/原題:To Sleep With Anger/日本語字幕:加藤初代
【監督・脚本】チャールズ・バーネット
【出演】ダニー・グローヴァー、ポール・バトラー、メアリー・アリス、ボネッタ・マクギー、カール・ランブリー、 リチャード・ブルックス、シェリル・リー・ラルフ、エセル・アイラー
■ストーリー
ロサンゼルスのサウスセントラルで暮らすギデオン(ポール・バトラー)とスージー(メアリー・アリス)夫妻の元に、南部時代の古い友人ハリー・メンション(ダニー・グローヴァー)が訪ねてくる。30年ぶりの再会に驚きながらも、2人は旧友を快く自宅に迎え入れる。陽気で人当たりの良いハリーはすぐに一家に溶け込み、とりわけ夫妻の 末息子ベイブ・ブラザー(リチャード・ブルックス)と親しくなる。そんななか、ギデオンが謎の病に倒れる。いっこうに立ち去る気配のないハリーは、次第に別の顔を見せ始める……。
■チャールズ・バーネット
1944年4月13日、ミシシッピ州ヴィックスバーグ生まれ。幼少期に一家でロサンゼルスのサウス・セントラル(現サウス・ロサンゼルス)に移り住み、南部からの移住者が多く住む貧 困地区ワッツで育つ。カルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)に進学し、ドキュメン タリー作家バジル・ライトらに師事。学生時代はジュリー・ダッシュ、ハイレ・ゲリマらと共に学び、後に「L.A. Rebellion」と呼ばれることになるインディペンデント映画監督グ ループの一員として、ハリウッド映画とは異なる新しい「黒人映画」を模索した。
1981年、初長編作『キラー・オブ・シープ』(77)がベルリン国際映画祭で国際批評家連 盟賞を受賞。続いて『マイ・ブラザーズ・ウェディング』(83)、『To Sleep with Anger』(90)、『The Glass Shield』(94)を発表。その後は長編映画だけでなくドキュメンタ リーや短編、テレビ映画でも監督を務めた。
バリー・ジェンキンスの『ムーンライト』がアカデミー作品賞を受賞した2017年、長年にわたる映画とアメリカ文化への貢献を讃えられ、名誉オスカーを受賞。
現在も精力的に制作を続けており、ドキュメンタリー『After the Lock Down: Black in LA』(21)を共同で監督したほか、実在した元奴隷ロバート・スモールズの奴隷制からの脱出を題材にしたアマゾン・スタジオ制作の映画『Steal Away』の監督を務めることも決定している。
先日限定7インチ「(Herman’s) House」を送り出したニューオーリンズのスペシャル・インタレスト。ついにアルバムのリリースがアナウンスされた。現在、ミッキー・ブランコをフィーチャーした先行シングル “Midnight Legend” が公開されている。声明によれば同曲は、朝クラブを出るすべての女の子たちへのラヴ・ソングであり、まわりに愛を抱けない(孤独な)すべての人びとへのラヴ・ソングだという。バンドにとっての3枚めのアルバムとなる新作『Endure』は、11月4日に〈ラフトレード〉より発売。
SPECIAL INTEREST
この社会からログアウトする!
ニューオーリンズ在住の4ピース・バンド、
スペシャル・インタレストが、最新アルバム『Endure』を11月4日に発売!
ミッキー・ブランコを迎えたリード・シングル「Midnight Legend」を公開!
ニューオーリンズのノー・ウェイブ・パンクバンド、スペシャル・インタレストは本日、〈Rough Trade Records〉から初となる、バンドにとっての3rdアルバム『Endure』を2022年11月4日(金)にリリースすることを発表した。この発表は、アイコニックなラッパー、パフォーマンス・アーティスト、詩人、活動家のミッキー・ブランコをフィーチャーしたリード・シングル「Midnight Legend」と、スペシャル・インタレストのボーカリスト、アリ・ログアウトが監督した素晴らしいミュージック・ビデオとともに公開された。最新アルバム『Endure』はセルフ・プロデュースされたアルバムで、エンジニアはジェームス・ウィッテン、ミックスはコリン・デュピュイ(エンジェル・オルセン、イヴ・トゥモア、ラナ・デル・レイ)、マスタリングはロンドンの〈Metropolis〉でマット・コルトンが担当した。
11月4日に発売となる、アルバム『Endure』CD/LPは本日より随時各店にて予約がスタートする。
“Midnight Legend” は、午前6時にクラブを出るすべての女の子へのラブソング、自分の周りで愛情が感じられないすべての人へのラブソング。孤立感や孤独感を感じるゆえに、自分自身を麻痺させたり、危険な行動に走ったりするのは、クラブやさまざまな娯楽施設、そして「パーティー友達」に助長されている部分もあると思う。この曲は、実際には決して聞かれることのない人々の声に耳を傾けている歌。このビデオで描かれている3人のレジェンドたちは、一人の人間でありながら、それぞれ異なる悲しみのプロセスを表現している。一人は、頭がおかしくなりすぎていっちゃってるやつ。もう一人は、体の関係を持つことで自分の心を麻痺させているアバズレ。そして、三人目は、ある瞬間、世界に心を再び開いて、愛情を受け入れられるようになる自分。ビデオの最後で、その三人は一つになり、元の自分自身に戻ることを意味している。──アリ・ログアウト
Special Interest - Midnight Legend ft. Mykki Blanco
https://www.youtube.com/watch?v=jss7mRU67e8
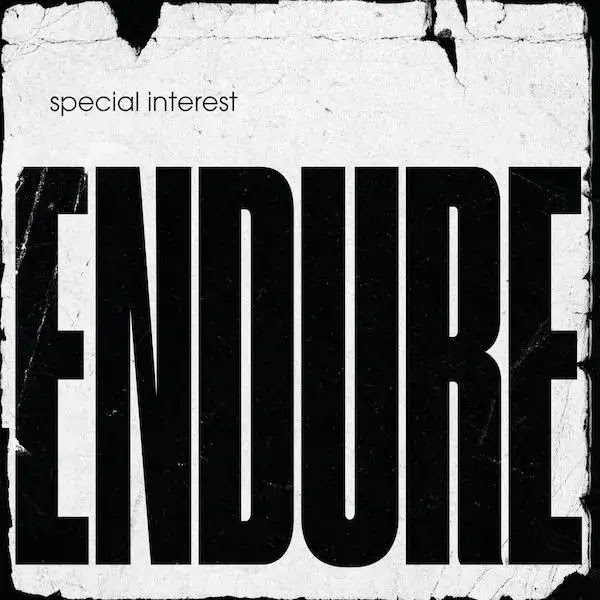
label: Rough Trade / Beat Records
artist: Special Interest
title: Endure
release: 2022.011.4 FRI ON SALE
国内流通仕様盤CD RT0303CDJP(解説付)¥2,200+税
輸入盤CD RT0303CD
通常LP RT0303LP
LP 限定盤 RT0303LPE(Yellow/LTD)
BEATINK.COM:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=12984
TRACKLISTING
01. Cherry Blue Intention
02. (Herman’s) House
03. Foul
04. Midnight Legend
05. Love Scene
06. Kurdish Radio
07. My Displeasure
08. Impulse Control
09. Concerning Peace
10. Interlude
11. LA Blues
クラウトロックにおいてもっとも重要なバンドを挙げろと言われたとき、CAN、クラフトワーク、そしてその次に来るのが、のちの影響力を考えると、おそらくノイ!になるのではないだろうか。クラウス・ディンガーによるモータリックと呼ばれる極めてミニマリスティックな当時としては革命的なビートは、いま聴いてもまったく古くはならないし、その影響はトータスやステレオラブ、ソニック・ユースやプライマル・スクリームにまで及んでいる。ギターのミヒャエル・ローターは、イーノに多大な影響を与えたハルモニアのメンバーでもあった。で、まあとにかく、“ハロガロ”はたとえ100年経ってもリスナーをうきうきさせてくれるだろう。聴いていてどんどん進んでいく感覚、目の前の風景が開けていくような感覚を覚える曲といえば、まさにあれだ。Neu!(ドイツ語のnew)はいまでも新しい!

来る9月28日、ノイ!のファースト・アルバムのリリース50周年を記念したボックスセットがリリースされる。ボックスには、3枚のオリジナル・アルバム(その3枚とも傑作)に『 NEU! ’86』とリミックス・アルバム、ステンシル、ブックレットが封入される。リミキサーには、モグワイ、スティーヴン・モリス(ニュー・オーダー)、ザ・ナショナル、アレクシス・テイラー(ホット・チップ)らが名を連ねている。また、P-VINE OFFICIAL SHOP限定でTシャツとトートバッグの販売も決定(P-VINE OFFICIAL SHOPにて対象商品を購入いただくと、ボックスセットのジャケットデザインのステッカーを対一でプレゼント)



■ご予約はこちらから
https://anywherestore.p-vine.jp/collections/neu-50thanniversary
アーティスト:ノイ!
Artist: NEU!
タイトル:50! CDボックス
Title: 50! CD Boxset
レーベル:P-VINE
フォーマット:CD BOX
発売日:2022/09/28
品番:PCD-17846/50
価格:¥13,200(税抜¥12,000)
完全限定生産
収録内容:
1. NEU! / NEU!
2. NEU! / NEU! 2
3. NEU! / NEU! 75
4. NEU! / NEU! ’86
5. NEU! / Tribute album
6. Stencil
7. Booklet
アーティスト:ノイ!
Artist: NEU!
タイトル:50! LPボックス
Title: 50! Vinyl Boxset
レーベル:P-VINE
フォーマット:LP BOX
発売日:2022/09/28
品番:PLP-7911/5
価格:¥30,800(税抜¥28,000)
完全限定生産
収録内容:
1. NEU! / NEU!
2. NEU! / NEU! 2
3. NEU! / NEU! 75
4. NEU! / Tribute album
5. NEU! / Tribute album
6. Stencil
7. Booklet
Ripatti Deluxe - Tambourine Love Hat (video by RuffMercy) from Vladislav Delay on Vimeo.
精力的な活動を続けるフィンランドのプロデューサー、ヴラディスラフ・ディレイ(本名:サス・リパッティ)による新名義、Ripatti Deluxe(リパッティ・デラックス)のアルバム『Speed Demon』が10月28日に 新レーベル〈Rajaton〉からリリースされる。
「国境という概念を意識しないとき、我々の心はどう動くのだろう?」——これが作品のひとつのモチベーションになっているようだが、もっとも大きなコンセプトは「速度」になる。アルバムには、「時間、時間に対する概念、時間に対する意識、時間に対する隷属、欲望などについて」の考察が反映されており、音楽的には「いままで聴いたことのない初期のレイヴやハッピー・ハードコアなどをランダムに見つけて、今度はそれらを大量のエフェクトを通してループさせたり、ひっくり返したりしたり」したことがヒントになっている。
■新レーベル〈Rajaton〉
〈Rajaton〉は、孤立、所有権、戦争が国境を強化するとき、物理的および精神的な境界の非存在を意味する。〈Rajaton〉の音楽のアウトプットとそれを積極的に聴くことは、私たちを再び無限にし、思考を広げるきっかけとなる。ヒエラルキーとジャッジメントを劣化させ、誠実な解釈と新しい形の完全な理解を得るための、多数の万物の存在。〈Rajaton〉は、Ripattiの前身である〈Huume Recordings〉と〈Ripatti〉に続くレーベルである。
■サス・リパッティ
90年代後半から00年代初頭にかけて、グリッチ、テクノ、アンビエント、フットワークといったエレクトロニック・ミュージック・シーンにおける重要人物。「Entain」、「Multila」、「Anima」といったカルト・クラシックや、Vladislav Delay, Uusitalo, Luomo, Conoco, Sistolとして20以上のアルバムをリリース、マイクロ・ハウスといったジャンルの先駆的な存在である。彼の音楽は〈Planet Mu〉, 〈Raster-Noton〉, 〈Chain Reaction〉, 〈Mille Plateaux〉, 〈Honest Jon's〉 などからリリースされている。また、過去には坂本龍一、シザー・シスターズ、AGF、ブラック・ダイス、マッシヴ・アタック、モーリッツ・フォン・オズワルド、ミカ・ヴァイニオ、クレイグ・アームストロング、ジャマイカの伝説的アーティスト、スライ&ロビー等とコラボレートしている。彼の音楽は、洗練された質感、セミランダムな要素、破砕とシンコペーションのパーカッション、そして脱構築で有名。
アヴァンギャルド・ジャズのトランペッター、ジェイミー・ブランチが8月 22日にブルックリンの自宅で亡くなったことを、先ごろレーベル〈International Anthem〉が発表した。2017年の彼女のデビュー・アルバム『Fly or Die』は、いまでも新しいリスナーを巻き込んでいる魅力的な1枚で、むしろこれから評価を上げていくであろうと思われていた作品だ。彼女の活躍は期待されていただけに残念でならない。シカゴのフットワークにも関心を寄せて、エレクトロニック・ミュージックへのアプローチも試みようとしていた矢先だったと言われている。また、Anteloperというプロジェクトでも今年はアルバムを1枚出している。近年は女性ジャズ・アーティストがしきりに目立つようになったが、彼女の名前は間違いなく歴史に刻まれるだろう。それになんといっても、キャップを被ってジャージ姿でジャズ・トランペットを吹きまくる女性という見た目も、じつに新鮮だった、
まずは『Fly or Die』を聴いて欲しい。
ホット・チップは、UKポップ音楽のお家芸と言える、ソウルやダンス・ミュージックを折衷するエレクトロ・ポップなロック・バンドで、そのサウンドには多幸感とメランコリーが交錯している。20年という彼らの長いキャリアにおいてバンドは着実に成長し、UKシンセ・ポップとしては、いわばニュー・オーダーの後継者というか、いまや今世紀における代表的な存在と言えるのかも。じっさい2019年の前作『A Bath Full of Ecstasy』は批評家から絶賛され、今作『Freakout/Release』も注目のアルバムとなった。
以下、日本のファンを代表して斎藤辰也──ホット・チップ以外は、ほとんどクラシック・ロックばかり聴いているようだが──その彼にまずはファン目線の解説を書いてもらった。その後に続くインタヴューともどもお楽しみください。
ミュージシャンがつまらない作品が出すと僕は追いかけるのをさっさとやめて悪態をつきがちなのですが、ホット・チップのことは14年近く追いかけています。僕がホット・チップをこんなにも好きでいるのは、彼らの音楽はつねに歌心を大事にしているからです。メロディとハーモニーを大事にしたやわらかい歌声でもって、ダンスビートの上で、人としての弱さや苦悩を明かしているからです。そうした歌を聴かせてくれるバンドは貴重です。LCDとかジンジャールートなんかでは、とてもじゃないけどダメなのです。この歌とハーモニーを実現できるバンドは、ホット・チップ以外にいないでしょう。
新型コロナに罹患して部屋にこもることになって思いついたのは、好きなミュージシャンのレコードを、キャリアの初めから最後まで、1日中ぶっ通しで聴くことでした。ボブ・ディラン。ニーナ・シモーン。ヴェルヴェッツ。大好きなビートルズとビーチ・ボーイズも聴きました。しかし、僕のすべてだと思い込んでいたその2組は、決していまの僕のすべてではないことに気づくことになりました。
部屋を侵食するレコードの山の中から10枚しか残せないとしたら、僕はまずホット・チップの作品から『ワン・ライフ・スタンド』を選ぶでしょう。5枚でもそうします。3枚でも、そうしましょう。1枚なら………シド・バレットのセカンドだと心に決めているので、大変な拮抗が生じます。だけど、いまな、ら、『ワン・ライ、フ・スタ、ンド』を、選、ぶ。かもし、れま、せん(大変な拮抗が生じています)。ホット・チップをこれから知る人にもこのアルバムを薦めます。タイトルどおり、彼らの音楽は一生の付き合いができそうな包容力があります。無理をしないで、いつでもありのままで向き合える、そんな気持ちにさせてくれます。弱いことは恥ずかしいことではないんだよと、そう言ってくれる気がするのです。ここでもし、そんなの要らないとあなたが言うのであれば、そもそも音楽なんて聴かなくていいと思います。
2008年の『ワン・ピュア・ソウト』の可愛いけどなんか変なMVを観たとき、シンセ主体の音楽を忌避してロックとヒップホップだけを聴いてきた僕の中で、とんでもないレベルで、なにかが弾けました。折衷という言葉では説明できません。その音楽の中に、僕が好きなもの以外にも、なにかわからないけど色んなものがトロトロになって煮込まれているのを感じたのです。いま食べてるので喩えますが、未知の具材たっぷりのカレーの鍋を覗き込んだと思ったら、画面の向こうから鍋の中身が飛び出して、全身にぶっかけられた。そんな衝撃でした。それ以降、彼らの作品や足跡を追いかけて、それまで知らなかった数々の音楽の扉を叩くことになりました。ニューウェイヴ。テクノ。ハウス。ノイズ。エレクトロ。音楽の広さを音楽を通じて教えてくれるバンドなんて、他にはビートルズくらいしか思いつきませんが、ホット・チップが教えてくれたのは、僕の大好きなビートルズやビーチ・ボーイズが教えてくれなかったものでした。ホット・チップが現代のバンドで、それをリアルタイムで聴くことができるのは、とてもラッキーなことだと思います。
ホット・チップは結成から20年以上が経ちました。ダンスフロアの流行り廃りに流されることもなく、メンバーの入れ替わりもないまま自分たちの地盤を固めることができたのは、アレクシス・テイラー&ジョー・ゴダードのふたりを核としたソングライティング、そして、それを彩るためのサウンド作りにメンバーが力を注いできた結果であると思います。まずもって馴染みやすいメロディと真摯な歌詞を大切にしながら、男性的な“強さ”を回避するアレクシスとジョーの優しい歌声が響いて、メンバーのハーモニーが重なり、それらをダンスのリズムとシンセサウンドが讃える。アレクシスとジョーのマイクリレーやハーモニーは、まるでブライアン・ウィルソンとマイク・ラヴの掛け合いが現代に生まれ変わって、同じバンドにいるかのようです。こうしたヴォーカルワークの美しいバンドは、他に類を見たくても、なかなか見れないと思います(メンバーのアレクシスと初めて会ったとき、僕はビーチ・ボーイズの未発表アルバム『スマイル』のブートの箱を渡しました。「なんでこれを僕にくれようと思ったの?」と言いつつニヤついた彼の笑顔は最高に面白かった。それに、彼とジョーなら『スマイル』は没にしないでしょう)。
今作、『フリークアウト/リリース』では、前作で強固になったダンスビートを引き継いでいますが、これまでのアルバムよりもシリアスなムードが通底しており、一聴すると重々しい印象が残るかもしれません。だけど、僕から述べておきたいのは、前述したようなバンドのあり方は変わっていないということです。明るい音楽で哀しいことを歌うように、人としての弱さや苦悩を隠しませんでした。そういったシンパシーを音楽の上で感じさせてくれます。ただただアッパーなダンスナンバーにもできたはずの“ブロークン”で「時々思う/僕は壊れている/もう壊れようがないほど」と歌うのを聴いて、僕は駅のホームで涙を流しながら歩いていました。いい大人が道端で目を赤くしているのは、通りがかった人にしてみれば不気味だったと思います。でも、不意にそういうことをさせてくる音楽なんです。(斎藤辰也)

右にいるのが質問に答えてくれたアレクシス・テイラー、その隣にいるのがジョー・ゴダード。
僕個人としては、大仰な政治的声明を打ち出そうとすることを楽しいとは思わないね。政治ってものは、自分の音楽にはほとんど入り込んでこない物事だ、そう感じる。ジョーの方なんじゃないかな、音楽にもうちょっと政治が入ってくるのは?
■4月からツアーが続いていますが、いまUKのライヴ状況は、いかがでしょうか? コロナ前の感じに戻ってきていますか?
アレクシス:そうだね、ライヴ/コンサートの状況について言えば、ほんとなにもかもが戻ってきている。会場も再開し規制もなくなったし。けれどもフェスティヴァル、たとえば何万もの人間が集うグラストンベリーのようなイヴェントは、結局数多くの感染者を出すことになった。だから、ある面では物事は「ノーマル」に戻ったけれども、やはりウィルスは依然消え去ってはいない。単に、人びとは感染しても以前ほど具合が悪くならなくなっただけであって、それはたぶんワクチン接種に少し守られているからだろう。
というわけで……たとえば自分たちがフェスでプレイして観客を眺めていても、以前みたいにCOVIDについて考えることはなくなった、そう言っていいと思う。というのも、みんなマスクを着けなくなったから。だから、カルチャーという意味では非常に変化したし、前より少し良くなったっていうのかな、規制が緩まったおかげで。けれどもそれと同時に、COVIDに感染するたび——僕自身、1ヶ月前くらいだったっけ? ウィルスに感染したし、その都度あれがどれだけ不快な体験かを思い出させられるっていう。
■前作『A Bath Full of Ecstasy』に引き続き、今作『Freakout/Release』もじつにパワフルなアルバムになったと思います。まずはサウンドについてお訊ねしますが、先行発表された “Down”は、力強いファンクのリズムが強調されていますよね。LCDサウンドシステムなんかともリンクするファンク・パンクを彷彿させます。
アレクシス:うん。
■それに表題曲の“Freakout/Release”や“Hard To Be Funky”にも強力なリズムがありますが、こうしたビート感、躍動感は、自然に生まれたものなのでしょうか? それともこれは今作において意図したことだったのですか?
アレクシス:リズム・トラック群やグルーヴ、あるいはファンキィな要素に関して言えば、自分たちはとくに「今回はこれまで作ってきた作品とは違う」とは考えていないと思う。過去の作品以上にそれらの要素が強調されていると人びとが感じるだろう、僕たちにそういう意識はなかった、と。けれども、うん、いま言われたように、僕たちは踊るのにすごくピッタリなものを作ろうとしていたね。そうやって人びとにエンジョイしてもらえるなにかを、音楽と人生と踊ることとを祝福できるなにかを人びとに与えたいと思っていた。ただ、思うに、いまの質問にあった印象/感想は――良い感想だけれども、僕たち自身はべつにこれといって、より「パンク・ファンク調」な方向を目指してはいなかったんだ。あれはとにかく、そうだなぁ、たぶん“Down”で使ったサンプリングに導かれたものだったんじゃないかな? あの曲で僕たちはファンク・チューンをサンプリングしたし、それが僕たちを音楽的にあの方向性に引っ張っていった、と。それもあるし、おそらく今回は、アル(・ドイル)があの曲やそれ以外のいくつかのトラックでも生演奏でベース・ギターをもうちょっと弾いているし、彼はLCDサウンドシステムでもプレイしているから、それもあったのかもしれない。彼がふたつのバンドでプレイするベースの奏法はやはり似通ってくる、と。
通訳:いま話に出た“Down”のサンプル、あれはUniversal Togetherness Bandのトラックですが——
アレクシス:そう。
斉藤:たぶん2015年あたりから、ソウルのレコードをサンプリングすることが新曲において増えてきている印象を受けます。これは意図的にそうしているのでしょうか? たとえば、70〜80年代のソウル/ディスコ/ファンク音楽の、そのルーツにお返ししよう、みたいな思いは大事でしょうか?
アレクシス:んー……もしかしたら、僕たちにもそうした思いはあるのかも? だけど、僕たちはずっとソウル/ファンク・ミュージックが好きだったからね。ファースト・アルバムを作ったときですら——あれはサンプリングではなかったけれども、たとえば“Keep Fallin’”のような曲をプレイしていたわけだし、あれはかなりこう、ファンク・ミュージックを作るためのプリミティヴかつ安上がりでローファイな試み、そういう風に聞こえる曲だと思う。とはいえまあ、ソウル・ミュージックからの影響はあるよね、僕たちのもっとも大きな影響源のひとつだと思う。おそらく……まあ、サンプル音源にソウル寄りな変化が起きているとしたら、それは要は、ジョー(・ゴダード)が買っているレコード次第なんじゃないかと思う。というのも、僕自身はレコードからサンプリングはしないし、ネタとして使えそうなセクションを探そうとしてレコードを聴くこともないから。
でも、そうは言いつつ、この同じアルバムで僕は「ファンキィであることについて」の歌(=“Hard To Be Funky”)を書いたわけだし、ということは、うん、たぶんその同じスレッドがこのアルバムの曲の多くにも流れているってことなのかもしれない。でも、いま言われたように、2015年以来、僕たちが「ダンス/ソウル音楽のルーツに敬意を表して」みたいにサンプル音源を選んでいるとか、べつにそういう意図的な決定ではなかったんだ。ただ単に、僕たち自身がああいうスタイルの音楽をずっと好きだからああなった、そういうことだと僕は思う。でまあ、要は、ジョーがレコード屋でなにか発見して、「お、これはグレイトな曲! ぜひサンプリングしたい」と思いついたってだけのことじゃないかと。
斉藤:今回、マイク・ホーナーと、ソウルワックスと、Superorganismのメンバーであるトゥーカンをアルバム制作に抜擢した意図やきっかけはなんですか?
アレクシス:まあ、前作『A Bath Full Of Ecstasy』をやったときも、マイク・ホーナーと一緒に作ったからね。マイクはすごく、すごく優秀だし、とにかく一緒にスタジオで過ごしていても本当に気持ちの良い人で。僕たちが彼と一緒にやることにした理由はそれだったし、彼は僕たちの求めていたサウンドを掴むのを助けてくれた。
ソウルワックスについては、……ジョーの思いつきだったはずだけど、彼が「ソウルワックスにこの2曲を送ってみないか」と言い出して。彼らに聴いてもらい、何を持ち込んでくれるか試しに見てみよう、と。そのうちの1曲は“Down”で、あれは結局彼らにプロダクションを手伝ってもらわずに済んで、ミックスだけやってもらった。もう1曲が“Freakout/Release”で、あれはこう、僕たちからすれば半分くらいまで出来上がっていた感じで――曲は書いたものの、サウンドがどうもいまひとつジャストに収まらない、と。それであの曲をソウルワックスに送り、共同プロデュースおよび追加プロダクションをお願いしたんだ、純粋に、あの曲をフィニッシュさせるためにね。
ホット・チップではコラボに関してはかなりカジュアルに物事が進むんだよ。今作でプレイしてくれたほかのコラボレーター、たとえばドラマーのIgor Cavalera(イゴー・カヴァレラ)、彼はセパルトゥラ(※メタル・バンド)のメンバーだったことで知られる人で——彼は“Eleanor”でドラムをプレイしてくれたけど、あれはメタルっぽい曲ではないよね。それからCadence Weapon(ケイデンス・ウェポンaka ローランド・ペンバートン)については、僕たちはあの“The Evil That Men Do”でラップを入れたいと考えていて、ジョーが彼のことを思いついた。彼とは昔、一緒にツアーをやったこともあった仲だし、運良くタイミングも合って、彼はグレイトなヴァースをあの歌のために書いてくれた。それからシンガーのLou Hayter(ルー・ヘイター)、彼女は僕たちのスタジオの近所に住んでいて、知り合いだし僕たちと一緒にDJをやったこともあるんだけど、まだコラボはやったことながくてね。で、ある日、彼女に「この“Hard To Be Funky”という曲で女性ヴォーカルが必要なんだけど、トライしてみる気はある?」と訊ねてみて、それで彼女がスタジオまで来てくれて、2、3時間で録ったんじゃないかな。そんな感じで、なにもかも……そうだなぁ、かなりこう、フレンドリーな、集団型な音楽の作り方だね。
トゥーカンに関しては、彼は以前、僕のシングルをミックスしてくれたことがあって。トゥーカンは良い要素を持ち込んでくれた。彼がミックスを担当してくれたトラックの多くは、シングルになっていったね。
■“Down”は、曲はパワフルなディスコ・ファンクですが、その歌詞は、質者には「労働」について書かれているように思いました。
アレクシス:うんうん。
■じっさいのところ、これは、どんなところから生まれた言葉なのでしょうか?
アレクシス:COVIDのせいで、僕たちは長いこと集まって一緒に作業することができなかった。だからあの曲はほんと、「遂に僕たちも、スタジオで一堂に会することができた」ってことについて語っているというか……僕にとってはこの自分の「仕事」、僕にとっての仕事であるミュージシャンをやること、歌をクリエイトすることは大事なんだ、と再確認してるっていうのかな。いや、ある意味、僕の周囲にいる人びとやホット・チップの面々、プロデューサーとしてのジョーはそういう風に見ていないのかもしれないよ。ただ、僕たちは努力しなくちゃらないんだ、自らにムチをぴしゃっと叩いてがんばり、この音楽をできる限り良いものにしなければならない、と。
というわけであの曲は、この曲を上手く機能させるために自分は自らを捧げるというか、自分はこの曲をできる限り良いものにするために努力したい、と言っている、そういう感じの曲で。うん、だからあれは一種の……「仕事」、そして「一所懸命働くこと」というテーマ、そしていかにしてこのとある恋愛関係に意味を見出すことができるかについて掘り下げたもの、というかな。ある面では音楽についての歌だし、ある面では誰かとのロマンチックな関係の意図的なメタファーにもなっていて、うん、そのふたつの異なる意味合いのある歌だね。だから、その意味ではかなり曖昧な曲と言えるけれども、一種こう、働くこと/なにかに取り組むことは楽しい行為になり得るってことを歌ってもいて……そうだね、がんばって働くことの肉体性という概念を、リズミックな働きぶりを祝福しているというのかな。だから1曲のなかにいろんなことが込められている。
自分たちにはそんなに多くの規範/ルールみたいなものはないと思う。ただ、今作に関して言えば、たぶん1曲を除いて、作った曲のすべてはまずまずダンサブル、あるいはファンキィと呼べるものだったんじゃないかな。
■あなたは、おそらく前作『A Bath Full of Ecstasy』から、意識的に政治や経済といったトピックを歌のなかに盛り込んでいるように思いますが、しかし音楽面においては、それがポップ・ミュージックであることにことだわっていますよね?
アレクシス:そうだな、意見や批判はダイレクトに表現していると思う。ただし、それらは多くの場合、政治的に声高ではない、という。そうは言いつつ、今作の“The Evil That Men Do”では、かなり政治的にはっきり意見を述べているけれども……。僕たちの歌の歌詞のいくつかは、聴き手が読み取り理解するのにちょっと手間のかかるものもあるとはいえ、逆にもっとダイレクトなものもあるし、その両方のケースがあるんじゃないかな。とにかく曲次第で違うね。でもたしかに、僕個人としては、大仰な政治的声明を打ち出そうとすることを楽しいとは思わないね。政治ってものは、自分の音楽にはほとんど入り込んでこない物事だ、そう感じる。ジョーの方なんじゃないかな、音楽にもうちょっと政治が入ってくるのは? 僕はお説教めいた、人びとに教えを垂れるような表現の仕方をやるよりも、もっと、あくまでパーソナルな視点から話をしようとしている。
■そもそも今作『Freakout/Release』を制作する上でのいちばんモチベーションはなんだったのでしょうか?
アレクシス:まあ、僕たちはかなり長いこと、全員でそろって一緒になにかに取り組むことができなかったわけだよね。僕はその間もソロ・レコード(『Silence』/2021)を作ったとはいえ、あの作品では本当に、リアルタイムでのコラボレーション、他のプレイヤーに来てもらい自分と一緒に音を出すという作業を含めることができなかった。ロックダウン中に作った作品だったからね。
だからたぶん、ホット・チップのレコードを作る段になった頃までには、僕たち5人が同じ空間に一緒に集まるのが可能になったし、とにかくなにかエキサイティングなものを作りたい、全員で一緒にジャムり、僕たちが音楽を演るのを楽しんでいる、聴き手にもそれが伝わるようなものを作りたいと思ったんだろうね。
それ以外の点で言えば、僕たちはある種の生々しい、パンキーなエネルギーを音楽に持ち込むことにも興味を抱いていたと思うけれども、結果的に、それほどパンクっぽい要素は残らなかったね。ごく一部、たとえば“Freakuout/Release”には、いわゆる「ロック」っぽい感触があるとはいえ……。僕たちはディストーションにも関心があったとはいえ、レコードが完成する頃までには、制作当初に考えていたそうした事柄のいくつかは抜け落ちていった、というのかな。だから、とてもディストーションの効いたピアノ・パートを用いたトラックがひとつあって、“Freakout/Release”もあり、また“Down”でもディストーションは使ったし、それらの楽曲を繋げてまとめる要素はあったものの、最終的にそのディストーションのかかったピアノを使った曲はアルバムから落とすことになった。ゆえにその面、ディストーションの哲学というか、ディストーションに対して僕たちの抱いていた関心、という面は伝わりにくくなったね。
うん……だから、僕たちには「これ」といったしっかりした計画はなかったんだ。とにかく、再び全員で一緒に音楽を作れることになってワクワクしていただけだし、それ以外で言えば、ビースティ・ボーイズのあの曲、“Sabotage”だけど、僕たちはあれをライヴでよくプレイしているし、どうすればあのエネルギーの一部を自分たちの音楽のなかにも取り込めるだろう、ということを考えていた。
通訳:あなたたちがライヴで“Sabotage”をカヴァーするのを聴くのは、ほんと楽しいです。すごく楽しそうに演奏しているのがありありと分かるので。
アレクシス:うん、そうだよね。

多くの人間にとって本当にきつい時期だったし、いまだにそれは続いている。そのせいで職を失った者もいるし、久しぶりに対人関係にさらされ、社交面でどう振る舞えばいいかの自信を無くした人だっていると思う。
斉藤:ホット・チップのアルバムを完成とするにあたって、最低限守っている規範意識、あるいは自分たちなりの基準のようなものはありますか?
アレクシス:フム、自分たちにはそんなに多くの規範/ルールみたいなものはないと思う。ただ、今作に関して言えば、たぶん1曲を除いて、作った曲のすべてはまずまずダンサブル、あるいはファンキィと呼べるものだったんじゃないかな。スローで静かな、全体のノリから浮いている曲は1曲だけだったってことだし、それはこのレコードに収録しないことになったんだ、バンドの他の面々はあの曲は今作の楽曲群にそぐわないと感じていたから。
ただ、僕たちはとにかく、自分たちにとって「ベストな曲だ」と感じられるものを選んでいこうとしているだけだ。僕たちの作る音楽は相当に折衷的だし。最近の僕は、昔よく聴いていたバンドに立ち返っていてね。たぶん自分は20 年以上聴いていなかったバンドだと思うけど、ウィーンを。
通訳:おお、ウィーンですか(笑)!
アレクシス:(苦笑)うん、彼らの作品を聴き返していたんだけど——
通訳:笑ってしまってすみません、意外だったので、つい。でも私もウィーンは好きです。
アレクシス:僕もだよ! でまあ、いまの自分がああしてウィーンの音楽を聴き返しているうちに、彼らのレコードってどれだけ折衷的で混ぜこぜかを思い出したんだ。彼らって、サウンド面で言えば、1枚のレコードのなかで別のバンドが20組くらいプレイしてるって感じじゃない?
通訳:(笑)ええ。
アレクシス:で、彼らはホット・チップの初期にかなり影響が大きかった存在だったことを思うと、ってことは僕たちも常にこの、幅広いスタイルの選択肢をもつことが許される地点にいたんじゃないか? と。だから、ひとつの曲から次の曲へ、そこでガラっと変わっても構わないわけ。
■今回は自分たちで設計したスタジオでの録音で、あなた自身も完成度には満足していると思います。アルバム全体には、ある種の暗さが通底しているように思えるのですが。“The Evil That Men Do”やポップ・ソングである“Guilty”のような曲にも、もちろん最後のじつに印象的な“Out Of My Depth”にも。
アレクシス:そうだな……アルバム曲のなかでも、たぶんもっともシリアスに響くんじゃないかと僕が思う歌詞――っていうか、コーラスと曲名がいちばん重そうに聞こえるのは“The Evil That Men Do”だと思うけど、あれはジョーが書いた言葉なんだ。だから、それは僕には説明できないとはいえ、彼がああいう声明を打ち出す必要性を感じていたのは、僕にも見えた。だから、この社会における男たちの振る舞いについて、彼らは自分たちの行動にどんな責任を負っているか、そして僕たち誰もが自らの振る舞いにどう責任を負っているか、その点についてジョーは何か言わずにいられなかった、と。彼があの曲で述べている声明はそれ、我々はみんな、なんらかの償いをしなくてはいけないってことだろうし……これまでずっと続いてきたひどい振る舞いの数々、そしてそれらが他の人びとにどんな影響をもたらしてきたか、そこに対する一種の「気づき」が必要なんじゃないかな。
通訳:なるほど。
アレクシス:そうは言っても、これはなにも、「男性的な振る舞い」だけがネガティヴなものだ、そう言っているわけではないんだよ。ただ、多くの破壊的な行為やネガな振る舞いの数々、それらはなるほどたしかに男性的なもののように思える、そう、かなり主張はしやすいよね? というわけで、あの曲はその点について歌っているし、この時点で——だから、イギリス内ではいろんな物事が植民地主義を基盤に築かれてきたわけで、その事実が社会全体から疑問を浴びはじめている、そういういまの時期を認識している曲なんだと思う。要するにブリテンの土台は、この「植民地主義」ってものの上に成り立っているわけだし、そこでジョーは、「その点を我々は認識しなくちゃいけない」って言っているっていう。そうやって、思うに彼は、一からやり直そう、これまで続いてきた実にネガで、破壊的で、人種差別で、暴力的な振る舞いの数々から教訓を学ぼうじゃないか、そう言っているんじゃないかな。
で、君の挙げた曲のなかで、僕が歌詞面でもっと多く貢献したもので言えば、あれらはとにかく……今回のアルバムを作っていた間に僕が感じていたあれこれに関して、もしくは自分の周辺にいる人びとが困難な時期を潜っていた姿を観察し描いたもの、そのどちらかじゃないかと思う。だから、彼らが体験し感じていたことを表現しようとした、というか……いや、どちらかではなくて、その両方だな、僕自身が感じていたパーソナルなこと、そして僕の周りの愛する、大事な人びとが状況に悪戦苦闘していた、その両方について歌っている。というのも多くの人間にとって本当にきつい時期だったし、いまだにそれは続いている。いやだから、なにもかもをいったん一時停止せざるを得なかったわけで、その余波/反動はやっぱり大きいよ。そのせいで職を失った者もいるし、それだけじゃなく、たとえばここしばらく隠遁者めいた暮らしを送ってきたせいで、久しぶりに対人関係にさらされ、社交面でどう振る舞えばいいかの自信を無くした人だっていると思う。そうした多くのもろもろが合わさって、物事は2年前以来困難なものになっている、と。だからだと思う、今回のアルバムでは君が言ったような、やや暗いテーマがあるのは。
だけど、そうは言いつつ“Out Of My Depth”のような曲は、とくにいまに限らず、僕のこれまでの人生のどの時点で生まれてもおかしくないものだと思う。あの曲は……物事が自分の思うようにいかないと感じる、あるいは自分にはコントロールできないと思うときのことを、「深みからなんとか泳いで水面に出る(swimming out of your depth)」というメタファーを使って表現している。要するに、ネガティヴな側面にこだわってグズついているのではなく、その状況から自分を引っ張り出す手段をなんとかして見つけていかなくちゃならないんだよ、と。そういう、一種のモチベーション高揚っぽい感情があるし、その感覚はいまに限らず、どの時期でも通用するものだと思う。
■UKには、OMDやウルトラヴォックス、ABCやヒューマン・リーグ、ニュー・オーダーやペット・ショップ・ボーイズなど、素晴らしい楽曲と言葉をもったシンセポップ・バンドが、ホット・チップ以前にいくつも出てきています。こうした歴代のUKバンドのなかで、あなたがとくに共感しているバンドがあったらぜひ教えてください。
アレクシス:ニュー・オーダー、ヒューマン・リーグ、それにデペッシュ・モードだね。
通訳:ああ、デペッシュもですよね、なるほど。
アレクシス:うん。でも……(軽くため息をつきつつ)いま名前の挙がった連中以外にも、グレイトな音楽を作ったシンセポップ・バンドはほかにもいると思うんだ、たとえばユーリズミックスとかは僕も大好きだし。ただ……いま言われたようなバンドは、まあ、これはちょっとおかしな話に聞こえるかもしれないけど、彼らの作ったレコードは——もちろんそれぞれファンタスティックな作品だとはいえ——僕自身にとっては、そのほかにもっと大切なレコードがある、という存在なんだよね。だからまあ、彼ら(英シンセポップ勢)の作品はホット・チップというバンドの基盤を成す作品群ではない、っていうのかな。僕たちが目指しているサウンドは必ずしもそれらではない、と。おそらく、僕たちがその手のバンドの音楽をいくつか聴くようになったのは、もっと最近の話じゃないかと思う。
いや、もちろんメンバーによって差はあるし、たぶんオーウェン(・クラーク)は、そういったバンド、OMDの音楽なんかには長く親しんできただろうね。でも、僕からすれば、いま名前の出たバンドのなかでよく知っていると言えるのはニュー・オーダーだけで、彼らの音楽は若い頃から本当によく聴いてきた。で、ヒューマン・リーグに関しては、そうだなぁ、15年くらい前に初めて少し聴き始めたし、アルバムまでは細かく知らないんだ。シングルをいくつか知っているくらいで、それらのシングルは素晴らしいとはいえ、自分にヒューマン・リーグについて詳しい知識があるとは、お世辞にも言えない。ABCはほんと、ラジオでかかる有名な曲以外は知らないし……ああ、それにスクリッティ・ポリッティ、彼らも僕にとってかなり重要な存在だと思う。でも、それらUKのシンセポップ系バンド以上に、僕にとって大事なのは——ソウル・ミュージックだと思う。たとえばスティーヴィー・ワンダーやカーティス・メイフィールド、マーヴィン・ゲイ。それにヒップホップ、プリンスのレコード、そしてUSのインディペンデントなローファイ系の音楽、それらの方がおそらく、僕個人の音楽の趣味という意味では、もっと大事だろうね。
ここ何年かTVドラマを観ていて「頼っていいんだよ」というセリフを何度か耳にした(いつ、どのドラマで誰のセリフ?と詰め寄られるとそこで会話は終わりです)。ドラマだけでなく社会的弱者を扱った報道番組でもそれなりに使われていたかもしれない。社会的に孤立した人たちが立て続けに放火事件や無差別の殺傷事件を引き起こしたからだろう、弱者の孤立はめぐりめぐって社会のためにならないという考え方が広がり、そうした人たちに「不審者」というレッテルを貼って終わりではなくなったことが背景をなしていると思われる。「頼っていいんだよ」というフレーズを繰り返し聞いていると、04年に幹事長時代の安倍晋三が国民に刷り込んだ「自己責任」というコンセプトが日本中に根を張り、その呪縛から少しでも逃れようとして列島全体がもがいているような錯覚を覚えてしまう(同じ年に派遣法改正があり、その2年後に公安調査庁の監視対象から統一教会を外したことが絡み合い、めぐりめぐって安倍銃撃事件につながったとしたら世話はないという気もするけれど)。「頼っていい」どころか6年ぶりとなるソロ7作目『Renaissance』のオープニングでクイーン・Bことビヨンセは「I didn’t want this power(わたしはこんなに強くなりたくなかった)」と歌う。ジェイ・Zのおかげでもないし、特別な足がかりがあったわけもなく自分はここまで来たと。そして、自分自身とその虚像をいささか分裂的に描写し、本来の自分はピューリタン的で、スポットライトを浴びる「あの女」は「アメリカ人らしくない」という告発めいたニュアンスを交えて歌詞は続いていく。この辺りから様子がおかしくなる。自分がスターになったのは自分がそれだけがんばってきたからだと歌ったかと思うと「彼らが自分をそうさせた」と疑問形で反転させ、どことなくアイデンティティ・クライシスを漂わせながら、「You know love is my weakness(人を愛してしまうことが自分の弱点だ)」とする部分では自分と虚像のどっちに立っているのかもわからないほど彼女の自我は混乱しているかに見える。“I’m That Girl”はそして、強くなった自分がキリスト教的な原罪を意識するフレーズで締めくくられる。そのために壁にかけられたバスキアの絵がはたき落とされ、そこだけを見ればクイーン・Bはまるで不審者である。この不可解な行動はレディ・ゴディヴァ(アメリカではゴダイヴァ)をモチーフとしたジャケット・デザインにもそのまま投影されている。11世紀のイギリスでゴディヴァ伯爵夫人は貧しい領民から容赦なく税金を取り立てる夫に「お前が裸になって町中を馬で回ることができれば税を下げる」と言われて実行に移したという伝説(史実ではない)を19世紀にジョン・コリアが描いた肖像画の構図を下敷きとしたもので、端的に言えば自分は富裕層だけれど、心は民衆と共にあるというアンビヴァレンツな感覚を視覚化したものといえる。アメリカで富裕層として生きる黒人の現在を描いたTVドラマ『Empire 成功の代償」と同じく、そうした葛藤がここでも繰り返されているのだろう。「I’m that girl(私があのビヨンセ)」「Don’t need drugs for some freak shit(盛り上がるのにドラッグはいらない)」「I don’t need no friends(友だちは必要)」と、クイーン・Bの立脚点はどうにも定まらず、もしかすると、いま、「頼っていいんだよ」という言葉を最も必要としているのはクイーン・Bかもという考えさえ頭をよぎっていく。
どれだけ社会の底辺にいて金も希望もないとしてもツイッターで罵詈雑言を吐き出すことによって保たれる平衡があるように、クイーン・Bには音楽があり、不安定な感情を平衡状態に戻す方法論は整えられている。パンデミック3部作の1枚目にあたり、エスケーピズムを扱ったという『Renaissance』で彼女は、そして、初めてハウス・ミュージックをその受け皿に選んでいる。クイーン・Bは元々、とんでもなく自我が強く、何を歌っても「私よ!」「私よ!」としか聞こえないシンガーだった。圧倒的なパワーに引き込まれる人もいただろうし、押し付けがましいと感じた人もいただろう。そんな彼女が少し柔らかくなったと僕が感じたのは13年にリリースされた5作目『Beyoncé』で、その次にリリースされた『Lemonade』の方が多くの人にアピールしたと思うけれど、『Beyoncé』の方が僕はなじみやすく、長く聴けるアルバムとなった。子どもが生まれたことが大きく影響したことは明らかで、テーマはフェミニズム、サウンドはヒップホップ・ソウルがメインと内省の要素が絶妙だったのかもしれない(個人の感想です)。BLMと交錯したことでパワーを増した『Lemonade』を脇にどけ、『Beyoncé』でトーン・ダウンした自己アピールをさらに後退させてみたらどうなるだろう。ヒップ・ホップや王道のロックが自己アピールを強く打ち出すのとは対照的に、どちらかと言えば没個性的で、みんなと場をシェアすることが喜びにつながるのがハウスであり、ディスコ・カルチャーである。『Renaissance』でハウス・ミュージックが選択された理由は自己主張を強めることよりも民衆と共にありたいというゴディヴァ夫人と同じような感覚が探り当てたものに近いものがあるからだろうか。先行シングルとなった“Break My Soul”ではマドンナ”Vogue”がサンプリングされ、アジーリア・バンクスを思わせるラップが随所で入ったり、“Energy”では♪ウラララ~とフージーズでおなじみテーナ・マリーのスキャットもインサートされたりするけれど、基本的にはアシッド・ハウス・ムーヴメントの先頭グループにいたラリー・ハードを思わせるカシャッ、カシャッというスネアをフィーチャーした曲が何曲も続いたあげく、最後にドナ・サマー“I Feel Love”を換骨した“Summer Renaissance”で締めくくられるという流れはそのままでディスコ~ハウスの歴史に身を置いているというステートメントになっている(それらを前提としたサンプリングやゲスト・ミュージシャンのリストだけでとんでもない量になるので詳細は省略)。『Renaissance』というタイトルは新型コロナを中世のペストに見立て、ロックダウンによって失われた人間性を回復するという意味を持たせているらしく、それは同時にニーナ・シモンやアレサ・フランクリンが苦渋を歌に込めていた時代を中世にたとえ、ディスコ以降に女性シンガーたちが喜びをストレートに表現する時代が到来したという意味にも取れなくはない。「Voting out 45(45代は再選させない)」(*45代大統領=ドナルド・トランプ)などという歌詞も挟まったりするけれど、基本的に“I’m That Girl”以外は歌って踊ってセックス三昧みたいな歌詞ばかりで、ヴォーカルも実に優しく、たまたま今日の昼間はあいみょん、4s4ki、Miyunaと張り詰めた女性ヴォーカルばかり聴いたせいか、「1996年みたい(That’s that 1996)という歌詞通り、全体にノスタルジックな響きを強く感じるほど素直でハッピーかつアナクロなムードさえあった。90年代にちょっと流行ったボールルームを取り上げた“Move”や“Thique”はしかし、めちゃくちゃ新鮮で、ボールルームというよりは南アのゴムに聞こえる“Cozy”やダンスホールを変形させた“Alien Superstar”とともにフロントラインと結びつけているところはさすがというか。ゴディヴァ伯爵夫人の肖像画は俯いているけれど、それを真似たクイーン・Bはピシッと背筋を伸ばしている。ビヨンセが本当は欲しくなかったという力をパンデミックからの回復のために使うというのは実に真っ当だと思うし、何よりもハウス・ミュージックをやることが自分自身のセラピーになっているのではないだろうか。
(8月31日、追記)
なお、7月に先行配信が開始された『Renaissance』の11曲目“HEATED“に「Spazzin’ on that ass, spaz on that ass(尻の上で震える)」という歌詞があり、この「spaz」という単語が手足に麻痺があったり、動作の鈍い人をからかう言葉として使用されることが多く、今年の6月にもリゾが“Grrrls”をリリースした際にも非難が殺到し、謝罪して歌詞を変更したばかり。ビヨンセも「意図的に使ったものではないが、歌詞を差し替える」と発表している。「spaz」はリッチー・ホウティンでおなじみ「Spastik(Spastic)」を縮めた言い方で、やはり「けいれん」という意味から俗語では「鈍臭いやつ」という侮蔑表現に転じている。 LAで10年代前半にJ・ポップをやっていたSpazzkidなどはわざと使っていたのだろう。
デビューしてからの3年間、ブラック・カントリー・ニューロードの活動の歴史は激動だった。ヴォーカルを担当していたメンバーの性的暴行が告発されたことによって前身バンド、ナーヴァス・コンディションズの解散が余儀なくされたとき、残ったメンバーのほとんどは再び集まりバンド活動を続けることを決意した。ステージの端でギターを弾いていたアイザック・ウッドの前にマイクが置かれ、ツイン・ドラムだったドラムは一台になり、サウス・ロンドン・シーンの新しいバンド、ブラック・カントリー・ニューロードはそんなふうにして姿を現した。喋るように唄うアイザック・ウッドのヴォーカルは鬼気迫るような迫力で、スリリングなポストパンクのサウンドと絡むそれは最初のライヴから何かとんでないことが起きていると感じさせ、ライヴを重ねるごとにその評価はどんどん高まっていった。熱を帯びるサウス・ロンドンのシーンのさなか、2020年にリリースされた1stアルバム『For the first time』はそんな狂気に充ちたライヴを続けていた時期を封じ込めたアルバムで、ファンもその熱を真っ向から受け止め、より一層に大きな評判を呼んだ。次に何が起きるのかわからないというスリルがそこに存在し、もしかしたらいま、この瞬間こそが歴史に残るような瞬間になるのではないかと小さな世界の中でそう大げさに思わせるようなドキドキと期待感が確かにそこに存在していたのだ。
そしてパンデミックがあった。2022年2月に発表された2ndアルバム『Ants From Up There』はライヴの熱狂を受けて制作された1stアルバムと打って変わって、観客のいない彼ら7人の間で作られたアルバムだった。ワイト島での3週間に渡った共同生活の中でレコーディングされた2ndアルバムは危険なポストパンクの匂いが消え柔らかくノスタルジックに響く、まるで違ったバンドになったみたいな新しいブラック・カントリー・ニューロードの姿がそこにあった。
だがこれらの曲が観客のもとに届けられるツアーがおこなわれることはなかった。2ndアルバムがリリースされる直前にヴォーカル/ギターのアイザック・ウッドがバンドを脱退するという発表があったのだ。「精神的な問題で、これ以上ステージに立つことは難しい」。Facebook上でそんなメッセージを受け取ったバンドは彼の意思を尊重した。そして長い話し合いの末に、残された6人のメンバーはこの活動を継続することを決めた。予定されていたツアーをキャンセルし、その後に出るライヴでは1stアルバムと2ndアルバムの曲は演奏しない。誰も見たことのない、新しいブラック・カントリー・ニューロードの姿で再びスタートを切ると彼らは決めたのだ。
ここにあるのはリアルタイムのドラマだ。その判断がどのような結果を生んだのか、それをいまの時点で考えるのは早すぎる。だが後から結果を見ただけではわからない、その過程にだけ存在する特別な何かがあるのだ(それはこれまでのBC,NRの活動が証明していることでもある)。6人でバンドを続けるという選択、アイザックひとりが担当していたヴォーカルを分け、新たに作った曲、新たな姿のバンドでこの夏のライヴに彼らは臨んだ。フジロックで初来日を果たしたブラック・カントリー・ニューロードのドラム、チャーリー・ウェインとキーボードのメイ・カーショウのふたりにバンドのこれまでと、そしてこれからについて話を聞いた。

向かって左がチャーリー・ウェイン(ドラム)、右がメイ・カーショウ(キーボード)
ロンドンのシーンのトレンドっていうのは僕らよりもうちょっと若いとか、あるいはもうちょっと多くロンドンでプレイしているバンドたちによって作られているって思っている(ウェイン)
■初来日のフジロックはどんな印象でしたか?
カーショウ:凄く良かったと思う。日本でプレイしたかったというのが叶ったのも良かったし、やってみてもっとプレイしたいってふうにも思って。何よりお客さんがリスペクトしてくれているっていうか曲をしっかり聞いてくれているみたいな感じがして嬉しかったな。他のフェスだとけっこう隣の人と話しながらだったりするんだけど全然そんなことなくて。
■今回、プレイする曲はすべて新曲ということで、かなり特殊で難しいシチュエーションだったと思いますが、その点はどうでしたか?
ウェイン:曲作りってことでいうと、いまもってありとあらゆるものを集めているって感じなんだ。1月にブッキング・エージェントから夏のフェスティヴァルの話が来て、新曲を持っていくこともできるって話になって、それで僕たちはそうすることを選んで曲を書きはじめた。でも、全部を新曲にするっていうのは本当に難しかったのは確かで、明らかにいまも発展途上。まだ曲は完成していないんだけど、でもその期間は楽しかったしエキサイティングな時間でもあったと思うよ。期限までに曲をプレイ可能な状態にしなきゃいけないってプレッシャーから来るストレスも同時にあったんだけどね。でも凄くエキサイティングだった。
■現在はタイラー(・ハイド)とメイ(・カーショウ)とルイス(・エヴァンス)の3人がそれぞれヴォーカルを担当していますよね? その3人がヴォーカルを担当することになった経緯を教えてください。
カーショウ:最初はみんなで唄うってプランもあって。っていうのは誰かひとりがメインでヴォーカルを担当するとその人のプレッシャーが凄いことになると思ったからで。みんな唄えるんだからそうしたらいいじゃないって。でもライヴまでの準備期間が4ヶ月しかなかったから、一から曲を作るんじゃなくてメンバーが個人で作っていた曲を膨らませる方向にシフトして。で、その曲はタイラーが持ってきたのもあればルイスや私が持ってきたのもあって、自然とそのまま元の曲を作った人が唄うことになったって感じかな。
編集部:バンドにブレインみたいな人はいないんですか? 方向性を決めたりする。
カーショウ:ブレインはいないかな。みんなで決める感じで。
ウェイン:うん。そういう誰かひとりがいると違うんじゃないかってなっちゃうし、演奏してても楽しくなくなっちゃうかもしれないし。だからお互いのパートを尊重して任せる感じかな。
カーショウ:その分話し合いは凄くするよね。友好的な口論みたいな「ちょっとちょっと、ここさぁ~」みたいな感じで。
■今後も確たるメイン・ヴァーカルを決めないこのスタイルでやっていくのですか?
カーショウ:いまのところはこの形だけど、アルバムを作るときはどうなるかな?
ウェイン:いまはまだ全然アルバムの曲を書いていなくて、そのときになったら考えようって。でも歌詞を書いて頭に描いたコンセプトをそこに落とし込んで、それを複数人でやると感情的に分散してしまうような、一貫したスルーラインが見えない音楽になってしまう危険性があると思うんだ。それを避けるっていうのは今後凄く重要になってくる。

僕たちは結局、ある意味でバラバラになってしまったんだと思う。忙しくなっていろんなことをやらなきゃいけなくなって、妥協しなきゃいけないこともあって。(ウェイン)
■まだアルバムの曲作りをしていないとのことで難しい質問になってしまうかもしれませんが、これから3rdアルバムはどんな方向性に進んでいくと思いますか。
ウェイン:いいアルバムになる方向(笑)。
カーショウ:これから作るから探していかなきゃね。
ウェイン:けど全然違う感じになると思う。1stアルバムと2ndアルバムも全然違ったものになったし。2ndアルバムはそのときの状況もあったけど1stとは違うものを作りたいっていうのが出発点だったから。だから今度のアルバムもいろんな理由で全然違う感じになると思う。でも聞いていて楽しめなかったりプレイして良くないって僕らが信じられないようなアルバムを出す気はないから……うん、だからやっぱり良いアルバムになるな(笑)。
■(配信で)ライヴを見ていて思ったのですが、いまはフルートを多用していますよね? 2ndアルバムでも使っていましたけどより比率があがったような印象で。
ウェイン:実のところルイスはもともとフルート奏者なんだよね。
カーショウ:そうそう。だから曲の雰囲気に合うって彼が思ったから使っているって感じじゃない?
■そのフルートが合うような感じに2ndアルバムで曲が変わったというのはなぜだったのでしょうか?
カーショウ:それはなんだろう? そのときに聞いている音楽の影響だったのかな。あとはロックダウンのときに感じたことの影響とか。
ウェイン:うん、いろいろな状況の影響はあるよ。1stアルバムの曲を書いてたときはライヴをいっぱいやってた時期で、尖ってて奇妙で魅力的な、グルーヴィな音楽を作りたかったんだ。でも2ndアルバムには恐れる観客はいなくて、代わりにみんなで集まって集中してアルバムを作れるって状況だった。その点についてはとてもラッキーだと思ってて。同じようなアルバムを作るのはつまらないって思いもあったし、こうやってみんなで集まって音楽を作れるってことは幸せだって感じるような、そういう感情になったってことが2ndアルバムの曲作りにも反映されたんだと思う。
編集部:2ndアルバムから似た雰囲気を感じたのですが、70年代のプログレッシヴ・ロック・バンド、ヴァン・ダー・グラフ・ジェネレーターは聴いたことがありますか?
ウェイン:聞いたことはあるけど影響を受けたかっていわれるとどうだろう? でもメンバーの誰かが聞いて影響を受けていてそれが反映されたっていうのはあるかもしれない。僕らみんな全然違う音楽から影響を受けていて、それがこのバンドをユニークにうまく機能させているってところがあるから。
[[SplitPage]]でも同時に全員これからも一緒にやっていこうっていう気持ちも強く持っていたと思う。(カーショウ)
■ちなみにいまはどんなバンドがお気に入りなんですか?
カーショウ:ジョアンナ・ニューサムが好き。
■あぁそれはライヴを見て感じました。メイのヴォーカルの曲はそんな感じがするなって。
カーショウ:本当? 良かった。
■そのことについて聞きたいのですが、メイのヴォーカルの曲で “The Boy” という曲がありますよね? チャプターがあって寓話を元にした劇みたいで、いままでのBC,NRの曲とは全然違う感じの印象の曲で。この曲はいつ頃作られたのですか?
カーショウ:いつだったかな? 今年のはじめの方? 曲のベースをそのくらいの時期に作って。バンドに持っていく前はもっとフォークっぽかったんだよね。ピアノで作ってて、そこからまたいろいろと変わっていったんだけど。
■じゃあまさにジョアンナ・ニューサムにハマってた頃?
カーショウ:(日本語で)はい。そうです。ふふっ。
■それこそこの曲はフルートに合うような音楽で。 最近UKのバンドでフルートを使っている人たちが増えてきている印象があって。ルイスがフルートを吹いてるマーサ・スカイ・マーフィーとかイーサン・P・フリンとか、あとはブルー・ベンディとか。その流れに沿っている部分もあるのかなと感じたのですが、いかがでしょう? BC,NRの1stアルバムが出た頃と2ndアルバムが出た頃ではロンドンのシーンの空気もだいぶ変わったんじゃないかと思うのですが。
ウェイン:うん。でも僕らはロンドンのミュージック・シーンのバンドだとは思うけど、でもそれに答えるのに適したチームとは言えないんじゃないかって。っていうのはロンドンのシーンのトレンドっていうのは僕らよりもうちょっと若いとか、あるいはもうちょっと多くロンドンでプレイしているバンドたちによって作られているって思っているからで。僕たちもロンドンでプレイするのは本当に大好きなんだけど、でもいまは充分にロンドンでプレイできてるとは言えなくて。ロンドンのバンドは僕たちに影響を与えてるし、僕たちもその一翼を担っているって思ってもいるけれど、ロンドンのシーンがどうかって説明するのはちょっと難しいかな。それは中にいるせいで俯瞰して全体像をとらえるのが難しいっていうのもあるのかもしれないけど。
■ありがとうございます。それでこれは何度も聞かれてうんざりかもしれませんが、アイザックがバンドを脱退するとわかったときに解散せずにこのままバンドを続けると決断したときの状況を教えていただける嬉しいです。
カーショウ:とても長い話し合いがあって……名前を変えて新しいバンドとしてスタートした方がプレッシャーが少ないんじゃないか、そうした方が比べられることもないんじゃないかって、私とジョージア(・エラリー)はそんなふうに考えてた。でも他のみんなはそうじゃなくて。みんなで決めて、もちろんいまは私もこれで良かったって思っているんだけど。
ウェイン:僕たちは結局、ある意味でバラバラになってしまったんだと思う。忙しくなっていろんなことをやらなきゃいけなくなって、妥協しなきゃいけないこともあって。
カーショウ:でも同時に全員これからも一緒にやっていこうっていう気持ちも強く持っていたと思う。
ウェイン:うん、どちらにしても間違いなく僕たちは一緒にプレイし続けただろうね。でも新しいバンドとしてスタートしたとしても比較されることは避けられなかった。名前を変えなかったからより直接的に比較されるわけだけど。でもなんていうか僕たちはまったく違うバンドじゃなくて、音楽的にも同じような世界観を持ち続けているバンドで……。難しいけど。でも名前を変えないってことに決めて、いまはそれがうまく機能していてその点では嬉しく思っているんだ。

明確なものとかパーソナルなものとか具体的な歌詞は書きたくなくて、それで自分が出てくるような話じゃなくて、ハリネズミとかモグラとか動物が出てくるストーリーを書いたんだと思う。(カーショウ)
■1stアルバムのインタヴューでルイスが「音楽よりも友情の方が大切さ」と言っていてそれが印象に残っています。ライヴの最初に披露された “Up Song” でメンバー6人全員が声を合わせて「BC,NR friends forever」と唄っていて、ある種の決意表明みたいにも思えたのですが、この部分を全員で唄うというのはどういう意図があったのですか?
ウェイン:ルイスはそんなこと言ってたんだ? でも僕だったら「音楽よりもお金の方が重要だ」って言うな(笑)。もちろん冗談だけど。
カーショウ:「BC,NR friends forever」っていうのもはじめはジョークだったんだよね。最初にやる曲としてちょっと面白いかなって。
ウェイン:結構こういうのってあるんだよね。ジョークからはじまった音楽的エフェクトが長く続けていくうちに音楽的にも感情的にも意味を持っていくみたいな。ほんと馬鹿なんだけどスタジオで練習しているときに誰かがやりはじめて。で、いざそれをステージに持ってくとみんな「イェー!」って盛り上がってくれて。最初にこれを披露したのはブライトンだったんだけど、初めて聞いたのにみんな「あぁああっー」って感じで超盛り上がってくれて、それでこれ凄いクールじゃんみたいな。
カーショウ:最初はその部分違ったよね? あれ? なんだっけBC,NRの後? 「BC,NR ~」(歌い出すメイ)……ダメ思い出せない。でもとにかく最初は全然違う文脈だった。
ウェイン:僕らはしばしば感情をハイジャックされるシチュエーションにおちいるんだ。
カーショウ:“Up Song” はもともとはタイラーが作った曲で歌詞もタイラーが書いたんだけど、そこにみんなで言葉を付け加える感じで。
ウェイン:そうそう。曲の構成を考えるとき、最初のラインが凄く響いたんだ。それでここのヴォーカル・ブレークに何か追加しようとして……アーケイド・ファイアに “Neighborhood #3 (Power Out)” って曲があるよね? 1stアルバムの。その曲に「we find a way!」って叫ぶ小さなセクションがあるんだけど、そんな感じにしたかったんだ。
■歌詞でいうと、メイの “The Boy” はどんなところから歌詞が出てきたんですか? 何かインスピレーションのもとになったようなお話があったんですか?
カーショウ:具体的にはないな。(日本語で)わかんない。なんだろう、頭の中にあったものを出したって感じだったから。でもとにかくこの曲を書いたときは明確なものとかパーソナルなものとか具体的な歌詞は書きたくなくて、それで自分が出てくるような話じゃなくて、ハリネズミとかモグラとか動物が出てくるストーリーを書いたんだと思う。
編集部:ちなみにここ(取材場所)は日本のすばらしいレコード店のひとつで、BIG LOVEというお店ですが、ふだん音楽を聴くときは配信やストリーミング、デジタルで聞くことが多いですか?
カーショウ:Spotifyで聞くことが多いかな。アーティストにとっては良くないのかもしれないけど、それで聞いちゃう。YouTubeでも聞くし。ジョアンナ・ニューサムはストリーミングで配信してないから、それは買って聞くみたいな。そんな感じ。
ウェイン:僕もそうだな。アーティストに支払われる金額が少ないからSpotifyで聞くのはあんまりよくないのかもしれないって思ってはいるんだけど。でもルイスはプレイヤーを持っているから、ルイスの家に行ってみんなでレコードを聞くこともあるよ。みんなで聞くときはそっちの方が良いし。でもほとんどデジタルだなぁ。
編集部:自分たちはアナログ盤を出していて複雑な気持ちになりません?
カーショウ:Spotifyがもっとお金を払ってくれたら自分たちもレコード買えるのに。(日本語で)冗談。
■最後にここまでの活動を振り返るという意味で、1stと2ndアルバムの曲でそれぞれ好きな曲を教えてもらえますか?
カーショウ:1stは演奏するのが楽しい曲が多いよね。
ウェイン:うん楽しかった。
カーショウ:でも “Track X” は別。あの曲はちょっと演奏するのがストレスだった。私とルイスとアイザックがそれぞれ違うビートで演奏するから、あの人たちの演奏を聞かないようにしようってするのが本当に大変で。好きなのは “Science Fair”、2ndアルバムの曲だと “Haldern” が好きだな。
ウェイン:そうだな、僕のお気に入りは……ちょっと定番過ぎて言うの恥ずかしいんだけど、でも1stだとやっぱり “Sunglasses” が好きだな。で、2ndだと “Basketball Shoes”(笑)。
カーショウ:ほんと定番(笑)。
ウェイン:うん(笑)。でも、本当に曲として素晴らしいんだよ!


