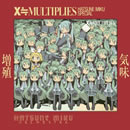 HMOとかの中の人。(PAw Laboratory.) - 増殖気味 X≒MULTIPLIES U/M/A/A Inc. |
「初音ミク」の開発者である佐々木渉氏は、発売当初から現在にいたるまで、「生みの親」としてさまざまな場で発言を求められてきた。功績ある開発者として、ビジネスの開拓者として、日本の新しいカルチャーの最前線を拓いた証言者として。しかしその一方で、初音ミクという複雑で巨大な遊び場(=プラットフォーム)が巻き込むありとあらゆる事象については、おおむね静観の姿勢をとっているようだ。開発者の立場から、多くの人が楽しむその遊び場を壊すようなことがあってはならない......氏はおそらくはそのような思いから、日々生まれてくるおびただしい初音ミクと、おびただしいコミュニケーションのありようとを見守っているのではないだろうか。初期『ele-king』0号からの読者であったというディープな音楽体験を持ち、アンダーグラウンド・カルチャーへの理解も人一倍である佐々木氏ならではの哲学が、そこには存在しているように思われる。
今回、そんな佐々木氏と、ele-kingの「生みの親」、野田努との対談を収録することができた。テクノの話題にはじまる音楽談義だが、初音ミクの少女性に向けた野田の素朴な疑問や、ボーカロイド以前のポップス史において、「声」の変調がいかなる意味を持ってきたのか、ボカロ文化を世界はどのように受け入れるのか、といった広い話題を含むトークになっている。前・後編に分けてお送りしましょう!
すべてはテクノにはじまる
エイフェックス・ツインの音楽もライターさんの書いてることも、「なんで、どうしてこうなっちゃったんだろう!?」みたいなことが多かったですよね。「夢のなかで音楽が浮かんで......」「彼はDJセットにやかんを持ち込んで......」とか(笑)。(佐々木)
あの頃は、作家の優位性みたいなものへの否定もありましたからね。いちど作品を投げてしまったら、どう解釈されようがそれは受け手の自由であるという態度がいっきに広がった。(野田)
佐々木:僕が初めにテクノのCDを買ったのは中学生の頃で、『テクノ・バイブル』というY.M.O.のボックスセットだったんです。当時は電気グルーヴなどが人気だった頃で、先輩の影響もあってテクノをどんどん聴いてました。でも、個人的にはいきなり『ガーデン・オン・ザ・パーム』(ケン・イシイ)なんかにすっと入っていけたタイミングでもあって、アンビエント寄りのものを、「クラブ向けのテクノとは違うものなんだなあ」と思いながら聴いたりしていました。
野田:へー。
佐々木:札幌もクラブはけっこうあったので、プレシャスホールなんかには高校の頃から行ってました。音はほんとに好奇心にまかせて聴いてましたね。『ele-king』は0号から読ませていただいていたんですが、思春期の自分はエイフェックス・ツインとかの取り上げられ方にすごく刺激を受けました。彼の音楽もライターさんの書いてることも、「なんで、どうしてこうなっちゃったんだろう!?」みたいなことが多かったですよね。「夢のなかで音楽が浮かんで......」「彼はDJセットにやかんを持ち込んで......」とか(笑)。
野田:あははは(笑)!
佐々木:そういうおもしろい音楽をやっているほうへどんどん向かっていきました。当時はインターネットとかがなくて、試聴できるといったら地元のCD屋くらいで。でもそこは〈ソニーテクノ〉(※1994年、〈ワープ〉〈R&S〉〈ライジング・ハイ〉の3レーベルを中心にソニーが日本盤として発売、90年代のテクノ・ブームの土台となった)だけは聴けたんですよ。
野田:ああー、試聴自体がまだ定着してない時代ですよね。
佐々木:それで、休みの日とかはCD屋でずっと〈ソニーテクノ〉のCDを聴いてたりしました。
野田:素晴らしいですね。しかし、中学生でいきなり『ガーデン・オン・ザ・パーム』だとハードルが高くないですか?
佐々木:いえ、不思議な音楽だなあと思ったことのほうが強くて、カッコイイなってふうにすぐには思えなかったですね。テクノって歌詞もないし、音像だけ感じながら聴いていられるものだったから、ライターさんが書いたレヴューやインタヴューと照らし合わせてすごく妄想を膨らませられるものでした。その体験がすごく強かったので、ブラック・ドッグなんかも、インタヴューで言っているようなことと、彼の音楽とがすごくリンクしやすくて。
野田:ブラック・ドッグですかぁ。それは面白いですね。当時のテクノはロックのスター主義へのアンチテーゼというのがすごくあって、自分の正体を明かさないっていう匿名性のコンセプトがすごく新鮮でね。売れはじめた頃のエイフェックス・ツインもたくさんの名義を使い分けてましたね。後からあれもこれもエイフェックス・ツインだったという、リスナーに名前を覚えさせないという方向に走ってましたね(笑)。
で、ブラック・ドッグは、匿名性にかけてはとくにハードコアな連中でね、当時は『NME』が紹介したときも顔がぼけた写真しか載せなくて、まともにインタヴューも受けなかったんですよ。作家の優位性みたいなものへの否定もありましたからね。いちど作品を投げてしまったら、どう解釈されようがそれは受け手の自由であるという態度がいっきに広がった。作品は作り手のものであって、正しい解釈がひとつしかないというふうに限定されることをすごく忌避していた時代でしたよね。いまでもよく覚えているのは、『スパナーズ』で初めてブラック・ドッグがインタヴューを受けたときのことです。当時としては画期的な、チャット形式でのインタヴューをやったんですよ。姿は見せない、「<<......」という記号が入った、チャット形式のインタヴュー。彼らの発言はドットの荒いフォントで載って、写真はなし。1994年だったかな......、そんなものが『フェイス』というお洒落なスタイル・マガジンのカヴァー・ストーリーになったんです。
佐々木:アーティストが機材の向こう側にいる感覚というか。『グルーヴ』だったか、その頃の記事で、ブラックドッグが昔のPCのキーボードで顔を隠してるみたいな写真が載っていたんですが、それがすごく脳裏に残ってますね。知らない場所で作られた音楽というようなニュアンスもあったりしたし、その匿名性の問題にしろ、メイン・ストリームの考え方とちょっと違うところでやってるのかなと思ってました。......思ってたらプラッドとひとりのブラックドッグに分かれていきましたけども。
野田:じゃあ、もうほんとに〈ワープ〉っ子だったんですね。
佐々木:そうですね、ずっと聴いてきたので。『アーティフィシャル・インテリジェンス2』のボックスとかも買ったりして。
野田:『アーティフィシャル・インテリジェンス2』の映像を初めて観たときに、みんなで叫んでたもんね。その場に(渡辺)健吾とか佐藤大なんかもいたんですが、「すげー、これ!!」ってね! 低解像度のCGで、いま思うと大したものじゃないのに、ほんとにあのときはみんなで涙流しながら......、いや、本気で泣いてました(笑)。
佐々木:このあたりはほんとに、ショックでしたね。光沢感とザラザラした感じが混じっていて。当時はゲームでも『バーチャファイター』なんかが出ていたので、3Dポリゴンは見たことがあったと思うんですが、音楽のサイケデリックさと、映像と相俟ったときのサイケデリックさというのがやはりちょっと違っていて、すごく印象深く残っています。いま話していてもどんどん思い浮かんできますね。スピーディー・Jの"シンメトリー"って曲の動画がすごくやばくて。イルカが亜空間の中で気持ち悪い球体になってどんどん食べられていく、あれですね(笑)。やっぱり、こうしたショックを受けて、アンビエント的なものに接近するようになりましたね。それになかなかパーティに通うようなお金もなかったですし、家で聴けるアンビエントのような音楽の方へ向かうのは、必然だったかもしれません。ピート・ナムルックとか......
野田:ピート・ナムルックは先日亡くなられたんですよね。
佐々木:ああ、そうなんですか......。ファックスのアンビエントは良い意味で精神的にトラウマになりましたね人生観にも影響するくらいサイケデリックで最初は意味が分からなかった。音楽に取り残された感じがした。世界は広いなーと。あと、アンビエントは日本人の方もけっこういらっしゃったりという部分で、関心もありました。テツ・イノウエさんとか。
野田:うぅ、いま、よくその名前が出てきましたね! テツ・イノウエさん。それこそ『アンビエント・オタク』っていうアルバムを当時出してるんだよね、ピート・ナムルックといっしょに。だから先月、ピート・ナムルックが亡くなられたときに、コンタクト取りたいんだけど、テツ・イノエさんの連絡先がわからないか? って、ベルリンの知人からメールが来たんですけど......(もし、この記事を見て、ご存じの方がいたら編集部までご一報を)。
で、この「A.I.シリーズ」っていうのは、レイヴのムーヴメントがいちど殺伐としたものになった後のエレクトロニック・ミュージックだったわけです。100%クラブに存しないところで音楽的な自由度をどんどん上げていって、わけのわからない領域まで達してしまっているというものではありますからね。そういうなかで、アンビエントなものとか、ラウンジーなものとか、あるいはエクスペリメンタルなものとか、ハウスから離れてやたら多様化した時期でしたね。それ以前は非常にわかりやすくて、「ハウス・ミュージック」っていうひと括りですべてを語ることができたんですが、「A.I.シリーズ」のようなもののおかげでほんとにわけのわからない、ひと括りにできないものになっていきましたね。
佐々木:そうですよね。レッド・スナッパーとかも「ポストロックやミクスチャー」っていうような性格の音楽の先駆けだったかもしれないですね。
[[SplitPage]]札幌アンダーグラウンド・シーンが生んだ〈クリプトン・フューチャー・メディア〉
ファックスのアンビエントは良い意味で精神的にトラウマになりましたね人生観にも影響するくらいサイケデリックで最初は意味が分からなかった。音楽に取り残された感じがした。世界は広いなーと。(佐々木)
野田:それで、テクノを聴かれてて、ソフトウェアの開発というところへ行くわけですよね。それ以前に音楽を作ったりされていたんですか?
佐々木:そうですね、紆余曲折ありまして(笑)。僕はライナーを見るのもすごく好きで、ワゴン・クライストの『スロッビング・ポウチ』を買ったときに......
野田:最高ですよね。それ、ライナー誰だっけ?
佐々木:竹村延和さんですね。竹村さんは全然ワゴン・クライストの話を書いてなくて、はじめはハービー・ハンコックの"ウォーターメロン・マン"の話をずーっとしている。で、「これはなんでテクノの棚にあったんだ」みたいなことが書かれていて、最後は「とにかく自分のリミックスがすばらしいから聴くように」という話になっている(笑)。
野田:あははは(笑)!
佐々木:これは何なんだろう? って(笑)。それから竹村さんの音楽を聴くようになりました。『ele-king』でも竹村さんが表紙で載っていらっしゃったことがあると思いますけど、彼を知ったことがひとつのショックでしたね。アンビエント的なジャンルの広がり方をさらに極端に押し進めているような気がしました。武満徹さんからヒップホップやノイズまで参照されていて、音楽ってジャンルがないものなのだな、と。そこからフリー・ジャズみたいなものも聴くようになりましたし、当時で言えばデヴィッド・トゥープさんとかがボーダーレスに音楽を紹介していて、そうしたものの影響も受けました。あるいはサンプリング・ミュージックも、ブラックドッグを素朴に聴いていたころよりもっと概念的に聴くようになったし、ニューヨーク・アンダーグラウンドのDJスプーキーやデヴィッド・シェーとかにも手をのばすようになって。
そうしているうちに、札幌にもアートっぽい、フリー・インプロっぽい音楽をやっている人が何人かいたので、少し交流するようになりました。そういうクラスターのなかに、いまのクリプトン(・フューチャー・メディア)の社長の仲間や、当時の社員もいらっしゃったんです。彼は『スタジオ・ボイス』とか『美術手帖』とかが90年代前半にフォローしてたような、サイバー・パンクとかインターネットで世界が変わるとか、アルヴィン・トフラー以降のそういう思想的なものが大好きな方ですね。僕は最終的にそこに就職することになるわけなんです。音楽制作については、サウンドアートやノイズ・ミュージックのようなものに関わりながらやっていたことはあります。
野田:機材とかはもう自分でいじってたんですか?
佐々木:はい、もう、サンプラーを買って遊びました。カットアップ・コラージュをしてみたり。でも池田亮司さんのサインウェーブ主体に行く前のファースト『1000フラグメンツ』を聴いて、ああ、これはぜんぜん歯が立たない、こういう人がすでにいるんなら生半可にサンプラーをいじるのはナシだなと思って(笑)、そんなに長続きはしませんでしたね。
野田:ははは、なるほど。
初音ミク=DX-7 ?
思春期におけるディープな〈ワープ〉体験を語ってくれる佐々木氏。デトロイト・テクノなどへも傾倒するなかで、氏はアナログ・シンセの再評価の文脈に立ち会うことになる。初音ミクの開発については、そうしたアナログ・シンセの太くあたたかみのある音の流行に対する、わずかなカウンター意識もあったようだ。シンセサイザーとしてのミクの声=音、そのゼロ地点に企図されていたものとは、どのようなものだろうか。
札幌にもアートっぽい、フリー・インプロっぽい音楽をやっている人が何人かいたので、少し交流するようになりました。そういうクラスターのなかに、いまのクリプトン(・フューチャー・メディア)の社長の仲間や、当時の社員もいらっしゃったんです。(佐々木)
僕は、それでなぜ佐々木さんが「声」というものに向かっていったのかということに興味がありますね。(野田)
佐々木: 90年代中盤までは、汎用コンプレッサーが高くて......。たとえばヒップホップだとDBX-160だったりとか、すごく限られたもので音圧をある程度稼げる状況だったと思うんです。安物のコンプレッサーを入れたら逆に音がぐちゃぐちゃになっちゃったり、というような状況ですね。だから、そもそも音が太い機材というものが必要でした。現在においては、プラグイン・エフェクトによって、どんなに音が細かろうと、手を尽くせば太く見せることが可能です。でも当時はそういうわけにもいきませんでした。
たしか『テクノボン』を読ませていただいたときに、FMのシンセサイザーというものが、それまでのアナログのシンセサイザーに比べて、出音の傾向が違うという指摘があったと思います。そういう音が80年代のエレポップみたいなものへつながっていって、キラキラしたシンセの音が街にあふれていくなかで、逆にデトロイトやハウスの太いシンセの音というのは身体にも気持ちいいという実感があったと思うんです。
で、ボーカロイドについてなんですが、これはもともと音の位相が自然でないものなんです。サンプリングした音の波形と、声をのばすときに使う波形とが違う。そのふたつの音波形を合成するので、そこで本来の音が持っているきれいな位相が失われててしまう、という面があるんです。初期のソフト・シンセもそうですが、低音がすごく弱い。なのでいまでもベースに太い音を使いたければ、ムーグのアナログ・シンセを買うべきだというような話は相変わらず生きていますよね。初音ミクは、そういう条件でいうと、「声が華奢で高い」という傾向にしなければモコモコ、シャカシャカしてしまって形にならないということが、実験の段階でわかってきました。それで、音圧がなくて、細くて、ちょっと人間離れした声に行ったんです。
さて、これをどうやって演出して見せていこうか? 女の子のヴィジュアルを付けるとして、どんなふうにこの人間離れした声への理由づけをするか。そのときにDX-7が出てきたときの状況にちょっと似てるなと思ったんです。いままでのシンセサイザーでは、ツマミをいじって直感的に音を作ることができていたのが、DX-7ではパネルになり、アルゴリズムになり、操作がやたら面倒で、ベルの音みたいなのは簡単にできるけど、凝ったアンビエントみたいな音を出そうとすると、すごく大変な作業をしなければいけなくなる。初音ミクも、人間らしい声を出そうと思うとすごく難しくなってしまうけど、なんとなく人間じゃないような女の子の声となれば、簡単に出せる。そのへんの相似的な関係を重ね合わせようかなと思って、ヴィジュアルのモチーフとしてDX-7を使わせてもらえないかなということでヤマハさんに問い合わせて、「商標をつかわないのなら」と、了承をもらったんです。なので、カウンターといっても、そういった事情のつじつま合わせという意味合いのほうが強いかもしれませんね。
野田:それも面白い話ですね。しかも、このところ80年代リヴァイヴァルが続いているから、若い世代のあいだではDX-7みたいな音がまたぶり返しているんですよね。ただ、いまではデジタルもアナログも選択肢のひとつというか、機材と音楽の関係性って、90年代以降は相対的な関係性なんですよね。たとえばヒューマン・リーグの時代って、まだシンセなんて高いから、若い奴は誰も買えないわけですよね。だから学生がシンセを手作りしている。で、ローランド社がエレキ・ギターを買えるような価格にして販売したものが、TRシリーズとかね。それがDX-7以降、とくにアシッド・ハウスやデトロイト・テクノ以降は生産中止だったこともあって値上がりしちゃったり。オウテカなんて初期の頃はエンソニックですよね。3枚めくらいからマックス側に寄っていく。そうするとフォロワーたちもみんなマックス側に寄っていく。するとオウテカはまたアナログに戻すというようなことになる。最近でも敢えてパソコンを使わない人と、敢えて使う人と両方いるし......。
僕は、それでなぜ佐々木さんが「声」というものに向かっていったのかということに興味がありますね。
機械と声の呪われた歴史
初音ミクも、人間らしい声を出そうと思うと難しいけど、なんとなく人間じゃないような女の子の声となれば、簡単に出せる。そのへんの相似的な関係を重ね合わせようかなと思って、ヴィジュアルのモチーフとしてDX-7を使わせてもらえないかなと思いました。(佐々木)
佐々木:われわれの会社はそもそもサンプル・ネタを販売する会社で、たとえばスタジオで録ってきたドラムのブレイクなんかをライセンス・フリーで売っているわけなんですが、そういうなかで、声の音ネタというのはかなり需要があったんです。「アー」とか「ハ~」とかもしくはダンス・ミュージック用の「ヘイ!」とか(笑)。
野田:へえー。『remix』をやっていた頃、けっこう、送っていただいているんですよね。初音ミクが出る数年前のことでしたが、たしか何度か紹介させてもらったことがあったと思うんですけど。当時は、札幌からなんでだろう? って感じでしたね(笑)。
佐々木:ビジネス的に、いちばん売れる音ネタでしたね。
野田:なるほど。サンプラーを買ってまず友だちや彼女に自慢するものといえば、声のサンプリングじゃないですか。「えー」とか、いろんな音階で鳴らして「すごいでしょう」って(笑)。声というのは素材は、音の合成機械にとってすごく何かあると思うんです。今年ele-kingでも重要作として挙げているメデリン・マーキーというシカゴの女の子の作品があるんですが、特徴としてひとつ挙げられるのはヴォコーダーを使ているということなんですね。ヴォコーダーを使ったアンビエントという感じですね。
ヴォコーダーの歴史がまた面白くて、あれは戦争中にアメリカのペンタゴンが音声を暗号化するために作り出した音声合成装置なんですよね。そのあたりのことは、今年出た『エレクトロ・ヴォイス』という本に詳しいんですが、広島に原爆を落としたりとか、ドイツへの攻撃の指令とかは酷いことは全部ヴォコーダーを通している(笑)。だからある意味、「機械で音声を変える」ということは人間の歴史のなかで非常に呪われた歴史を持っているわけです。ケネディ大統領なんかも盗聴をされたりするわけですけれども、その陰にもつねにヴォコーダーの存在がある。そういう起源の一方で、クラフトワークがヴォコーダーで歌うということがはじまるんですよね。
クラフトワークの前にも大衆音楽において機械っぽい声が使用されるという例はいくつかあって、ウォルター・カルロスが『時計じかけのオレンジ』のサントラでベートーベンの『第九』とかをやるじゃないですか。あれでロボ声を使っているんですよ。偉大なるベートーベンの交響曲をロボ声でやったということが、当時は大人からすごく反感を買った。声をいじるというのは、やはり世の中に対してノイズを立てるような側面があるわけなんですよね。かたやクラフトワークは、『アウトバーン』で大々的にヴォコーダーを使用しましたが、そうしたメソッドがアメリカのブラック・コミュニティでバカ受けするわけです。いわば殺人兵器が反殺人兵器化するんですね。だからヴォイス・マシーンの歴史のなかに位置づけていくと、初音ミクもまたもうひとつ違った見え方がしてくるのかもと思います。やっぱうちの3歳の娘も反応するほど、可愛いもんね(笑)。
佐々木:自分としては、物心ついたころから加工された声というのはある程度世の中に普及していて、J-POPにおけるピッチの調整やハーモナイズ処理なんかも90年代中頃から盛んにされていきますよね。なので逆に加工音に慣れた耳で声に衝撃を受けた体験というと、NYアンダーグラウンドの、たとえばマイク・パットンのようなノイズ系のボイス・パフォーマーであったり、ヤマタカアイさんのネイキッド・シティみたいなものだったりとか。
野田:じゃ、機械というよりも人間ぢからのほうなんですね。
佐々木:(笑)人間というか、単純に強く個性的な声を出せば注目を浴びるものなんだなという驚きはありましたよね。
野田:初音ミクがヒットしている傍らで、R&Bからジェイムス・ブレイクにいたるまで、この数年とことんオートチューンの流行がありましたよね。何かわからないけど、生の声を加工することに対する大いなる好奇心というものが、またこの数年でいっきに拡大しています。
佐々木:自分のなかで、10代の頃には変な音とかノイズとか、音響とかもかなり通っていたので、当たり前になってしまっている部分はありました。一方でポップスの傾向としては、90年代からの小室哲哉さんの女性プロデュース物であるとか広瀬香美さんみたいな、とにかく高いキーで歌わせるというような流れと、「みんなもヤマハのイオスみたいなシンセサイザーを買って、ポップスを作って、女の子に歌わせてプロデューサーになろう!」みたいな作曲コンペティションが盛んになされるような状況とがあったと思います。それでそういうユーザーによる高い声の需要はありつつも、実際人間にはそう高い声が出せるものではない。だから、とにかく高い声を出させたいというのであれば、人間をどう歌わせるのかという点をそこまで突き詰めなくても、ボーカロイドのようなものでいいんじゃないかなという思いもありました。
初音ミクの前に英語版のボーカロイドを出していたときがあったんですが、そのとき自分の尊敬する作曲家の方から、「なんて使えないモノなんだ」というようなご意見をいただいたことがあります。発音記号と音の関係性がもっと詰められてちゃんとしたものだと思っていらっしゃったようなんですが、ボーカロイドというのはサンプリングの音の断片がたくさん入っているというものなので、発音記号を指定すれば、リップノイズのような記号的な音まで細かくひとつひとつ合成されて出てくるかというと、そういうわけでもないんですよ。それで、「あ、これはアカデミックな層のかたに使ってもらうのはむずかしいな」とわかりまして(笑)。そういうわけなので、ボーカロイドも初期の頃は海外ではことごとく売れなかったです。アカデミックな研究に寄り添うにはサンプリングに寄りすぎているイメージですね。
野田:現代のスピーク・アンド・スペルみたいなもの? いや、でもあれは音程は変えられないもんね。
佐々木:そうですね......。日本語のボーカロイドは50音にひとつひとつの音が対応しているので、「あ」と入れれば「あ」という音が出てくるし、「い」にしても同様です。ただ、英語はスペルによって発音記号が変わるし、フレーズによって音の流れが変わったりするので、細かいところが微妙に欠落して、中身が粗かったりするんですよ。その粗い部分がそのまま置きざりにされていて。技術は確立してるのに、中身をきっちり整えていくという作業が未成熟で、当時とても中途半端なものだったんですよね。技術開発にかかったコストに対して売り上げが全然ついていかなくて、初音ミクをやる段階では、もうプロジェクトを閉じようかという話もあったくらいなんです。これで最後の製品だ、ぐらいの。携わる人数もぐっと減っていました。そんなわけで、初音ミクが生まれる前夜は、なにかおもしろいことをしなければいけないんじゃない? というようなムードにはなっていましたね。
[[SplitPage]]ボーカロイドがツールを超えたとき
ヴォコーダーは、戦争中にアメリカのペンタゴンが音声を暗号化するために作り出した音声合成装置なんですよね。広島に原爆を落としたりとかの指令は全部ヴォコーダーを通している。だからある意味、「機械で音声を変える」ということは人間の歴史のなかで非常に呪われた歴史を持っているわけです。(野田)
そのとき感じたのは、もう音楽の向こう側で音がどんなふうに鳴っているのかというのは、視聴者にとってはわからない世界になっていくんだなということです。(佐々木)
クリエイターの創作上の利便性を上げる、いちツールとして開発されたに過ぎない音声合成ソフトが、ひとつのヴィジュアル・イメージと、思いもかけないほど多くの人びとの想像力、創作物、コミュニケーションによって、存在や人格をありありと錯覚させられるような広がりを得た。そこに「ただの女性の声ネタ」を開発するという以上の狙いはなかったのだろうか?
佐々木:まず「アニメ・ソング」というジャンル名を耳にしたときに、まったく何の音楽ジャンルでもないことに驚いて、でも若い人にすごく違和感なく浸透しているなという強い印象がありました。「アニメの主題歌であれば皆知っているし好きだからOK!」みたいなノリ。更にアンダーになると声優さんのキャラクターソングと言われるデフォルメされた声ありきの世界や、アダルトを含むゲーム由来のテーマ曲が許容されていく世界......。また、クリプトンに僕が入ったのが2005年ですが、当時オーケストラの音をサンプリングしていて、そこそこのクオリティのソフトを作れてたんです。生かサンプリングかわからないというレベルくらいには。でもそれを見たときに少しさみしい気持ちにもなりました。「一般の人がこれ聴いても、どっちかわかんないよね」というのは狙い通りでいいことなんですけど、テクノやエレクトロニック・ミュージックの歴史のなかでは、あまりポジティヴな使い方ではないと思った......要は「○○もどき」みたいなふうにして人に聴かせるやり方や、その需要が増えてきたんだなと思いました。当時、ゲームで言えば『ファイナル・ファンタジー』の〈スクウェア・エニックス〉さんとか、映画音楽なんかでも、オーケストラを呼ぶよりもコントロールしやすい音源でなんとかしようという感覚があって、いろんな部分でそういうことが起こりつつありました。
そのとき感じたのは、もう音楽の向こう側で音がどんなふうに鳴っているのかというのは、視聴者にとってはわからない世界になっていくんだなということです。バンドが演奏しているのか、打ち込みで作られたものなのか、誰がどんな意図で鳴らしたものなのか、そういう音とそれを出す動機の関係性が本当にあやふやになっていく感じ。機材が良くなるなかで、音も多様性を持っていくということはこれまでにもありましたが、いまじゃプリセット枠がぐわーっと増えて、それこそオーケストラの音色にしても何でもあって、使い方によっては何でもできるという状況が、ほんとにいいのか悪いのか、その思考自体を止めてしまっている状況というか。リズムマシンから始まった演奏者の代用的なツールが、歌声合成(VOCALOID)の汎用化を可能にするところまで来た。だから昔の自分が初音ミクを見たら第一声「なんじゃこりゃ」とは言うでしょうね。ただ、これは声の質としてはアニメとかを視聴している人にはある程度親和性を見いだせるようなものなのかなと思いますし、人間的な要素も欠落していて、声の表現もつたないわけなんですが、そういうすごく素っ気なかったり朴訥に聞こえたりするところは、むしろよい部分でもあるのではないかと思いました。人間の代用のはずなんだけど、真正面からの人間の代用とは違う、おもちゃとしての適当さを持たせたものにしたかったというのはありますね。
初音ミクは、自分をかわいらしく見せようとしている女の子の声を、ひたすら録りつづけた音源をボーカロイドにしているんです。だから、もともとは自分はかわいいでしょ、と一生懸命に自己主張していたものなのに、ばらばらにされてしまって、言葉のつながりとか感情とかが入っていないものになってしまっている。それが最終的に音として出てくると、なんだか間抜けなような感じがします。でもそこがとてもかわいいという部分もある。
初音ミクと性の問題
例えば南米のトロピカリアのような、ちょっとふざけたような音楽、トン・ゼーがそのへんの床を洗う機械を面白がって音楽に用いたりする感覚に似ていると思います。軽やかなおふざけというか。初音ミクというのは自分のなかではそうしたものに近いです。(佐々木)
野田:なるほどね、とても重要なポイントがいくつかありますね。まず、ボーカロイドの波形の話。きれいな波形と壊れた波形を重ねるから音が汚くなるというお話をされていましたけれども、音楽における機械声、ロボ声の使用はこれまでほぼ例外なく汚い音でしたよね。ヴォコーダーもそうだけど、だからおもしろいと言えるし、だから反感を抱かれる、という歴史をたどって来てもいるわけです。クラフトワークでさえ、はじめは笑われていたんですからね。
もうひとつは、かわいらしい女の子の声にしたということ。僕みたいなかわいい文化の対極にいるような人間が言うのもなんですが。
佐々木:藤田さん(藤田咲)という演者さんに声をお願いしたんですが、スタジオに入ったときに、まずどういうふうに声を出せばいいんですか? と質問されました。彼女に読んでもらうのは、セリフでも日本語でもなくて、呪文みたいに50音が羅列されているものです。まったく何の意味も持っていないけど、ただ、それを読んでいるときの声の表情はそのままボーカロイドに使われます。その1語1語を細かく切ったものがボーカロイドになるわけです。で、こちらからお願いしたのは、とにかく意味不明な台本は意識せずにとにかくかわいらしくお願いしますということでした。あまりなにも考えないで、とにかく楽しく、かわいく! と煽っていたんですが、そんな問答を続けていたら、藤田さんがもう吹っ切れてしまったようで、途中で腕を振りだしたんです。テンポに合わせて体を揺らしながら声を出しはじめた。それから良いテンションになり「わたしかわいいでしょ?」という雰囲気で50音を発音しつづけてもらったので、かなり不思議な録音になりました。
これの前にカイトとかメイコといったボーカロイドを作っているんですが、それはふつうのシンガーの方にお願いしていたので、ヴォイス・トレーニングのような録音だったんです。正しく、きれいな発音、発声。それを切って音程なしにつなげると、駅のプラットホームの音声アナウンスのようなフラットな感じになるんですが、ミクの場合は、とにかく「わたしかわいいでしょ!?」というテンションが凝縮されているので、切って貼って、そのテンションが高く口を開いた「ら」と、口が閉じ気味だけど表現を可愛くしようとした「ぬ」とかが並んだときに、ちょっと変な感じ、変な印象になります。聴き手は、歌い手側になにかメッセージか感情表現があるものという前提で聴くわけですが、そこがバラバラになるわけですね。自分はそれはユーモラスに感じるんです。例えば南米のトロピカリアのような、ちょっとふざけたような音楽、トン・ゼーがそのへんの床を洗う機械を面白がって音楽に用いたりする感覚に似ていると思います。軽やかなおふざけというか。初音ミクというのは自分のなかではそうしたものに近いです。
音声合成として全然完璧なものではないですしね。もともとヨーロッパの会社がボーカロイド作ってたんですけど、そっちは声が人間ぽくならないのを逆手にとって、フランケンシュタインみたいな表現で、「これは人造人間みたいなものですよ」という売り方をしていたんです。それがなんとも自虐的というか、売れなさそうで(笑)、この方向はナシだなと思ったりしました。そこで日本の文化的な環境に適したものとして思い浮かぶのは、SFチックでかわいらしい女の子かなというところで、ご存知のとおりの姿かたちになっています。
野田:なるほどー。ソフトウェアのパッケージングとして重要な部分を支えている絵だというのはわかったんですが、ぶっちゃけ、このヴィジュアル自体にエロティシズムは意識されていないんですか?
佐々木:いや、僕自身もともとアニメ・カルチャーにさほど詳しいわけではないんですが......エロティシズムとは少し違うものでしょうか。昔は、男の子の性的な欲求の捌け口というと、エロ本やAVみたいなものだったりしたと思うんですけど、ある時期から肉感的なリアルな女性像が受け入れられないなどの理由で、アダルト・アニメやエロゲーなどに向かう人も一方で増えていったんだと思います。過度に母性を感じさせるように、胸が大きかったり、過度に恥ずかしそうに頬が赤らんでいたりという、アニメ等の記号的な性の表現は、自分としては作為的かつ刹那的と感じていたんです。初音ミクはそういうディテールがありつつも、頬の赤みや胸の大きさというのは極限までカットしていきました。それに、そもそもこの初音ミクの声ではあまり性的なイメージに結びつかないだろうなとも思いました。VOCALOIDの音として冷静に人間の声と比較すると、考えなしに淡々としている印象もありますし。この声を出している女の子がいるとすれば、それはおそらく胸も小さくて、性的なアプローチに乏しい姿なのではないか。それで少しストイックにしたというところはありますね。
最近は女性のファンの方も多いですし、ニコニコ動画などの視聴者にもとても若い女性の方がいらっしゃいますから、変に性的に強調されていると、違和感になっただろうなとも感じます。
野田:ああ、なるほど。サイバー・フェミニズムっていうタームがありますよね。デジタル空間では、女性は旧来的なジェンダーから解放されるというね。ローレル・ヘイローのアルバムの会田誠の切腹女子高生の引用は、アメリカのデジタル文化になぞって言うと、サイバー・フェミニズム的なものを感じなくもないのですが、さっきのうちの娘じゃないけど、初音ミクは、女性性に受け入れられるんですね。なんか。
佐々木:もちろん最初は男の方が多かったですけどね。プログラマーとかIT系のお仕事をされながら、ネット・カルチャーのなかで情報収集をされる方がおもしろがって集まってきてくれました。一番乗りで動画を作られていた方では、鉄道オタクの方も結構いらっしゃいましたしね。
野田:なぜ鉄道オタクの人が(笑)!?
佐々木:山手線のメロディをひとつひとつ歌わせてくれるんですよ(笑)。新しもの好きで鉄道も好きという方はけっこういらっしゃると思います。
野田:ああ、そうかもねえ。
時間を忘れて語る両氏。このあと野田がさらに初音ミクの少女性をめぐって切り込みます! 後編を乞うご期待!


