世界一クールなインディペンデント・ゲイ・カルチャー・マガジン『BUTT』に、全裸で肩車をして登場していたのは、世界一クールなゲイ・カップルであるマトモスだった。記事は2002年、ドリュー・ダニエルとマーティン・シュミットのふたりはすでに理知的で奔放なアウトサイダーとしてそこにいる。マトモスがいなければ、マシュー・ハーバートはアルバムのコンセプトを見つけられなかったかもしれないし、ビョークは先鋭性とポップを両立させられなかっただろうし、アメリカの音楽シーンにおけるゲイ・カルチャーはいまより遥かに退屈なものになっていたに違いない。彼らを一躍有名にした、外科手術のサンプリング音が素材である『ア・チャンス・トゥ・カット・イズ・ア・チャンス・トゥ・キュア』の頃から、マトモスはつねに狂気じみた笑いを携えながらきわどい実験を繰り返してきた。
マトモスはいつだって知性としてのユーモアを忘れることはなかったが、しかしたとえば2006年に発表された『ザ・ローズ・ハズ・ティース・イン・ザ・マウス・オブ・ア・ビースト』は、ブッシュ政権下における闘争宣言とも思えるほど目的意識に貫かれたものだった。キリスト教原理主義が同性愛を罪悪とするならば、あるいは良識のあるリベラルが結局安全なゲイ・カルチャーを周到に選んで支持するのならば、マトモスは同性愛者やジェンダーのはぐれ者のもっとも厄介な部分を抽出し、それを讃えてみせた。精液のしたたる音、カタツムリがテルミンを演奏する音、ハッテン場でのゲイのセックスの音、タバコを腕に押し当てる音など......を使って。エクストリームにヤバい同性愛者として、過剰な生を送った先達を音で描写するというコンセプト自体がラディカルだったし、何よりも......それを心から楽しそうにやってのけるふたりの姿こそが、退屈な常識とモラルに縛られた社会に対する、朗らかゆえに危険な反逆のようだった。
だから、タイトルにある「婚姻」という言葉は同性婚についての言及なのだろうと思ったが、それはあまりに短絡的な発想だったようだ。ゲイ性を強調してもしなくても、マトモスはいつでも異端者なのである。
シャープなシンセ・ポップがマトモスとしては新鮮だった『シュプリーム・バルーン』からじつに5年ぶりとなる新作『ザ・マリッジ・オブ・トゥルー・マインズ』は、ふたりのマッド・サイエンティスト的な側面が健やかに発揮されたアルバムだ。ドリュー・ダニエルのライナーノーツ、あるいは〈スリル・ジョッキー〉のインフォメーションを読めば、このアルバムのテーマはテレパシーだという。用いられたのはガンツフェルド・エクスペリメントという実験メソッドであり、ボランティアの被験者はピンポン玉を半分に割ったもので目を覆われ、ノイズを聴かされながらダニエルに新作のコンセプトを心理のなかに「送られた」という。そして、被験者は心に浮かんだ形や音を口頭でレポート、それが本作の音楽的構造の基本となる。......と、言われても......?? 凡人にはにわかに理解しがたいがしかし、マトモスの本領はもちろん、再生ボタンを押した瞬間から発揮される。
アルバムを通して言えるのは、迷いなくマトモスらしさ、彼らの「節」が開放されているということだ。オープニングの"ユー"はレスリー・ウェイナーと(パレ・シャンブルクの)ホルガー・ヒラーの曲のカヴァーで、ピアノが妖しく鳴り響きながらエレクトロニカとジャズとテック・ハウスの狭間をさ迷う。そのなかをニューエイジ的に声が囁く、「テレパシー......わたしたちが知りたいもの」。続く"ヴェリー・ラージ・グリーン・トライアングル"は4小節ごとにさまざまなリフやループ、サンプリングがカットイン/カットアウトする最高にスリリングなハウス・トラックで、まるでコズミック・ディスコ......というか〈パラダイス・ガラージ〉時代のディスコ・ナンバーとグリッチ・テクノとIDMが「婚姻」を交わすようだ。"メンタル・レイディオ"のパーカッシヴなトロピカリアとラグタイムと、ふざけたフリー・ジャズのいい加減なミックス。"ティーンエイジ・パラノーマル・ロマンス"の、不気味でメロディックでファニーなテクノ。ダン・ディーコンが参加し、まさにディーコン的に無闇なアップリフティングさでシンセがトランス状態へ突入する"トンネル"もアルバムのピークを演出する。耳に残る奇怪な音色に彩られながら、マトモスの音楽は愉しさに満ち溢れている。ここではポップとアヴァンギャルドは矛盾せず、くっつけられてグチャグチャに丸められて、何か経験したことのない快感へと姿を変える。
ラストの"E.S.P."はバズコックスのカヴァー。8分間でパンク的な皮肉とユーモア、テクノの実験主義が手を取り合って、わけもなくユーフォリックな領域へとリスナーを連れて行ってしまう。ダニエルが被験者の心に送ったというコンセプトはシュミットにすら明かされていないというが、彼のテレパシーはアルバムにおいてビザールなサウンドとなって放たれている。これはダニエルによる奇を衒ったジョークでありつつ、真摯なコミュニケーション欲求でもあるのだ。そして僕には、"E.S.P."のサイケデリアが歓喜そのものに聞こえる。ふたりが20年近くに渡って体現してきた、規範からの遠慮のない逸脱についての。その歓びはそして、僕たちが生きるための矜持にすらなるだろう。
「Nothingã€ã¨ä¸€è‡´ã™ã‚‹ã‚‚ã®

突然ですがみなさん、いま〈Looking Glass Studios〉が熱いです。と言っても何がなにやらわかりませんね。すみません、NaBaBaです。年度初めの今日このごろ、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
いきなりで失礼致しましたが、今回の連載は昨年から予告していた『Dishonored』のレヴューをついに行いたいと思います。〈Arkane Studios〉が開発したこのオリジナル新作は昨年遊んだ作品のなかでもとくに素晴らしいもので、ぜひ書こうと思いつつ延びに延びてこの時期になってしまいました。
しかしいまこの時期となると、ゲーマーの間でいちばんの注目の的となっているのはやはり26日に発売された(国内では4月25日)『BioShock: Infinite』ではないでしょうか。現代のゲーム業界きっての名手、Ken Levine率いる〈Irrational Games〉が開発した同作の評判はすさまじいもので、海外ゲーム・レヴュー・サイト各所でも満点の続出で、「IGN」では「全てのジャンルを前に推し進める革新的な作品」と、異例の絶賛ぶりが披露されています。
かくいう自分にとっても今年の一、二を争う期待作なのですが、じつはこの『BioShock: Infinite』と『Dishonored』はある種の兄弟関係にあることはご存知でしょうか。これら2作のそれぞれの開発スタジオは、どちらもあるひとつのスタジオから分離した会社なのです。
その大元でいまや伝説となっているのが、冒頭で述べた〈Looking Glass Studios〉(以下LGS)。90年代に大活躍したこの技巧派のスタジオは、『Thief』や『System Shock 2』等のゲーム史に残る名作を数多く生み出し、後続に多大な影響を与えるとともに、多くの名クリエイターを輩出しました。
たとえば連載第3回にご紹介した、『Deus Ex』を手掛けたWarren Spectorもそのひとりで、『Deus Ex』自体は〈Ion Storm〉という別スタジオが主導の作品ですが、『System Shock 2』のスタッフも多く出入りして開発されていたようで、〈LGS〉とは非常に深い関係にあったと言えるでしょう。
しかしながら〈LGS〉は2000年に倒産しています。ではすでになきスタジオが何故いま熱いのか。それは〈LGS〉の遺伝子を受け継いだ人々が、近年各所で目覚ましい活躍を見せているからです。
その先駆けとなったのが一昨年発売された『Deus Ex: Human Revolution』。開発した〈Eidos Montreal〉は〈LGS〉や初代『Deus Ex』の開発陣とは直接的な繋がりはありませんが、本作で確かな完成度を発揮し、シリーズのリブートを成功させました。
また今年に入ってからは『BioShock』シリーズの前進である『System Shock 2』が、長きにわたる権利関係のゴタゴタによる販売凍結状態を乗り越え、遂に〈GOG.com〉で再販を果たし、さらに〈Eidos Montreal〉が今度は〈LGS〉のもうひとつの名作、『Thief』シリーズの9年ぶりの最新作を発表しています。
『System Shock 2』はKen Levineの実質デビュー作であり、後の〈LGS〉系作品の独特の自由度はこの作品で確立された。
そしてもちろん忘れてはならないのが大本命の『BioShock: Infinite』と、今回主役の『Dishonored』です。〈Irrational Games〉と〈Arkane Studios〉はともに〈LGS〉から独立・派生したスタジオであり、比較的近い時期に両スタジオの作品が出揃ったのは、90年代来の洋ゲー・オタク的にはぐっと来るものがあるのです。熱い、これは熱いのですよ。
こうした背景もあるので、当初は〈LGS〉を振り返りつつ、『Dishonored』と『BioShock: Infinite』の両方を同時にレヴューしようかとも思いましたが、ちょっと長くなりすぎるような気がしたのと、これを執筆している時点で『BioShock: Infinite』を遊ぶまでまだ少しかかりそうだったので、2回に分けて書いていきたいと思います。そういうわけで今回は『Dishonored』のレヴューです。
[[SplitPage]]■業界の異端児スタジオに多くの才能が集結した
『Dishonored』はいまどきでは珍しい一人称視点のスニーク(隠密)アクション。女王殺害の冤罪を着せられた主人公が、自らを陥れた相手に復讐していくストーリーで、潜入からターゲットの暗殺に至るまでのアプローチの多彩さや、豊富なガジェットや特殊能力による自由度の高さが売りの作品です。
開発した〈Arkane Studios〉は前述した通り〈LGS〉倒産後独立したスタジオのひとつで、これまで『Arx Fatalis』や『Dark Messiah: Might and Magic』等、〈LGS〉の名作『Ultima Underworld』の名残を感じさせるファンタジー作品を手掛けてきました。といっても両作品とも当時の主流からは外れたゲーム・デザインで、良く言えばユニーク、悪く言えば奇ゲーという評価が多数の、いまひとつマイナー・スタジオの域を出られていなかったように思えます。

『Dark Messiah: Might and Magic』は近接戦に力を入れたファンタジー作品で、そのノウハウは『Dishonored』にも生きている。
『Dishonored』も、見た目やシステムの奇妙さがこれまでの〈Arkane Studios〉節を彷彿させ、発売直前まで一抹の不安があったのは事実です。しかし遊んでみると同スタジオらしさは良い方向に作用しているとともに、表面上の奇抜さに反して実際のゲーム・デザインは、〈LGS〉作品の持ち味をとても忠実に継承していると感じました。
これは今回新たにプロジェクトに加わったViktor AntonovとHarvey Smith両氏の力が大きいのでしょう。
Viktor Antonovは連載第1回でご紹介した『Half-Life 2』で特徴的なアートを手掛けた人物で、今回は氏の持ち味がさらに全面的に発揮されていますね。時代掛かったイギリス風の街並みに無機質な金属の構築物が埋め込まれたかのようなデザインは大変ユニークで、それに説得力をもたらす世界観の構築も非常に緻密。これまでの同スタジオの作品はもちろん、他の同時代のゲームも軽く凌駕するオリジナリティがある。ことアートワークに限って言えば、ここ4、5年でもトップクラスと断言出来ます。

骨組み剥き出しの建造物の数々が、作品に得も言われぬ威圧感を与えている。
一方、本作のディレクターのHarvey Smithは、かつては〈LGS〉に在籍し、また『Deus Ex』ではプロデューサーを務めた人物で、本作のゲーム・デザインも彼の経歴がとても色濃く反映されています。
それこそ遊んだときの第一印象、とりわけ問題解決のための手段の多さはすごく『Deus Ex』らしさを感じたし、豊富な超能力を駆使するところは『System Shock 2』や『BioShock』も想起させます。そしてダークな世界観や観視点でのスニーキングに主眼をおいたゲーム・デザインは『Thief』に通ずるものがある。
実際のところ本作のゲーム・デザインの骨組みは、宝を盗むのがターゲットを暗殺することに替わっている以外は『Thief』にとても似通っています。むしろそうした骨子に適合する範囲で他の〈LGS〉系列のゲームのシステムや、その他諸々現代のトレンドを組み合わせたのが『Dishonored』とも言い換えられるでしょう。
■二つの方角から掘り下げられた自由度
具体的に見ていくと、まずゲームはステージ性で、各ステージはターゲットの拠点とその周辺地域が舞台となり、その範囲内でプレイヤーは自由に歩きまわれるデザインです。ステージはとても複雑かつ立体的に構成されていて、主要な建物は内装がしっかり作りこまれている凝り具合。当然ターゲットのもとにたどり着くまでには無数のルートが存在し、どのように進めるかはプレイヤー次第となっています。
このあたりの自由度はいかにも『Thief』や『Deus Ex』的と言え、自分の頭で考えて進むべき道を決めていけるのは楽しいし、ルートごとにしっかり差別化されつつゲームに破綻が生じないのは見事。『Deus Ex』のレヴューでも触れましたが、ゲームの自由度という点において即興性が重視されるようになった現代に、レベル・デザインの作り込みで遊ばせてくれる作品は希少です。
逆に『Thief』や『Deus Ex』と違っていまどきのゲームらしいのは、ルートの多彩さが予めプレイヤーに開示されていることが多い点でしょう。どういうことかというと、本作では後述する特殊能力を駆使して屋根や屋上等高所を移動ルートとする機会が多いのですが、その高所は先の状況を一望できる絶好のポイントにもなるわけです。高所なら敵に見つかる心配がないので、安心してじっくり戦略を練ることができるというメリットもある。
また市民の立ち話や拾った書類等に、秘密の部屋だとか警備が手薄な場所だとかの情報があると、自動的にジャーナルのリストに追加されます。いちいち覚えていなくてもジャーナルを見ればどんな攻め方が有効か一目瞭然で、これもまた選択肢をプレイヤーに開示している例のひとつでしょう。
こういう親切設計はじつにいまどきのゲームらしく、『Deus Ex』当時ではあり得ないものですが、自由度の高さを楽しんでもらうための誘導としてよく機能しているシステムだと思います。

屋根に登って下を見下ろし、先へ進む戦略を考える。これが本作の基本だ。
対してもうひとつの特徴である豊富なガジェットや超能力もよくできています。とりわけ超能力は『Deus Ex』のAugや『BioShock』のPlasmidを原型にしていると感じられますが、その種類は短い距離を瞬間移動するものから時を止めるもの、なかには周囲の小動物や人間に乗り移るもの等々、一見すると変てこなものも多いです。
しかし実際に使ってみるとどの能力も意外なくらい使い勝手が良くて、たとえば瞬間移動は屋根から屋根、道なき道を進んでいく手段としてゲーム中もっとも重宝する他、敵の目前を気づかれずにすり抜けるのにも使えます。乗り移る能力であればネズミや魚に乗り移れば排水溝を伝って建物内に潜入できるし、ターゲットに乗り移れば人目のないところまで誘導してから暗殺するということも可能。

動物に乗り移れば不審がられることなく衛兵の横を通過できる。しかし足元に寄りすぎると踏まれるので注意。
このように各能力は応用性が高く、プレイヤーの想像力次第でステルスから戦闘までいろいろな使い道が考えられます。これはレベル・デザインとは違いより即興的な自由度とも言え、その場の思いつきをその場で実験したくなる魅力がありますね。とくに戦闘時にこれは顕著で、瞬時の判断が求められる状況で創意工夫して敵を倒し弄ぶ楽しさは、『BioShock』もかくやと言わんばかり。
こうした即興性は『Thief』や『Deus Ex』に欠けていた要素であり、逆に『BioShock』は即興性優先で、レベル・デザインの濃さは大分減退していました。『Dishonored』の優れているところはその両方を持っていることであり、〈LGS〉の系譜のさまざまな要素をまとめ上げた、これまでの総決算的な作品であると評価することが出できます。
[[SplitPage]]■「何でもできる」は良いことばかりではない
さて、〈LGS〉の系譜の現代的復刻という点で思い出すのが『Deus Ex: Human Revolution』ですが、この作品と『Dishonored』は当然似ている部分がありつつも、根幹の方向性はやや異なっています。
最大の違いは自由度の範囲で、『Deus Ex: Human Revolution』はオリジナルに比べ敵との戦闘に大きくフォーカスしていて、反面複雑・立体的なレベル・デザインは減退し、より直線的なゲーム進行になっていました。言ってしまえば普通のアクション・シューティングに近くなっていたと言えます。

『Deus Ex: Human Revolution』の戦闘重視のデザインは、これはこれでまた評価がわかれるところではある。
対する『Dishonored』は自由度をかぎりなく拡張していく姿勢で作られており、その点をもって僕はこの作品は楽しめたわけですが、しかしこれは人によって評価が分かれるところだろうとも思うのです。
本作はスニーク・アクションというジャンルではありますが、コソコソ隠れるだけでなく敵とガチンコで戦うことも可能で、なおかつその振れ幅も大きく、ひとりの敵にも見つからずにクリアすることができれば、正面玄関から殴りこんでの皆殺しも可能になっています。この手のゲームにしては主人公がかなり強いということもあり、本作のスニークというのは生存戦略上の必然というよりも、プレイヤーの好み次第という面が強いのです。
しかし本作に限らずステルスも皆殺しも自由自在みたいなゲーム性は今世代のゲームではとてもよく聞く謳い文句のひとつなのですが、プレイ・スタイルをプレイヤーの好みに委ねている分、効率だけを追求されたら途端に味気ない遊びになる恐れや、どんなプレイ・スタイルでも遊べるということは、逆に何をやっても何とかなるという意味でもあり、全体的に緊張感が欠けてしまうという問題点が付きまとっています。
本作もこの点を完全には払拭できていないのが残念なところで、無傷で手軽に進みたければ、屋上からペシペシ撃っていればそれでOKみたいな、身の蓋もない事態になる危険性は否定できません。自由度を高くしたがゆえの、楽勝な進め方が存在してしまっています。

ただ倒したいだけだったらピストルを何発も撃ちこめばいい。これもまた自由ではあるが味気ない。
ただプレイヤー側が遊び方に明確な目的意識を持てば、それに見合った楽しさが返ってくるところに救いはある。敵にいちども見つからずに進めようと思ったらやはり相応の手応えは生じてくるし、なるべく多くの武器を使いこなして敵を殲滅してみようとすれば、こちらの戦術に柔軟に対応してくる敵の反応を見ることができるはずです。
そういう意味では人を選ぶゲームであることには違いなく、おもしろさのポテンシャルは高いんですが、楽しみ方をわかってないとそれを十分に味わえない恐れがある。それに比べると『Deus Ex: Human Revolution』は、自由度が減退した分、遊び方は明快になっていて、どんな遊び方でも比較的一定のおもしろさや手応えが保障される面があるのは確か。
だからと言ってどっちの方が優れているという話ではありませんが、少なくとも『Dishonored』を遊ぶ際は上記の点は予め留意しておいた方が、より楽しめるかと思います。
■まとめ
前述した〈LGS〉の系譜の総決算という言葉がふさわしい作品で、自由度の高さは近年では屈指のもの。〈LGS〉ファンはもちろん、自由度の高いゲームが好きな人や、ユニークな世界観が好きな人にピッタリの作品です。
逆にそれらが好きでない人には合わないゲームでもあり、また自由度が高いとは言え純粋なアクションやスニークと同等の面白さや緊張感を求めても期待外れになるでしょう。あくまでも自由度の高さを楽しみ、味わう作品だと思います。
インダストリアルとゴシックは、時代の変節点に起きたきしみという意味で同じカードの裏表だ。19世紀末、ロンドンの街にデパートが誕生し、オスカー・ワイルドが扇風機の音に心酔した時代に、ネオゴシックの画家は丘の上の古城を、闇夜を走る稲妻を、荒れ狂う海原を描いた。ダークなタッチに表出した近代的合理に対する違和感は、他方では、田園を賞揚したロマン主義とも、これまた同じカードの裏表と言える。で、いったい何枚のカードを用意するればいい。ひとつ言えるのは、時代の変節的を迎えている今日にも、似たようなことが起きていること。デジタル革命があり、だからインダストリアルとゴシック(ないしはアンビエント)は顕在化している。それらが、激動に対して、ある種のマゾヒスティックな反応を見せていると言えるなら、変化に対してサディスティックに反応しているのが、そう、シカゴのフットワーク/ジュークだと言えよう。
DJラシャドは、この界隈では、少なく見積もっても2年前から騒がれていた逸材である。昨年も、ディスタルとの「Stuck Up Money」や配信のみの『Teklife Volume 1』、アジソン・グルーヴのリミックスやトラックスマンのアルバムへの参加など、何気に彼への期待を煽るような動きをしている。抜け目のないロンドンの〈ハイパーダブ〉からリリースされた4曲入りの2枚組12インチ「ローリン」は、そして、期待を裏切らないどころか、今年のベスト・トラック候補だ。"ローリン"が素晴らし過ぎる。
ジェフ・ミルズは、いかにもポストモダンな情熱で、いまさら歴史を知る必要はないと言い張るが、どうだろう。"ローリン"からも、あるいは昨年の『ダ・マインド・オブ・トラックスマン』からも、そしてトラックスマンのDJプレイからも、歴史(シカゴ・ハウスとエレクロ)がビシビシ伝わってくる。鼓膜に新鮮な、このキックドラムの乱れ打ちが、ここ数年で生まれたものではないことを、とくにトラックスマンの音楽は主張しているように思う。ずっと続いているものであり、これからも続くものとして。"ローリン"は、DJダイアモンドよりもトラックスマンの側に位置づけられる。つまり、こいつは、切り刻まれ、さらにまた切り刻まれながら、しかし、ずば抜けてソウルフルなのだ。
そして、"レット・イット・ゴー"、これはジャングルだ。90年代半ばの4ヒーローを思わせる色気と凄みがある。魂と攻撃のバランスが絶妙過ぎる。DJメニーとの共作"ドラムス・プリーズ"、これは壮絶なジャズだ。暴れまくるドラミングの叙情詩である。カール・クレイグの"マイ・マシーン"を、骨董品に追いやるほどの勢いだ。DJスピンとの"ブロークン・ハーテッド"、これはもう、そのままスティーヴィー・ワンダーのフットワーク・ヴァージョンである。ソウル・ソングの切ない響きの背後では、バタバタとせっかちな、紛れもないシカゴの若いリズムがファンキーに鳴り響いている。
この先、ブラック・ミュージックとしての洗練が待っているのだろうか。しかし大切なのは、いつだって現在だ。たったいま、この瞬間、"ローリン"の輝きは圧倒的である。
bim、in-d、PalBedStockの3人からなるTHE OTOGIBANASHI'S(以下、OTG)は、昨年YouTubeで発表した"Pool"で一気に好事家たちの話題をかっさらった。"Pool"はあらべぇという気鋭の若手プロデューサーが制作したナンバーで、BUNの『Adieu a X』に影響を受けたと語るその言葉通り、非常にエディット感/クリック感の強いトラックの上で3人が浮遊感というより、フワフワとしたラップを繰り広げるナンバーだった。しかしOTGがユニークだったのは、そのビデオクリップをただのPVとして仕上げるのではなく、自分たちのカルチャーをゲットー・ハリウッドイズムあふれるスタイルでぶち込んだことだろう。フォスター・ザ・ピープルにデヴィッド・ボウイ、SUPREME×Comme des Garcons SHIRTのキャップ、ピスト、スケートボード、代官山、カフェ......。ストリートのしがらみa.k.a.縦社会から完全に自由なOTGのスマートさ、というかボンボン感。それはついにRIP SLYMEの後継者が現れたことを感じさせた。
今回リリースされるアルバム『TOY BOX』はPUNPEEの登場以降、徐々に声を上げはじめた文科系B-BOYというサイレント・マジョリティたちにとってはたまらない一枚と言えるだろう。内容は彼らが"Pool"のPVで見せた東京の(怖くないほうの)ストリート・カルチャーのごった煮感と、ディズニーのような寓話をミックスしたようなコンセプト・アルバムの体がとられている。リリックでも"Frozen Beer"では「NBの997でも履いてろ」、"kutibue"では「泥がオールデンに付いた / 味が出ると俺は許す」、"Fountain Mountain"では「映画館で観た映画が / 今の俺を作ってるとしたら / このTシャツもスナップバックもあいつの影響なのかな」などなど、露骨なまでに自分たちの嗜好を詳らかにしている。
OTGはシングルやEPですら1枚もリリースしてないのに雑誌「POPEYE」や「WARP」などに登場しており、すでにファッション方面からも熱視線を注がれている。このあたりも、どんなに捻くれた作品をリリースしても、やたらとメジャー感だけは醸し出るRIP SLYMEに似ていると言えなくもない。前述の"Fountain Mountain"のトラックなどは明らかに"楽園ベイベー"へのオマージュを感じさせるし、OTGもRIP SLYMEのようにヒップホップセレブ化していってほしいものである。
2枚の名盤、しかもけっこう入手困難で、中古で恐ろしい値段が付けられていたアルバムが再発されました。
1枚は、デトロイト・テクノのカール・クレイグの、初期作品集『エレメンツ 1989-1990』。彼が19歳から21歳にかけて作ったトラック集ですが、この音楽が、エイフェックス・ツインやカーク・ディジョージオ、そしてミックスマスター・モリスに与えた影響ははかりしれません。アンビエント色が強く、また、素晴らしい旋律を持っている"エレメンツ"は必聴。他にも、セクシャルな"クラックダウン"、ばっちり叙情的な"エヴォリューション"、真夜中のハウス"プリーズ・スタンド・バイ"、タンジェリン・ドリームめいた"ニューロティック・ビヘイヴィア"......この機会に聴きましょう。
もう1枚は2009年に忽然とリリースされ、世界中のディープ・ハウス・リスナーを虜にした、フレッドP ことブラック・ジャズ・コンソーティアムの幻の『ストラクチャー』。スピリチュアルで、メロウで、催眠的で、中毒性の高いアンビエント・テイストはハンパないです。オリジナルはジャケ無しでリリースされましたが、今回はジャケ付きの再発です。
家のリヴィングで、リラックスしながら聴きましょう。
 |
サイケ/BFC エレメンツ 1989-1990 Planet E/Pヴァイン |
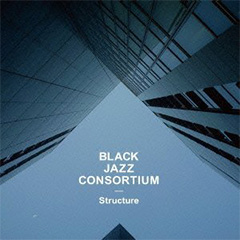 |
ブラック・ジャズ・コンソーティアム ストラクチャー Soul People Music/Pヴァイン |

先週土曜は、ブシュウィックの会場シェ・スタジア(liveatsheastadium.com)で、インディ・ロックDIYのショーケースを見た。エド・シュレイダーを見に行ったのだが、結果見たすべてのバンドが面白かったのでひとつずつレポートします。日本のレコード店で見つけたらチェックしてみて!
■フリー・ブラッド:freeblood.bandcamp.com
!!!のメンバーでもあったジョンがはじめたバンドで、昔、著者が働いていたカフェにメンバー、ふたりでよく来ていたので、ライヴを見にいっていたのだが、最近はご無沙汰していた。メンバーが、ふたりから4人になり、黒髪の女性から、金髪で赤い口紅、レザージャケットのLAっぽい女の子に変わっていた。サウンドは前と大きな変わりはなく、男女ツイン・ヴォーカルにギターとビートが乗ったエクスペリメンタル・ポップ・ソウル。ジョンはドラムを叩きながら歌い(片手にマイク、片手にスティック)、たまに鐘も鳴らす。前の女子メンバーが、お酒をステージに持ってきたりしていたので、関係は良好であるらしい。
ショーの後に話したら、バンドは10年ぐらいやってるとか、日本ツアーも経験済み。
■ジャマイカン・クイーンズ:https://jamaicanqueens.com/
今日の大発見! 男の子3ピースで、インディ・ポップと呼ぶには新しいので、サザン・ラップを取り入れたトラップ・ポップと呼んでみる。スタイルは、ウエィブスに近いかな?
メンバーは、メインの男の子が、ギター、シンセを弾き、歌を歌い、ベースガイは、弾きながら、スティックを持ってエレキドラムを叩いたり、シンセを操作したり、ふたりともマルチ・プレイヤー。
中盤で、メガネ、三つ編み、金髪、赤ニット、タイト黒パンツの可愛い女子が、1曲ゲストヴォーカルで登場する。ふわふわした高い声が裏返るところが、少しグライムスを思い起こさせる。2012年に結成されて、すでに全米ツアーも敢行する、2013年注目バンド。『Lマガジン』でも、このバンドを、なぜもっとみんなが注目しないのかと熱い思いが書かれている。
https://www.thelmagazine.com/...
■エド・シュレイダーズ・ミュージック・ビート:https://edschradersmusicbeat.blogspot.com
何年か前にp.s1(クイーンズにある現代美術館)で彼らのプレイを偶然見て以来、もう1回見たいと思っていた。M.I.Aか本の展覧会を見に行って、帰ろうと、館内から外に出るときに、階段の踊り場でセットアップしていたのが彼らだった。ライトニングボルトに、ポップ・ソングを乗せた(+叫び系)と言ったらわかりやすいかな。
2ピースで、ベースとフロア・タムそして歌、というシンプルなセット。ヴォーカル(エド)はフロア・タムを叩きながら、ライトのスイッチ(タムのなかから照らしている)を足でオン・オフしたり、Tシャツでタムを覆って音を調節したり(タムに直接ペンで演目が書いてある)、自分の家の鍵の束をタムに載せてジャラジャラ音を出しながらそのまま叩いたりの新世代感覚。普通、家の鍵をドラムに載せて音を出そうなんて発想は古典的なバンドには起こらないだろう。
上半身裸で、タムにライトをチカチカさせ(下から照らすのでゴースト見たいに見える)、あまりに近くで見るので(ステージでなくフロア)、例えば、'I can't stop eating sugar'を言い続けているだけの歌なのに、訴えかけ方がハンパなく、がんがん心動かされる。
すべての歌が短く、いきなり終わるし、後奏がないし、アカペラがあるし、ところどころで今日のバンドや会場、お客さんに感謝の念を忘れないし、とっちらかっているパワフルさがこのバンドの魅力。
会場の都合で、共演バンドがバラバラなことが多く、目当てのバンドが終わるとさっさと帰ってしまうことも多いなか、今回は、最初から最後までいたお客さんが多かったように思う。共演バンドが、お互いを尊敬し合い、今日を「いままででいちばんのショー」、と思ってプレイするバンドの姿勢と気合が見えた。
仲が良いので、一緒にツアーしているのかと思ったが、実際はバラバラで、フリー・ブラッドはプロヴィデンス、ジャマイカン・クイーンズはフィラデルフィア、エド・シュライダーは、フィラデルフィア(ジャマイカン・クイーンズとは違うショー)から別々に来たらしい。
こんな貴重な瞬間に立ち会え、こんなバンドたちがいる限り、ショーに行くのはやめられない。オーガナイズをしたシェ・スタジアムに感謝しつつ、来週は誰が来るか、チェックしたら、ミネアポリスからハーマー・スーパースターの友だちの日本人男の子ふたり組が来るみたい。
ハード・ミニマルとは、ジェフ・ミルズがひとりで切り拓いたダンスのサブジャンルだ。最近ではそれが、大雑把に言って、インダストリアル・ミニマルとして呼び名の元でリヴァイヴァルしている。20年後にして、『ウェイヴフォーム・トランスミッション』のようなサウンドをふたたび聴くことになるとは思ってもいなかった。そして、ジェフ・ミルズがそうしたリヴァイヴァル現象を良く思っているはずもなかった......。
昨年の、彼自身のレーベル〈アクシス〉20周年を記念してのベスト盤『シーケンス』を経てリリースされるジェフ・ミルズの新作は、驚くべきことに、宇宙飛行士である毛利衛との共作となった。毛利衛がストーリーを書いて、ジェフ・ミルズが音を加えた。『ウェア・ライト・エンズ』=明かりが消えるところ=闇=宇宙ないしは宇宙体験がテーマだ。
精力的な活動を続けながら、とにかく迎合することを忌避し、誰もやっていないことにエネルギーを注ぐデトロイト・テクノの重要人物のひとりに話を聞いた。
僕のインダストリアルな感覚は、もともとファイナル・カットのスタイルから来ている。当時、デトロイトでウィザードとしてDJをやっていたときも、インダストリアルとハウスとテクノをミックスしていた。
 Jeff Mills Where Light Ends U/M/A/A Inc. |
 Jeff Mills SEQUENCE-A Retrospective of Axis Records(2CD Japan Edition) U/M/A/A Inc. |
■この取材では、新作の『ウェア・ライト・エンズ』について、そして、昨年の〈アクシス〉レーベル20周年にも焦点を当ててやりたいと思います。
ジェフ:これから何をしたいのか、何を考えているのか話すことのほうが興味深いかもしれないけどね。
■ぜひ、過去と未来のふたつで。
ジェフ:何かについての作品を作るというプロジェクトをやり続けてきている。その基盤がいまできていて、それは10年、15年前にはなかったことだから、ぜひ先のことについても話したいんだ。
■若い読者も多いので、昔のことも訊かせて下さい。
ジェフ:オッケー。
■昨年、〈アクシス〉レーベル20周年企画のBOXセット『シーケンス』を出しましたが、ジェフが自分で書いたそれぞれの曲に関するコメントが面白かったです。そのなかで、〈アクシス〉レーベルのマニフェストとして、最初に「AXISは失敗を犯さない。失敗とは目的と計画が明確ではない場合にあり得ることであるからだ」とありますよね。ジェフらしい言葉だなと思いましたが、これはあなたの人生にも当てはまることですか?
ジェフ:ノー(笑)。人生には当てはまらない。
■はははは。
ジェフ:アイデアにチャレンジして、そしてうまくいかなかったとしても、それが他の場面で役に立つこともある。失敗を失敗として片付けてしまうことはない。アクションを起こしてからアイデアをキャンセルしたこともない。別の機会をうかがうということもつねに考えているから。
それは、自分以外の、ほかのインディペンデント・レーベルをやっている人たちの視点を変えることでもある。つねに、正解はない。状況が変われば結果に結びつく。だからすべてはポジティヴであって、ネガティヴに捉えることはないと思っている。
■なるほど。失敗と言えば、"コンドル・トゥ・マヨルカ"という曲のエピソードも面白かったですね。プロモーターが迎えに来なくて、マヨルカ島行きの飛行機に乗り遅れて、せっかくの休暇が台無しになった話です。あの曲に、まさかそんな背景があったとは(笑)......その旅費は、その曲を作ることで取り戻せたのですね?
ジェフ:あのときは、まったくがっかりした。とてもタフな体験だった。いまのようにビジネスクラスに乗れるわけではなかったし、まだ空の旅にはいろいろな制約があった。あのときの自分にできることは、このバカげた体験に関するトラックを作ることだけだった。お金のためというか、ちょうどのその頃、『ウェイヴフォーム・トランスミッションvol.3』(1994年)を作っていたので、旅ということで、そのアルバムにもうまくハマるんじゃないかと考えた。当時はDJとしてツアーするのも乗り継ぎなど大変だったな。若かったからできたんだと思う。
■『ウェイヴフォーム・トランスミッションvol.1』の1曲目は、"デア・クラング・デア・ファミリエ"というラブパレードのテーマ曲でもあったトラックを使っていますが、初期のあなたにとってベルリンとはとても重要な都市だったと思います。当時のベルリンに関する思い出を教えてください。
ジェフ:初めてベルリンに行ったのは、1989年だった。インダストリアル・バンドのファイナル・カットのメンバーとして行った。そのときにトーマス・フェルマンやモーリッツ・オズワルドたちと知り合った。
デトロイト・テクノの初期の頃、デリック・メイ、ホアン・アトキンス、ケヴィン・サンダーソンたちはイギリスを中心にツアーしていた。そこで、僕とマイク・バンクスはドイツを選んだ。最初、僕たちにとってのドイツの窓口は、〈トレゾア〉だけだった。〈トレゾア〉が自分たちの音楽に興味を持ってくれたからね。そして、リリースできるかもしれないという話から、デトロイトとベルリンとの関係がはじまった。ちょうどデトロイトでも、デリックやホアンたちとは別の、テクノの進化型が生まれつつあった時期だった。ベルリンではラヴパレードやメイデイがはじまって、メディアも創刊されて、すべてが新しかった。
■当時のあなたの作品は、とてもハードでした。あのハードさはどこから来たものなんでしょうか?
ジェフ:ああいうインダストリアルな感覚は、もともとファイナル・カットのスタイルから来ている。当時、デトロイトでウィザードとしてDJをやっていたときも、インダストリアルとハウスとテクノをミックスしていた。ミート・ビート・マニフェストとスクーリー・DとDJピエールをミックスするようなスタイルだね(笑)。だから音楽を制作するうえでもいろいろな要素が加えられた。それにマイク・バンクスは、フォースフルな(力を持った)音楽の必要性を考えていた。また、ヨーロッパのクラウドの規模がだんだん大きくなって、1万人規模の人たちを動かすことを考えると、密度であったり、強さを持ったものではないと効果はでなかった。
最初にヨーロッパに行ったときは、僕にはそんな考えはなかったよ。ヴォーカル・ハウスだったり、ハードではない音楽をプレイしていた。しかし、ハードでなければダンスしてもらえない。相手のドイツ人はそんなにうまくダンスできる人たちでもない。それで考えたのが、もっとカオティックで、踊れなくてもうわーっと熱狂できるような、そしてよりハードでより速い音楽を目指した。必ずしもそれがもっともやりたいことではなかったけれど、効果はあった。自分では、ソウルフルな音楽を作りたいと思っていたんだけどね。
■初期の頃のあなたはヘッドフォンだけを使って、低い音量で作っていたとありますが、そのことも意外に思いました。その理由を教えてください。
ジェフ:音量を下げたほうがすべてのフリーケンシーが聴こえるんだ。スタジオでは、たいていニア・フィールド・スピーカーで音像が目の前に来るようにセッティングしているんだけれど、大きくしてしまうと、音のエンヴェロープが前ではなく頭の後ろで鳴ってしまい、どうなっているのかわかなくなる。もちろん大きな、ちゃんと設備の整ったスタジオなら大きな音を出してもすべての音がしっかり聴こえる。しかし、インディペンデントでやっている小さなスピーカーでは難しい。フルステレオの音の領域を聴くには、小さな音量のほうがいいこともある。さらにヘッドフォンで聴けば、サウンドのロスが少ない。これがレコーディングの話だ。
ところが現場では、スピーカーがぜんぜん違う。ロウが強くて、中域がなくて、高音が強いという、いわゆるクラブの音になるので、スタジオで作業していたときの音との違いに気がつく。だから現場でどう鳴るのかを補正しながら作っていくようになるんだ。90年代なかばのトレンドは、各チャンネルの音量を目一杯上げて作ることだった。それがエレクトロニック・ミュージックがミニマルになっていく大きな要因でもあったし、ある意味、音が画一化されていく要因でもあった。
音楽はどういう風に聴くかでも変化するものだろうね。現代のPCDJたちは、ヘッドフォンすら使わなくなっている。つまり、出音で、オーディエンスに聴こえる音と同じ音でDJしているわけだ。それによってサウンドのクオリティは良くなってくべきだ。
■あなたのベースに対する考え方を教えてもらえますか? あなたのベースのアプローチの仕方はユニークだと思います。
ジェフ:ベースラインは、デトロイトの音楽にとって重要な要素だ。僕は、メロディとベースを同時に弾いている。右手でメロディを弾いて、左手でベースラインを弾いている。右手と左手が同時に鍵盤を押すことはない。ベースとメロディが同時に鳴っていることはないんだ。タイミングがあって、順序がある。普通のやり方とは違っているから、独特なベースになっているんだと思う。
■パーカッシヴな感覚ですか?
ジェフ:そうだね。パーカッションに近いと思う。
■あるジャズ・ミュージシャンによれば、あなたの音楽は譜面に書くとブルースだそうですね。自分では意識していますか?
ジェフ:それは僕が生まれてから生きてきた長い人生の経験、環境から来ていることだ。子供の頃に何を聴いて、そして、どれが良い音楽なのか、そうした判断力などすべてと関係している。モータウン、ジャズやブルース、ゴスペルからの影響を無視して語るわけにはいかない。音楽は、自分がどういう風に感じているのかを反映するものだから、デトロイト・テクノにはある種のブルース・フィーリングが滲み出ているんだろう。
[[SplitPage]]いまだにうまく説明できないことが多くあることに驚きを覚えた。とくに宇宙の暗さ、闇の深さ、黒さは、僕たちが見ている黒さを越えた黒さがある。地球にはない黒さだから、その説明が難しいんだろう。
■あなたがデトロイトを離れて久しいですが、デトロイトに戻らない理由をあらためて教えてください。
ジェフ:そこは、もう自分が育ったデトロイトではないからだよ。犯罪や経済のことを言っているんじゃない。人が変わってしまった。80年代なかばには多くの人がエクソダスした。90年代には人びとの精神が変化してしまった。自分がDJするためだけでも戻らない理由は、トゥー・マッチだからだ。どこでやるのか、誰のパーティでやるのか、ベルリンもそうだが、小さなエリア内に多くのプロデューサーがいると、批評も度が過ぎて、別のことでジャッジされてしまう。人間関係のちょっとした政治が生まれてしまう。そういう人間関係がある場所では、純粋に楽しめない。たとえばウィザード名義でデトロイトでやったとしても、昔踊っていた人たちは来ないし、何でヒップホップをかけているの? と思われてしまう。昔のように、聴いたことがない音楽を聴きに来る人たちが少なくなってしまった。フェスティヴァルをやっても、当たり前のメンツが出るだけだからね。
■もし100万円で宇宙旅行に行けたら行きますか?
ジェフ:100万円じゃ安いだろ(笑)!
■あ、そうか(笑)。では、いくらまでだったら真剣に宇宙旅行を考えますか?
ジェフ:いくらにしようか......(笑)。うーん、まあ、1億で行けるなら払う(笑)!
■新作の『ホエア・ライト・エンズ』を作るきっかけになった宇宙飛行士との対話ですが、あなたがもっとも強く印象に残っている話なんでしょうか?
ジェフ:彼には多くの質問をしたんだけど、いまだにうまく説明できないことが多くあることに驚きを覚えた。とくに宇宙の暗さ、闇の深さ、黒さは、僕たちが見ている黒さを越えた黒さがある。地球にはない黒さだから、その説明が難しいんだろう。他には、大気や湿気がないから、どれだけ外がクリアに、鮮明に見えるか、そのことを彼がいまだにうまく説明できないこと。もう20年も講演会などで話していることなのに、いまだに説明できないこと、それが実に興味深かった。
■その宇宙飛行士、毛利(衛)さんが今回の作品に寄せたコメントも興味深いですよね。「彼の音楽を聴いた私は、正直、宇宙で聴きたいものではないと感じました。なぜなら、宇宙ではむしろ自分が地球にいたことを感じられるような安心感を得たいからです。彼の音楽は、まさに宇宙そのものを表現していました」とありますね。
ジェフ:宇宙にいるというのは、いつ危険な目に遭うかわからない。決してイージーな場所ではないから。僕の音楽が毛利さんにそういう緊張感を思い出させたのではないだろうか。そして僕の音楽が宇宙とはそれほど遠くはない、いつか行ける場所であるんだという身近な感覚をもたらしているのであれば、それはいいんじゃないかと思う。
■「AXISは未来の音楽を制作しているのではない。未来を考える理由を制作している」とあなたは言いますが、「未来を考える」には何らかの問題意識があるはずです。それは何でしょうか?
ジェフ:メンタル的なこと、精神病的な状況に問題を感じている。アメリカでは、診療心理学的にアウトな状態ではなくても、精神病的になっている人が大勢いる。ある種の躁鬱病的に、現実を正しく受け止めることができない人がたくさんいるのではないかと思う。現実を受け止められず、現実の社会を合理的に捉えることができない人たち、非論理的なことが社会に浸食するかもしれない。たとえば、インターネット上では、クレイジーなことを書き込んでいるのに、いざ人前に立つと普通に振る舞っている人がいる。そういう潜在的な、おかしい人たちがこれから増えていくだろうね。
■ひとりのオーガナイザーが同じ時間帯、同じギャランティでDJをやって欲しいと、ただし、場所だけは自分で選べと言われたらどんなところでDJをやりたいですか?
ジェフ:僕たちと一緒に成長していった人たちに囲まれてやりたい。昔から知っている友人たちと一緒に、音楽で繋がっている人たちに囲まれてやりたい。音楽のコンテクストも理解している人たち、音楽の背景も理解している人たちのなかで。そのパーティはスペシャルなものになるだろう。
■ふだん、家にいるときに、自分がリラックスするためにはどんな音楽を聴いていますか?
ジェフ:ジャズをよく聴いている、あるいは......ディスコを聴くことも多いね。
■ディスコを聴いていたらリラックスするというか、気持ちが上がってしまいませんか?
ジェフ:いや、全盛期のディスコは、最高の演奏者による最高の録音物でもあるから。クオリティが高く、とてもプロフェッショナルな作品が多いし、ダンス・ミュージックとしてはもっとも進化した形態だったと思う。最高級の職人芸による賜物だよ。いまのダンス・ミュージックはもう、ホームスタジオで、ひとりで作るものになっているけど、ディスコの時代のプロダクションには、才能あるベーシスト、最高のドラマーがいて、最高のスタジオと素晴らしいエンジニアもいる。そうした最高のクオリティを楽しむためにディスコを聴くんだ。
■"ジ・インダストリー・オブ・ドリーム"では、「人類は夢を生産する目的のための家畜に過ぎない」というコンセプトがありますが、これは何のメタファーなのでしょう?
ジェフ:僕たちが家畜を飼っているのではなく、僕たち自身が家畜かもしれないという発想から来ているんだけど、それはあくまでも、『ザ・メッセンジャー』(2011年)というアルバムのために描いたシナリオのいち部。僕はふだん考えていないことを考えるきっかけを作っているんだ。
■それでは最後の質問ですが、ここ数年、90年代初頭のテクノがリヴァイヴァルしていますが、どう思いますか?
ジェフ:まったく興味がないし、実につまらない現象だと思う。現代は、90年代とは環境も違うわけだし、いまのテクノロジーを使えばずっと進化した音楽を作れるはずだ。いまさら90年代に戻る必要などない。
■しかし、ときとして、歴史を知ることも必要なのでは?
ジェフ:いや、そうは思わないな。いまさら"ストリングス・オブ・ライフ"を知る必要もない。若い人たちは、歴史に囚われずに未来を見て欲しいと思う。
JEFF MILLS(ジェフ・ミルズ)新作動画公開、と同時に「宇宙新聞」(号外)を発行!!
毛利衛氏とのコラボによる新作アルバム『Where Light Ends』いよいよ発売!!
日本科学未来館館長・宇宙飛行士 毛利衛氏とのコラボレイトによるジェフ・ミルズの新作『Where Light Ends』が、本日4月3日(水)に発売される。
これまで宇宙をテーマに作品を作り続けてきたジェフ・ミルズが実際の宇宙体験を持つ宇宙飛行士とコラボレイトして作品を作り上げたことや、ジェフとして初めて他アーティストによるリミックス作品を自身のオリジナル・アルバムに収録したことでも話題を呼んでおり、KEN ISHII、Q'HEY、Gonno、DUB-Russell、MONOTIX、Calla Soiledらベテランから気鋭のアーティストまでが名を連ねる作品となっている。
そして今回、『Where Light Ends』の発売と同じくして公開されたのがアルバムからの1曲“STS-47: Up Into The Beyond”をフィーチャーした新作動画「Jeff Mills "Where Light Ends" Comic Video」である。
「Jeff Mills "Where Light Ends" Comic Video」この動画では、本アルバムの制作にあたるジェフ・ミルズ自身の姿と、毛利氏のオリジナル・ストーリーの中で描かれた宇宙観が表現されたもので、ジェフが幼少期にSF作品に触れ多大な影響を受けたアメリカン・コミックの手法が用いられている。
この動画の制作を手がけたのは、LA在住のGustavo Alberto Garcia Vaca(グスタボ・アルベルト・ガルシア・ヴァカ)とKenny Keil (ケニー・ケイル)というふたりのアーティストで、それぞれ音楽とコラボレイトした作品も多数発表しており、今回は英語版に先駆けて日本語Ver.が公開された。
また今回、来日中のさまざまなイヴェントで配布されたのがジェフ・ミルズ発案による「宇宙新聞(スペース・タイムス)」である。この新聞のなかでは『Where Light Ends』が作られるにいたった経緯や、関係者のインタヴュー、宇宙関連の基礎的情報から最新のトピックスまで紹介されている。JEFF MILLSの作品をリリースしている音楽レーベル、〈U/M/A/A〉のHPで見ることができるのでこちらもぜひご覧頂きたい。
宇宙新聞Link(U/M/A/A)
https://www.umaa.net/news/p517.html
JEFF MILLS アーティスト・プロフィール [U/M/A/A HP]:
https://www.umaa.net/what/wherelightends.html
メジャー・レイザーが帰ってきた! 別にどこかに行っていたわけじゃないんだけど。
僕は、メジャー・レイザーの『ガンズ・ドント・キル・ピープル・レイザーズ・ドゥ(銃は人を殺さない......レイザーはやる)』(2009年)が好きだ。レゲエが、冗談が、ポップが、軽薄さが好きだ。ジャマイカのゆるさが、リディムとベースが、いい加減さが......
こう言ってはナンだが、この音楽は政治的だ。なにせ、同性愛嫌悪でリベラル派から非難を浴びていたダンスホールのMCを引っ張ってきて、一緒に踊らせている。説教くさい連中とはやり方がひと味違っている。
メジャー・レイザーには、ディプロ、そしてスイッチのふたりがいるから良いという意見がある。その観点で言えば、4年ぶりの『フリー・ザ・ユニヴァース』には一抹の不安があるかもしれない。スイッチはプロジェクトを去った。新生メジャー・レイザーといっても、スイッチが抜けただけではないのか......と思っても無理はない。
しかし、僕は、昨年リリースされた7インチ、「ゲット・フリー」、ダーティー・プロジェクターズのアンバー・コフマンがロックステディ風にレゲエを歌うこの曲を聴いたとき、心配が無用だとわかった。新作『フリー・ザ・ユニヴァース』を聴いたいま、自分がこの音楽のファンであることを再認識している。
周知のように、メジャー・レイザーはディプロのレゲエ・プロジェクトだが、新作には、ジューク(ニューオーリンズ・バウンス)風のビート、ジャングル、レイヴ、ダブステップ、トライバルなど多彩なビートがミックスされている。MCやシンガーのメンツは、信じられないほど豪華だ。ダンスホールの大物、シャギーやエレファント・マン、ヴァイブス・カーテル、、ヴァンパイア・ウィークエンドのエズラ・クーニグ、ダーティー・プロジェクターズのアンバー・コフマン、ピーチーズ、サンティゴールド、オランダのベテラン・テクノDJ、レイドバック・ルーク、UKのベテラン女性MC、ミス・ダイナマイト......そしてワイクリフ・ジョン等々。『フリー・ザ・ユニヴァース』は、4月10日に発売。
Watch Out For This(Bummaye Lyric Video)
Get Free (feat. Amber of Dirty Projectors)
Jah No Partial (feat. Flux Pavilion)
チャージしなければと思って券売機の前に並んでいたら、前のやつがあまりに遅い。なにをどうすればそんなに時間がかかるのかと思うほど、券売機の前から動かない。社会を混乱させるために左翼が考え出した新手のひとりデモかと思いはじめたあたりで、やっとそいつがどいた。その間に隣の列は3人ぐらい進んでいた。僕の後ろには誰もいない。ここで「前のやつ」に過剰な憎しみを覚えるのがレイシストというやつに繋がるのではないかと思うけれど、世のなかには切符を買おうがチャージしようが、このような制度に慣れていない人はまだけっこういることもたしかである。それなのにディジタル化された券売機は以前より数が減り、たまに切符を買ったり、チャージしようと思うと、以前と同じことをやっていても、よりストレスは高負荷になっている。悪いのは券売機の数が減ったことや、新しい制度に慣れさせようとしていることだと思うのに、それにまだ順応できない人たちがイラダチの対象になってしまう。少し前、友人たち何人かと電車に乗るとき、僕はわざとひとりだけ切符を買うようにしてみた。僕ひとりが切符を買うために全体の動きが遅れる。これに文句を言う人はけっこういた。面と向かって文句は言わないものの、「なんでSUICAを使わないの?」と聞いてくる人はかなり多く、文句を言う人と同じことを感じているのはありありとわかった。「持っているよ」といってSUICAを見せると、それ以上、文句を言う人はいなかった。
個人に文句を言うことはたやすい。「お前さえいなければ、すぐにチャージができるんだ」と。システムに疑問をぶつけても、返事が返ってくることはまずない。社会や鉄道制度を変えることは、ほとんどの場合、個人の手には余る。僕も自動改札をやめたらいいと思うわけではない。それを制度として理解し、従順に利用するだけである。それはその制度が追求してきた効率性という価値観を共有し、券売機の列に並ぶことを「待たされる快楽」として認識できなかったからである。インド人は待たされることが最高の楽しみだという記述をどこかで読んだことがあるけれど、そのような世界観を共有できれば、「前のやつ」も「制度」もすべては疑問の対象外となり、楽しく暮らせるのかもしれないけれど......
「スロウフット=足が遅い」と名乗るダンス・レーベルがようやくまとめた『ジェットの軌跡を残す』というコンピレイションがとてもよかった......ので、以上のようなことを思わず考えた。なるほど2001年からスタートして、いまだに21作しかリリースされていないとは奄美出身の松村正人も驚きだろう。松村くんといえば(......ま、いいか)。しかも、僕がこのレーベルの存在に気づいたのは、2年前、ハーバートの「ワン」シリーズに参加してい(て、来日メンバーでもあっ)たクルードスンがデビュー・アルバムとなる『グラヴィティ』をリリースしたからで、ほかに名の通ったミュージシャンもプロデューサーも誰もいない。当然のことながら『ジェットの軌跡......』もクルードスンだけが目当てで聴いてみた。そして、その無名の嵐どもがやろうとしてきたことにあっさりと持っていかれてしまったのである。ひと言で言おう。このレーベルがやろうとしてきたことは、(次号のエレキングで特集した)元ヴェクスドやアンディ・ストットとは対照的にダブステップをインダストリアルの文脈で理解するのではなく、アシッド・ジャズやブロークン・ビーツの延長にあるものとして捉え、そこにポテンシャリティのありったけを注いだものなのである。生楽器を持ち出す人もいるし、スウィング感を出すだけで終わっている人もいる。もちろんダブステップでもなんでもない人も混ざっている。アフロ・ビート、UKガラージ、クラウトロック、ミュージック・コンクレートも召喚されている。寄り道もたいがいにしろと思うような折衷ぶりで、なるほど、「足が遅い」からできたことだという気はする。
ひとりひとりが......というよりは全体で面白い内容になっていると思うんだけど、そのなかにはディス・ヒートのチャールズ・ヘイワードによるモンキー・パズル・トリオも含まれている。流れで聴いていると、これはさすがにダブステップには聴こえないものの、大して違和感がなく収まっているのはやはりレーベル・マジックとしか思えない。3年前にリリースされたイタリアの新鋭、ゴルとのジョイント・アルバムがあまりに旧態としていてアヴァンギャルド・ミュージックに限界を感じるようになったきっかけでもあったので、このようなリクルートは素直に嬉しいものがある。あるいは編集の手腕というのかな(ちなみに同じくディス・ヒートのチャールズ・バレンはサーカディアン・リズムの名義で98年にデトロイト・テクノのアルバム『インターナル・クロック』をリリースしている)。
対照的にサラブレッド的な存在感を放っていたマシュウデイヴィッドのリーヴィングは金でモメたか何かしたみたいで、初のレーベル・コンピレイションをブレインフィーダーではなく〈ストーンズ・スロウ〉からリリースすることになった(正確には昨年、カセットでリリースしていたものからマシュウデイヴィッドによるスキットを除いた構成に)。これも同じようにオープニングはジャズ・ドラム。続いてサイクリストによるテクノもどきからマシュウデイヴィッドとセレンゲティことデヴィッド・コーンによるデイヴィスのクラウド・ラップ(?)へと続き、なんとなくグダグダに曲がつながっていく。並べ方の問題なのか、僕の心が捻じ曲がっているのか、ダク(=屋根)やヤック(=不潔なもの)など、面白い曲はけっこうあるのにどれも引き立っていないように聴こえてしまい、全体としては満足感が低い。サン・アローやアンチコンのオッド・ノズダムなどリーヴィングに縁のあったミュージシャンは総出でフィーチャーされ、ジュリア・ホルターに至ってはアーサー・ラッセルへのトリビュート・ソングがそれなりにいい感じにもかかわらず、客席が騒々しくて誰も聴いてないライヴ・ヴァージョンが収録されていたり(なんで?)。
もっとも聴きたかったのはデム・ハンガー。これは、どんよりとしたスペイシー・ブレイクビーツで......曲がちょっと短かいせいもあって、もっと聴きたくなった。あんまり聴きたくなかったのに入っていたのがランDMT。しかも、これは......サン・アローのパクリだろうか?(エンディングのセーミアも同一人物) カップ・ケイヴとキングフィッシャーグによるセアリヴァや優雅な作風を聴かせるディンテルなど、不思議なコネクションのものもあれば、トランス・ファーマーズやラプチィなどなんだかわからないものが上手く混ざり合ってはいるので、一応は成功なのだろう。〈リーヴィング〉が目をつけているところもありきたりなものではないし、この先、なにが起きるかわからないと思わせるだけのものはある。最初のリリースから(まだ? もう?)5年。マシュウデイヴィッドは、しかし、何かを少し急ぎすぎてしまった気がしないでもない......
マリ共和国の名歌手サリフ・ケイタのこの新作は、ちょっと枯れたエキゾチックな哀愁味のある歌手が、ボビー・マクファーリン、エスペランサといったアメリカのジャズ系歌手や、イギリスのラッパー、ルーツ・マヌーヴァをゲストに迎えた、エキゾチックなポップ・ヴォーカル・アルバムということになるだろう。
アルバムのプロデューサーは、フィリップ・コーエン・ソラール。90年代末にタンゴとエレクトロニックなドラムのビートを組み合わせて、フロアでもリスニング・ルームでも聞ける音楽を作り出したゴタン・プロジェクトの中心人物だ。
レゲエのファンがダブを聴けば、レゲエの典型的なリズムの一部分しか鳴っていなくても、頭の中で音を補ってレゲエを連想できるように、タンゴをダブ的手法で分解し、再構成したゴタン・プロジェクトの音楽は、タンゴを少しでも知っている人が聴けば、音を補って容易にタンゴを連想できた。
フィリップ・コーエンは、その手法をこのアルバムでも応用している。といっても、サリフ・ケイタにタンゴをうたわせているわけではなく、マンデ・ポップと呼ばれる西アフリカのポップスをその手法で料理しているのだ。
"ダ""また明日""サンフィ"などは、打ち込みのダンス・リズムが強調されたり、細部にダブ処理が施されたりしているが、これまでの彼の音楽を踏襲した典型的なマンデ・ポップ。子供がフランス語でコーラスする"ナディ"はマンデ・ポップのディスコ化だし、"タレ"のマンデ・ポップ風の女声コーラスは終盤では欧米風に変化していく。"タッシー"はキューバン・リズムを使った親しみやすい歌ものだ。
2曲目の"セ・ボン、セ・ボン"はいちばん複雑で、ダブ的な音処理をほどこしたトラックにのって、マンデ・ポップ的な女声コーラスのくりかえしや、パセティックなサリフの歌や、ルーツ・マヌーヴァのラップが入れかわりたちかわり現われる。最もフィリップ・コーエンならではと思わせるのは"明後日"という曲。歌は断片的に入るだけで、"ソウル・マコッサ"のヒットで知られるカメルーンのマヌ・ディバンゴのサックスをフィーチャーした完全なダブ・ナンバーだ。
西アフリカの伝統的なリズム・アンサンブルの緻密さを求める人には好まれないかもしれないが、弦楽器のンゴニやコラをはじめ、細部では伝統的な楽器も使って、ダブが伝統と乖離するものでないことをさりげなく匂わせる。リズムや和音のこの豊かな引き出しはフレデリック・ガリアーノと西アフリカのミュージシャンの10年前の先駆的な試みにはなかったものだ。サリフ・ケイタのポップな面を見事に引き出したアルバムだと思う。






