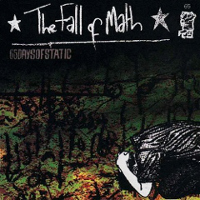英国映画の定番。というか、誰の家に行っても必ず本棚に並んでいるDVDがある。で、そういう映画ほどなぜか日本では観ることができないことが多い。
例えば、シェーン・メドウズ監督の『メイド・オブ・ストーン』が日本公開された時。
宣伝する側は(わたしも含めて)「『This Is England』の監督が撮ったストーン・ローゼズのドキュメンタリー」と書いた。しかし、実際にメドウズが初めてイアン・ブラウンに会った時、イアンは「僕は君の『Dead Man’s Shoes』が大好きだよ」とメドウズに言ったのであり、ジョン・スクワイアも「『Dead Man’s Shoes』の監督だからシェーンに(ドキュメンタリーを)任せようと思った」と『メイド・オブ・ストーン』のUKプレミアで語った。
つまり、英国の音楽や映画が好きな人々の間では、シェーン・メドウズといえば『Dead Man’s Shoes』の監督なのだが、残念なことに日本では公開されていない。見れない映画について書いたところでしょうがないと思いつつ、拙著にこの映画のレヴューを入れたのは、UKの音楽やカルチャーが好きな人は押さえておくべき1本だと思ったからだ。
そしてこの『ウィズネイルと僕』こそ、そういう映画の代表的作品である。
わたしが10年前にHP活動をはじめた時、ジョン・ライドンの応援ページ(当時、世間はB級セレブ番組に出演したライドンへの非難と怒号に満ちていた)と共に作成したのが、この映画のページだった。
その後、この映画の邦版DVD発売を求める運動を行っている方々の存在を知った。日本でも吉祥寺バウスシアターで単館上映されたことがあると知った。で、そのバウスシアターが閉館するという。そのクロージング・イヴェントが行われている5月を通じて、同館が上映しているのが『ウィズネイルと僕』らしい。バウスの閉館を飾るのに、これほど相応しい作品があるだろうか。別の言葉で言えば、『ウィズネイルと僕』を日本で唯一上映したような映画館が閉じるのである。日本の人々はそれでいいのか。わたしが日本にいたら暴れる。
************
いまデーモン・アルバーンのソロを聴いているのだが、デーモンも『ウィズネイルと僕』ラヴァーであることを公言している(そう思うと、彼のソロはパロディ・アルバムじゃないかというわたしの疑念はいよいよ強まる)。
そういえば、ブリットポップ期は『さらば青春の光』と『ウィズネイルと僕』人気の再燃期でもあった。ブラーとオアシスがこの2作を「好きな映画」に挙げたからだ。オアシスがモッズの『さらば青春の光』派で、ブラーが『ウィズネイルと僕』派といえばいかにもの構図だが、実はその辺が微妙にクロスオーヴァーもしていて、デーモンは“パークライフ”で『さらば青春の光』のフィル・ダニエルズとデュエットし、リアムは『ウィズネイルと僕』でリチャード・E・グラントが着用したコートをTV司会者と取り合って話題になった(リアムはオークションで競り負けた)。
モリッシーの『Vauxhall & I』のタイトルが『ウィズネイルと僕(“Withnail & I”)』にちなんだものであることは知られているし、米国のキングス・オブ・レオンの曲の歌詞にも「Withnail & I」は登場する。元ミュージシャンのジョニー・デップは「死ぬ前に見たい映画」に本作を挙げているし、UKでもっとも激辛な映画批評を書くガーディアン紙の名物ライター、ピーター・ブラッドショーがレヴューで5つ星を付けた奇跡のような映画でもある。
この映画がそれほど人びとを魅了するのは何故だろう。
それは、一言でいえば「UKらしさ」だとわたしは思っている。
ここでわたしが言うUKとは、ガーデニングとかアフタヌーン・ティーとかのUKではない。それらの要素はどうでもいいんだけど、それでも「UK好き」を自認する人は、好きな要素がすべてここにあるだろう。
悲喜劇。は英国人が得意とする分野だ。しかし『ウィズネイルと僕』は喜悲劇の域に達している。
「後にも先にも、この映画のような作品は存在しない」
と、あのピーター・ブラッドショーが書く所以である。
これは「笑って泣かせる」映画じゃない。あるシーンでは笑わせ、次のシーンでは泣かせるような作品ではないのだ。全編を通じて「大笑いしながらも心の奥底で泣きたい」ような映画だ。
ふたりの売れない俳優志望の青年が、だらだらといい加減に日常を生きているというだけのストーリーは、誰も死なないし、何らの衝撃的なツイストがあるわけでもない。ただ全編ふざけているだけのような映画でもある。だが、大笑いさせられながらも何故か奥底にくすぶっていたせつなさを一気に噴出させるようなラストシーン。雨の中でウィズネイルがロンドン動物園のオオカミたちを前に「ハムレット」のセリフを朗々と叫ぶ場面は英国映画史上に残る名シーンである。
やることなすこと失敗し、アル中になったブランメルみたいなウィズネイルというキャラクターは、セックス・ピストルズのジョニー・ロットンやグレアム・グリーンの「ブライトン・ロック」のピンキーに匹敵するアンチ・ヒーローでもある。
UKほど魅力的なアンチ・ヒーローを生み出す国はない。
UKほど滑稽なルーザーをクールに見せる国はない。
それは英国が負けるということの美学を、勇ましく竹槍を突き上げることのダサさを知り抜いている国だからだろう。この国のヒーローは「勝つ」なんて無粋なことをしてはいけないのだ。
その証拠に、リアム・ギャラガーだけではない。人生のある時点で、猛烈にウィズネイルのコートを着てみたかったという英国人の男性をわたしは何人も知っている。