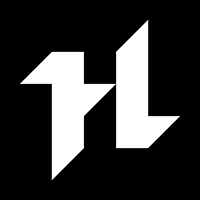ギターによる弾き語りを中心に演奏活動を行いながらも、映画やアニメーションの音楽も手がけ、あるいはミュージック・ビデオやアクリル画の制作から自主レーベルの運営まで、シンガー・ソングライターの枠に収まりきらない多才さをみせる音楽家、ハナカタマサキ。『Lentment』は、そうした彼のデビュー・アルバムとなる作品である。本盤に収録された数々の楽器による演奏、たとえばギター、ウクレレ、バンジョー、マンドリン、シタール、三味線、大正琴、グロッケンシュピール、シロフォン、メロディオン等々……打楽器や玩具楽器を含めればこの倍以上はあると思われるさまざまな楽器による演奏は、すべてハナカタひとりの手によるものだという。さらにはミックスからマスタリングまで、加えてジャケット・デザインも彼によるものである。3年近くもの歳月を費やして制作されたというこのアルバムは、その全行程をハナカタマサキひとりが手がけたと言えるものであり、ファースト・アルバムにふさわしい記念碑的な作品となっている。
あくまで生楽器にこだわって生み出された音楽は、多様な弦楽器が織りなす無国籍的なエキゾティシズムが、ペンギン・カフェ・オーケストラのあらゆるジャンルを渉猟する室内楽的な響きを思わせもすれば、トイピアノや廃物となった空き缶を用いた不安定で不協和な響きを多用するところなど、パスカル・コムラードのラディカルな童心に通ずる部分もある。特徴的なのは、ハードロックに傾倒していた時期に鍛え上げられたという技巧的なギター・フレーズが、プログレッシブ・ロックの影響を匂わせる変則的な拍子と相俟って、複雑な構成美のうちに披露されている点だろうか。しかし技巧派の音楽にありがちな厚かましさは微塵もなく、優しく語りかけるような歌声がアコースティックな楽器による温かい音色と溶け合って親しみ深い音楽になっている。
親しみ深さは音だけではない。本盤に収められた楽曲はどれも1分から3分、長くとも6分には満たない小品なのであるが、そのひとつひとつをテーマとしたさまざまな動物の絵と、最後の楽曲である“OWL”から連想されて描き進められたというフクロウの絵が、40ページにわたる画集となってブックレットに収められている。画家を生業とする両親の影響もあって描きはじめたという絵は、洗練された絵画というよりも、児童文学における挿画のようなものに近い。その暗い色調と多分に抽象的な動物の姿は、ともするとアール・ブリュットふうでもあるが、それがこの音楽とともにあることによって、愛らしさを帯びてくる。音楽も画集も、毒を含みながらそれを喧伝しないスマートな装いが心地いい。
比較されることも多いと思われるトクマルシューゴのミニマリスティックでもある音楽に対して、生楽器に徹したチープな響きと、そうでありながら生演奏で再現することをはじめから目指していないかのような宅録でのこだわりが、ハナカタマサキに独自の魅力を生み出しているのではなかろうか。アルバムには収録されていないが、ここに挙げるキング・クリムゾンの誰もが知るだろう名曲をカヴァーした音源からも、その特異性は聴き取れるはずである。