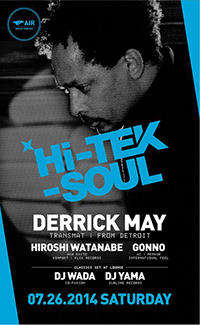How To Dress Well- What Is This Heart? Weird World / ホステス |
「人生を豊かにしようと、意味のあるものにしようとしているんだ」。ハウ・トゥ・ドレス・ウェルの音楽を語るならば、その言葉に尽きる。デビュー作(『ラヴ・リメインズ』)の、割れていびつに増幅されたゴーストのような音像は、セカンド(『トータル・ロス』)においては驚くほどなめらかに整えられ、ポップ・アルバムとしての輪郭を得ることとなった。ひたすらエコーしていたループ・コーラスは、旋律として彫琢され彩色をほどこされて唄のかたちに結実した。R&Bの新世代を象徴するような見られ方をするようになったのはこの頃だ。──ノイズがスムースなR&Bに変化したことを「進化」ととらえるのはあまりに単純・短絡的かもしれないが、クレルにとってそれはおそらく、そのくらいシンプルなことなのではないだろうか。前作のインタヴューからもうかがわれるが、ファーストとセカンドの間には、混乱と克服(整理)という明確な対比がある。ジャケットに自身の顔がフィーチャーされるようになったのもこのことと無関係ではないだろう。音を楽しむのではない、生を豊かにしようというのが彼の音楽であればこそ、クレルは敬虔なまでに思索をつづけ、己れの姿を鍛えようとするのだ。
インディR&B、オルタナティヴR&B、チル&B。ともあれこれはあたらしい時代感覚を持ったR&Bなのだ、という主張とともに見いだされるようになったアーティスト群は、ザ・ウィークエンドしかり、インクしかり、たいていがシンガーとプロデューサーを兼ね、ベッドルーム規模のR&Bを発信することを出発点としていた。それがまさに「インディ」「オルタナティヴ」と冠される彼らのリアリティのひとつであったわけだが、クレルが共有するのはそうしたスタイルや時代感覚であって、R&Bというフォームはむしろ偶然的な要素にすぎないようにみえる。いや、ここまで書いてひっくり返すようだが、彼らはみなそうなのかもしれない。初期においてはウィッチ・ハウスとも交差し、クラムス・カジノらとも比較されるベッドルーム・プロデューサーとして注目を集めたクレルを筆頭に、彼らはブラック・ミュージック史にとっては客人にもひとしいのだろう。しかし、それぞれの出自と、現ポップ・シーンのヘゲモニーたるR&Bとの境界で、彼らはおのおのの領域を拡張しつづけている。
さて、ハウ・トゥ・ドレス・ウェルのサードとなる最新作『ホワット・イズ・ディス・ハート?』がリリースされた。インタヴュー中でも繰り返されるように、本作のテーマは愛、というか本作自体が愛をめぐる思弁そのものである。ピアノが好きだと言っていたが、本作のやさしいピアノは、音楽であるよりもまずクレルの愛の観念をつまびらかにするものだ。ノイズは歌へ、歌は愛へ。アルバム3枚を重ねるなかで、まるで塵と芥から球体の星がひとつできあがるように、彼の生は求心力を得、すべやかに鍛えられている。
よくわからない闇夜のジャケットは、自身の顔の彫像へ、そしてさらにシンプルなポートレートへと変わっていった。こんなふうにパーソナルで尊い心の鍛錬が、普遍的なオルタナティヴとして鳴っていることに筆者は何万度も感動する。
■How To Dress Well(ハウ・トゥ・ドレス・ウェル)
ベルリンを拠点に活動するトム・クレルによるソロ・プロジェクト。新世代のR&Bを象徴的する存在としても注目される。2010年にデビュー作『ラヴ・リメインズ』を〈レフス〉から、2012年にセカンド・アルバム『トータル・ロス』を〈ウィアード・ワールド〉からリリース。2年ぶりとなる新作『ホワット・イズ・ディス・ハート』では、前作にひきつづき共同プロデューサーとしてロディ・マクドナルドを起用。デビュー当時ウィッチ・ハウスにも比較されたミステリアスな音楽性は、アルバムを重ねるごとに歌ものを主体としたポップな相貌を見せるようになっている。
どんな成長も、失うものと新しく得るものの組み合わせなんだよね。剥ぐこと、進化すること、作り出すこと、生み出すこと、探求すること、認めること、否定すること。
■以前にインタヴューさせていただいた折、黒沢清監督の映画『回路(英題:パルス)』に出てくる、人の思念の痕のようなシミと、『ラヴ・リメインズ』(2010年)の音像が似ているというお話をしました。あの彷徨う影のような思いのかたまりは、いまはずいぶんと磨かれて、くっきりとかたちを持つ魂のようになったと感じます。この4年ほどのあいだに、あなたの音と精神生活も、洗練されたり整理されたりしてきたのでしょうか?
トム・クレル:間違いなく『ラヴ・リメインズ』以来成長したとは思うよ──時は過ぎていて、時とともに僕も動いているからね。人生を豊かにしようと、意味のあるものにしようとしているんだ。
■むしろその過程で失ったように思うものはありますか?
TK:どんな成長も、失うものと新しく得るものの組み合わせなんだよね。剥ぐこと、進化すること、作り出すこと、生み出すこと、探求すること、認めること、否定すること。
■このアルバムにおいては、構成や曲順をどのように行っていますか?
TK:どの作品も同じなんだけど、この作品も直感に頼って、非概念的な、「生きた」過程を通って生まれた作品なんだ。曲が揃った時点ですでに順番は見当がついていたよ。
■7曲め“ポー・シリル(Pour Cyril)”の子どものモチーフは具象的なものですか?
TK:具象的であって、具象的ではない。「Broken Child(壊れた子供)」がいてはいけないって僕は本当に信じているからね──壊れた世界なんて世界のあり様じゃないだろ? それから、僕が歌う子ども、「Sweet little life(可愛い小さな命)」は真実、簡潔さ、愛、そして意味を象徴している隠喩なんだ。
■子どものモチーフは他の曲にも散見されますが、人の父になることについて考えるのですか?
TK:もちろんさ──。小さい頃から自分の子どもが生まれることは想像していたよ。子どもが大好きなんだ。バカ正直だし、とにかくおかしい。
■あなたのうたう「愛」は「人類愛」のニュアンスとも少し異なるように思いますが、かといって対象が特定できるほどパーソナルなものですか?
TK:愛はすべてだと思うよ。つねに僕はそれについて歌っている。愛は僕にとっていちばん大切で、ふだん忘れられがちだけど、人間が持つパワーのひとつだと思っている。
■とくにこの曲であなたの特徴でもある過剰にコンプレッサーをかけるようなプロダクションを用いるのはなぜです?
TK:コンプレッサーはそんなに使っていないよ──最近出てきている音楽に比べれば、僕の音楽はグラスのよう、あんまりコンプレッサーにはかかっていない。
愛はすべてだと思うよ。つねに僕はそれについて歌っている。
■以前ココロージー(CocoRosie)のTシャツを着ておられましたがジョアンナ・ニューサム(Joanna Newsom)も好んで聴かれるそうですね。彼女たちのサイケデリックでフォーキーな音楽性は、あなたが「新世代のR&B」というふうに目される以前の音を思い出させます。彼女らへのシンパシーについておうかがいしたいです。
TK:彼らはヴォーカルの先駆者だよ。独特な声で歌い上げるところがとても気に入っているんだ。ココロージーもジョアンナ・ニューサムもとてもディープで考えさせられる歌詞を書くんだよね。
■11曲め“ヴェリー・ベスト・フレンド(Very Best Friend)”などの軽やかなビート感覚がとても新鮮に思われました。詞のシンプルさからみても、ポップスとしての整った輪郭をもった曲だと感じます。こうした曲の誕生には、ロディ・マクドナルド(Rodaidh McDonald)氏のアイディアやアドヴァイスなどもあったりするのでしょうか?
TK:そうでもないんじゃないかな。この曲は一日で書き終えたんだ。とても簡易だけど、「合って」いたんだよね。「Ya it's dumb but sometimes it's just right(間抜けだけどときどきそれが正しいこともある)」って曲中歌っているんだけど、その歌詞こそがこの曲に対しての思いを表しているよ。
■“プレシャス・ラヴ(Precious Love)”では、たとえばマーヴィン・ゲイとダイアナ・ロスを思い出しましたが、この曲や“ワーズ・アイ・ドント・リメンバー(Words I Don't Remember)”など、スムースな手触りのシンセ・ポップやソウル・ナンバーも、前作から発展的に生じた新機軸のひとつではないかと思いますが、いかがですか?
TK:僕の中で“プレシャス・ラヴ”はマーヴィン・ゲイよりもバックストリート・ボーイズなんだよね。とにかくいろんな音楽を聴いてきて、そのすべて(エヴリシング・バット・ザ・ガール、バックストリート・ボーイズ、インフィニット・ボディ、リッチ・ホーミー・クァン、アントニー、ブライアン・マックナイト、スピリチュアライズド、etc.)が、僕の作曲のプロセスに反映されているんだ。
■音楽の豊かさには、それをつくる人間自身の充実や豊かさが直結すると思いますか?
TK:そうとは限らないんじゃないかな。充実していて豊かな人生っていうのを手に入れるのは難しいことだし、人それぞれ捉え方が違うものだからね。
■あなたが音楽において意図するものは、聴き手に十全に通じていると思いますか? また、あなたは、あなたの音楽を通して世界になんらかの変革がもたらされることを望みますか?
TK:聴き手から自分の音楽について学べることがたくさんある。変革をもたらしたいとは思っていないよ。
■ドイツでの録音ということですね。他の場所ではなくその地を選んだ理由を教えてください。
TK:ベルリンに住んでいたからそこでレコーディングしただけさ。
■たくさんのミュージシャンたちと仕事をしたいと思いますか?
TK:もちろんだよ! ドレイクと作曲したいね。グルーパー(Grouper)とコラボレートもしたいし、アントニーと演奏したい! 話しはじめたらキリがないよ!