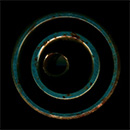UKブラック・ミュージックのストリート部門で活躍するスウィンドルとロスカが今週末に来日する。
グライムとジャズ、ソウル、ファンクを繋げたスウィンドルの果たした功績はやはり大きい。2012年のフロア・ヒットとなった“Do The Jazz”と、翌年のアルバム『Long Live The Jazz』では(ともにリリース元は〈Deep Medi Musik〉)、卓越した鍵盤のテクニックとメロディとリズムのセンスを見せた。
ロスカはリンスFMの看板DJとしてだけではなく、プロデューサーとしても好調で、今年に入り〈Tectonic〉テクノ色が強くなった「Hyperion EP」をリリース。UKファンキーの可能性を押し広げていく姿勢がシーンをリードしている。ちなみに、彼がロンドンで主宰するパーティ〈Roska Presents〉には、本誌で取り上げたピンチやジョーカーたちも出演してきた。細分化が進むUKベース・シーンを繋げる存在としても、ロスカからまだまだ目が離せない。
東京公演にはPart2Style Sound、Prettybwoy、Hyper Juiceといった日本のベース・シーンの第一線でプレイするメンツが出演する。
DBS presents " SPRING FUNKY BASS!!! "
3.21 (SAT) @ UNIT x SALOON
UNIT:
SWINDLE
ROSKA
PART2STYLE SOUND
DJ RS
HYPER JUICE
Live Painting:
The Spilt Ink
SALOON:
DJ DON
DJ MIYU
PRETTYBWOY
ZUKAROHI
ANDREW
open/start 23:30
adv.3,150 yen / door 3,500 yen
info. 03.5459.8630 UNIT
www.unit-tokyo.com
https://www.dbs-tokyo.com
<UNIT>
Za HOUSE BLD. 1-34-17 EBISU-NISHI, SHIBUYA-KU, TOKYO
tel.03-5459-8630
www.unit-tokyo.com
SWINDLE (Butterz / Deep Medi Musik / Brownswood, UK)
 13年に"MALA IN CUBA LIVE"のキーボード奏者としてDBSで来日、単独DJセットでフロアーを狂喜させたスウィンドルはグライム/ダブステップ・シーンのマエストロ。幼少からピアノ等の楽器を習得、レゲエ、ジャズ、ソウルから影響を受ける。16才の頃からスタジオワークに着手し、インストゥルメンタルのMIX CDを制作。07年にグライムMCをフィーチャーした『THE 140 MIXTAPE』はトップ・ラジオDJから支持され、注目を集める。そしてSO SOLID CREWのASHER Dの傘下で数々のプロダクションを手掛けた後、09年に自己のSwindle Productionsからインストアルバム『CURRICULUM VITAE』を発表。その後もPlanet Mu、Rwina、Butterz等からUKG、グライム、ダブステップ、エレクトロニカ等を自在に行き交う個性的なトラックを連発、12年にはMALAのDeep Mediから"Do The Jazz"、"Forest Funk"を発表、ジャジーかつディープ&ファンキーなサウンドで評価を決定づける。そして13年の新作『LONG LIVE THE JAZZ』(Deep Medi)は話題を独占し、フュージョン界の巨匠、LONNIE LISTON SMITHとの共演、自身のライヴ・パフォーマンスも大反響を呼ぶ。最新シングル"Walter's Call"(deep medi/Brownswood)でジャズ/ファンク/ダブ・ベースの真骨頂を発揮したスウィンドル、必見の再来日!
13年に"MALA IN CUBA LIVE"のキーボード奏者としてDBSで来日、単独DJセットでフロアーを狂喜させたスウィンドルはグライム/ダブステップ・シーンのマエストロ。幼少からピアノ等の楽器を習得、レゲエ、ジャズ、ソウルから影響を受ける。16才の頃からスタジオワークに着手し、インストゥルメンタルのMIX CDを制作。07年にグライムMCをフィーチャーした『THE 140 MIXTAPE』はトップ・ラジオDJから支持され、注目を集める。そしてSO SOLID CREWのASHER Dの傘下で数々のプロダクションを手掛けた後、09年に自己のSwindle Productionsからインストアルバム『CURRICULUM VITAE』を発表。その後もPlanet Mu、Rwina、Butterz等からUKG、グライム、ダブステップ、エレクトロニカ等を自在に行き交う個性的なトラックを連発、12年にはMALAのDeep Mediから"Do The Jazz"、"Forest Funk"を発表、ジャジーかつディープ&ファンキーなサウンドで評価を決定づける。そして13年の新作『LONG LIVE THE JAZZ』(Deep Medi)は話題を独占し、フュージョン界の巨匠、LONNIE LISTON SMITHとの共演、自身のライヴ・パフォーマンスも大反響を呼ぶ。最新シングル"Walter's Call"(deep medi/Brownswood)でジャズ/ファンク/ダブ・ベースの真骨頂を発揮したスウィンドル、必見の再来日!
ROSKA (Roska Kicks & Snares / Rinse, Tectonic, UK)
 トライバルハウス、ディープハウス、UKガラージ等のエッセンスを重低音でハイブリッドしたベースミュージックの新機軸"UKファンキー" の革新者、ロスカ。08年に自己のRoska Kicks & Snaresから"Elevated Level EP"、"The Climate Change EP"をリリース。彼のトラックはSKREAM、ZINC、DIPLO、KODE9を始め錚々たるDJのサポートを受け、一躍脚光を浴びる。09年にはシーンを牽引するRinse FMのレジデントに抜擢され、そのフレッシュでロウなダブ音源でUKファンキーの台頭をリードする。10年にはRinse Recordingsと契約し、キラートラックとなった"Wonderful Day"、"Love 2 Nite"を収録したアルバム『ROSKA』をドロップ。BBC Radio 1のEssential Mixにも登場し、その存在を確固たるものとする。11年にSCUBAのHotflushからのEP、PINCHとの共作発表、Rinseのミックスの監修等を経て、12年は更なる飛躍を遂げ、Rinseからアルバム『ROSKA 2』を発表、ハウスを基調にグライム、ダブステップ、ガラージを独自のスタイルで昇華する。その後は世界各地でのDJ、ラジオショーで多忙を極める中、TectonicからPINCHとの共作"Shoulda Rolla"、Rinseから"Shocking EP"をリリースし、Roska の快進撃はとどまる事を知らない。Tectonicから先頃リリースされた最新作"Hyperion EP"では新境地も伺え、来日プレイの期待は高まるばかり!
トライバルハウス、ディープハウス、UKガラージ等のエッセンスを重低音でハイブリッドしたベースミュージックの新機軸"UKファンキー" の革新者、ロスカ。08年に自己のRoska Kicks & Snaresから"Elevated Level EP"、"The Climate Change EP"をリリース。彼のトラックはSKREAM、ZINC、DIPLO、KODE9を始め錚々たるDJのサポートを受け、一躍脚光を浴びる。09年にはシーンを牽引するRinse FMのレジデントに抜擢され、そのフレッシュでロウなダブ音源でUKファンキーの台頭をリードする。10年にはRinse Recordingsと契約し、キラートラックとなった"Wonderful Day"、"Love 2 Nite"を収録したアルバム『ROSKA』をドロップ。BBC Radio 1のEssential Mixにも登場し、その存在を確固たるものとする。11年にSCUBAのHotflushからのEP、PINCHとの共作発表、Rinseのミックスの監修等を経て、12年は更なる飛躍を遂げ、Rinseからアルバム『ROSKA 2』を発表、ハウスを基調にグライム、ダブステップ、ガラージを独自のスタイルで昇華する。その後は世界各地でのDJ、ラジオショーで多忙を極める中、TectonicからPINCHとの共作"Shoulda Rolla"、Rinseから"Shocking EP"をリリースし、Roska の快進撃はとどまる事を知らない。Tectonicから先頃リリースされた最新作"Hyperion EP"では新境地も伺え、来日プレイの期待は高まるばかり!