初めてマシンを鳴らしたときのようにあまりにも新鮮な、いや、空っぽな、いや、無邪気な、いや、アシッディな……いや、なんにせよ、こうも空っぽの音楽、ありそうで実はなかなかないぞ。『オーファンド・ディージェイ・セレク 2006 - 2008』は、リチャード・D・ジェイムスの昨年の『サイロ』~「コンピュータ・コントロールド・アコースティック・インストゥルメンツ pt2 EP」に続く、新作である。
 AFX ORPHANED DEEJAY SELEK 2006-2008 Warp/ビート |
というか、13年ぶりにアルバムを出したと思ったら、数ヶ月後にはEP、およそ1年後には新作。何なんだ~この攻めの姿勢は〜と不可解に思う方もいるかもしれないけれど、ワーナーと契約する以前の、『アンビエント・ワークス』やポリゴン・ウィンドウ時代のリチャード・D・ジェイムスはこんな感じだった。本来の彼に戻っただけである。そう、『アンビエント・ワークス』みたいな牧歌的で、郷愁的な作品を出すその傍らで、彼は当時は名義を代えてまったくクーダラナイ、アシッド・ハウスの変異体を出したりしていたのだった。要するに、『オーファンド・ディージェイ・セレク 2006 - 2008』は、クーダラナイ音楽を作り、プロモーションもなにも考えずにとにかく発表してみるという、リチャード・D・ジェイムスのもうひとつの真実を象徴していると言えるだろう。
『サイロ』を『アンビエント・ワークス』に喩えるなら、新作はAFX名義での作品、あるいはコウスティック・ウィンドウ名義の一連の作品と連なっている。が、『サイロ』がそうであったように、過去の焼き直しではない。サウンドは確実に面白くなっている。リスナーはあらためてエイフェックス・ツインのドライな側面の、底知れぬ魅力に気づかされるだろう。
それにしてもエイフェックス・ツインについて佐々木渉と話していると時間があっという間に過ぎる。わずかふたりの人間でさえそうなのだから、世界中のAFXファンが、飽きもせずに研究し、調査し、分析し、嬉々と議論し続けるのも無理はない。エイフェックス・ツインは聴いている最中ばかりでなく、その後も、まあとにかく面白いのだ。

AFXって、なんでこうも見事なくらい空っぽなんでしょうね? ──野田
本当に時代背景がバラバラな機材を集めて、「どうすんだろこれ?」っていう(笑)。──佐々木
野田:今回はAFX名義なんですよね。
佐々木:どういう事情なんでしょうね。
野田:ていうかまず、『サイロ』(2014年)からこんなにも連続で出てくるとは(笑)。『ele-king Vol.14』のインタヴューでは年内に出すとは言っていたけど、「あれはいつもの気まぐれだろうな」ぐらいに思っていたら、本当に出した。で、しかもその作品、『コンピュータ・コントロールド・アコースティック・インストゥルメンツ pt2 EP』がまず良かった(笑)。それも驚きでしたね。
佐々木:そうですね。クオリティが高い電子音楽を、一杯聴けて嬉しいですよね!でも、サウンドクラウドに大量にアップロードされた音源とかも含めて、割と溜まってたんだなと。音源が溜まってたというよりは、キッカケがあれば、ぶわーっと出てくるテンションがあったんだなという感じがしますよね。
野田:やっぱり『サイロ』で自信をつけたんでしょうね。
佐々木:それもあるでしょうし、もともと最近の作品の方向性に自信があったんだなっていう(笑)。
野田:リチャード・D・ジェームスみたいな天才でも、時代とズレてきたかも? って不安を抱いたときもあったと思うんですよ。「アナロード」シリーズだって、最後まで付いていったファンって、佐々木さんみたいな本当にコアな人たちでしょう?
佐々木:「アナロード」シリーズを評価していた人たちっていうのが、あんまり見えないとうか。リチャードのイメージそものの原点回帰というか、チルアウトというか……。あの頃って「アナロード」シリーズとかについてメディアとかで語ったりとかではなかったですよね。
野田:当時は『remix』誌でも、「こういうシリーズがはじまりました」と取り上げていたんですけど、5枚くらいから正直疲れたんです(笑)。でもあれは、完走した人たちは、最後が良かったって言うよね。ぼくみたいに途中で下山してしまった人間はダメですね。でも、時代の向きとしては、エイフェックス・ツインに追い風はなかったよ。あの頃、ゼロ年代のなかばでは、90年代の頃のずば抜けた存在感も、だいぶ薄れていたというのは正直あったと思うんですよね。
佐々木:90年代のときの暴れん坊的なエイフェックス・ツインのイメージからすると、「アナロード」は随分地味に見えました。本人も自発的にシーンへの立ち位置みたいなものを変えてきてるんだろうなと。飛び抜けて尖ったことをやろうとして、ああいうものを出したとは絶対に考えられない。むしろ当時だと、エイフェックスがサウンド傾向をソリッド化させて、クラークみたいな方向でもうひと暴れするんじゃないか、という勝手な妄想がありましたね。
野田:クラークが出てきたときは、『…アイ・ケア・ビコーズ・ユー・ドゥ』(1995年)を好きだった人たちの耳をさらったよね。クリス・クラーク名義で出した最初の2枚とかはね。〈リフレックス〉というレーベル自体は『グライム』(2004年)という名のダブステップのコンピレーションを出したりとか、その先見の明は後々すごかったとなるわけですけど、とくに2枚目の『グライム2』(2004年)はすごかったんですけど、エイフェックス・ツイン自身がシーンのなかで突出しているわけではなかったですよね。
佐々木:世界的に拡散したエレクトロニカ/IDMムーヴメントとちょっと距離を置いて、あえて台風の目だった〈ワープ〉を避け、〈リフレックス〉の方から出していたんでしょうかね? エレクトロニカとの距離感が上手かったのは、〈プラネット・ミュー〉とかもそうですけれどね。エレクトロニカの飽和や、いままでのテクノのイメージとは違う流れっていうものを、ある種引き算的に打ち出して、独自に強度を上げて、うまいことコアな方に戻ってきている感じがしますね。ずば抜けた直感みたいなものが本人たちにあるのかなと思ってしまう程度には、コーンウォールの人たちはすごかったんだなと、いまでも思っちゃたりするところはあります(笑)。
野田:『サイロ』まで時間がかかったというのは、名義的なことだったり、他にもいろんな要因があったんでしょうね。とにかく、『サイロ』は勝負作だったと。そして、実際にそれが完成度の高い素晴らしい作品だったし、日本でもウケて、世界でもウケた。で、『サイロ』が日本でウケたってことが、ぼくはさらに素晴らしかったと思うんですよね。
というのも、エイフェックス・ツインの音楽って、本当に意味がないでしょ(笑)。まあ、リチャードには牧歌性とか少年時代への郷愁とか、そういったものを喚起させる曲もあって、もちろんそれは彼の最大の魅力で、『サイロ』にはそれがあったわけですけど、今回のAFX名義の『オーファンド・ディージェイ・セレク 2006-2008』は、ものの見事に空っぽなんですよ(笑)。
この意味のなさってすごくないですか? いまは本当に意味を求められる時代で、何をやるにしても、アイドルにだって意味が必要で、大義がなければいけない。何かのためになるとか、社会的な大義がなければいけないような時代において、ここまで何もない音楽があって良いのかという(笑)。純粋に音楽をただ楽しむっていうね、しかも、この音楽を楽しめる人がたくさんいるってことが、本当に良いですね(笑)。インタヴューでは社会に対して深刻な危機感を抱きながらも、作品でここまでふざけられるリチャードが素晴らしいですね。
佐々木:ぼく、今日こうやって対談させていただくというところで、すごく悩んでしまったのは、リチャード・D・ジェームスの存在感と、音楽の意味とかジャンルとかは関係ないと思ったほうが良いと思いたいんですよね。真偽ともかく……。リチャードの提示している音楽やその存在感と、昨今のエレクトロニック・ミュージックのジャンルだったり歴史だったりが対比されることは、掘り下げれば下げるほど意味がない気がする。
リチャードが『ele-king』のインタヴューで、若手アーティストのガンツだとか、その辺の若手に対して、「彼らは彼らなりにラップトップを使っていろんな音を試していろんなことを学んでいるんじゃないか?」と言っていますが、それこそ、エイフェックス本人が、そうやってずっとやってきたらだと思うんです。「音が出る面白いおもちゃがあったら徹底的にいろいろ試すだろ? ガンツの遊び心はセンス有るよね」みたいな。90年代の終わりにラップトップが入ってきて誰でもエレクトロニカを作れるようになったとき、みんないっせいに音遊びをはじめるようになったというところで、リチャードは「もっと違う音遊び」をするために、ハード機材などを模索し始めていたんだとしたら……すごい割り切り方だなと(笑)。やっぱり思考回路が違うんだろうなというところが……
野田:あまりにも天然っていうか、唯一無二ってこと?
佐々木:リチャードの『サイロ』のときのプレスの出し方、アルバムの内容、パッケージの出し方も含めて、とにかく、「うわー」っとなっちゃったというか……。「ちゃんと機材を吟味して、テクノロジーごとの特性や、個性の組み合わせを考えて、テクノを作ったら、こんなにすごいのができるんだ」以外の感想が僕にはなっかたんですよ。
野田:もちろんぼくも最初はそう思いましたね。
佐々木:だから何て言うんですかね……。音に、リチャードの音楽探求の成果があったんです。逆に、自分は頭では考えすぎて誤解をちょっとしていたな、と。音楽は変顔じゃない…という、パブリック・イメージのリチャードの意味のなさを、またリチャードが示してくれたというか(笑)。
[[SplitPage]]機材の名前が曲というか。1曲のタイトルのなかに下手をしたらふたつくらい機材の名前が入っているんですが(笑)。──佐々木
ついに出ましたね、佐々木渉の機材話(笑)! ──野田
野田:『サイロ』のすごいところはあの完成度の高さなんですけど、では『サイロ』というタイトルにはどんな意味があるのかというと、人生を読み解くような意味はない。ラヴだとかハッピーだとか、なにかそういったメッセージもない。でも、音楽に叙情性があったから、リスナーの内面に喚起させるものはあったと思うんですね。しかし、今回の『オーファンド・ディージェイ・セレク』は、そういうものがない。エイフェックス・ツインらしさがひとつ極まったというか……
佐々木:少なくとも、機材と音響周りの独自のロジックを極めていたというか。他にない方向にいっていたので。
野田:去年のドミューンでの佐々木さんの『サイロ』の解説がほんと面白かったんですよね。使われた機材のなかでトピックとなりえるものをひとつひとつ説明してくれたんですけど、あれは聞いててとてもタメになりました。
佐々木:ぼくは機材の収集家ではなくて……仕事柄、様々なハード機材をサンプリングしたシンセサイザー・ライブラリのマーケティングをしていた経験だけですが、リチャードの機材のラインナップが、異様だったんですよね。とくに、使い難くてマイナーな初期デジタルシンセやサンプラーの比率が多かった。
どうしてもエレクトロニカとの対比になってしまいますが、大きな流れとして、池田亮司さんとかカールステン・ニコライとか、シンプルで純粋な音波があって、それで構成された音楽がアートであるとかデザインに近いものであるっていうアプローチがあったと思います。2000年代以降の純粋で音が良いイメージって、ああいうクリーンでコンセプチュアルな方面にも引っ張られていたと思うんですよ。『サイロ』の音の良さってそういうものに真っ向から対峙するものだったといいますか(笑)。いわゆる純粋できれいな音じゃなくて、初期デジタル機材の音信号を制御しきれていない故のノイズ、ダーティなアナログ感、ひとつひとつ違う回路を通ったエレクトロニクス・サウンドの絡み合いだったり、質感のもつれ合いだったりを、自分は全部を把握していて絵の具のパレットのように使い分けられるんだよねっていうアピールそのもので、そういう方向を極めているアーティストって他に全く思い当たらないんですよね。
昔の現代音楽の人であれ、エレクトロニクスのインプロヴァイザーであれ、ひとつの機材を掘り下げることや、ある特定の範囲で決められたセットアップを極める傾向がありますが、リチャードはひとつの脳みそや部屋に収まりきらないぐらいのいろいろな機材にそれぞれ思い入れを持って、それを繋ぎ合わせて使おうしていますよね。それにはものすごい時間と労力と頭の切り替えが必要で、それがものすごく好きじゃないとできないことなんですよ。一番はっきりわかるのが、リチャード・D・ジェームスの集中力だったりとか機械に対する特別な思いだったりとかの度が過ぎていて、尋常じゃない執念とか精神があるんだなと(笑)。
野田:なんだろうね。機材が自分の神経系と繋がってるんですかね(笑)。
佐々木:「自分の音響テクノロジーへの執着と経験自体が一番SF的だったんだよね~」って言いはじめちゃってるんだなという感がします。
野田:初音ミクってメタ・ミュージック的なものかもしれないけど、リチャードは古典的な送り手なわけですよね。テクノ・ミュージックって、多かれ少なかれテクノロジーによって規定されるものですけど、リチャードは、それを越えているということですか?
佐々木:えーと……。初音ミクもリチャードも超変態ですよね、イメージも、認識のレベルで特異な存在。でもリチャードの思考回路は彼のなかで閉じてるわけだから、唯一性が凄い。
野田:とにかくあの人の機材の選び方が、いわゆる古今東西とか常識的なベッドルーム・ミュージックからは並外れているというか、境界がないじゃないですか? とりあえず電流を流して、音が出るものであれば全て使うでしょう?
佐々木:エピソードでいくつか言うと、昔のインタヴューで取材中の空調の音が気に入ったらしくて、これを録音してシンセの音として使いたいと言っていたりするんですけど、たぶんそれを読んだときに、パフォーマンスかと思ったのですが、いま思うと、境目がないんでしょうね。気になった音や気に入った音は、全部、気になる体質みたいな。
野田:ジョン・ケージっぽいというか。
佐々木:ジョン・ケージというよりは、良い音だからそこに耳がいっちゃうっていう意識のレベルというか。もっと変な……楽音と環境音、電子音を区別しない意識みたいな。
野田:コンセプトを言っているわけではなくて、本当に音が良いと言っていると。
佐々木:そうですね。リチャードの自作シンセの話だったり、同郷のスクエアプッシャーだったりもアリの足音をサンプリングしようとしたとか逸話がありましたけど、既存の枠組みと違うことを音響的に意識したり解釈することを是としている。日本だと竹村延和さんだとかが音の意味そのものを考えるって方向にいきましたよね。それもけっこうコンセプト的な方向にひっぱられちゃうわけですけど、リチャードは最後の最後まで音にしか引っ張られていない感じがします。音以外のことを気にしていたら、こんな音の積み上げ方はできないだろうなというか。
機材リストにしてみても、あれをシンセサイザー好きに見せても「なんじゃこりゃ?」って言うようなリストなんですよね。いわゆる名器の割合は多くなくて、不均衡な状態を保つかのように、時代の狭間に置き去りにされたものや、置き去りにされそうなものが多くを締めているんですよ。「なに基準でこれを選んだの?」っていうのが2、3割ぐらいあって(笑)。
野田:エレクトリックギターで有名なフェンダー社のアナログシンセとかすごかったもんね。あと軍事用途のテープレコーダーとかね。
佐々木:本当に時代背景がバラバラな機材を集めてこういう風にリストしちゃう人がいるんだなっていう感じが強かったですよね。「どうすんだろこれ?」っていう(笑)。
野田:使い終わったあとね(笑)。
佐々木:使い終わったあとというか、まとめられてる気がしない。エンジニアの視点だったらエンジニア視点で……やっぱり、こういうラインナップはレア過ぎるなと。
野田:やっぱりイギリス人気質みたいなものを感じませんか? 自己パロディのセンスも含めて。
佐々木:アメリカじゃないですよね。
野田:ベーシック・チャンネルのアプローチともぜんぜん違うし。
佐々木:比較もできないんじゃないかと。
野田:まあ、昔のアナログ機材やモジュラー・シンセに行く人はけっこういて、もっとマニアだとクセナキスやシュトックハウゼンが使っていたような機材を使おうとする人もいるんですけど、リチャードの場合は、機材の選択においては、あまりにも脈絡がないわけでしょう?
佐々木:わざわざ操作が面倒くさいのを選んでるのが多いし、TX16WとかASR10とかOSを書き換えられるサンプラーも多いし、最新の機材も微妙に含んでいて、どこまでカスタムかどうかはみんなわからない。このリストはポップな感じがなくて面倒くさい(苦笑)。昔のインタヴューとはまた違う意味で本当かどうかがわからないものを今回提示してきていますね。
野田:たとえばいまグライムで売れているプロデューサーのマムダンスっているでしょ。彼が『FACT MAG』の取材で自分のベッドルーム・スタジオを見せていたんですが、絵に描いたようなイクイップメントでね、909やアナログシンセがあり、サンプラーがあり、PCがあり、しっかりしたミキサーがあるんです。とても綺麗に並んでいてね、機材好きが真っ当に憧れている機材ががっつり揃っているわけですよ。リチャードは、そういう感性とは全然違っているわけですよね。
佐々木:リチャードの機材リストであるとか、音に対するアプローチっていうのは、たぶんリチャードしかやらないだろうから、ジャンル的な広がりも横の広がりもできないだろうから、これはもうリチャードでいいんじゃないかなという気になってしまうところはありますね。本当にリチャードが唯一無二の感じといいますか。たとえばジャズのジャンルですが、〈ECM〉的な独自のサウンド・カラーがはっきり主張し過ぎていて、あるジャンルに属しながら孤立する感じというか……、そういうものとしてリチャードが出てきちゃったというか。安心して今後死ぬまでリチャードの作品を聴ける感じがするというか、またPCとかシンプルな機材に戻るっていうのもあるのかもしれないですけど。
野田:『オーファンド・ディージェイ・セレク』は、アシッド・ハウスですよね。これを聴いて、AFX流のアシッド・ハウスの最新版だとぼくは思った。リチャード・D・ジェイムスには、牧歌的な顔ともうひとつの顔があって、それはコースティック・ウィンドウ名義で見せていた、大のアシッド好きの顔でね……ちょっと話逸れちゃうけど、石野卓球もアシッド・ハウスが好きでしょ。意味のないことをやり続けているという観点で言えば、電気グルーヴとエフェックス・ツインって似ているよね。ただ、エイフェックスは、さっきも言ったけど、ものすごくイギリス的、ひねくれ方がイギリス的だよ。イギリス人的なアシッド・ハウス解釈のものすごく極端なカタチっていうかね。
佐々木:アシッド・ハウスというか、アシッド感そのものへのフォーカスというか……。よくこんなに粘着質な音楽を作れるよなくらいにグニョグニョしていて。機材リストを見た割と多くの人が「303を使ってないんだ」って言っていたんです(笑)。303の神話から脱却しながら、アシッドなことを求めていく流れは有ると思いますが、ぞれをこの人はずっとやっていたんだなっていう(笑)。
野田:初期の頃、303と606だけで作っている盤もあるけど、そういうすごくフェティッシュ的なところもあったとは思うのね。でも、やっぱりシカゴのアシッド・ハウスのとことんDIYであるがゆえのくだらなさ、あの爆発力をいかに継承するのかってことですよね。あの感じを継承するってけっこう難しいと思うんですよ。一発芸で終わってしまいかねない。
あとアシッド・ハウスって、たとえば“アシッド・サンダー”とか“アシッド・オーヴァー”とか、アシッド何とかとか、多くの曲にとって曲名なんかどうでもいいんですよね。少なくとも“ストリングス・オブ・ライフ”と名付けるのとは違う情熱なわけですよ。
同じように、リチャード・D・ジェームスにとっても曲名なんかはどうでもいい。たとえばAFX名義の最初の「アナログ・バブルバス Vol.3」(1993年)の曲名は、全部数字です。しかも6桁以上の数字なんで、覚えられるわけないっていう(笑)。その次の「アナログ・バブルバス Vol.4」(1994年)にいたっては曲名がないんだけど、佐々木さんはリアル・タイムで聴いていたから知っているだろうけど、声が入る曲があるじゃないですか?
佐々木:ええ。あの象の鳴き声が入るものとか。
野田:あの曲は日本のフロアでもヒットしたよね。あの曲がかかるとみんな笑うっていう。曲名がなくても曲がヒットするって、すごいよね。それって、音そものものでしかないんだから。『オーファンド・ディージェイ・セレク』は、間口の広かった『サイロ』を自分で解体しているっていうか、なんかそんな感じがします。
佐々木:解体というのはどういう方向の解体ですか?
野田:さっぱりわからんない(笑)。とにかく、『サイロ』のようなアプローチではないよね。『サイロ』と同じように、この音楽に感情移入できる人もそういないと思うし、でも、実はこの新作こそがリチャードのもうひとつの本質ってことですよ。だから、『オーファンド・ディージェイ・セレク』を好きな人は本当にエイフェックス・ツインの音楽が好きな人だと思う。
佐々木:このタイトルにある「2006 - 2008」っていうのは、一応『サイロ』よりも前に作っていた暗示なんですよね。だからこの頃には骨組みは完成していたんだよねっていう意図はわかるんですけど、それにしても4曲目の“ボーナスEMTビーツ”とか、シンセの音は最後の40秒でちょろっと入るだけなんですよね(笑)。あとは全部ドラムマシンが鳴っているだけっていう(笑)。ぎりぎりの線で、トレンドを振り払って、ただドラムマシンを鳴らしてますみたいな印象なんだけど、音はとんでもないみたいな。凄い自己アピールだなと思います。
野田:この『ディージェイ・セレク(DEEJAY SELEK)』っていうタイトルのいい加減さも良いよね。「セレクテッド」じゃなくてね(笑)。もうそのあとの言葉すら、めんどくさいんでしょうね。
佐々木:はははは。シンプルなものばかりを集めたってことですよね。なんでそれをいまになって(笑)。
野田:でも、この「2006 - 2008」っていうのは意外と真実かもよ。基本的には誠実な人だとは思うし。ハッタリをかますようなタイプではないと思うんです。ジャーナリストに対して若気の至りで言ってきた部分もあるんですけど。
佐々木:まあ、インタヴューの前後に『アンビエント・ワークス・vol 2』やポリゴン・ウィンドウみたいな音楽を作っていたら、変な言葉も吐きますよね(笑)。
野田:インタヴューとかめんどくさかったと思うんですよ。でもだからと言って悪意がある感じではなかったので。
佐々木:若干分裂気味だったり、思考が一度途切れて持ち直しているんだろうなみたいな瞬間はインタヴューを見ていても思いました。
野田:まあ、『アンビエント・ワークス・vol 2』のときの「夢を見ながら作った」というのは「本当かよ?」と思いましたけどね。でも本当なんじゃないかと思えてくるところが彼のすごいところですよね。そういう意味でいうと、「2006 - 2008」というのはそうなんだろうなとは思うんですけど。
佐々木:僕もそれは同感です。最近になってシリアスに本当だと思えてきてます。
野田:で、〈ワープ〉的には、いきなりこれを出すわけにはいなかっただろうし。「リチャード、これはさすがに……」ってね(笑)。やっぱ、『サイロ』が成功したから出せたと思うし。
佐々木:『サイロ』があって『コンピュータ・コントロールド・アコースティック・インストゥルメンツ Pt.2』があって、本作。リチャードがすることが分裂したようで、作家性への信用が固まっていく感じ。作風が違うようでリチャードでしかない感じは、本人の調子の良さの現れだろうっていう(笑)。彼が、溜め込んできたものまでサウンドクラウドでも垣間見られて、いろいろと選択肢があったなかで、次はこれか、『ディージェイ・セレク』かっていう(笑)。気持ち良い裏切り感。でも『サイロ』と同じで、やっぱり機材の名前が曲というか。1曲のタイトルのなかの下手をしたらふたつくらい機材の名前が入っているんですが(笑)。
野田:出ましたね、佐々木渉の機材話が(笑)! それを聞きたかったんです。
佐々木:最初の曲の“セージ”ってモジュラーシンセと2曲目にある“DMX”のリズムマシンは有名ですよね。3曲目の”オーバーハイム”も“ブラケット”もシンセメーカーの名前です。次の“EMT”もエフェクターの名前ですし、 “ミディ”も規格名、“SDS3”はドラムマシンの名前です。で、最後はローランドの“R8M”とかドラム音源の名前で締めると。「シンプルな機材で遊んだんだよね」って言っているみたいです(笑)。それで音数少な目にまとまっていて勢いがある。
ビートのパターン自体は結構、誰でも鳴らせられるものなんですよね。でも、勢いとか音の粘りだとか、粒立ちの立体感だとか、やっぱり聴いたこともないものになっている。誰でもやれそうで出来ない感じ。リチャードのファンって音楽を作ったことがある人や機材に興味がある人が多いと思うんです。『サイロ』は割と色んな機材を使っているんだけど、音源という意味で「実はドラムマシン一台で俺はここまでいけるんだぜ? すごいだろ」みたいな。
最近ネットで流行っているゲーム実況という、ゲームをやっているところを録画して、それを視聴者が見るってやつがありますけど、これはリチャードなりの作業風景が見える、テクノ実況というか。
ドラムマシンを立ち上げます、3分で打ち込んでスタート・ボタンを押して、テンポをいじって、形ができたらいきなり5分くらいでいろんな機材のバランスをとって、パッと作って、「はいっできました。でも、この機材の組み合わせだとか勢いって俺にしか作れないでしょう?」ってというのを感じる。職人的というか(笑)。そういうテクノロジーを応用しているリチャード自身の凄みを少なからず感じるところがあって。最後のR8Mみたいな機材を使ってこういうビートを作るって、いまこういうことをやる人っていないですからね。最初期のオウテカとかが使ってたような機材ですけど、これをいま使うんだ、リチャードっていう(笑)。
野田:機材がわからない人に解説すると、たとえばどういうものになるんですか?
佐々木:ヴィンテージでもなければレトロでもない。いまその辺のリサイクルショップに行けば、これが数千円以下とかで売っていてもおかしくないんですよね(※オークションの動作確認品でも2500円から1万円前後ぐらいの落札価格)。そういう機材が主役としてピックアップされる不思議、これがすごい評価されている機材ばっかり並んでいたら、ああ、そうだね。すごいね。で終わるんですけど。この機材の今、誰も着目しないポテンシャルを、質感くわえて歪ませて、こうやって引き出すのか……というのが凄い。
野田:そうなると、意味がないと言ったけど、別の意味が見えてきますね(笑)。
佐々木:テクノロジーとの関わり方だったりとか。
野田:それは何なんですかね。ざっくり言ってしまえば機材に対する批評性みたいなものというか、そういう捉え方もできるのかな。それはあると思いますか?
佐々木:ちょっとリチャードのことを考えると頭が痛くなっちゃって、日本語がうまくなくて申し訳ないんですけど(笑)。たぶん世のなかの人は次のタイミングに使う機械ってキューベースとか、FLスタジオとか、エイブルトン・ライブとか、もしくはエレクトロンのハードウェアだったりとか、ヒップホップのプロデューサーで昔はMPC3000やSP-1200を使っていた人がiPadだけで曲を作っていたりする時代に、リチャードが曲作りにコミットするときに使う機材というのが、時代性も存在意義もすごくランダムなもので、いまラックマウント型のR8Mと、最新の機材のMProsser、APIのハードウェアエフェクターとパソコンのレコーダーを繋げられるという状況が、世のなかにはあんまりないはずなんですよ。その接続の妙を楽しんでいる感じといいますか。
スクエアプッシャーとかもインタヴューで、テクノロジーとの関わり方について発言が激しいですけれど、リチャードは行為の規模が激しいなという感じがすごいして、さすが親分みたいな(笑)。むかしのリチャードの作品を聴いても、そういう楽しそうにいろんなテクノロジーと戯れて楽しそうみたいな。
野田:それはむちゃくちゃあった。初期の頃は雑誌にベッドルームの写真が載っていたりしたけど、部屋が機材とシールドだらけで、自分で作ったエフェクターととかね。本当に機材が好きなんでしょうね。
佐々木:機材が好きというよりも、機材同士を繋げるのが好きなのかもしれないですね。
野田:なるほどね。
佐々木:普通の人は機材が好きで、808が好きな人は808の素の音の質感や揺らぎが好きだから、それをどういう風に生かすかを考えるんですけど、リチャードはいろんな機材を繋げて、で、また繋げて、歪ませて、サンプリングして、同時に走らせて、混ぜて変な音が出たら喜ぶみたいな(笑)。そういう処理するルーティンに遊びがある故の偶然性というかなんというか。
野田:いいですねー(笑)。
佐々木:スマートフォンなどによってテクノロジーの存在が日常的でハードとしての挙動が画一的なものになっていて、古いテクノロジーは新しいフレーム内に置き換えられていく。逆に、古いテクノロジーの応用の可能性が広がるにつれて、リチャードがどんどん自由になっているというか。いろんな時代背景の異なる機械を組み合わせる価値とか意味とかがリチャードには見えているというか。異なる年代のテクノロジーの組み合わせで、独自の世界観を作るというのはロマンティックですよね。機材のなかで、ヴィンテージらしいシンセは少ないのですが、音の質感を作る、プリアンプなどはビンテージものが多くて、心地よい歪に歪みに覆われているのもそのせいも大きいと思います。こういう様々な機材を個人スタジオでレイヤーしていく感じは、新しい。いまは、ハードの質感はUAD社とかのPCのシミュレーションもので済ませる人が多いなかで、なかなか、追いつけないサウンドだと思いますね
野田:なるほど。しかも『サイロ』みたいな金字塔を作っておいて、新しいのがいきなりコレかよみたいな。ロックやジャズじゃこんなことできないでしょうね。どこまで自由なのかという。
佐々木:自由というより、むき出しでスカスカ。音はなんだかんだでチューニングされていて、とくに音の粒がユニークに飽和させられて、歪んでいる方向性があって、〈モダン・ラヴ〉とか日本でいえばフードマンとか、あの辺のある種、新しい感覚で歪んでいてインダストリアルでみたいなものを、エイフェックス・ツイン流に昇華している感じが『サイロ』とこのアルバムからは感じるところがあるんですよ。
[[SplitPage]]これはいわばリチャードのもうひとつの本質、アシッド・ハウスへの偏愛の具現化ですね。 ──野田
ヴィンテージでもなければレトロでもない。その辺のリサイクルショップに行けば数千円以下で売っていてもおかしくない機材が曲の主役なんです。──佐々木
野田:インダストリアルは、エイフェックス・ツインの真逆だよね。いまの社会は暗いからそれを反映した暗い音楽を作らなければいけないみたいな。だから自分たちのやっていることには価値があると。エイフェックス・ツインはそういった意味づけすべてを放棄するものであって(笑)。でも、佐々木さんの言っているリチャードのインダストリアルぽさって、音の歪みというところだよね? “クォース”みたいな曲に象徴されるような。“ヴェントリン”(1995年)も、インダストリアル調だったもんね。
佐々木:あの頃はストレートに歪みすぎてる感じがありますが、いまのは“エクスタル”のある種ピュアだった方向性で、かつ音の厚みが増して、周波数的にも上下に情報量が増えた感じ。音のクオリティっていうところで、歪に定評のある、アンディ・スットトやハドソン・モホークと比べて「エイフェックスも全く負けていない」っていうか。リチャードは最新の音楽はほとんど聴いていると言ってましたよね? だから意識的にやっているのかもしれませんね。グライム以降の歪み感だとかうねり感だとか。シリアスなアンビエント感みたいなものを内包していてかつエイフェックス・ツイン流に自由にっていう(笑)。
野田:今回の『ディージェイ・セレク』は、「2006 - 2008」を信じるのでであれば、インダストリアルが流行る前だよね?
佐々木:その頃には彼のなかでのかっこいい歪んだっぽい音ができていたんですかね。その可能性は大いにありうるなと。ルーク(・ヴァイバート)のリミックスを名前を伏せてやっているみたいなところも要素としてあるんですけど、試していたんでしょうね。すごいのが’できたから、ライヴでちらっとみんなに聴いてもらってその反応を見てみたりだとか、ネットで名義を変えて出してみたりっていうテストを経て、「これはいけるぞ」というところで『サイロ』でガシッとしたものを出した。さらに今回はスカスカにして「骨組みだけでもカッコいいでしょう?」みたいなものをと。自分の都合のいい妄想的な捉え方ですけど、事情がどうであれ「かっこいいな」っていう(笑)。
野田:本当にスカスカだよね。ロンドンで見たリチャードのDJがまさに今回の『ディージェイ・セレク』のような曲ばかりかけていたけど、客がまったくいなかったね(笑)。しかも隣のメインルームでロラン・ガルニエがやっていたら、普通ガルニエに行くよね(笑)。
佐々木:音楽的に人間っぽくないですよね(笑)。
野田:独特としか言いようがない。骨組みだけのアシッド・ハウス……それをリチャード・D・ジェームスはまだまだ好きなんですよ。今回のデザインは、1989年頃の、初期の〈ブリープ〉時代の〈ワープ〉のロゴをモチーフにしているんだけど、これも深読みするとアシッド・ハウス時代へのオマージュとも受け取れなくもない。実際に“アシッド・テスト”って曲もあるし。
佐々木:思いっきり言っちゃってますよね。
野田:リチャード・D・ジェームスの存在っていうのは、つくづく別格なんだなと思うけど、まあ、しかしふざけ過ぎじゃないですか?
佐々木:純粋ではあると思うんですよね。テクノである以前に、マシン・ミュージックというか、シーケンシャル・ミュージックというか。音の流行がリバイバルを重ねたことで、テクノもエレクトロニカも気にしなくても、こういう機械の音でシンプルにできている作品が出てくる余地が出来たのは良かった。いきなりこれにぶち当たった人は刺激的に「何これ?」と感じると思うんですよね。
野田:『ディージェイ・セレク』は、しかし、いまこんな時代だからこそ聴くと最高ですよ。本当に、こういう空っぽの音楽を作れる人はすごい。
佐々木:そうですね。でも、何かが引っかかるとは思うんですよ。
野田:結果論というか、当たり前だけど、この順番のリリースでよかったですね。最初が『サイロ』、続いて「コンピュータ・コントロールド・アコースティック・インストゥルメンツpt2 EP」が来て、で、今回の『ディージェイ・セレク』という順番で。
佐々木:いきなりこれだったらびっくりというかね。
野田:誰も聴かなかったかもしれないよ(笑)。でも、『サイロ』はどのメディアも好意的だった。しかし、その次の「コンピュータ・コントロールド~」から評価が分かれていくところもエイフェックス・ツインらしくて良いですね。
佐々木:今回はライナーを書いたので、そこでちらっと触れたんですけど、そのメディアの「好き」や「評価」のポイントが全部ズレているんですよ(笑)。それも面白かったですね。
野田:ぼくと佐々木さんが、同じ好きでもこれだけ違うもん(笑)。佐々木さんはいま35歳で、リチャードがデビューしたのが91年とかだから、当時は10歳くらい?
佐々木:ぼくは『テクノ専門学校 Vol.2』(1994年)に入っていたエイフェックス・ツインの“デジリドゥ”からで、聴いてすぐにポリゴン・ウィンドウを買いました。
野田:じゃあ、中学生くらいのときだ。
佐々木:そうですね。
野田:やっぱりショックでした?
佐々木:ショックでしたね。“デジリドゥ”は、めっちゃアシッドじゃないですか(笑)。「アシッドとかテクノってシンセのグチョグチョした音の全開のはずなのに、アボリジニの民族楽器由来ってどういうこと?」みたいな。
野田:こんなものが世界で聴かれて、これから世のなかはどうなっちまうんだろう? ぐらいな衝撃ですよね(笑)。
佐々木:それこそ本当に電気グルーヴがいて、みんな電気のことは好きでしたが、そこからテクノも掘っていけばいくほど、よくわからないアンビエントやインダストリアルみたいなものが出てきた。“デジリドゥ”は民族楽器を使っている曲として意識して聴いていて、このオーガニックなのかアシッドなのかわからないサイケデリックなものは何だろうと思っていたんです。そしたら、ソニー・テクノのシリーズでエスニックなベドウィン・アセントが入っていて、ああいうものまで聴いちゃったときに、テクノとかエレクトロ・ミュージックと言うよりも、やっぱり自分のイメージの向こう側に怖い世界が待ているんだなぁというか(笑)。
野田:アナログ盤を買いはじめたのはいつなんですか?
佐々木:その2、3年後くらいですね。最初はソース・ダイレクトでしたね(笑)。
野田:懐かしいね(笑)。
佐々木:学校が終わったら札幌のシスコに自転車で行ってました(笑)。タワーに通って視聴期のコーナーにかじりついたりとか、そういう時代もありましたね。実際にすごい時期だったような気がしますけどね。レコード屋の風景が変わっていく感じというか、1週間毎にプッシュされるものが変わって、サイケデリックなものからフロア向けなものまで、ぶわーっと壁を覆い尽くしていて。
ウータンみたなドロドロしたヒップホップから、ピート・ナムルックの気持ち悪い3DCGジャケットまでぐちゃぐちゃにあるなかで、リチャードの笑顔が並んでいたときの衝撃はたしかにこの目で見ていたので、世のなかはどうなっちゃうんだろう? とは思いました。これを全部信じちゃいけないとも思いましたね(笑)。テクノとかじゃなくて、自分の生きている状況をリアルに信じちゃいけないんだと。海の向こうのこれが普通ならどうしようと(笑)。
野田:テクノというタームでひと括りにされるけど、エイフェックス・ツインはクラフトワークやYMOといったテクノの王道とは断絶がありますよね。それは、繰り返しにしなるけど、アシッド・ハウスってことだと思うんだけど。今日、佐々木さんが教えてくれたように、機材へのアプローチの仕方にもそれは表れていると思う。リチャード本人は、もちろんクラフトワークもYMOも通っているんだろうけど、LFOのような影響のされ方はしていない。『アンビエント・ワークス』のアンビエントという言葉で、ようやく過去のエレクトロニック・ミュージックと繋がった感じはあったけど。
佐々木:自分のなかでは『セレクテッド・アンビエント・ワークス 85-92』を聴き過ぎたんですよ(笑)。なんの音楽知識もなかった頃にあれをループ再生していた自分っていま考えると怖いなって(笑)。
野田:明らかに、次世代の感性を解放したよね。その功績はすごく大きいですよ。不格好の自作の機材も、機材という名のブランド志向からの解放だったとも言えるわけだし。でも、たとえば、エイフェックスとオウテカって、似ているようで全然違うよね。オウテカは、すごく批評的に機材を選択するよね。ソフトウェアで作って、みんながそれをやりはじめるとアナログに戻ってっていう感じで。
佐々木:オウテカはいまのエイフェックス・ツインがどう見えるでしょうね? エイフェックス・ツインもPCだけで音楽を作るのが簡単過ぎると言ってましたが、オウテカは批評性が強いですよね。昔、ファンクストロングの制作システムを批判していたのとか思い出します。
野田:スクエアプッシャーの『ダモジェン・フューリーズ』は、誰もが同じ機材でつまらないから、自分でソフトウェアを作ったという作品だったけど、それも批評性だよね。
佐々木:リチャードの場合は、楽しく機材をいじりたいし、それで興奮をしたいというところがすごく強いというか。
野田:変態ですね。
佐々木:でも、インターネットで世の中がこれだけパロディ化というか、デフォルメ化された情報が飛び交っているなかで、ここまで精神性の通った意味のないパロディというか………。変わっていない感じしてすごい安心感があるんです。だからCD買っちゃうんですよね(笑)。
野田:佐々木さんは、タス(2007年)が最高だって言っていたくらいだからなぁ。タスこそ世間的にリチャードが難しかった時期ですよね。そろそろ話を締めたいんですけど、さっきの機材の話で、「R8Mなんてみんなは使わないよ」って話が面白かったので、他にも「この機材は!」というものがあったらぜひ教えて下さい。
佐々木:4曲目の“ボーナスEMTビーツ という、ドラムだけの曲なんですけど(笑)、タイトルの真んなかにある“EMT”って鉄板なんですよね。この会議室がいっぱいになるくらいの大きさの鉄板のリヴァーブなんです。鉄が音を反射して、その音が入っているっていう(笑)。
野田:電流を流すものではないんですね(笑)。
佐々木:電源入りますけどね(笑)。スプリング・リヴァーブの鉄板みたいなものですね。プレート・リヴァーブと呼ばれるものの実物を持っているようで、それをこれだけシンプルな曲のなかでこうやって主役のように使うという(笑)。しかも曲名のなかの“EMT”っに下線が入っているから、それを強調しているんだなと(笑)。しかも曲名が“ボーナスEMTビーツ”とあるように、ボーナスのビーツということになりますね(笑)。
野田:それを家のどこに置いておくんだろうな。
佐々木:きっと家が広いんでしょうね。しかも、いまはソフトでそれが再現できるので、わざわざそれをリアルで持っているということは、実際の機材とコンピュータが違うということなのか、あるいは「持っている俺、すてき」というか(笑)。それはわからないですね。
野田:こうして話していると、話が尽きないんですけど、ますますリチャードっていったい何なのかがわからなくなってきますよね(笑)。ただ、リチャードの機材に対する執着心というか偏愛というかね、並々ならないものがあるわけですけど、それはiPad一台で作ってしまうような現代のトレンドには思いっきり逆らっていますよね。少なくとも、便利さのほうにはいかないでしょ。
佐々木:関わり方が違いますね。リチャードは、操作が直感的かどうかもあんまり気にしてないのかもしれない。
野田:ぼくはPC一台で音楽を作っても、iPad一台で作っても、ぜんぜん良いと思うんです。機材が必ずしも音楽を決定しない、音楽の価値は機材によって決まらないという立場にぼくはいるんですね。でも、今日の佐々木さんの話を聞いていると、リチャードみたいな機材のアプローチの仕方っていうのは、ある意味では音楽の価値に明らかに影響してくるんだなとは思いました。機材の選択というのは……、よく取材で、アナログシンセは音が良いっていうのがあって、けっこうそれを言う人は多いんですけど、リチャードの発想力は、そんなものではないと。
佐々木:リチャードがテクノロジーを制御している感じがすればイイというか、リチャードが作ったフレーズだったり、リチャードが付けた曲名、選んだテクノロジーがあったりするんですが、何を使ったって良い曲は作れると思うんです。でもそこにさらに彫り込みを入れていっているような感じで痕跡が良い。デジタル配信とかプレイリストって、逆に言うとちょっとしたことで消えちゃうというか。消えちゃったら忘れちゃったりするわけじゃないですか? そうすると自分に何も残らない感じっていうのがありますよね。リチャードの場合はあの顔は忘れられないし、音楽へのアプローチも手あかだらけというか、リチャードが籠めたものというのが、音源も機械もスタンスも発言も全部が消えそうにないものだなという感じがありますよね。
野田:まあ、これだけの人が数千円で売っているような機材を使って、これだけユニークな音楽を作って、新作を出していることが良いですよね。しかもそれが純粋に楽しんでいるっていうね。
佐々木:ジョン・ケージの時代ならいざ知らず、このひと通りやり尽くされた時代に、こんなアプローチをやり続けて……、しかも自分自身の意味性に消費されずに残っていることは、つくづくすごいと思います。


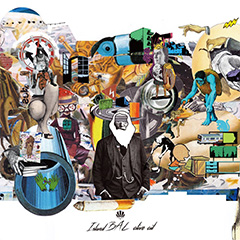
 BLACK SMOKER RECORDS PRESENTS
BLACK SMOKER RECORDS PRESENTS

